本日は、情報戦略テクノロジー(以下、IST)のエンジニア執行役員である野沢さんにお話を伺いました。創業からISTを支え、エンジニア部門を率いる野沢さんの視点から、会社の歩みや価値観、社会人として大切なことなど語っていただきました。
目次
自己紹介と経歴
これまでのキャリア
高井さんとの出会いとIST創業期のリアル
立ち上げ当初からの夢の実現
組織における「役割」の重要性
過去の経験にとらわれない成長の姿勢
ベンチャーから大企業へ—
キャリア相談と恐怖を取り除く関係づくり
「理念が強い会社」としてのIST
自己紹介と経歴
ー 本日は情報戦略テクノロジーのエンジニア担当執行役員の野沢さんに来ていただきました。本日はよろしくお願いいたします。
情報戦略テクノロジーの執行役員を務めております野沢と申します。元々エンジニア出身で、ISTには創業メンバーとして入社し、現在執行役員に就任しております。本日はよろしくお願いします。
(左:インタビュアー、右:野沢)
これまでのキャリア
ー 高井さん(IST代表)と出会うまでの経歴について詳しく教えていただけますか?
はい、1999年に大学を卒業して、エンジニアとして最初の会社に入社しました。ちょうど2000年問題の対応をするのが1年目でした。プログラムをアップデートして適用し、2000年に切り替わる時に何が起こるか分からないので、年末年始の日付が切り替わる時に会社にいて電話対応をするために控えていたり...結局、電話は一回も鳴りませんでしたが(笑)まさにミレニアムの記念の時に社会人スタートをしました。
一社目では上流工程しかやっておらず、エンジニアとして知識が足りないと思い、社会人3〜4年目に転職を決意しました。その二社目で、高井さんがいた会社で働くこととなりました。
高井さんとの出会いとIST創業期のリアル
ー 高井さんとはどのような形で出会い、ISTの創業メンバーとして参画することになったのでしょうか?
最初の出会いは二社目に入った会社で高井さんが採用担当をしていて、たまたま私の面接官が高井さんだったという偶然なんです。当時は高井さん配下で普通の一社員として働いていたのでそこまで関わりがあったわけではなかったんです。
ただ、高井さんがソフトハウスへ転職をするタイミングで「一緒に来ませんか」と誘いを受けたんですね。そこで東京支社の立ち上げをする高井さんについて行ってエンジニアとして経験を積み、マネジメント能力を買われてグループリーダーのような役職についていました。
その後、高井さんがISTを立ち上げるという話になり、次は私から「行きます」という形で立ち上げに参画しました。東京支社立ち上げの際にたった3年ほどで0から100人近い会社に拡大させた実績を見ていたので、この人なら大丈夫だという信頼がありました。立ち上げ時は社員が本当に4人くらいの規模で、ひたすら現場仕事を頑張っていました。2015年くらいに、いわゆる課長クラスの役職につきました。そこから2018年に部長になり、2022年に役員になり、今に至ります。
立ち上げ当初からの夢の実現
ー ISTに入社してから一番感慨深かった出来事は何ですか?
一番感慨深かったのは、実はこの恵比寿ガーデンプレイスに引っ越したことなんです。社員が10人くらいの頃から「いつかガーデンプレイスにオフィスを構えよう!」という話をしていたので、それが実現したのは本当に嬉しかったです。
他にも嬉しかったことはいくつかあって、私はもともと高井さんから役職者になる対象から外されていたんです。前職で課長クラスをやっていたので、私がISTの課長になるとそこが基準になってしまい、新たな課長が生まれないという考えがあったようです。しかし、月日が経って改めて「課長をやってくれないか」という打診をもらった時は嬉しかったですし、部長に任命された時も同様に嬉しかったです。
高井さんは「役職は偉いわけではなく、ただの役割である」とずっと言っていましたし、私も役割としての視座を持てるようにしていますが、それでも役職が与えられるのは「その役割を十分に期待できる」と評価された証でもあると思うので、嬉しかったですね。
組織における「役割」の重要性
ー 役割という言葉が出ましたが、野沢さんにとって「役割」とは何ですか?
規模が大きくなればなるほど、組織には引っ張るリーダーが絶対に必要です。リーダーが組織を引っ張っていかないと、組織は成長しないし正しく機能しません。その人に引っ張る意志や力があるかは別として、引っ張る「役割」を演じなければならないと思うんです。
組織的な課題があった時に、その人が積極的に解決に動かなければならないし、責任を取るという役割があります。役職が上がるにつれて、その役割も大きくなっていきます。
過去の経験にとらわれない成長の姿勢
ー 役割とはいえ、役職が上がっていく中でその役割をこなすことには難しさもあると思います。野沢さん自身がこれまで役職が変わられてきた中で、気を付けていたことはありますか?
過去の経験にとらわれすぎると視座を上げられないと思いますし、新しい役割もこなせないと思います。上の役割がこなせるようになったから上がるというよりも、役職が上がってみてからできるかどうか試される抜擢のパターンで昇格する方が世の中では多いと思います。
能力以上に重要なのは、先入観をどれだけ捨てられるかだと思っています。例えばエンジニアからいきなり役員に上がった場合、求められることは真逆です。エンジニアはきっちり役割が決まっていて期限通りに成果を上げることを求められますが、役員は決まった仕事があるわけではなく、自分で仕事を作って会社の利益に貢献するよう動かなければなりません。
役員になった時に「自分はエンジニア出身だからここまでしかやらない」という線引きをしてしまうと、役割をこなせなくなります。今まで自分がやってきたことを捨てて、今求められていることを柔軟に・素直にこなせるかどうかが重要だと考えています。
この観点は、新卒の最終面接をする際にも学生に対して話をしています。結局、自分がやりたいことにこだわりすぎると、自分の成長が阻害されてしまうので、「とりあえずやってみることが大事」ということを話しています。
ー これは若手にとっても重要な視点ですね。
そうですね。任された仕事をやってみるという話は、チャレンジするスタートラインに立つことに繋がっていますし、与えられた仕事を避けている時点で、チャレンジするスタートラインにも立てないんです。「ここは経験したくない」と思って避けた仕事が、後から「この経験がないから仕事任せられませんね」と言われてしまい、取り返しがつかなくなってしまうケースも世の中あります。
任された仕事は、将来長い目で見ると無駄なことなんて一つもないんです。任された仕事はすべてチャンスだと捉えて、積極的に経験してみてもらいたいです。
ー 確かに過去を振り返って「この業務は無駄だった」と思うことはないですよね。
そうなんです。この視点を持っているかどうかで今後が大きく左右されると思います。40代を超えている人ならその視点を持っていると思いますが、若いうちから「目の前の仕事は将来絶対に役に立つ」と思える人はかなり強いと思います。
ベンチャーから大企業へ—
ー ISTが創業から現在まで、どのように変わってきたと感じますか?
一番大きく変わったのは、ベンチャー企業としての空気感が少しずつ変わってきているところだと思います。今は組織として大きく強くなった一方で、逆に少人数の時にあった「みんなで家族のようにわいわいやる雰囲気」は少なくなってきています。
ー たしかにそういった変化はあるかもしれませんね。私は1年前に入社しましたが、前職が大手だったので、そこと比較すると家族感はむしろ感じていたところでした。ただ、昨年上場した背景もあってか、ここ1年だけ見ても徐々に大手企業に近づいているのかもしれません。その中でも、大手と比較したときにISTはどこが強みだと感じますか?
やはり、キャリアの自由度が高いところだと思います。自分でどう成長して、どういうキャリアを歩むかという自由度はかなり高いです。
大手企業のキャリア育成は会社によって違うので一概には言えませんが、「これができなければダメ」というような決まった枠組みが、うちの会社にはほとんどありません。それぞれ向いている分野や方向性は人それぞれ違うという考え方があるので、成長する方向性の多様性は、大手に比べたら全然広いと思います。
ー 確かに、選べる幅が広いですよね。
そうですね。先ほど、「とりあえずやってみて」という話がありましたが、キャリアについても挑戦してみてもらう風土が強いと思います。まずやってみることでスタートラインに立てる。だからこそ任された仕事をやってみる姿勢がないと、チャレンジするスタートラインにも立てなかったりするんですね。
キャリア相談と恐怖を取り除く関係づくり
ー 中途入社の方々のキャリア形成についてはどのように支援されていますか?
社外の方の話を聞いていると、上司にキャリアの相談をすることはかなり敷居が高いのだなと感じます。「わがままを言ったら出世の道が閉ざされるのではないか」「こう言ったら怒られるのではないか」「裏で出世の道が閉じられているのではないか」といった恐怖があるのだとと思います。その中で、そういった恐怖を取り除くことが重要だと考えています。なので、まずはある程度会話を重ねて本音を話してもらえるような関係を作ることを大切にしています。キャリアの方向性を相談したい人は結構多いと思います。そういった相談を引き出した上で、どういった形で実現していくかを一緒に考えるのが部長としての仕事だと考えています。
ー 相談しやすい環境づくりについてはどのように意識されていますか?
1on1の時間を30分ほど取っていますが、場合によってはその30分を雑談などのアイスブレイクだけで終わらせることもあります。話しやすい空気感を感じてもらうことが重要だと思っています。また、エンジニア部署とは別枠でキャリア相談窓口を年に2回ほど設けているので、そこで相談してくれる人もいます。
「理念が強い会社」としてのIST
ー 最後に、ISTを一言で表すとどのような会社だと思いますか?
私はこの会社のイメージとして「理念が強い会社」だと思っています。上場していても理念を大切にして、「売上だけ上げればいい」とだけならない会社は意外になかなか無いと思うんです。
情報戦略テクノロジーは、売上だけ上げても褒められない会社です。会社の理念があって、それを実現するための売上を上げることができて初めて認められる会社です。そういった理念を持ち続けているところがISTの一番の良さです。
これは私自身が一番この会社の好きなところでもありますし、みんなもそこが好きだから残ってくれているんだと思います。
ー 本日はたくさんお話しいただき、ありがとうございました!初めての方にもISTのことがしっかり伝わったのではないかと思います!
こちらこそ、ありがとうございました!みなさんぜひお会いできることを楽しみにしております!
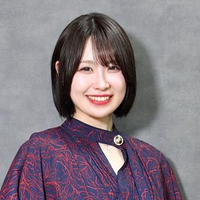






/assets/images/14287758/original/41aa6faf-6f8c-427c-9316-d03b39f542f1?1692955864)
/assets/images/14287758/original/41aa6faf-6f8c-427c-9316-d03b39f542f1?1692955864)

