本日は、情報戦略テクノロジー(以下、IST)の執行役員人事部門担当である瀧本さんにお話を伺いました。前回に引き続き多様なキャリアを歩んできた瀧本さんから、AI時代との向き合い方について語っていただきました。(前回の記事はこちら!)
目次
AI時代の到来とその受け止め方
AIが変える仕事の構造
AI時代に必要な意図的な「下積み」
若手へのメッセージ
AI時代の到来とその受け止め方
ー ここまでベーススキルの話をありがとうございました!次はAI時代に今後を生き抜くための話をお聞きしたいです。近年、生成AIが急速に発展していますが、AIを乗りこなすにはどんなポイントがありますでしょうか。
みなさん、普通にパソコンを使いますよね?インターネットもSNSも使いますよね?そこに違和感はないですよね?
ー ないですね。
AIも全く同じことが、もう早々にやってくると思います。何の疑問もなく、当たり前のように使っている状態になる。この1、2年でものすごく変化のスピードが加速して、数ヶ月後には「ググる」のと同じレベル感で「チャトる(ChatGPTに聞く)」のが当たり前になる気がします。あるいは、もう当たり前になっているかもしれません。
なのでそんなに身構えることはなくて、いかに抵抗しないかが大事だと思っています。抵抗する心をどれだけ抑制できるかが肝心で、習得しようとか前のめりになる必要性は全くありません。いかに抵抗せずに順応するかの心だけが大切なんです。
ー 抵抗するというのは、どういったイメージでしょうか?
「こんなの使えない」とか「こんなことやってるより、これをやった方がいい」「自分はいいや」とか思うことです。新しい産業や技術が出てくる時、人間は基本的に変化を嫌うので、新しいものに警戒する心が強いんです。でもそこを抑制さえできれば、自然と乗っかれると思います。
僕は未来予知ができるわけではありません。ただ、これまで技術革新が起きてきた時の歴史のパターンをAIに当てはめて考えているだけです。パソコンが普及した時も、インターネットが普及した時も、スマホが普及した時も、最初はみんな抵抗感があった。でも今では当たり前のように使っています。AIも同じ道をたどると思います。
AIが変える仕事の構造
ー AIの発展により、組織や仕事の構造も変わってくると思います。瀧本さんはどのような変化が起きると予想されていますか?
形として、「中心にAIがいて、その周辺に人がいる」という時代になると思います。特に人事の領域では、業務の中心にAIがいて、その周辺に人が介在し、人と人との間を繋いだり、部署と部署の間を繋いだりする分野で活躍するような形になっていくでしょう。
インターネットが現れたことによって人と人にあった知識の壁は越えられたんですよ。誰しもが同じ知識を持てる。でも、経験の壁は越えられなかったんです。ところが、AIが出てきて「あれ、これまで越えられなかった経験の壁も越えられそうだな」と僕は思っているんです。
ー 「経験の壁」ですか?
そう、経験値がなければわからないこと、旧来では経験していく上で掴んでいくもののことです。でも、これからはAIが経験値の領域までカバーしてくれるようになるんです。これは今のAIが単なる学習ベースではなく、推論モデルだからです。AIが推論できるようになったからこそ、経験の壁を超えられるようになった。だからこそ前に話したベーススキルがあれば、経験値がない新しい仕事でも、AIとペアを組むことによって、一定の成果を出せるという、そんな構図が僕には見えているんですよね。
ー 前回お話しいただいたベーススキルとテクニカルスキルの関係性もより変化していきそうですね。
そうですね。前回お話したように、僕はスキルを「ベーススキル」と「テクニカルスキル」に分けて考えています。ベーススキルは基本的な仕事の能力で、コミュニケーション力や思考力など。テクニカルスキルは専門性があるスキルで、プログラミング言語や特定の業界知識などです。
仕事力はベーススキルにテクニカルスキルの掛け算だと言いましたが、AI時代ではこの関係性がさらに重要になります。なぜなら、テクニカルスキルの多くはAIが補完してくれるようになるからです。でも、ベーススキルはAIでは補えない。むしろ、AIを使いこなすためにはベーススキルがより重要になってくるんです。
またパソコンの例になりますが、AIという高性能なアプリケーションを動かすには、しっかりとしたOSが必要なんです。そのOSに当たるのがベーススキル。だからこそ、これからはテクニカルスキルへの投資を薄めて、ベーススキルにより投資していくべきだと思っているんです。
さらに進化すると、一人の人間にたくさんのAIアシスタントがぶら下がっている状態も来ると思います。例えば、スケジュール管理AI、情報収集AI、文書作成AI、データ分析AIなど、様々な専門AIが一人のビジネスパーソンをサポートする形になるでしょう。そうなると、僕の時代の新人像と、令和からAI時代の新人像では、だいぶ毛色が変わってきます。
ー これからの変化について具体的に話を聞きたいです!
今の若者に対しては羨ましい面もありつつ、可哀そうだなと思う面もあります。どういうことかというと、僕の時代は新人には当たり前のように下積みの時代があって、資料のコピーばかり取っていたり、寿司屋で言えば皿洗いばかりやっていたりする期間がありました。そのまま寿司屋の例えでいうと、ひたすら皿洗いをして、包丁を持たせてもらうのが2年後で、包丁を持たせてもらったと思ったら、ひたすら皮むきだけをまた2年やる、みたいな修行があるわけです。
それには経験値を積む修行の意味合いもありましたが、その一方で、そういう下積み処理をしてくれる人間が大量に必要だったんです。ひたすら皮を剥いてくれる人がいないと、寿司を握る人だけでは下処理の方がボリュームが大きいので、対応できなくなってしまう。そんな風に若手とベテランのバランスがうまく噛み合って成立していました。
でもAI時代になると、いきなり新人がディレクターからスタートするようになります。AIがアシスタント業務をやってくれるから、入社してすぐからAIをアシスタントに携えて、ディレクター業務から始まるんです。普通はみんなアシスタントから始まって、ディレクターになっていくものですが、その順序が変わってしまう。
下積みがなくていいなと思う一方で、アシスタント業務の中にも学ぶべき本質的な経験がいっぱいあって、そういう機会を失っているとも言えます。例えば、資料作成の基本的なスキルや、会議の段取り、クライアントとのコミュニケーションの基礎など、これまで下積み時代に自然と身についていたものが、AIに任せることで学べなくなる可能性があります。だから「羨ましいな」半分、「もったいないな」半分という感じ。
昔はみんな算盤をやっていましたが、電卓ができたことによって算盤をやらなくてもよくなりました。でも算盤が出来ることはマイナスにはならず、むしろ計算力や集中力が鍛えられるなど良いことがあるから、今でも算盤教室はあり続けるし、子どもに習わせる親がいる。AIと下積みもこれと同じ話なんです。必要性と価値は別物なんですよ。
AI時代に必要な意図的な「下積み」
ー なるほど。そんなAI時代での若手育成について、何か考えていることはありますか?
AIが当たり前になると、意図的に「下積み」の機会を作る必要があるかもしれないと思っています。これは半分冗談ですが、半分本気です。
下積みがない前提に立つと、そこにある様々な本質や心理に触れられないのは可哀そうです。そこから気づきを得て欲しいので、徹底的に下積み仕事だったものをやらせる時間を設けるなど、そういった経験の場が必要かもしれません。算盤も、出来ないより出来るようになっていた方がいいな、と思う人は多いはずです。
何でもそうですが、色々なものが当たり前になった途端に、ありがたみってなくなりますよね。だからあえて当たり前にそばにあるものがない世界を経験させるとか、そういう環境を作っていかなければならないと思います。
例えば、僕は学生の頃、お金がなくて水道を止められたことがあります。水が出ないというのは、日本では滅多に経験しないことですが、それを経験すると水のありがたみがすごくわかります。
AIが当たり前、インターネットが当たり前、スマホがあるのが当たり前の時代だからこそ、たまにそれらがない状態を経験することで、新たな気づきが得られるんです。僕は長期休暇の時に、スマホを1日しまって過ごすことを定期的にやったりします。そうするとまた色々な気づきがあるんですよ。
若手へのメッセージ
ー では、AI時代を生きる若手へのメッセージをお願いします。
僕は、「仕事がない」という状況も「仕事が多すぎる」という状況も、どちらも学びの機会でした。特に「仕事がない」という状況は辛いものですが、そこから「仕事があることのありがたみ」を学べました。
AIの時代だからこそ、基本的なことを大切にして欲しいと思います。AIに頼りすぎず、自分の頭で考える力を磨いてください。変化を恐れず、新しいものに抵抗せず、常に学び続ける姿勢を持つことが大切です。
ー 貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
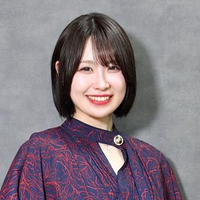





/assets/images/14287758/original/41aa6faf-6f8c-427c-9316-d03b39f542f1?1692955864)
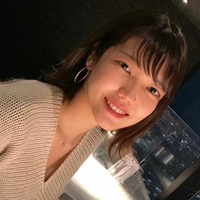

/assets/images/14287758/original/41aa6faf-6f8c-427c-9316-d03b39f542f1?1692955864)

