本日は、情報戦略テクノロジー(以下、IST)の執行役員人事部門担当である瀧本さんにお話を伺いました。多様なキャリアを歩んできた瀧本さんから、私たちが今の時代で得るべきスキルの本質について語っていただきました。
目次
自己紹介とこれまでのキャリア
「ベーススキル強者」が勝つ時代へ
時代の変化とスキルの価値
効果的なベーススキルの磨き方
役員は目指してなるものではない?!
さいごに
自己紹介とこれまでのキャリア
ー 本日は情報戦略テクノロジーの執行役員人事部門担当の瀧本さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。まず簡単に自己紹介をお願いできますか?
瀧本です。2016年に情報戦略テクノロジーに人事総務部長として入りました。その後、自社サービスのWhiteBoxの立ち上げをやったり、営業部門を見たりと、色んなことをやりながら現在に至っています。実は元々理系出身のエンジニアで、1社目はソフトハウスに入社していました。社会人1年目の配属後いきなり半年間の空き稼働を経験したと思ったら、次はハードな現場で働く、という経験もしています。まあ、何でも屋さんですね。
ー そうだったのですね。空き稼働の直後が激務だなんて、振れ幅が大きい!
半年間の空き稼働を経験したことで、「仕事がない」という不幸を得たんです。何もやらない半年間、そして何もやってないのに毎月お給料が払われる。この矛盾の中で、仕事がもらえることの喜びやありがたみを感じるようになりました。これが「何でも屋さん」に繋がったんです。
仕事の苦痛には、「仕事がない苦痛」と「仕事が多すぎる苦痛」の二種類があって、どちらも経験した僕にとっては「仕事がない苦痛」の方が圧倒的に辛かったんです。だから「仕事が増えれば増えるほどうれしい」という新たな価値観が育まれました。
(写真:瀧本)
「ベーススキル強者」が勝つ時代へ
ー 幅広い経験を積まれてきた瀧本さんだからこそ、今後の社会を乗りこなしていく上で大切にしている視点があれば、ぜひお伺いしたいです。
僕はスキルというものを「ベーススキル」と「テクニカルスキル」に分けて考えるようにしています。
ベーススキルというのは基本的な仕事の能力です。例えば人と会話をする、自分が考えていることを正しく相手に伝える力、相手が伝えたいことを正しく理解する力、計算する力、推理する力といったもの。
一方、テクニカルスキルは専門性があるスキルです。例えば英語が話せるとか、Javaが書けるとか、六法全書を全部理解しているといったものです。
ベーススキルはどんな職種や業種であっても、仕事をする上で必要となる力。テクニカルスキルは特定の職種や業種で生きる専門的な力ということになります。
ただ世の中には、コミュニケーション力や思考力といったベーススキルを伸ばそうという意識が全く無いままに、とにかく英語を話せるようになろうとか、プログラミングができるようになろうとか、時間の投資先が偏っている人が多いと感じています。
でも実は、仕事力というのはベーススキルにテクニカルスキルを掛け算したものなんです。極端な話、ベーススキルがゼロの人がテクニカルスキル100を身につけても、掛け算するとゼロになってしまう。ベーススキルが大事なのに、そこに意識がない人が多いと感じます。
ー なるほど、土台にベーススキルがあって、そこにテクニカルスキルが乗るというイメージですね。
そうですね。もう少し掘り下げると、パソコンをイメージするとわかりやすいかもしれません。性能のいいOSがあってこそ、高い性能を必要とするアプリケーションがちゃんと動く。古いパソコンに新しいアプリケーションを載せても、上手く動かないですよね。「OS力」と「アプリケーション力」という表現をする人もいます
(左:インタビュアー白、右:瀧本)
時代の変化とスキルの価値
ー それほどに重要なベーススキルを軽視してしまい、テクニカルスキルのみを投資先として選んでしまうのは何故なのでしょうか。
やはり時代の流れが大きいと思います。昔、テクニカルスキルの価値はすごく高かったんです。でもインターネットが出てきてから、テクニカルスキルとベーススキルのポジショニングが逆転し始めました。
例えば、Googleが出てきて「ググる」ことは一般化されました。これは「知識を誰でも手に入れられる」ということを意味します。つまり、知識の保有そのものに価値がなくなってきているんです。インターネットの普及によって、昔なら「六法全書を全部頭に入れています」という人にはとてつもない価値がありましたが、今は基本的な知識が全てインターネット上にあり、誰もが簡単にアクセスできる。それにより、「知識を持っている」という専門性の価値がまず一回下がったんです。
さらに今、AI社会が到来していて、AIが当たり前のように活躍する未来がもう訪れています。そうすると、専門性はAIが得意とする領域なので、法律の専門家に質問するのと同じか、それ以上の回答がAIから返ってくる可能性があります。これによりもう一段、専門性の価値が下がったと感じています。
ここで逆転が起こるので、これからはテクニカルスキルへの投資を薄めて、ベーススキルを軸足として投資をしていくべきだと考えています。テクニカルスキルが全く不要だとは思いませんが、バランスが変わってきているんです。
ある種、「僕みたいな人間が活躍しやすい時代がやってきた」と感じています。というのも、僕、実は専門性はそんなになくて。今までのキャリアの中で、会社という組織の中で困っているものや課題に対して「わかりました、ちょっとやってみますね」という姿勢で社会人生活を送ってきました。ただひたすらにその場で必要とされたことや困りごとに対して種類関係なく向き合い続けてきたんです。だから人から見ると、「僕の専門性って何?」となるんです。
ー それこそ最初におっしゃっていた「何でも屋」はそういったところからなんですね。
そうなんです。営業だったら「僕は営業です」、法律家だったら「僕は法律家です」と答えられると思うんですけど、僕の場合は「何屋さんですか?」と聞かれると「何でも屋です」になってしまうんです。何かのスペシャリストになることなくジェネラリストとしてやってきたから。
でもさっき話したように、時代の変化によって専門性の価値が以前より高くなくなってきた今、僕みたいに幅広くやってきて、ベーススキルを磨き続けた、高め続けたような人間が脚光を浴びる時代がやってきたのかもしれないと、感じているんです。
効果的なベーススキルの磨き方
ー ベーススキルはかなり幅広く、身に付けようとしても取っ掛かりが難しいものに感じます。これをどういう形で身につけていくのが最適でしょうか?
僕がやってきた経験からすると、「仕事を選り好みしない」というスタンスが大事だと思います。仕事には共通している部分があって、数学的に言うと因数分解のようなものです。
例えば10,000という数字は一見複雑に見えますが、素因数分解すると2と5のたった2つの素数が複数掛け合わさった数でしかありません。仕事も同じで、分解すると所詮は話すこと、テキストを書くこと、聞くことなど、基本的な動詞の掛け合わせでしかないんです。
だからどんな仕事も選り好みせずにやっていくと、ベーススキルが磨かれていくと思います。これは僕が新人時代に「仕事がない苦痛」を経験して、仕事を選り好みせずやってきたからこそ強く感じることかもしれません。仕事があることのありがたみを知ったことで、どんな仕事でも喜んで引き受ける姿勢が身について今がある、そう思うんです。
ー 一方で、学生や若手社員は早く成長したい一心で「まずテクニカルスキルを学ばなきゃ」と思っている方が多いように思うんですが、どう考えますか?
例えば、テクニカルスキルの話と関連して、資格を取ることそのものには、私はそんなに価値を感じていません。でも、資格を取るという目標を設定して、マイルストーンを組んで、どんなに眠くても疲れていても「今日は10ページ勉強する」と決めたことをやり切る力、これもベーススキルなんです。
目標を立てて、計画を立てて、その計画通りに自分を律して自分をコントロールする。資格にはそういう価値、ベーススキルを磨く効果があると思います。
営業の仕事でも、エンジニアの仕事でも、目標を立てて、それに向けて差分を出して計画を立て、立てた計画通りに自分をコントロールするというプロセスは共通しています。全ての仕事は、あるべき理想の姿と現状のギャップを埋めていく作業なんです。仕事内容で例えると、営業ならアポを月何件取って何件訪問しましょうって目標が立てられて、といった具合です。
新人は「この目標に意味があるのか」「これは自分がやるべきことなのか」「こんなことを繰り返して何になるのか」という邪念が出てくるものです。そんな邪念を気にせず、とにかく目標を立てて、達成できる計画を立て、その計画通りに自分を律して行動するというゲームやトレーニングと思ってやっていくと、自然とベーススキルが磨かれていくと思いますよ。
役員は目指してなるものではない?!
ー 瀧本さんは「何でも屋」として様々な役割を担ってこられましたが、役員になるまでの道のりについてお聞かせください。
そもそも、僕の中で「役員は目指してなるものなのか、気づいたらなっているものなのか」という問いがあります。僕の場合は、本当に目の前のことを必死に食らいついてやっていたら、気がついたらなっていた、という感じです。望んでなったというよりは、結果としてなったんです。
今は人事役員をしていますが、人事の仕事をやって色々な人のキャリアに触れる中で、実は役員というポジションは、野心を持って目指してなった人より、一生懸命やっていたらなった人の方が多いんじゃないかと感じています。
例えば、僕は中学高校と野球部に所属していたのですが、当時の監督がよく言っていた言葉があります。「ホームランは狙って打つんじゃない。ヒットを狙って打って、その延長線上の結果がホームランなんだ」と。
とにかく綺麗なスイングで、きちんとバットの芯をボールで叩く。そうするとヒットが出る。そして一定の確率で、ヒットの延長線上にホームランが発生する。逆に、ホームランを狙おうとぶん回している人はホームランを打てないんです。
今になって、あの時の教えとキャリアの積み方は共通するなと思います。ずっと「役員になりたい」と野心満々でいる人には、むしろチャンスや信頼が少なくなるかもしれない。とにかく黙々と「困っていること、なんとかしたいです」「あなたの悩みに答えたいです」「なんでもやります」というスタンスでいると、結果としてのホームランが出るんじゃないかと。
少なくとも僕はそのスタンスで生きてきて、今があります。
ー 今の話、すごく納得感があります。私もソフトボールをやっていましたが、思い切り振り回すよりも、コンパクトに締めてミートを心がけると、実際に飛ぶんですよね。
そうそう、一定確率で塀を越えるんです。力む必要はないんですよ。逆に力んだらバントにすら当たらない(笑)力を抜いて、とにかく目の前のボールをきちんと芯で叩いてミートする、これだけを考えていれば、ホームランは結果として出る。
ホームランを狙って力む状態というのは、さっき話したような「すごくやりたい、やりたい」と前のめりになってしまっている状態に似ています。そうなると、自分の目の前にある仕事が見えなくなってしまったり、ベーススキルを得られる機会を見落としてしまったりすることにつながるんです。ぶん回そうと思った時点で、もうボールが見えなくなってくる。顔が上がって、先を見すぎてしまうんです。
僕もこの年になって、世の中ってすごくシンプルだし、多くの人がもしかしたら「逆」のことをしているかもしれないな、と感じることが多いんです。今の話もまさに逆じゃないですか。「ぶん回せば飛ぶ」と思っているけど、実は「コンパクトにやれば飛ぶ」というのが真実。こういうことが実はそこら中に転がっていて、一部の人だけがそれを知っていて、ちゃんと「逆打ち」をしている。世の多くの人が思っていることは、大体逆なんです。
ー 確かに、人はやりがいや活躍したい夢があるからこそ頑張れるけれど、そこに生き急ぎすぎると、かえって遠回りになってしまうんですね。急がば回れと言いますね。
そうなんです。先にそこに生き急ぎすぎると、テクニカルスキルに偏ってしまったり、ぶん回しちゃったりする。でも実は、コツコツとベーススキルを磨いていくことが、結果的に大きな成果につながるんです。
さいごに
ー 最後に若手のみなさんへメッセージをお願いします。
みなさん、特に新入社員や学生、若手社員の方には、目標を立てて、それに向かって計画を立て、自分を律して行動するというプロセスを大切にして欲しいと思います。
また、野球の例えで言ったように、大きな成果を焦って力まずに、目の前の仕事に真摯に向き合うことが大切です。ホームランを狙わずにヒットを積み重ねる。そうすれば、結果として大きな成果も自然とついてくるでしょう。
どんな仕事も選り好みせずに取り組む姿勢が、長い目で見たときに大きな差になると思います。ベーススキルを磨くことを忘れずに、一歩一歩着実に進んでいってください!
ー 貴重なお話をありがとうございました。基本に立ち返ることの大切さを教えていただきました。
ありがとうございました。みなさん、一緒にがんばりましょう!応援しています!
(気になる後編はこちらから!)
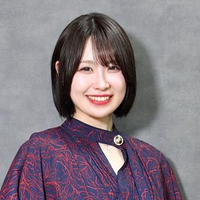







/assets/images/14287758/original/41aa6faf-6f8c-427c-9316-d03b39f542f1?1692955864)

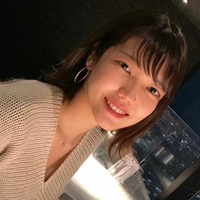

/assets/images/14287758/original/41aa6faf-6f8c-427c-9316-d03b39f542f1?1692955864)

