本日は、情報戦略テクノロジー(以下、IST)のDX推進2部部長であるH.Kさんにお話を伺いました。70名近いエンジニアのキャリア開発を担当し、若手から慕われるH.Kさんの視点から、ISTの魅力や挑戦についてお聞きしました。インタビュアーはスペシャルゲスト、IST人事部長です。
自己紹介と経歴
ー 本日はよろしくお願いします。早速ですが自己紹介と経歴を教えていただいてもよろしいですか?
自己紹介ですが、20歳からITエンジニア業界に入ってきて、今40歳で業界21年目のエンジニア部長をやっております。ISTに入ったのが2013年1月なので、会社歴では今13年目になります。
もともとは調理師の仕事をしていたんですが自分に合わず、母から「ちゃんと働きなさい」と怒られた中で、エンジニアの道を選んだので、IT未経験という形でこの業界に入ってきています。当然、未経験なので最初は40人とか30人とかの小さな会社で働いてきて、言われたことをただやっていくだけでした。正しいものに触れる機会もなかなかない状態だったので転職を決意しました。2社目の会社ではウェブがやりたくて転職をしたものの、結局会社の都合でWindowsアプリを作ることになり、ずっと設計書の修正だったり別のツールの選定だったり、エンジニアっぽくないことをやらされていたにもかかわらず、給料はそんなに高くなかったんです。ちょうど子供も生まれたので、このままこの業界で仕事をするなら、もっといい会社に行こうというので、再度転職活動をしてISTに入りました。
(左:インタビュアー 右:H.K)
ーISTを選んだのはなぜだったのでしょうか
ISTに入った決め手になったのは、面接です。面接官として出てきた代表の高井さんが「なんでうちの会社が設立したのかということと、この業界の問題点についてお話させていただこうと思います」と言って、1時間半ほど話をしてくれました(笑)その時に言っていたのが、「多重下請け構造が問題だよね」ということと、「一次請けだとしても、お客さんが使うのは僕らが作ったもの。使われる側になっててはいけない。お客さんと一緒になって仕事をすることが、うちの会社の存在意義である」というのを聞いて、ここでなら面白いことができそうだなと思って入社しました。
当時会社規模は20人ぐらいだったので、役員がいて社員がいてという二層構造だったところに、中間管理職を作りましょうという話になって、2013年4月から中間管理職候補としてやって、入社4ヶ月で役職者になりました。
現在部長としては70人弱ぐらいのメンバーを見ていて、それぞれのキャリアを上げていったり、給料を上げていったりというところが一つメインの仕事です。あと最近は採用側にも顔を出させていただいて、エージェントの方としゃべったり、どうやってうちの社員を増やしていくかといったところを話していくのが仕事かなというところです。
DX推進2部の役割と業務
ー一般的に70名の方を部長として見るのは結構大変だと思うんですが、どうやっているのか気になります。
もし目の前に70人いて、それぞれを平等に評価しなければいけないとなったら大変だと思います。でもここではどれぐらいの仕事量をどうやってるかというのが目に見えています。ISTはコンピテンシーの評価だったり、週報で上がってくる情報だったり、営業から上がってくる情報だったりと複数の情報があるので、「この人頑張ってるよね、頑張ってるから、もっと頑張るためには会社側がどういうサポートをすればもっとモチベーション高く頑張れるのか」というのを考えていくだけなんです。当然、取りこぼしはどうしても出ちゃう時もあるけれども、そんなに言うほど大変かと言われると、むしろ楽しいです。
ー 楽しさの方が勝っているんですね。DX推進2部という部署がどういう部署で、その中で部長として普段どういう業務をしているかを教えていただけますか?
DX推進2部は簡単に言うと、エンジニアのキャリア開発、キャリア形成を行って、それぞれのやりたいことをやれるようにしていく部署です。なので、他部署に異動したい、例えばラボ開発部に異動したい、DXコンサルティング部に異動したいといった希望を叶えたりするのが役割です。
それをやっていくために、それぞれのやりたいことが何なのか、今やりたいことがやれてるのかをヒアリングします。でも事実、多くのエンジニアは「やりたいことなんか無い」「キャリアどうしたらいいんですか」という人たちの方が多いので、「今何ができているのか」「3年後どうなっていたいのか」「30歳でどうなっていたいか」と聞いても答えがないんです。なので、「いくら稼ぎたいのか」「じゃあそのいくらを稼ぐためには、これぐらいの単価を取らなきゃいけないよね」「じゃあ、その単価を取るために何をしていこうか」という話をしたり、あとは『ザ・コーチ』という本があるので、それをもとに目標の在り方について話したりしています。
私は、自分の仕事と人生って切っても切り離せないと思っています。だからこそ、仕事において、人生においてやりたいこと、例えば世界一周したいとか、それなら仕事でいくら稼かなきゃいけないんだろうねというようなことを一緒に考えて、毎月1on1をしています。
当然、エンジニア側からの話に応えるためには、営業側とも話をしなければいけないし、他部署の部長、ラボ開発部、DXコンサルティング部といったところとも繋がりも作っておかないといけません。実際異動したいという話が出たときに異動できない、ということがないように調整をするのも仕事だと思います。あとは評価制度をブラッシュアップしています。ISTのエンジニアがより過ごしやすく、ISTに居続けるメリットがある会社にしていくのが部長としての仕事かなと思います。
マネジメントスタイルと若手との関わり方
ー普段マネジメントや若手と関わる中で意識していることがあれば是非聞きたいです。
意識しているところとして、うちの経営理念に「チャレンジし続ける人を増やす」というのがあります。チャレンジし続ける人を増やすためには何があるかというと、失敗を恐れずにやる人が増えなきゃいけない。じゃあどんな失敗をみんなが恐れるかというと、クビになるんじゃないか、給料が下がるんじゃないか、会社が潰れるんじゃないかみたいな、自分に降りかかる負の側面があると、人ってすごいチャレンジしづらい。なので、「失敗は全部俺が引き受けてやる。だからやりたいことをやりなさい」ということは意識しています。
これは経営理念にあるからというのもありますが、私が中間管理職に上がったときの話が大きいです。入社からずっと管理ポジションをやりたい、やってみたかったというのを代表の高井にずっと言い続けていて、とある飲み会の帰りのタクシーで「そうだ、来月から役職作るんだけど、やる?」と急に言われました。やりたいと思っていたことをちゃんと覚えていて見つけてくれた、拾ってくれたんです。そのとき高井さんが私にやってくれたことは、私自身もやらなければいけないことだと思っているし、それをやった結果、下の子たちが成長できるんだったら、それはすごく面白いと思っています。
もう1つ、新卒入社の子に「君はエンジニアだと思う。ものづくりの人だよ。当然、自分自身が作ったものには責任を持たなければいけないし、自分自身が作ったものは素晴らしいものだし、でも自分自身が作ったものが一番疑わしいものだ。」という話をしたから慕われているのかな、懐かれているのかなというのもあります。今はAIだったりPMO業務があったりしますが、基本的にはこのIT業界の仕事は全てものづくりなんだということを言うようにしています。
エンジニアの本質とものづくり
ー ちょっと今そのお話が出たので、もう1つ深掘りたいんですけど、H.Kさんにとってのエンジニアって何ですか?
ものを作る人です。大工さんと一緒だと思っていて、物理的に三次元にものができるわけではなくて、あくまでコンピューター上で動くものしか作らないんだけど、自分たちが作ったものを誰かが使うものであるし、誰かの生活を豊かにしていく、誰かの仕事を楽にしていくようなものなので、いいものを作らなければと思っています。
AIに奪われる部分の仕事だけで言うのであれば、誰にでもできる仕事だと思います。だからこそ、より早く、より良く作りたいです。常にどうしたらもっといいものが作れるのか考える。それは環境を用意すれば作れるのか、スキルアップすれば作れるのか、いろいろ方法はあると思います。ものづくりだからこそ、よりいいものをちゃんと作っていこうと考えています。
仕事と家庭の両立
ー 話の軸を変えるんですけど、ご家族がいらっしゃってお子さんもいらっしゃるということで、仕事と家族とプライベートのバランスについて、どういう風に向き合われていますか?
奥さんがすごいできた人なんです。自分が家のことをほぼやれないので、家事に価値を感じているし、やってもらうことに対して感謝の気持ちがあります。だからメンバーから「結婚しました」とか「子供生まれるんです」と言われたときは、「ちゃんと奥さんと話をしなさい。言わなくても分かるだろうではなく、ちゃんと自分は仕事でこういうことを成し遂げたい、こういうことをやりたいから、例えば今はちょっと仕事が忙しいから、そういうことをお願いするかもしれない」という話をちゃんとしておきなさいというのと、「感謝を忘れちゃだめだよ。ちゃんとありがとうが必要なんだよ。やってもらうのが当然じゃないからね」というような話をしています。
子供たちが今私のことを慕ってくれるのは、おそらく奥さんが父親の私のことをちゃんと話してくれていたおかげだと思うので、そういうところを忘れないようにしています。
目標と求める人材像
ー H.Kさん自身の成し遂げたいことや目標はありますか?
ないです。ないからこそ、メンバーの子たちがやりたいことをやれるところに対してすごい共感を持つし、「こういうことやりたい」「じゃあ何ができるだろう」というサポートすることが私の仕事だと思っています。もともとそんなに長生きすると思っていなかったんだけど、40のこの歳になって意外と元気だなと。あと20年は仕事できてしまう感じですね。であれば、下の子たちを部長に上げるとか、会社を大きくしていくことが一つ自分のやりたいことと役目に繋がってくると思ってます。メンバーのやりたいことをちゃんと支えていく、実現させていくといったところに、自分のリソースを全部割けちゃうような感じです。
ー どんな人にうちの会社に来て欲しいですか?
やっぱり自立してる人ですね。誰かが言ったから、誰かがこうだったからというよりも、自分自身がエンジニアとしてどうなりたいかを思っていて、そこに対して自分の人生の理想を描ける人とかが、このAIが台頭してくるような業界において活躍できる人だと思うし、すごい成長できる人だと思っています。そういう人に対しては、ISTが成長に貢献しますし、やりたい仕事も飛んできます。なりたいものがあるとか、100人マネジメントしたいとかそういうのではなくて、単純にエンジニアとしてチャレンジしていきたいからそのために努力ができる、いい給料が欲しいからそのために努力ができる、みたいな人が来てくれると楽しい会社になるなと思います。
逆に、今未来に迷ってる方...PMになろうか、コンサルになろうか、テックになろうか...という人は一度ISTに来てもらえると、その人の適性に合わせた育成だったり、未来を見つけてあげることができるんじゃないかなと思います。
AI時代のエンジニア像
ー 最近AIというものが台頭してきて、社会全体で関心が高く、うちの会社の中でもこれから推進していこうみたいな話が出ているかなと思います。H.Kさんの視点で、AIに対してどんなエンジニアだと活躍できるか、どう向き合って欲しいかについて教えてください。
真っ向からちゃんとぶつかって欲しくて、「所詮AIだよね」みたいな浅い見方ではなくて、「AIはどんなことができるんだろう」といった向き合い方をしてほしいなと思います。
当然、自分自身も使っていて、ソースコードなんかは本当にプロンプトが優秀であれば簡単に書けてしまうんですね。なので、「AIに負けない自分の強みって何なんだろう」というのをしっかりと探して欲しいと思います。もし見つからなければ作って欲しいと思います。
今後どんなエンジニアだったらAIに勝てるんだろうか、という答えは、正直もうソフトスキルベースの高さになってくるんじゃないかなと思っています。なぜならば、AIは嘘をつくので、AIを使いながら、お客さんに対して、ユーザーに対して、一緒になって仕事に取り組める人がやっぱり生き残っていくんじゃないかなと思っています。
いわゆるコピペエンジニアはダメだと思っています。自分のコーディングの強みを考えてみてください。手が速いでも良いし、綺麗に書けるでも良いし、品質が良いでも良い。今少しでも駄目なところがあるのであれば、必ずAIに負ける時代が来るので、そこに対してしっかりと武器を作っていく、そういうことができる人じゃないと、多分もうエンジニアは生き残れないと思います。
応募者へのメッセージ
ー 最後に、この記事を見てるみなさん宛に、メッセージがあれば一言お願いします。
今やりたいことがなくても構わないです。「お給料を上げたいんです」だけでも構わないです。ただ、ご縁があって入社された時には一緒になって、キャリアを作っていければいいかなと思っています。是非、面接だけでもいいので来ていただけると嬉しいです。
あと、採用候補者の方という意味で言うと、面接の場は基本お見合いの場だと思っているので、こちらからも色々聞きますし、応募者の方からもいろいろ聞いて欲しいです。質問が多いから「この人は駄目だな」みたいなことはまったくなく、質問をいっぱいしてもらった方が、弊社に興味を持ってもらってるという風にも見えてきます。
ー みなさんにお会いできることを楽しみにお待ちしております。H.Kさん今日はありがとうございました。
ありがとうございました!
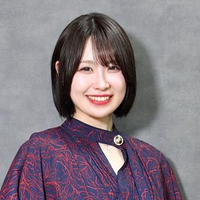






/assets/images/14287758/original/41aa6faf-6f8c-427c-9316-d03b39f542f1?1692955864)
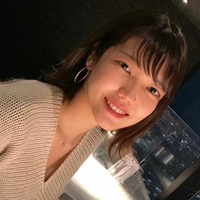


/assets/images/14287758/original/41aa6faf-6f8c-427c-9316-d03b39f542f1?1692955864)

