本日は、情報戦略テクノロジー(以下、IST)の執行役員である新井隼人さんにお話を伺いました。エンジニア組織を統括し、特に若手育成に力を入れている新井さんの視点から、ISTの魅力や挑戦についてお聞きしました。
目次
自己紹介と経歴
大手企業からの転職とその決め手
入社後の印象と会社の変化
新卒育成への取り組み
技術トレンドの追い方
AI活用の現状と展望
ワークライフバランスの実現
ISTとは
自己紹介と経歴
ー新井さん本日はよろしくお願いいたします!簡単に自己紹介をお願いできますか?
ISTのエンジニア組織に対して執行役員を務めております新井です。最近は特に新卒に限らず若手育成の領域に関わることが多いですね。経歴としては、2016年にISTに転職してきて、少し現場業務をやった後に部長として部門を持ち、2022年12月に執行役員になりました。それから今の業務を担当しています。よろしくお願いいたします。
ー転職というワードが出てきましたが、前職はどのような会社だったのでしょうか?
はい、前職は1社のみで、NECソリューションイノベーターという、NEC系の子会社でした。子会社といっても12,000人ほどの社員がいる大きな会社です。システム開発を行う一般的なSEが多く、官公庁向けのシステム開発や一般企業向けのシステム開発、昔はガラケー関連の事業部もありました。
(左:インタビュアー、右:新井隼人さん)
大手企業からの転職とその決め手
ー大手企業からの転職は大きな決断だったと思います。どういったきっかけで転職を決めたのでしょうか?
きっかけは前職でエンジニアとしての成長に頭打ちを感じていたことが大きいですね。大きい会社なので、やり方が古かったり、なかなか変えられなかったりという部分がありました。世の中にはもっと新しい技術や効率的なやり方があるのに、今の環境ではエンジニアとしての成長が難しいと感じて転職活動を始めました。
ーISTとの出会い、気になります。
実はISTは転職活動を始めて最初に出会った企業でした。情報収集のために転職フェアに行ったんですが、当時ISTは入り口の一番近くにブースを出していて、来場者をどんどん誘い込む作戦を取っていました。私もそこに引っかかった形です(笑)簡単に話を聞いた後、別途詳しく話をする機会を設けていただき、そこから選考を進めていきました。
ー ISTを転職先として選んだ一番の理由は何だったのでしょうか?
一番の理由は「ここが一番チャレンジできそうだ」と感じた点です。前職ではシステムエンジニアとして働いていましたが、自分の強みというものがあまりなかったんです。世の中にもっとレベルの高いやり方とかがある中で、何とか自分の強みの領域を絞り出して、それを軸に転職活動をしていました。
そして面白いことに、ISTではその強みとした領域の仕事が当時ほとんどなかったんです。ただ、「その領域の仕事を広げていきたいので、一緒に広げていくのを手伝ってほしい」と言われました。他の会社も見ていた中で、ここが一番チャレンジできそうだというのが決め手になりました。
入社後の印象と会社の変化
ー「チャレンジできそう」というところで入社されて、実際に入社してみていかがでしたか?
良かったことは、前職ではまさにエンジニアリングの作業部分を他の会社に任せることが多かったのですが、ISTでは自分たちで一貫してプロジェクトをやっている人たちが周りにいて。自分が転職前に目的としていたエンジニアとしての成長が想像よりも短期間で実現できちゃったんですよ。また、志の高い人や成長力のある人が多いというのも良かった点です。
一方で戸惑ったのは、成長真っただ中の企業だったのでルールなどがまだ整備されておらず、個人の力に頼る部分が多かったことです。ある人ならできるけど、他の人だとできないというようなことも多く、会社としての未熟な部分も見えました。
ー当時と比べて、現在はどのように変わっていますか?
ルールについては、皆さんも感じていると思いますが、かなりしっかり整備されてきています。ただ、前職と比較してまだ弱いのは事業の成熟性ですね。ISTのエンジニアはお客様と一緒にシステム開発をする際に自由度はありますが、会社としての強みが何かというと、皆さんも悩むところかもしれません。
前職では事業領域がしっかり決まっていて、特定のお客様と長期間システム開発をしていたので、事業の成熟性は高かったです。これは大手と比較して、ISTが現在弱いところだと思います。ただ、この課題に対しては既に手を打ち始めていて、ラボ開発部などもその一つだと考えています。
新卒育成への取り組み
ー最近の取り組みについて教えてください。
私の仕事は特定のターゲット層に対するものが多く、皆さんには見えづらいかもしれません。ここ数年は特に新卒育成に力を入れていて、研修の企画から実際の内容作成、運営までを担当しています。
最近では、新卒が現場に配属された後の成長をどのようにサポートするかということも、エンジニアの皆さんと協議しながら進めています。さらに、新卒の枠組みを卒業した人たちが中核やリーダーになっていくための支援の仕組みも作り始めています。
ー その取り組みはどのように始まり、現在はどのフェーズにあるのでしょうか?
新卒育成を会社の重要なミッションとする方針は、2年少し前から経営レベルで強い問題意識として存在していました。それがちょうど今年になって成果が見え始めています。具体的には2023年入社の方々が若手が属する開発育成部から各部門に異動する「卒業」の段階に達しました。
新卒育成はブラッシュアップを続けていますが、基盤ができて改善していけるフェーズになったと感じています。ただ、次の課題として認識しているのは、新卒の枠組みを卒業した人たちがプロジェクトの中核になっていくことです。ここについては、新卒エンジニアの育成ロードマップを敷いていくなど、フォーカスを当てて手を打ち始めている状況です。
ー確かに新卒の比率も大きくなっているので、今から手を打つことで未来の中堅社員が育っていくイメージですね。
そうですね。後からでは遅いので、3年後、5年後を見据えて成長の道筋や仕組みを作っていくことが重要だと考えています。
技術トレンドの追い方
ー現場から離れている中で、技術トレンドなどはどのように追っているのでしょうか?
実際にはかなり大変です。やはり実務から離れると分からないことが多いですね。そのため、大きなトレンドや発信をニュースなどから日常的にキャッチして、今どういった領域がメジャーで使われているのか、どんな新技術が出ているのかをざっくりと把握するようにしています。
また、実際にそれを使っているエンジニアの方々に機会があれば話を聞いて、自分の中でイメージの解像度を上げるようにしています。
ー情報収集はどのようなところから行っていますか?
個人的に一番使っているのははてなブックマークかもしれません。ジャンルごとにニュースが出てきて、テクノロジー関連の情報を得ることができます。ただ、それだけでなくXなどのSNSや技術記事を投稿しているサイト、最近の勉強会のテーマなども参考にしています。
深掘りが必要な場合は社員の方々に聞いたり、概論をしっかり押さえたい時は本を読んだり、テーマに沿った記事を探して読んだりしています。
ーちなみに本はどのくらい読まれていますか?
最近は家庭の都合もあって読書ペースが落ちていますが、調子がいい時は年間100冊以上読んでいた時期もありました。移動中に読むこともあれば、業務で特定の領域のキャッチアップが必要になった時に、そのテーマに関する本を一気に10冊ほど読むこともあります。
AI活用の現状と展望
ー社内開発しているAIシステムもありますが、AI活用について、どのように取り組まれていますか?
AIは今後、皆さんの業務でも必ずどこかで使われていくものになるという認識を持っています。現在、AIについて全社で統一したプロジェクトを進めているわけではなく、特に興味関心がある人や、業務に活用できそうなイメージを持っている人が、それぞれの領域で取り組んでいる状態です。
各自が取り組んだ事例を「誰がどういう場面でAIを活用した」という形で共有することで、知見を広げています。
ー共有はどのようにして行われているのでしょうか?
まだ決まった場は設けていないのが現状です。思いついた人が自発的に発信するという形で進められており、各部門の管理職・メンバーそれぞれで、積極的に取り組む姿も見られてきました。
今後は、AIの活用が個人の興味関心レベルから、組織的な取り組みへと発展していくことが重要だと考えています。AIを単なるツールとしてではなく、業務プロセス全体を見直す契機として捉え、より効率的で創造的な仕事の仕方を模索していきたいですね。
また、AIの活用においては、単に作業を自動化するだけでなく、人間の創造性や判断力と組み合わせることで、より高い価値を生み出せると考えています。ISTでは技術だけでなく、ビジネス価値の創出を重視していますので、AIもその文脈で活用していくことが大切です。
ワークライフバランスの実現
ーISTには家庭を持つ方も多いですが、忙しい業務との両立はどのようにされているのでしょうか?
私も立場上忙しいですが、私以上に頑張っている方も多くいます。それでも仕事と家庭の両立に努力されている方が多いと感じています。
一般的なエンジニアの忙しさを超えるような特別な忙しさはないと思いますし、世の中のエンジニアの働き方も時代とともに大きく変わってきています。昔は過労死ラインを超えて働くことも珍しくありませんでしたが、今はそういった時代ではありません。ISTは皆さん自身で時間のコントロールがしやすい環境なのではないかと思います。
ISTとは
ー最後に、ISTを一言で表すとしたら何でしょうか?
一言で言うと、「成長中」ですね。やはり前職と比較することになりがちですが、前職は既に成熟していた中で、ISTはまだまだ成長中だと感じています。
例えば、組織変更が頻繁に行われていることもそうです。「こんな頻度で変わって皆さんついていけるのか」と思うほどです。しかし、これは世の中の状況や我々の仕事、お客様の状況を総合的に見て、最適なタイミングで行っているものです。
今ISTで皆さんが今やっている仕事は、1年前や2年前には想像もしていなかったことかもしれません。それは変化した、つまり、成長したということだと思います。そしてこれからもその成長は続いていくでしょう。そういう意味で「成長中」という言葉が最も適していると思います。
ー最後に、読んでくださった方へのメッセージをお願いします。
ISTはIT企業ではありますが、かなり特殊な会社だと思います。技術力だけでなく、お客様に価値を届けるために何をすべきかを、あらゆる職種の人が考えて行動している会社だからです。
エンジニアとしての仕事や作業だけでなく、ビジネスとしてどのような価値を残せるか、自分は何が最大限できるかを考えられる人がチャレンジできる環境だと思っています。技術だけでなく、ビジネス価値の創出にも興味がある方には、ぜひ挑戦していただきたい会社です。
ー新井さん、本日はありがとうございました!
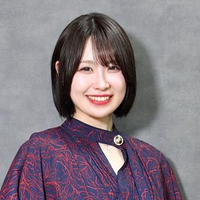







/assets/images/14287758/original/41aa6faf-6f8c-427c-9316-d03b39f542f1?1692955864)

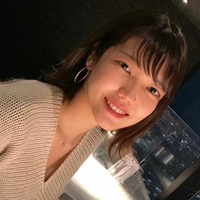

/assets/images/14287758/original/41aa6faf-6f8c-427c-9316-d03b39f542f1?1692955864)

