こんにちは、広報担当の沼澤です。
今回は、DX豚舎事業の中心メンバーとして活躍する島倉さんにお話を伺いました。
柔術、サーフィン、研究、そして養豚DX。
どれも異なる世界のようですが、すべてがいまの島倉さんに繋がっていました。
「ブラジリアン柔術です」
—— 突然ですが、島倉さん。最近ハマっていることってありますか?
いきなり来ましたね(笑)。実はブラジリアン柔術なんです。
打撃がなくて、寝技中心の格闘技なんですけど、相手の体勢や重心を読みながら、少しずつ有利な位置を取っていく。
“ヒューマンチェス”と呼ばれるくらい、理詰めなんです。
—— ブラジリアン柔術!珍しいですね。始めたきっかけは?
もともと大学院時代、サーフィンをしていたんですが、研究室の先生に誘われて柔術に転向しました。その先生も昔サーファーで、柔術とサーフィンの親和性を語られて体験してみたんです。
最初は相手に転がされて終わり(笑)。
でも、すぐに夢中になりました。
ブラジリアン柔術って、「相手がこう動いたら自分はこう動く」という無数の“型”があるんです。
相手が腕を掴んでくれば、こちらは腰を落として体をずらす。
腰を浮かせてくれば、逆に足を絡めて“ガード”を取る。
すべての局面に定石があり、そこから分岐していく。
一手ごとに思考と反応が重なる、その連鎖が最高に面白いんです。
動きながら考え、考えながら動く。
まさに“構造を体で理解するスポーツ”ですね。
—— たしかに、頭脳と体の両方を使うタイプの格闘技ですね。
はい。相手の呼吸やリズムを読むことが勝負なんです。
柔術の世界では「読み」と「間」が命。
これは後で話しますが、DXの仕事にも通じていると感じます。
あと、アブダビの世界大会で優勝したこともあります。
カテゴリーは細かく分かれていますが、“世界一”の称号をもらえたのは嬉しかったですね。
—— 研究者であり、世界王者。なんという二刀流(笑)。

「サーフィンは、“待つ力”を教えてくれた」
—— 柔術の話で、サーフィンの話が出てきました。
そうなんです。柔術を始める前は、大学院の同僚や友人と毎週末海に行ってました。
サーフィンって、実は2時間のうち波に乗っているのはほんの数分。
残りは、ずっと海を見ながら“待つ”んです。
その時間、何も考えない。波の動きだけを見て、呼吸を合わせる。
あの感覚は、いまの自分の思考スタイルの原点だと思っています。
—— “待つ”って、意外と能動的な行為かも知れませんね。
そうですね。焦って動いてもうまくいかない。
波を読む力って、相手を読む柔術にも、仕事にも通じるような気がします。
「ここで動く」「ここは待つ」——その見極めがすべてです。
「獣医の家で育ち、“問い”を学んだ」
—— そもそも島倉さんの原点ってどこにあるんでしょう?
実家が動物病院で、小さい頃から動物が周りにいました。
大学は日本獣医生命科学大学に進み、放射線学と腫瘍学を専攻。
犬のがん治療をテーマに放射線を使った研究をしていました。
最初は「実験が楽しい!」という単純な理由だったんですが、
研究室での日々を過ごしていて、問いの立て方が一番大事だと気づいたんです。
何を明らかにしたいのか。どういう道筋を目指すべきなのか。
そこが研究の本質であり、柔術で言う「型の設計」と同じかなと思います。
—— なるほど。島倉さんらしい、理論的なアプローチです。
研究をしていたころから、「論理的にものごとを理解すれば、何にでも応用できる」と考えていました。
それが今、DX豚舎の事業設計にすごく生きています。
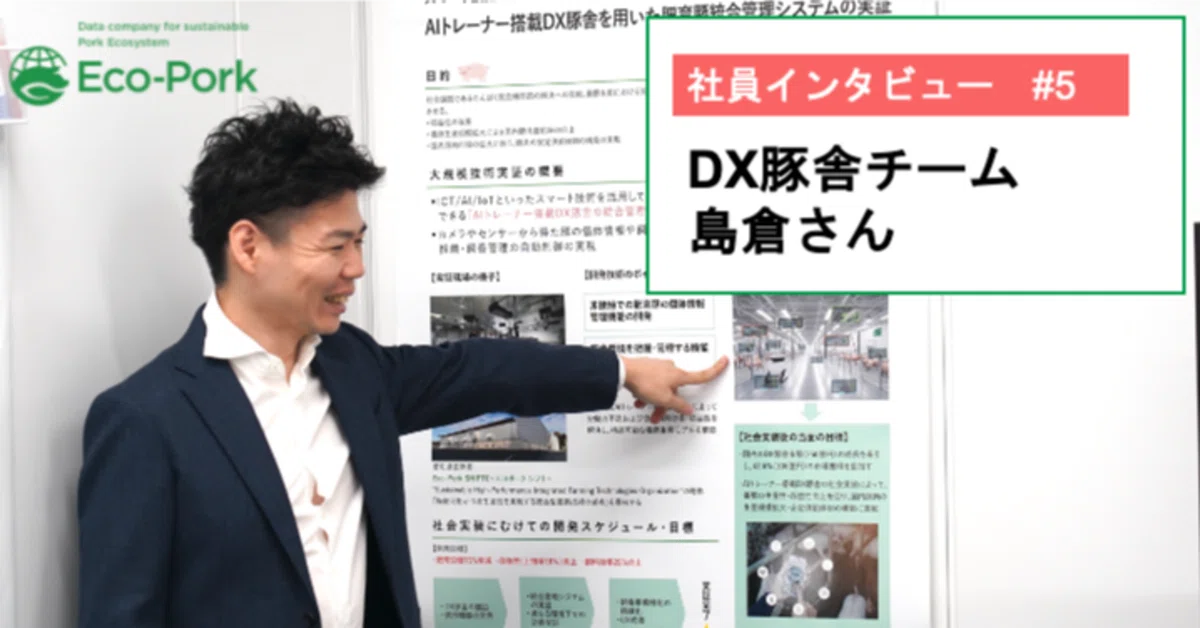
「妻へのA4プレゼンで決めた、Eco-Pork入社」
—— 研究の世界から、なぜ養豚DXへ?
研究を続けるうちに、「この成果、誰のためにあるんだろう?」と感じて。
もっと現場で役に立つことがしたくなったんです。
学生時代に酪農家でファームステイをした経験もあり、一次産業の現場がずっと心に残っていました。
そんなときに出会ったのがEco-Pork。
獣医師資格を持っていることもあり、研究が社会の役に立ちそうだと直感しました。
ただ妻には「なんで豚?」って言われました(笑)。
そこでA4二枚の比較表を作ってプレゼンしました。
「ここが一番おもしろい。自分の強みを活かして、社会のためになる仕事ができる」と。
今思えば、最初のプロジェクトは家庭内から始まってたかもしれません(笑)。
「DX豚舎では、“人に頼らず育てる仕組み”をつくる」
—— 現在の仕事について教えてください。
DX豚舎事業を担当しています。
目的は、“極力人に頼らず、データで豚を育てられる環境をつくる”こと。
畜産の人手不足を補うだけでなく、データを通じてコストと生産性を最適化する仕組みを構築しています。
センサー配置ひとつでデータの精度が変わる。
仮説を立て、実装し、検証して、修正していく。
研究の思考をそのまま現場に持ち込めるのが魅力です。
—— ブラジリアン柔術で出てきた「相手の動きに合わせて型を選ぶ」みたいですね。
そうかも知れません。
状況を見て、最適な手を選ぶ。
定石はあるけれど、現場では常に例外が起きる。
そこをどう読むかが勝負かな、と思います。

「構造化して前へ進める。そして、新しい定石をつくる」
—— 最後に、これから挑戦したいことを教えてください。
養豚DXを、ひいては養豚業や一次産業全体を“人が前のめりになる仕事”にしたいです。
現場で成功した仕組みを型に落とし、誰でも再現できるようにする。
研究でも柔術でも共通しているのは、定石を疑って、次の定石をつくること。
やり方を少し変えるだけで、世界は動く。
その変化を見たいですね。
最後に
柔術で磨いた「構造的思考」
サーフィンで得た待つ力」
獣医学で培った「問いの立て方」
島倉さんは、それらを一つの流れとして集約させて、Eco-PorkでDX豚舎事業設計に活かしています。
Eco-Porkにはさまざまな経歴を持った仲間が集まり、養豚業界のDXや社会課題解決に挑戦しています。

/assets/images/14717060/original/92f9c5d8-c05d-49fb-b5b2-248133226e60?1696242204)


/assets/images/14717060/original/92f9c5d8-c05d-49fb-b5b2-248133226e60?1696242204)
/assets/images/14717060/original/92f9c5d8-c05d-49fb-b5b2-248133226e60?1696242204)

