- 長期インターン生募集
- フルスタックエンジニア
- 営業職
- Other occupations (3)
- Development
- Business
- Other
こんにちは!
nocallの経営陣3名とマーケ担当インターンの中から2名ずつが社内の様子・サービス開発の裏話・生成AIなど最新のテックニュースなど、スタートアップのリアルをお届けしていきます!今回は「TomoCodeからのピボットの話 後編」です!
伸びるマーケットはどこか?市場選択の話
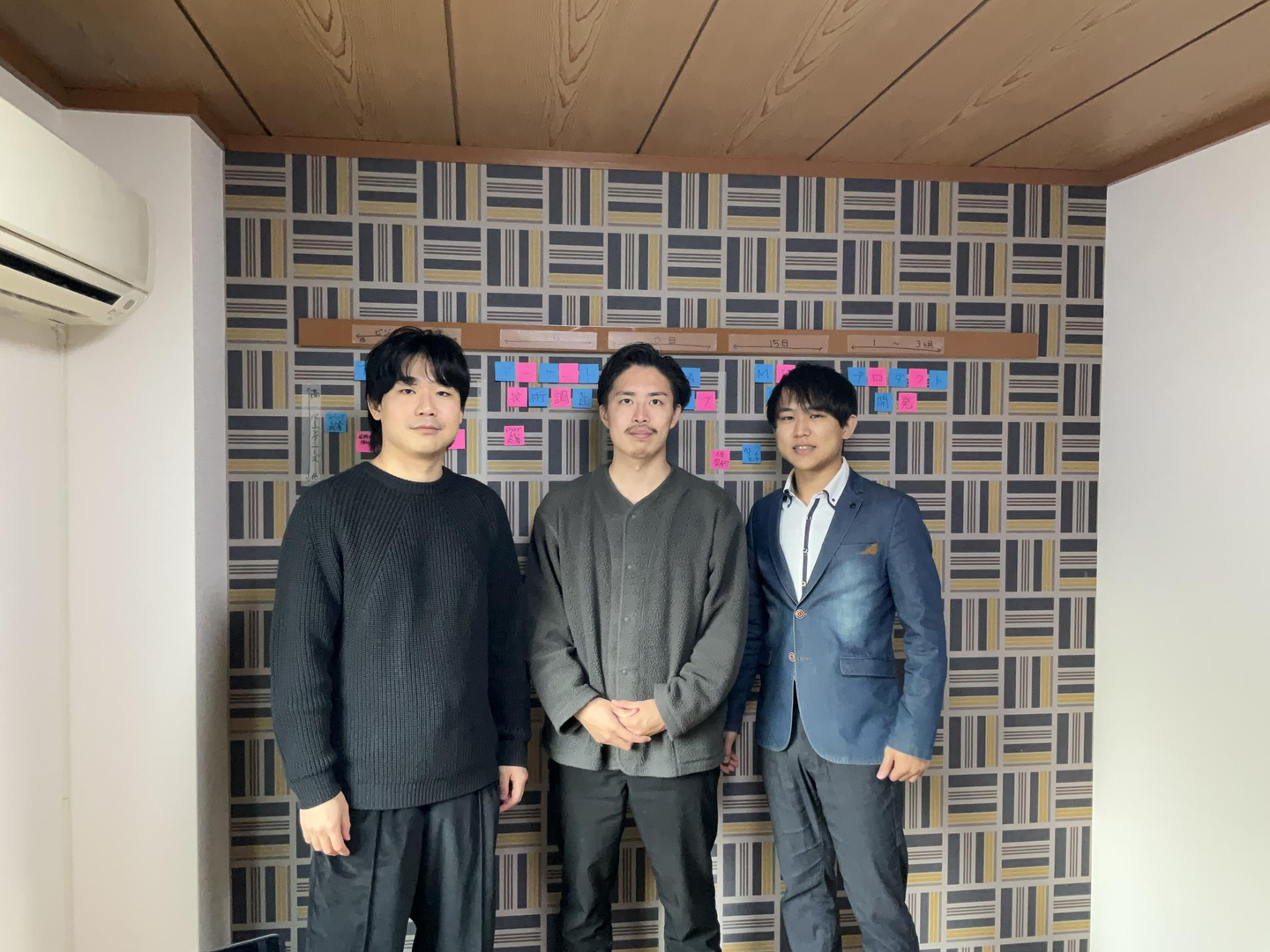
今回は「TomoCodeからのピボットの話 後編」ということで、前回の続きです。前回はEdTechに興味を持ってTomoCodeを始め、そこからなぜnocall.aiを始めるのかというところで、市場選択のお話まで前回は記載しました。市場選択するまでの間にも試行錯誤の小さなピボットみたいなのがありましたので、そこから今回はお話しします。マーケット選択としては、「生成AIと何でやるか?」って考えた時に、マーケットは伸びるものでやりたかったというお話しからです。
マーケットってエスカレーターみたいなもので、マーケットが沈んでいる時って全体が沈んでいってるので、下りのエスカレーターを逆走するみたいな感じになるんですよね。でも上りのエスカレーターって、立ってれば上がっていくんです。走ったらめっちゃ早い。
その分、チャレンジする方は多くいますが、大きくなっていくマーケットにはそれだけの有利がある。また、日本のスタートアップは海外に比べるとエスカレーター混んでないんですよね。インターネット出たての時の起業家って、今結構いいポジションについて偉くなったりしてますけど、学生起業してホームページ作ってましたみたいな人とか多いんですよね。そのときにそのポジションにいたから良い機会に恵まれる、っていうことすごいあると思うんです。
生成AIはあくまで技術の1個で、「IT」みたいな、カテゴリになっていくと思うので、その中でどの産業でやるかをまず考えていました。伸びっていう意味で言うと、日本は海外に比べてECの普及率が低くて、毎年かなりのスピードで伸びてるんです。ECとAIを両方やったらこれは勝てる、爆速のエスカレーターだなと思ったんですよね。
ディストリビューション・チャネルを見定める

事業を選定する上でもう一つ重要なことが、ディストリビューション・チャネルに乗っかることだと思ってるんです。日本語で言うと「配布」みたいな意味なんですけど、沢山の人に一気に広まるチャネルみたいなもの。GAFAMみたいなテック企業もそういうものに乗っかって大きくなってるんです。Amazonでいえばインターネットだし、FacebookでいうとAppStoreっていうディストリビューション・チャネルがあった。AI時代のディストリビューション・チャネルって何になるんだろう?って考えた時に、音声になるんじゃないかと。
サービスがどういう形でお客さんに提供されるかっていうところで、広げる速さが早いものが、これからは音声だってことですね。2023年は音声なんて注目されてなくて、アプリケーションは6割チャット、3割画像、残りはその他って感じ。でもチャットでのやりとりってこれからずっと続くのかな?って疑問で。
人間は生まれた時から喋れるようにできてるし、何千年と喋ってきてる。チャットって最近の話だし、打つの面倒じゃないですか。音声っていうものが次のインターフェースになるんじゃないのかなと思って。ディストリビューション・チャネルが音声であるということと、マーケットが生成AIとECである、という2つを軸にピボットしようとしたんです。
電話×AIに決定、nocall.aiのはじまり

話は戻るんですけど、結局、電話をかけてくる、かける、っていうマーケットの需要のほうがめちゃめちゃ大きいと思ったので、ECは一旦無視して、電話のユースケースの方にフォーカスしてnocall.aiを2ヶ月くらいで作ってリリースしました。
生成AIだとやりとりっていうもの自体が省略化されて、聞きたいことだけ聞けばよくなるんで、秘書雇ってるみたいな感覚に近いですよね。秘書に「あれってどう?」「これやっといて」って言えばあとは勝手にやってくれるみたいな世界観になると思ってます。
生成AIで電話サービスをするにあたって架電と受電があると思いますが、nocallaiは架電に特化してるんですよね。生成AIの電話って、コールセンターのオペレーター対応を自動化するみたいな受電のイメージをされるけど、うちはそうではないんです。なぜかというと、受電側だとめちゃくちゃハルシネーションを起こすことに気づいたんです。これが一番大きいですね。
受電はAI的に難しいんです。AIに情報を持たせるのって基本的にFAQ情報のみなんですね。質問する側が無限のパターンで質問してくると、それに答えられる情報がなくいとそれっぽい嘘を返答してしまうのが生成AIの課題で。正しくないかもしれないことをとりあえず返すのに価値があるのか?と。
架電であれば、FAQ情報の他にトークスクリプトもあるんです。例えばカーディーラーの車検のリマインドで使ってもらってたりするんですけど、「◯◯様ですか?そろそろ車検の時期になりましたのでお車の調子見させていただきたいのですが、いつ頃ご都合よろしいですか?」みたいに喋ることが決まってたりするんですよ。
そうすると振れ幅がほぼほぼなくて、途中で何か質問されてもFAQ情報である程度答えられるから、圧倒的に精度が高くできる。なので生成AIができることをベースに考えると、今は架電のユースケースがデカくていいなというところでしたね。
あともう1個あるとすると、 架電は売り上げるを上げる行為で、受電はコストカットなんですよね。将来的に受電もやりたいとは思うし、日本の労働生産性とかを考えるとやるべきだと思っていますけど。架電はこれまでリーチできていなかったお客さんにAIがリーチして売上に貢献するので、導入としてもコストカットよりは売り上げUPの方がサービスとしては良いなと思いました。
架電だからこその難点としてはユースーケースがイメージしてもらいにくいとことかありますね。普通の人はAIから電話なんて考えないですよね。最終的に、電話に出る人がどのくらい柔軟に対応できるか、っていうのが一番大きな課題なんじゃないかと思うんです。
そこは、今後よりどう人間に近づけていくかとか。今の話良いPRになったなと思ったんですけど、今すでに人間と勘違いされるくらい近いクオリティにはきていますよね。画像生成もそこに近づいてるし、そういうものになっていくのが一つの解だと思います。
アメリカとかはほぼAIで答えるのが当たり前になってますね。コールセンターとかまだ人がやってるのかって、シリコンバレーの人とかに言うと驚かれます。カルチャーとして浸透させていくってことですよね、人が足りなくなってるのが現状なので、そうせざるを得なくなっていくなとは思います。
人間の方がAIに対応できるようにするっていうのは、習慣を変えるような問題なので、うち1社でやるというよりは社会のムーブメントの話だと思っています。うちで取り組むのは、人間かAIかわからないような精度の追求だと思っています。、技術的に可能でもリソース不足で世の中にまだ出せてないことってまだあるので、ガンガン実装していきたいですね。
/assets/images/20462376/original/01b6bff5-7ad1-474a-9690-53d579d3ecd4?1739842882)
/assets/images/20462376/original/01b6bff5-7ad1-474a-9690-53d579d3ecd4?1739842882)

/assets/images/20462376/original/01b6bff5-7ad1-474a-9690-53d579d3ecd4?1739842882)
