【創業15周年 代表インタビュー】京都から「創る、つなげる、届ける」。コンテンツ企業支援で見えてきた会社の未来図
2023 年に創立15 周年を迎えたディレクターズ・ユニブ(以下:DU)。会社がこれまでどのように道を切り拓き、ここからどこへ向かうのか─。共同代表・板倉と小澤による周年記念対談です。
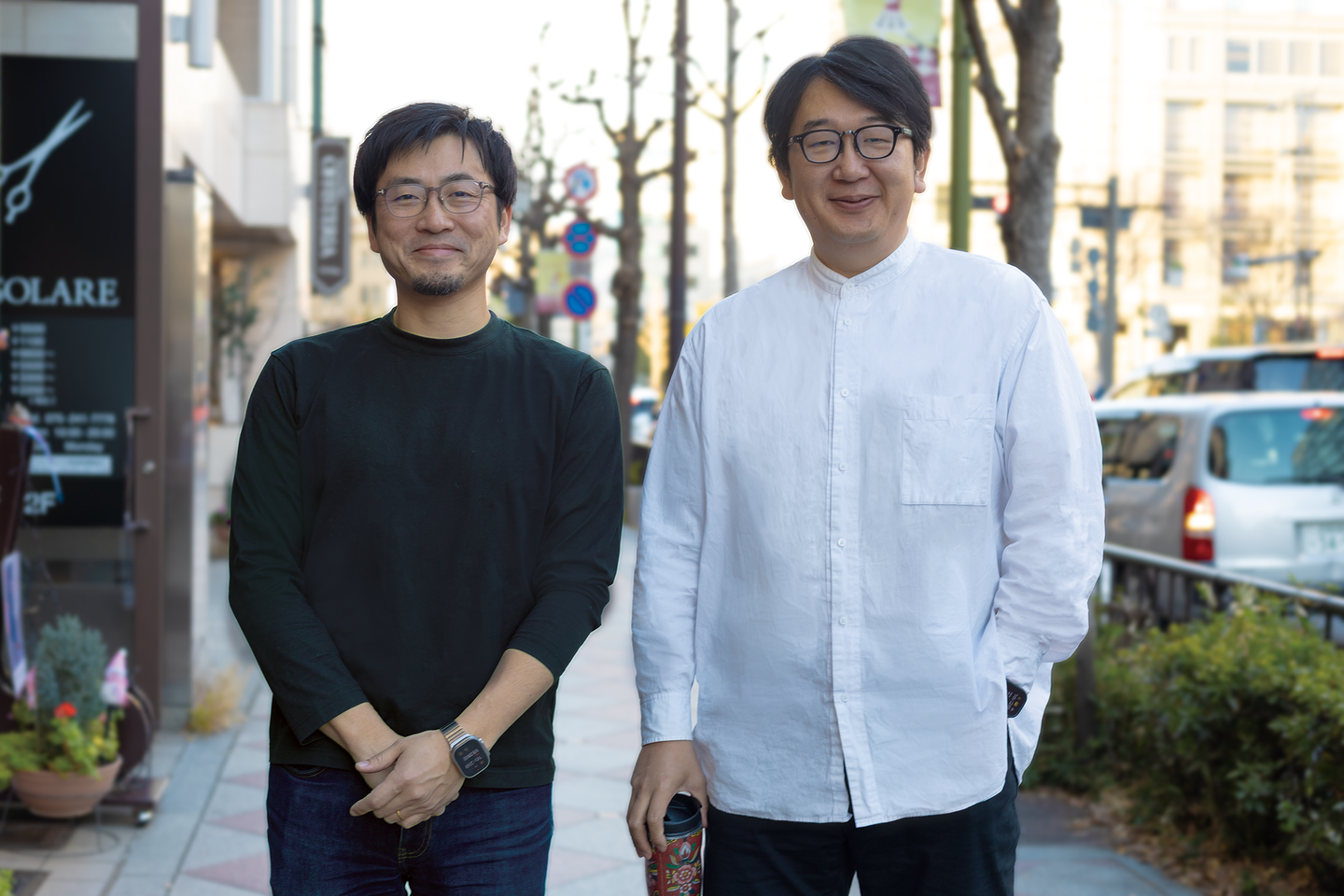
前職の縁がつないだ初期のコンテンツ事業
―まずは、お二人がコンテンツ事業に関わるようになったきっかけから教えてください。
板倉:僕は元々大学コンソーシアム京都で働いていて、在職時は「京都国際学生映画祭」の事務局担当だった。そのつながりで京都の映画関係者と知り合いになったんだけど、小澤と一緒にDUを立ち上げた25、6 歳の頃、京都フィルムメーカーズラボ※1 や京都ヒストリカ国際映画祭※2を立ち上げる話が京都府で持ち上がったんだよね。そのときに京都文化博物館の学芸員・森脇清隆さん※3が僕を推薦してくれて、仲間に入れてくれたのが、今のDU の仕事につながるきっかけかな。
小澤:当時はどこの馬の骨ともわからない奴にできるのか、みたいな空気もあったよね。
板倉:そうそう。でも僕はそういう懐疑的な人に対してもわりとはっきり意見を言うタイプだったから、太秦にはない新たな“ピース”として面白がってもらえたのかも。ちょうど同じ頃、太秦で出会った東映の髙橋剣さんのプッシュもあり、映像産業振興機構(VIPO)※4の京都事務所をDU で引き継ぐことにもなった。それが2010 年のことで、その頃から京都府のコンテンツ産業振興に近いところで仕事をすることが増えていったんだと思う。
※1…撮影所での時代劇の撮影や講義を通し、国内外の若手映像作家を育成するワークショップ。
※2…歴史映画に特化した国際映画祭。2025 年に第17 回を迎える。
※3…京都文化博物館の映画担当にして※1、※2 の主要運営メンバー。
※4…日本のコンテンツ産業の振興を目的とした団体。2010 年~ 2016 年までDU が京都事務所を運営した。

京都の企業支援で見えてきたコンテンツの現在値
― 2016 年には京都クロスメディア推進戦略拠点(KCROP)※5 の運営も始まりました。京都のコンテンツ関連企業やクリエイターの支援を行うなかで感じることはありますか?
小澤:最近思うのは、京都発のコンテンツが作られ、世に出ていく仕組みがもっと必要だということ。京都はゲーム企業は多いけど、テレビ関係の就職先は少ない。だから学生たちがせっかく芸大や映像学部で学んでも、地元で就職先が見つからずに東京へ出ていってしまう。一番熱量の高い「何か作ってやるぞ」という時期を京都で過ごしてもらえないのはもったいないなと思う。一方で、今は大手企業に就職しなくても情報発信できる時代だから、個人やインディー※6で特色あるコンテンツを作って、発表していくことはできるはずだとも思う。
板倉:映像コンテンツは大手と個人が作るもので2 極化してきていて、その中間のインディー層がなくなってきていると感じる。ゲームはインディーというジャンルが確立されているけど、アニメと映画はインディーでの制作がまだまだ難しい状況にある。
小澤:僕らが学生の頃は、小劇団や映画サークルが京都にもっとたくさんあって、そこからインディー系の映像コンテンツが生まれる流れもあったと思う。でもYouTube が流行し始めて、そうした活動が一気に衰退していった感はあるし、インディー映画よりも“バズる動画” が注目されるようになっていった。まぁこれは京都だけの話じゃなくて、全国的な話だと思うんだけど。
※5…京都府が設置したコンテンツ産業支援拠点。京都発のコンテンツ制作やクリエイターのネットワーク作りを推進している。
※6…広義あるが、ここでは個人ではなく、小規模な制作チームや独立系の団体が自主的に作品を制作・発信するスタイルのこと。
※7…京都映画賞の関連企画として開催されている野外映画上映イベント。

―そうした流れの中でも『侍タイムスリッパー』など、低予算でもヒットする映画は出てきていますよね。
小澤:たしかにインディー映画は減っているけど可能性は拓かれてきてもいる。今はiPhoneでも4Kが撮れる時代だし、昔は100 人いないと撮れなかった映像が、少人数でも形になるようになったよね。
板倉:ただ、それでも東京以外にいて、映画で食べていけているのは限られた人だけ。要するに構造的にはプレイヤーが全然変わっていない。だから映画でビジネスしていこうという若い人がなかなか出てこないんだと思っている。
小澤:たしかに新陳代謝が起きづらい業界ではあるよね。でも、テレビにYouTubeという対抗馬が出てきたように、映画にも有料動画チャンネルみたいな対抗馬が現れて、少しずつビジネスの形も変わってきている感じはする。
野外上映という“自発的な”挑戦
―会社の新たな事業として取り組まれている野外上映について教えてください。
板倉:きっかけは、2018 年にロシアW杯を現地で観たことかな。屋外のスクリーンで観る試合がすごく気持ちよかった。
小澤:そうそう。ビール飲みながら皆で喜びを共有する雰囲気がよかった。
板倉:これまでの15 年間、誰かに依頼された仕事だけをやってきたから、何か自分たちが面白いと思うものを作ったり、お客さんに見せたりしたいという気持ちがあった。そこに京都映画賞の野外映画上映会「京都シネマスクエア」※7の依頼も重なって、少しずつ想いがかたちになってきている感じはする。
小澤:僕もここ数年でようやく「楽しい」と思える仕事ができるようになってきた感覚がある。元々DUは板倉と2 人でDVDを焼くような仕事から始まったけど、最近は企画段階からアサインしてもらえる仕事も増えてきた。これまで会社に蓄積されてきた信用が、ようやく実務につながっている感じがしてうれしいよね。
板倉:野外上映もクリエイティブの仕事もそうだけど、「京都発」や「地域密着」っていう言葉に甘えずに、府外の行政や企業からも選んでもらえるような会社になっていきたいと思う。そのためにはクオリティが大事。速さや便利さではなく、仕事の質で選んでもらえるようになりたい。

民間企業との仕事が生んだ社内の変化
―最近は民間企業からの依頼も増えているそうですね。
板倉:行政や学校法人は年度予算の制約が大きくて、そのなかでどれだけいいものを納品できるかが勝負なんだけど、民間企業は期間や予算に柔軟性があるし、企業ごとの“色”があって面白い。ここ数年で社内にディレクターが育ってきたのも、案件の幅が広がったからだと思う。
小澤:営業メンバーの存在も大きいよね。彼らのおかげで新しい顧客層が増えたから、求められるデザインも媒体も多様化して、制作メンバーの力も鍛えられてる。以前は皆が“何でも屋” だったけど、今はチームで動くようになって、少しずつプロフェッショナル化が進んでいる。
板倉:スキルの専門化が進み、人数が増えてくることで、セールスやデザイナーなどの職種・役割が明確化していくことはとてもいいこと。一方で、肩書きに自分をはめてしまい、成長が止まってしまうケースもよく見かける。社内では「いいもの、面白いものを目指す」という目的の上で、足りない役割や機能は積極的に皆でカバーし合う風土を大事にしたいなと思う。

「DU 発コンテンツ」というネクストステージ
―最後に、今後挑戦してみたいことを教えてください。
板倉:映画を作ったり、本を出したり、自分たちの媒体を作って発信したり、今ある技術を使って“DU 発” のコンテンツを世に送り出してみたい。映画はお金も人も必要だけど、時代劇とか作ってみたいと密かに思ってる。あとはワインを作ってみたい、本屋をやりたい、というのもあるんだけど、まずは今のメンバー構成で、自分たちが面白いと思えることができたらいいな。
小澤:僕はもっとドラマが作りたい。テレビドラマじゃなくて、ストーリーのある動画という意味でのドラマね。今まで仕事で作ってきた動画は情報をまとめるものやドキュメンタリーが多かったけど、ドラマ的な演出によって動かされる感情があるし、訴求できるターゲットも広がると思う。これから会社として、もっとお客さんに提案できる動画の幅を広げたい。
板倉:やっぱり色んな分野の人と仕事をして、知的好奇心を刺激されることが一番楽しい。会社の濃度をもっと高めて、インパクトのある仕事をしていきたい。

/assets/images/21899866/original/b570fa95-3c74-45d0-8e6c-d3429f391868?1756108152)


/assets/images/21899866/original/b570fa95-3c74-45d0-8e6c-d3429f391868?1756108152)

/assets/images/21899866/original/b570fa95-3c74-45d0-8e6c-d3429f391868?1756108152)

