目次
射出成形1級技能士への初挑戦
資格挑戦に向けての社内の雰囲気
実技試験と学科試験
社内の成形機を土日に自由に開放
実技試験を受検
射出成形1級技能士への挑戦が会社文化に
射出成形1級技能士への初挑戦
当社が国家資格に向けて初めて挑戦したのが、約15年以上前のお話です。中堅社員を中心に全社を挙げて挑戦する事になりました。といっても筆者は当時は入社しておらず、自分が入社する前の出来事になります。
会社としての初挑戦でしたので、当然ながら社内に有資格者がいる状態ではありませんでした。そのため自分たちへの自信が無く、有資格者の方へのリスペクトが強かったとの事です。もしかすると過剰すぎるくらいのリスペクトだったのかもしれません。他社様の技術者の方が工場見学にいらっしゃるといった話を耳にすると、「1級技能士の方がいらっしゃるから、勉強させてもらいなさい!」「1級技能士の方がいらっしゃるので、清掃をキチンとやらないとダメだぞ!」なんて言葉が飛び交っていたと聞きます。
そんな中で、当時の経営者から「皆で射出成形2級技能士に挑戦せよ」というお達しがあったそうです。もちろん社内にも一定の動揺はあった事と思いますが、会社内のメンバーの中には「先輩や上司たちから認められるチャンスだ!」とばかりに発奮した社員もいたのも事実です。そんな中で、当時の社長による定期的な社内の勉強会を実施したりしていました。皆で過去問を解いたりする中で、分からない問題に対してとにかく質問をぶつけていく。普段から勉強なんてしていなかったメンバーもおり、とにかく勉強習慣をつけるところから始まった2級技能士への挑戦でした。
タイトルには1級技能士への挑戦とかかれているのに、2級技能士への挑戦?と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、当時は本当に2級技能士への挑戦のつもりだったんです。
しかし発奮した社員たちの勉強への熱量や知識の向上がめざましかったとのことで、当時の経営者は「ここまで頑張るのなら、2級じゃなくて皆で1級に挑戦してこい!」という経緯で、目標が途中で1級技能士への挑戦へと変わる事になりました。しかし射出成形1級技能士の合格率は大体25%前後。大きく難易度を上げる事になったのは言うまでもありません。
資格挑戦に向けての社内の雰囲気
本格的に1級に挑戦するという雰囲気が出来上がると、業務中にも学科試験問題を相互にクイズを出しあうような雰囲気だったと聞きます。意外と1人で勉強しているよりも、こうやってクイズ形式で問題出し合っている方が頭の中で整理整頓されていくと思いますし、良い勉強方法だなぁと思います。
小さいお子さんがいらっしゃる家庭のお父さんなんかは、自宅のリビングでは勉強できる空気感ではなく自分の家のトイレに籠って勉強していた…なんてエピソードも耳にした事があります。皆さん必死だったんだと思います。社内の勉強会では過去問から抜粋した模擬問題なんかを解いたり、業務中には相互にクイズを出しあったりしながら社員さん同士の知識はみるみると身についていったのだと思います。
実技試験と学科試験
射出成形1級技能士という試験では、実技試験 と 学科試験 の2つの合格しなければなりません。
学科試験については筆記試験形式なので、受験勉強のように過去問を解いたりしながら知識を増やす努力を重ねていくことで、合格率を高めていきやすい部分はあります。しかし実技試験はなかなか事前に努力するのが難しいんです。
実技試験は何が難しいのか。1つ目のハードルとしては「制限時間のタイトさ」にあると筆者は考えています。
ものすごくざっくり言うと
指定された2種類の樹脂を使って、190分(3時間10分)以内に良品を確保し、試験開始前の状態に戻すという試験内容です。
それぞれ2種類の材料別で良品を各40個確保する必要があるのですが、1個の製品を確保するのに約1分ほどかかります。単純計算で40個×2種類×1分間=80分間はものを作るのに最低限必要な時間です。
もちろん良品を取るまでにも条件設定が必要ですし、金型交換をしたり、寸法測定したり、材料用意したり、さまざまな工程をテキパキとこなしていかないと、あっという間に時間オーバーです。
この射出成形1級技能試験において、受検者の約半数がこの時間オーバーによって打ち切り失格となってしまいます。つまり各作業においては頭で考えるよりも身体が先に動くくらいの熟練度が必要であり、しっかりと身体にしみこませる必要があるわけです。
社内の成形機を土日に自由に開放
実技に関しては日々の業務だけでなく、実際の実技試験のシミュレーションをしながら身体に覚えていくしかありません。そこで当時は受検者の皆に土日に成形機を開放し、各々が自由にシミュレーションができるようにしていました。
「この作業をしたら、次はこの作業をして・・・」
「この温度が上がるまでの待ち時間には、この数値設定をやっておけば時間短縮になるな・・・」
「この作業をちゃんとやっておかないと、安全面で減点される可能性があるな・・・」
「この作業時間を少しでも早くできるようにすれば、こっちに時間を当てられるな・・・」
そんなふうに実際の作業しながら時間経過も含めてシミュレーションをする事で、皆の実技試験のイメージは固まってきたのだと思います。難易度が高い試験ではあるし、全員合格できないにしても何とか自分は合格したい。そんなプレッシャーと戦いながら実技試験本番を迎えていたのだと思います。

実技試験を受検
当時は、会社としては計5名での受検となりました。実技試験は機械を使っての試験になるため、同時受検ではなく日にちがバラバラです。一人一人と受検していくこととなります。勉強したり、シミュレーションを一緒にする事はできても受検当日は1人で試験会場に向かっていくわけです。ドキドキですよね。
そして1人目の受検は当時の一番のベテラン社員さんがトップバッターでしたが、受検中に想定外のトラブルの発生があり、最後まで工程を完了させることができずに打ち切り失格となってしまいました。
「あの人でも、ダメなのか・・・やっぱり難しいんだな」
きっと、そんな空気感が会社内でも漂ったことと思います。
そんな中でも、これからの受検する後輩たちのために「自分が実施した際には、こういった想定外な事象が起きた」とか「これは本番で実際の自分の目で確認しながら、作業に入った方がいい」といった自分のトラブルをしっかりと後輩にバトンとして渡してくれたのです。
そんな中で2番手以降の挑戦者たちから、実技試験を終えるなり
「金型、時間内に無事に降りました!!!」
という喜びの声があがったりと、バトンを受け取った4名は時間打ち切りになることなく最後まで実技試験をやり切る事ができました。結果的に、最後まで実技試験をやり終えることができた4名は全員合格。初挑戦によって4名の1級合格者が出ることは素晴らしく、個々の皆さんの努力と会社のバックアップの両方があってこその結果だと思います。
射出成形1級技能士への挑戦が会社文化に
その後は会社内でも実力をつけてきたら、射出成形1級技能士および2級技能士に挑戦するという会社文化ができあがってきました。1級および2級技能士になることで、社内的にも1人前と認められるような風土もあるため、こうした資格取得を目標にすることで若手や中堅社員の社内の技術レベルの向上に繋がっていると思います。
実は筆者の挑戦は上記に記載した時の5人が受検した以降での久しぶりの挑戦となりました。社内的には多くの人が初回挑戦で合格している中で「自分も初挑戦で合格しなければ…!」といったプレッシャーが大きかったのは覚えています。1人での挑戦でしたが、無事に筆者も1発合格することができました。もはや、合格の喜びというよりも安堵感の方が強かったですね。
現在当社では1級技能士が7名。2級技能士が2名と当時から更に合格者を積み上げています。これからも社内技術レベルの向上に向けて、新しい射出成形技能士を育成して参ろうと思います。
/assets/images/5015970/original/180d86a9-9cd0-4ca8-9bd8-0d8dbd2a632c?1589429132)
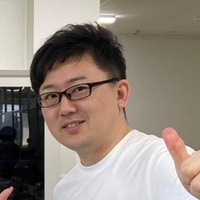
/assets/images/5015970/original/180d86a9-9cd0-4ca8-9bd8-0d8dbd2a632c?1589429132)
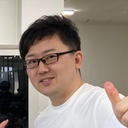

/assets/images/5015970/original/180d86a9-9cd0-4ca8-9bd8-0d8dbd2a632c?1589429132)

/assets/images/5015970/original/180d86a9-9cd0-4ca8-9bd8-0d8dbd2a632c?1589429132)

