【社員リレーインタビュー企画!】Vol.3:小倉 礁さん「環境×テクノロジー」で未来をつなぐ――小倉さんのキャリアストーリー
こんにちは!
株式会社LCAエキスパートセンター(LEC/レック)です。
今回はリレーインタビューの第三弾。
定例では毎回、自然・生物の豆知識で場を和ませる。そんなLECの癒し担当、小倉さんのキャリアストーリーをご紹介します!
🎤インタビュアー:金(キム)
目次
■これまでのキャリアと環境分野への道のり
■LCAとの出会いとLECでの挑戦
■仕事のやりがいと難しさ
■LCAエキスパートセンターの文化について
■5年後に目指すこと、そして未来の仲間に伝えたいこと
■リレー企画
■これまでのキャリアと環境分野への道のり
金: まずは、これまでのご経歴について教えてください!
小倉: 私は1988年にシステムエンジニアとして社会人生活をスタートしました。当時としては珍しく、社内に環境問題を専門に扱う部署があり、私はその20名ほどのチームに配属されました。
その部署では、大気や水質に関するシミュレーションをコンピューターで行い、国や研究機関、自治体からの依頼を受けて報告書を作成するのが主な仕事でした。当時は大型コンピューターでなければ計算できなかったので、自社のマシンを使って大気のシミュレーションを回し、結果をまとめて報告するのが最初に担当した業務でした。
金: 1988年にすでに環境シミュレーションをされていたなんて、本当に先駆者ですね!アメリカでも1970年代後半からようやく議論が始まった頃だと聞きました!驚きです!
小倉: 大学時代は生物学を専攻していましたが、大学院では陸域の環境アセスメントをテーマに研究していました。たとえば、道路を建設した際に周辺の動植物にどんな影響があるのかを調査するような内容です。
実は大学院生の頃、「この分野で本当に食べていけるのか?」と不安に思っていました。(笑)当時の生物系の環境コンサルといえば、工事の前後に生物調査をするような仕事が主流でしたから。
金: 私も大学院時代に似たような悩みを抱えていたので、すごく共感できます!
小倉: 私も最終的には、「自然保護か開発か」という二項対立ではなく、開発を進める側に立って、何か意味のあることができないかと考えるようになりました。そして、コンピューターを活用した環境分析という分野に可能性を感じて、入社を決めたんです。
金: 当時で20人規模の部署って、今の大企業基準で見てもかなり大きいですよね。
小倉: そうですね。当時は国や自治体と密接に連携していて、環境アセス以外の民間企業の仕事はほとんどありませんでした。衛星データを用いて大気中の二酸化炭素濃度を分析するアルゴリズムを開発する人もいました。そのような先端科学の面白いプログラムを作る仕事を研究者と一緒に考えているチームが近くにいました。
金: そのチーム出身の方々、今では宇宙産業の中心人物になっているかもしれませんね!(興奮して笑)
小倉: そうかもしれません(笑)。ただ、当時は環境関連の業務は今のようにお金のある省庁と連携していたわけではなく、予算も潤沢ではありませんでした。
それが2000年代に入った頃から、外圧でISO14000の取得が広まり、地球温暖化への対応が企業の課題として浮上してきたことで、民間企業からの環境関連の仕事が徐々に増えていきましたね。
金: その流れの中で、企業内の環境データを管理するシステムの開発も始まったんですね。
小倉: そうです。行政や研究機関においてコンピューターをベースにした新しい仕事を継続的に生み出すのは簡単ではなく、次第に民間向けのISO関連の業務が中心になっていきました。
また、環境アセスメントの仕事も、道路建設の前後に行う調査などが主でしたが、最終的には「場所が決まった後にやれる対策には限界がある」というある種の諦めもありました。モニタリングにも限界がありますしね。
金: そうだったんですね!私も研究者としてそういった限界を感じて、最終的にコンサルティングに転向したんです。
小倉: 私も同じです。世の中の動きとしては、例えば風力発電所をどこに設置するかを決める際に、植生の分布や生物多様性を考慮して、「このエリアの中ではここが一番適しているのではないか」と判断するような戦略的アセスの動きも出てきましたね。結局、場所が決まってしまうと、その後にできることはあまり多くないんですよね。
■LCAとの出会いとLECでの挑戦
金: 小倉さんがLCAという分野に初めて出会ったのは、いつ頃だったんですか?
小倉: 2000年頃ですね。当時、グループ会社内でも「製品の環境面をもっとしっかりやろう」という雰囲気があって、その流れの中で会社でLCAを少しずつ始めることになりました。
このインタビュー第一号である、胡さんは同じグループ会社の研究所にいらっしゃって、たしかCPUなどのコンピュータ部品のLCAを手がけられていたと思います。当時、かなり早い時期にコンピュータ関連でエコリーフ(EPD)を取得したのも、そのチームだったと記憶しています。
金: すごいですね、LCAの黎明期から関わっていらっしゃったんですね!胡さんもその頃から一緒だったんですね。
小倉: 直接、業務を一緒に行ったことはないのですが、いつの間にか知る間柄となり、仕事としてのコミュニケーションは取ってなく、アイコンタクトだけなんですが、そうなんです(笑)。当時は今のように精緻なデータベースがあったわけではないので、LCAの概念から一つひとつ学びながら始めました。見よう見まねでしたよ(笑)。
それに、当時は大気シミュレーションの仕事も並行してやっていて、その仕事を通じて、産業環境管理協会(今のSuMPO)とのご縁もできました。
金: そして、定年を迎えた後に、再びLCAの世界に戻ってこられたんですね?
小倉: はい。60歳で定年を迎えたあと、「これから何をしようか」と考えていたときに、たまたまLCA関連の求人情報を見つけたんです。以前から関わりのあったところだったので、「一度挑戦してみよう」と思って、履歴書を出しました。
小倉:最初は、LCAエキスパート養成講座を受講して、毎回課題を提出しながら数か月かけて修了し、LCAエキスパートとしての資格を取得しました。その後、1年間ほど専門家として活動し、昨年、LECの社員として入社することになりました。
金: 実は私もLCAエキスパート養成講座の第15期生で、全体の半分以上の内容をしっかり受けています!
入社と同時にLCAエキスパートとしてのトレーニングを受けられるのも、この会社の魅力のひとつだと思います。
これからの自分未来を、より幅広い業務にチャレンジできる選択肢があるのも嬉しいですね!
金: では、LCAエキスパートをしながら、今のLECにつながっているんですね?
小倉: そうですね。入社前は個々の業務毎に契約という形でLCAの専門家として働き始めました。その過程で、胡さんとも再会しました。同じチームで働くのは初めてでした。
金: ということは、LECが立ち上がったタイミングとほぼ同時に合流された、いわば初期メンバーなんですね!
小倉: そうですね。ほぼ同じ時期でした。「この会社なら、これまでやってきたことを続けられる」と確信がありましたし、何よりLCAという分野にこれからも関わっていたいという気持ちが強かったので、自然な流れで社員としての入社を決めました。
金: 今振り返ると、本当に素敵なキャリアの流れですね。当時は「システムエンジニア」という肩書きだったかもしれませんが、実際には環境ビジネスの最前線で活躍されていたんですね。
小倉:正直、自分のことを「システムエンジニア」だと思ったことはあまりないんです(笑)。
むしろ、環境と技術をつなぐ役割を担ってきたと思っています。そして今も、その延長線上で仕事をしている感覚ですね。
■仕事のやりがいと難しさ
金: 正直に聞きますが、「これは大変だな…」と思うことってありますか?それでも続けられる理由はなんでしょう?
小倉: 定年後も環境の仕事でご飯が食べられているということ自体に、やりがいを感じています。仕事そのものは本当に楽しいし、不満はあまりありません。
今はLCAを通じて、車載バッテリーや蓄電池、パーム油、海底ケーブルなど、社会を動かすテーマに関われていて、未知や予想外のことも多いけど、それがまた面白いんです。
金: まさに“アメリカを開拓するパイオニア”みたいですね!先頭を走る船団の一員という感じ!
小倉: ただ、その船団に乗っている以上、最新情報を常に勉強しないといけないのが大変ですね。お客様の業務すべてを知っている必要はないけれど、「LCAの専門家」として入っている以上、ある程度は理解していないといけない。そこがちょっとしんどいところです(笑)
小倉: 今ある規制やルールを読み解いて、「これからこうなるかもしれない」という仮説を立てて提案する。でも、制度がまだ整っていないから、相談されても「それ、誰が認証するの?」という状態だったりして…。
LCAの手法や結果の妥当性についても、認証機関がOKを出すかどうか分からない中で答えなきゃいけないのは、正直プレッシャーです。
金: 氷の張った湖の上を、足元を確かめながら歩いているような感覚ですね。
小倉: まさにそう(笑)。でも、そういう不確実性があるからこそ、やりがいもあるんです。
金: 危険があるからこそ、情熱も深まる…ですね!恋愛もそうですもんね。
小倉: ただ、年齢的にはあまり冒険したくない気持ちもあります(笑)。責任の所在も気になるけど、最終的には上司が責任を取ってくれるはずなので(笑)、若い人たちがどんどん挑戦できるように、私は支える側に回りたいですね。
金: 前職での経験が、今の仕事にどう活かされていますか?
小倉: 前の会社でも「担当は君だ!」と突然いろんな仕事を任されることが多くて(笑)、その経験が今の“薄氷を踏むような”プロジェクトでも役立っています。無茶ぶりにも慣れてますし、最終的な責任も自分で取るスタイルだったので、今の仕事にも自然と馴染めました。
大企業でも小さな会社でも、結局やることは同じだなって思います。理想の上司がどこにでもいるわけじゃないし、自分で段取りして、楽しんでやるのが一番。昭和世代としての“免疫”と“段取り力”が、今の仕事の武器ですね(笑)
金: 経験からにじみ出る真実ですね…!「大きな会社も小さな会社も、結局は同じ」って。(なるほど!)
小倉: 同世代の人と話していても、最近の若い人たちは「3年働いたら転職するのが当たり前」みたいな風潮があるみたいで。
私たちの時代は、結婚したら辞める女性が半分程度はいたし、育児で職場を離れるのも当然という空気がありましたが、特に男性は、入った会社で勤め上げるというのが主流の考えだったと思います。でも今は社会の考え方も変わってきてますよね。
新卒でも中途でも、3年で辞めるのが当たり前という時代。いろんな選択肢があるのはいいことだと思います。

上記写真:「これは無理だ」と思うことでも、限界を見極めながらお仕事に夢中になっている、小倉さんのカッコイイ姿✨
■LCAエキスパートセンターの文化について
金: LCAエキスパートセンターの文化を一言で表すと、どんなチームだと思いますか?
小倉: 年齢や役職に関係なく、自由に意見を言い合えるチームですね。
若手もベテランも関係なく、フラットに議論できる雰囲気があります。自分の意見を持っていて、それを伝えることが歓迎される文化です。
金: それってすごく働きやすい環境ですね。実際にそう感じるエピソードってありますか?
小倉:私自身も、年齢に関係なく意見を求められることが多くて、「まだまだ現役でいけるな」と感じます(笑)
金:業務の中で仕事の質を高めるために、意識していることはありますか?
小倉: やっぱり「お客さんと会話すること」「可能であれば現場に行くこと」ですね。お客様の工場を実際に見て、話を聞いて、現場の空気を感じることで、顧客とのコミュニケーション中でも共通認識が生まれやすくなります。
現場で得た気づきや学びを共有することで、顧客と自然と会話も増えるし、信頼関係も深まると思います。
■5年後に目指すこと、そして未来の仲間に伝えたいこと
金: この仕事を通じて、5年後にどんな社会が実現されていたら嬉しいですか?
小倉: 答えのない問いに向き合い続けることが、社会を少しずつ変えていくと思っています。「これは無理だ」と思うことでも、限界を見極めながら、できるところまで挑戦していきたい。
LCAという分野を通じて、社会にもっと広く貢献できるような仕事をしていきたいですね。
金: 小倉さんの仕事が広がれば、環境とテクノロジーの橋渡し役として、LCA業界を広げる影響を与えそうですね!(笑)
では 最後に、これからチームに加わる未来の仲間にメッセージをお願いします!
小倉: 表立って文句は言わないから、なんでも気軽に話しかけてください(笑)
年を取ると、誰も注意してくれなくなるんですよ。だからこそ、遠慮せずに「それ違うんじゃないですか?」って言ってほしい。
そうじゃないと、“触れてはいけない偏屈おじさん”になっちゃうので(心配+笑)
そうならないように努力しますので、ぜひ一緒に楽しく働きましょう!
■リレー企画
あなたの“仕事の相棒”3選!
今回は小倉さんの“仕事の相棒”を教えていただきます!

🦭 アザラシのライブカメラ(オランダの保護施設):写真左
最近知ったんですが、オランダにあるアザラシ保護施設のライブカメラを夜な夜なテレビの画面に映して見ています。
病気やケガをした子アザラシたちが元気になって海に帰っていく様子を見ていると、心が癒されます。模様で個体識別もできるようになってきました(笑)
業務のための精神バッテリー充電に!
※写真のアザラシはAIイメージです
▼アザラシ保護、研究施設Zeehondencentrum Pieterburenのyoutubeサイト
Zeehondencentrum Pieterburen - YouTube
📱 Biomeアプリ:写真右
自分で撮った写真をアップすると、昆虫や植物の種をAIが判別してくれるアプリです。不思議な生き物たちを集め、一緒に冒険したり図鑑にまとめたりする某人気ゲームがありますが、そのリアル版みたいで、自然観察が趣味の私にはぴったりです。
▼株式会社バイオームのいきものコレクションアプリBiomeサイト
いきものコレクションアプリBiome(バイオーム)で、いきもの探しの冒険に出よう! - 株式会社バイオーム
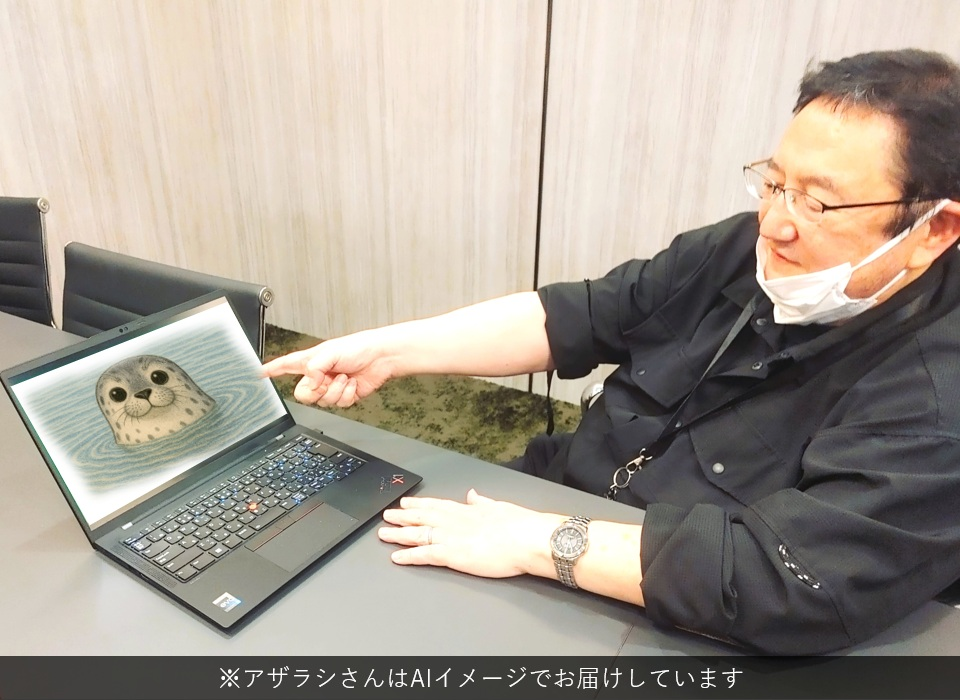
上記写真:この子で癒されたら、どんなに大変であろうと次の業務も大丈夫!
※写真のアザラシはAIイメージです
~編集後記~
今回のインタビューでは、小倉さんの圧倒的な経験値と、変化を楽しむ柔軟な姿勢に触れることができました。
「正解がないからこそ、考える!楽しい!不安でも未来を期待する」「年齢に関係なく、なんでも言ってほしい」——そんな言葉の一つひとつに、LCAという専門分野に対する誠実さと、LECというチームへの愛情がにじみ出ていました。
そして、アザラシのライブカメラに癒される姿からは、どこか“少年の心”を忘れない小倉さんの一面も垣間見えました。
次回のリレーインタビューも、どうぞお楽しみに!
/assets/images/21750850/original/5a81ea55-bd4d-418e-8df4-cce02d3f5d3d?1754288924)
/assets/images/21750850/original/5a81ea55-bd4d-418e-8df4-cce02d3f5d3d?1754288924)

/assets/images/21750850/original/5a81ea55-bd4d-418e-8df4-cce02d3f5d3d?1754288924)
