- 機械学習エンジニア
- Digital Marketer
- 機械学習・データエンジニア
- Other occupations (1)
- Development
- Business
近年、AIやクラウド技術の発展によってこれまで人が行っていた作業の多くが自動化されていますが、「このままでは、自分のスキルが通用しなくなるのでは?」 と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。 ですが、心配する必要はありません。むしろ今こそエンジニアとしての価値を高めるチャンスなのです。
本記事では食いっぱぐれない人材になるための秘訣について解説していきますので、ぜひ最後までお付き合いください!
AIの進化によるエンジニア業界の変化

かつてのエンジニアの業務とは、システムやソフトウェアの開発、運用、保守など技術的なものが中心でした。また、コーディングなども手作業であることが多く、バグの修正や性能改善も彼ら自身が細かく対応したため職人のような印象が強く、特に黎明期はその技術が何よりの価値であったわけです。
具体的な変化の例としては、2000年代以前は要件定義から設計・開発・運用まで長い期間をかけて開発を進めるウォーターフォール開発が一般的であったのに対し、2001年、短期間のサイクルで開発とリリースを繰り返すアジャイル開発というモデルが普及し始めたことなどが挙げられます。
このように開発形態の選択肢が増え、最適化される一方で、エンジニアの仕事は減りつつあります。自動化によってAIが人間の仕事を肩代わりし始めた、これは人にしかできない仕事が減ったということです。こう言うとエンジニアの価値が低下したように思えてきますが、実際には違います。
AIに任せられる業務が増える=エンジニアがより高度で創造的な仕事に集中できるということ。
つまり、これからのエンジニアには、AIを活用しつつ「人にしかできない役割」を担う力が求められているのです。
次章にてAIと人間それぞれの得意分野からエンジニアの業務を分析し、続く章で【これからのエンジニアに求められるスキル5つ】を解説します。そして最後に食いっぱぐれないエンジニアになるために必須の心構えを確認しましょう!
AIの得意分野・人間の得意分野
AIの得意分野
人工知能とは、人間の知識やデータなどの膨大な情報を記憶しており、それらに基づいて定型化された作業を行える機械です。バグの検出やコードの最適化、データ処理、分析の一部など、単純なタスクであれば人間よりも速く、正確にこなすことができ、休みを必要としないため開発やメンテナンス程度のコストで半永久的に作業し続けることが可能です。
さらに、感情や疲労などによるブレがなくイエスorノーで判断するシステムの性質上、チェスなどの①「範囲」と②「矛盾しない絶対的ルール」が定められ、③「選択肢による行動決定が可能なフィールド」においてはAIが人間を上回ることも可能であると言えます。
つまり、AIは決められたルールに沿った作業を低コストで正確に、人間を上回るスピードでこなして、均質な結果を大量生産してくれるというわけです。
人間の得意分野
一方、人間は想像力や感情、独自の経験、応用力など、未だAIが持ちえない曖昧なものを備えており、これらは人間の進化に大きく寄与してきました。時には合理性や精度に欠けるものの、言葉や文明などものを新しく生み出すには欠かせません。また、実体を伴っているからこそできることも大いにあるのです。不確定要素の多い状況でも臨機応変に、その場に合わせて意思決定をして行動できるのは、個々の経験とそれに基づいた知識が存在し、物事の価値や基準を判断・実行できる人間だから可能なことですよね。
データから確率を算出して推測するだけでなく、それぞれの規律や倫理、意思に基づいて未知のもの、複雑な事象に対して自主的・能動的に働きかけられるということこそが人間の強みなのです。
つまり、人間は例外処理や修理、改善などAI運用に関わるサポート、対人関係を通じての問題解決などAIが100%活用されるための行動を起こすことができるのです。
ここまで、それぞれの得意分野について解説しましたが、そもそもAIとは人間が作ったものであり、適切な管理があってこそ真に力を発揮するものです。AIの得意分野を理解し、それをうまく活用しながら、人間にしかできない役割を担うエンジニアが今後の主役となるのです。
ズバリ!これからのエンジニアに求められる5つの力
AI時代に活躍するエンジニアには次の5つのスキルが欠かせません。

AI活用力
これまではシステムを作ること自体がエンジニアの主な業務でしたが、その技術も大きく発展してきましたし、今後さらなる進歩や変化が起こることでしょう。この先の未来を見据えるエンジニアに必要な力の1つ目は「AI活用力」です。AIを活用して、より良い結果を生み出せる力が必要です。
ただ開発するだけではなく、どんなAIをどう使うか、どんな使い方ができるのかまで考えられる、技術力だけではない価値を持つエンジニアを企業は求めているのです。
創造力
「新しいアイデアなんて思いつかない…」そう思ったことはありませんか?実際、アイデアの創出というのはとても難しいことです。ですが、既存のものを素材にしてみるのならどうでしょう。実は、既存の技術や発想を組み合わせるだけでも、十分な創造力になり得ます。ゼロから生み出さなければ!と思い込まず、柔軟に考える力がカギです。
論理的思考力
AIが導き出したデータをどう活かすかは、エンジニアの腕次第。 データの本質を見抜き、正しい判断をするための論理的思考が重要です。また、これに似た批判的思考の習得も大切です。論理的に考えて妥当な結論を導き出す力に加えて、事実をベースにその本質を見極める力を身につけることで矛盾や漏れを抑制し、結果をより確かなものにすることが可能です。
課題解決能力
課題解決能力とは、目標の達成に向けて行動する中で生じる課題を解決していく能力を指します。また、課題に対する適切な把握と適切な対応、それらを実現する総合力を指します。会社やチームが1つの目標達成に向けて仕事に取り組むときやAIが予測できないトラブルが起きた時、解決策を導き出せるのは人間です。 問題を冷静に分析し、適切な対応を取る力が求められます。
コミュニケーション能力
「技術がわかれば十分」と思っていませんか?人間関係を構築する上でも必要となる力ですが、クライアントとの折衝や、チーム内での不和を生じないように折り合いをつける事は重要ですよね。また、中には専門用語に詳しい方もいらっしゃるかもしれませんが、エンジニアではない方にもわかりやすく伝える力、正しく理解してもらえる力を身につけ、実践できなければなりません。
食いっぱぐれないエンジニアとは
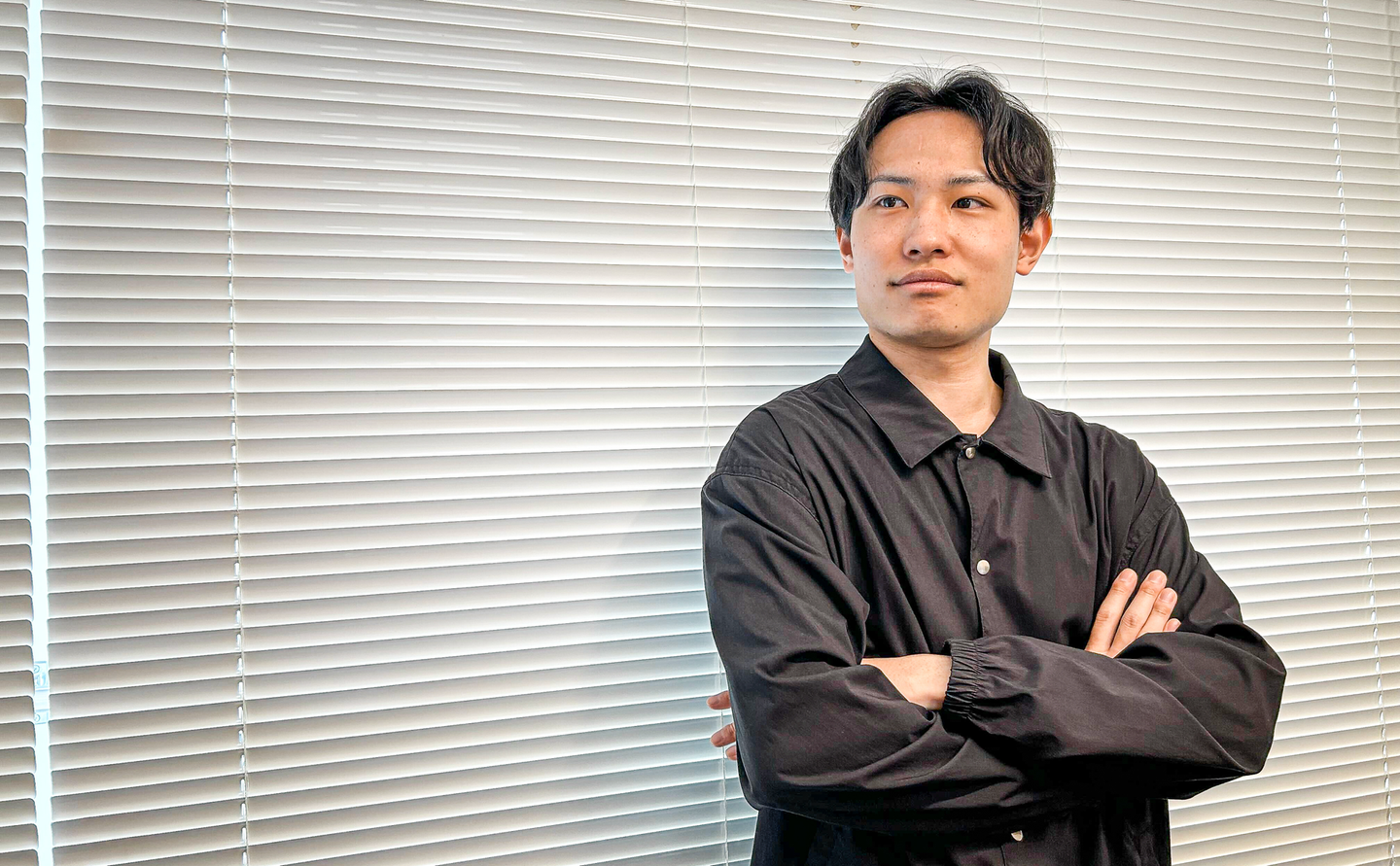
ここまで読んで、そもそも食いっぱぐれないエンジニアってなんだ?と疑問を抱いた方も多いかと思います。食いっぱぐれない、と一口に言っても人それぞれ、経歴も事情もさまざまですよね。そのため、ここではエンジニアとして生き残るために欠かせない、企業から「こんな人材がほしい!」と言われる人材が備えている心構えを2つお伝えします。
それは「上を目指す姿勢」と「経験を実力に変える意欲」です。
上を見て「自分には無理だ…」と諦めてしまう人と「まだこんなに伸びしろがある!」と考えられる人では、後者こそ企業にとっての良い人材であり、求められるエンジニアです。
また、これまでの経験をただの思い出にするのではなく、次のステップの糧として生かし、実力を身につけるという意欲が、あなたのスキルアップにつながるのです。
休憩しながらも着実に前に進み、通ってきた過程を意欲的に実力に変えて日々パワーアップする人材には日進月歩で進化してゆくこの業界に通ずる所があると思いませんか?
この記事では業界の変化から今後のエンジニアに求められるスキルや心構えについてまとめました。結論として、「AI時代で生き残るエンジニア」というのは「AIを活用するスキルを持ち、より創造的な、人にしかできない仕事に挑む姿勢を持った人」です。
最初から全てを兼ね備えている人というのはなかなかいませんが、持っていないものは全て可能性であり、現状を変えるのはあなた自身です。
変化を受容し、次は何ができるのか、その先を見る人材を企業は求めています。
Nucoであなたの価値を磨いてみませんか?
/assets/images/17033527/original/adf07eda-9151-44e3-bbfc-6d1193c0c364?1708089823)

/assets/images/19438646/original/c5431c90-ce56-447b-b293-73302ad700ab?1729045386)

/assets/images/17033527/original/adf07eda-9151-44e3-bbfc-6d1193c0c364?1708089823)

/assets/images/17033527/original/adf07eda-9151-44e3-bbfc-6d1193c0c364?1708089823)

