ZAICOでは、月に一度、エンジニアによるLT会を開催しています。今回は2025年10月24日(金)に行われた第二回ZAICO 社内LT会の様子をお届けします。
ZAICOのLT会は「最近の学び」「チャレンジ」「失敗と気づき」などの自由なテーマで1人あたり10分ほどで共有するイベントです。
今回のLT会では、4名のエンジニアが、モバイル、Web、インフラの領域で発表を行いました。技術的な課題解決から、開発体験の改善、実際に発生した不具合からの学びなど、実務に根ざした内容が共有された充実した時間でした。
iOS開発におけるUI KitとSwiftUIの共存(iOS:Fさん)
Fさんの発表はUI KitとSwiftUIという2つのiOS UIフレームワークの違いと共存についての発表でした。
UI Kitは歴史が長く安定している一方で、コードが肥大化しやすく、コンフリクトの課題も。
対してSwiftUIは宣言的で少ないコード量で書けますが、まだ一部機能不足もあるとのことで…現在、zaicoではUI Kitが主に使われていますが、SwiftUIも一部の画面で導入されている状況で「どちらかを選ぶ」ではなく、両者の強みを活かした共存が今後の鍵になりそうです。
【発表者Fさんからのコメント】
あまり人前で話するのが得意な方ではないので、慣れる事も兼ねて「ミスっても社内LTやし、それも次に活かせばいいか」という気持ちで今回のLT会に手を挙げました。
なのでテーマはとりあえず手を挙げてから考えました!
発表中は緊張しましたがみなさん真剣に話を聞いてくださり、並行してSlackのチャンネル内でコメントもしていただいてよかったです。
iOSエンジニアにとってかなり初心者向けの内容にはなりましたが、個人的な目的としては「webエンジニアの方に少しでもiOS開発について知ってもらおう」という目的だったので、「iOS側のUIってこうやって実装しとるんや」といったコメントもいただき今回LTを行った目的は達成できたのかなと思います。
今後も機会があれば是非登壇したいと思います!
入庫処理に潜む“49.999個問題”とdecimal.jsによる修正(Web:Sさん)
実際にzaicoで起こった不具合からの学びを、Sさんが発表してくれました。単位換算機能を利用して入庫した際、換算計算の結果が「49.999999999999999個」と表示されてしまう問題。その原因は浮動小数点の誤差でした。
この問題に対し、decimal.jsという高精度計算ライブラリで計算することで、誤差を防ぐよう修正しました。金額や在庫数量などの正確性が求められる計算では、浮動小数点の特性を理解し、適切なライブラリを利用することの重要性がチームに共有されました。
在庫管理の精度を守る、まさに“縁の下の力持ち”な改善です。
【発表者Sさんからのコメント】
LT会の募集があったので、話すテーマを思いつく前にやってみようと手を挙げました。
ある不具合対応で遭遇した浮動小数点の誤差について、なぜ誤差が発生するのか、どう防いだかというテーマで話しました。
業務の合間を縫って準備するのは少し大変だったのですが、Claudeと壁打ちしながら内容を整理していくうちに、資料づくりが楽しくなっていきました。
また、発表の準備を通して、起きていた不具合への理解がより深まりました。不具合から得た学びを他の方に共有することができてよかったです。
当日、LTに対して反応をいただけてとてもうれしかったです。またやりたいと思います!
Railsエンジニアにとって快適なフロント開発体験を実現(Web:Nさん)
Nさんからは、RailsのERBテンプレートのように、Vueを扱う工夫が紹介されました。
通常Railsでモダンフレームワークを導入すると、API通信や状態管理の設計が煩雑になりがちです。そこでRailsの自動レンダリングやインスタンス変数共有の仕組みをVueでも再現。結果として「ERBを書くようにVueを開発できる」快適な体験を実現することができました。
ただし課題もあり、コントローラーをページ表示用とAPI用に分ける必要があるなど、まだ試行錯誤の段階。
それでも「Railsになれているエンジニアが快適にフロントを書ける」工夫は、チーム全体の生産性向上に繋がる、と期待の持てる発表でした。
【発表者Nさんからのコメント】
今回が人生初LTでした!
素直にやってよかったですし、機会があればぜひまたやりたいです!
今回、自分は他の方が過去に実装した、Railsへのモダンフロントエンドフレームワークの導入やその構成について内容で発表しました。どのような意図で今の構成にしたのかを調査して自分の言葉で紹介することはとても勉強になりました。
発表中やその後にもリアクションをくれたり、実装者の方から当時考えていたことなどのコメントをいただけたのが嬉しかったです。
OpenTelemetryで“見える化”を推進(インフラ:Tさん)
「オブザーバビリティ(観測可能性)」という言葉を聞いたことがありますか?
Tさんからは、システムの状態をトレースから観測できるようにする取り組みが紹介されました。
zaicoではログやメトリクスは取得できていたものの、トレースの観点はまだまだ未整備でした。そこで導入したのがOpenTelemetry。
メリットは
- トレースの実装などを標準化できるので知見が蓄積される
- APM(Application Performance Monitoring)ツールなどの切り替えが容易になる
これにより、最近のDBアップデート作業ではユーザー視点で影響を定量的に把握でき、安心して対応できたとのことです。
「仕組みが動いている理由を説明できる状態」を作る——
まさにオブザーバビリティの本質を体現する発表でした。
【発表者Tさんからのコメント】
今回のLTでは「OpenTelemetryでオブザーバビリティを高めている話」というテーマでお話しさせていただきました。
これまでAPMツールとしての情報は社内で共有していましたが、その基盤となる実装であるOpenTelemetryについては十分にお伝えできていなかったため、このようにエンジニアが集まる場で共有できて良かったです。
この機会に一人でも多くの方にオブザーバビリティへの関心を持っていただき、少しずつ社内に浸透していけば嬉しいと考えています。今後も機会があれば、積極的に参加し発信していきたいと思います!
おまけ
今回のLT会には、代表田村さんもリスナーとして参加していました。
「発表のレベルが高く、多くのことを学べました」と発表者を労っていました。
来月のLT会は田村さんも発表者として参加するので、メンバーの期待値も上がっています!
今回のLT会も実務に即した発表で、有意義な時間となりました。
今後も定期的にLT会の情報を共有していきますね!



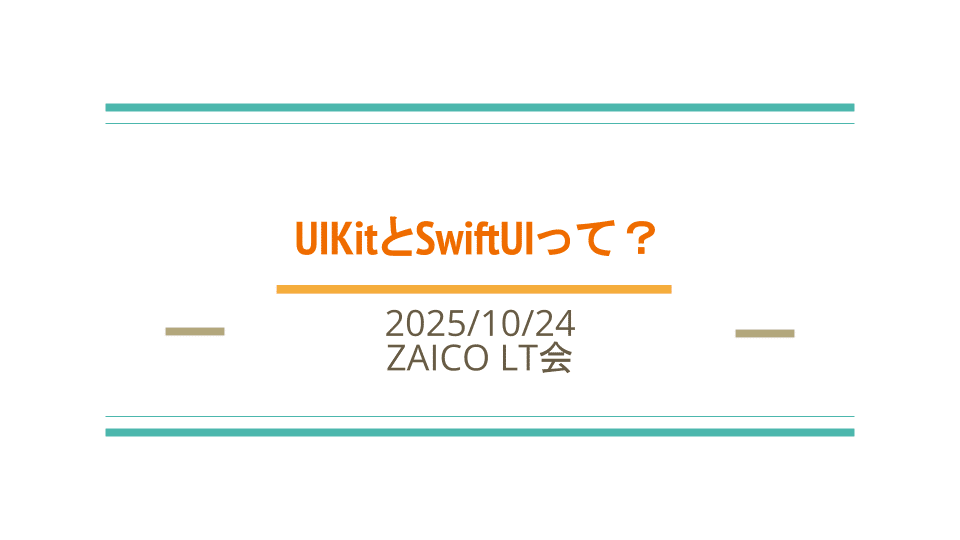
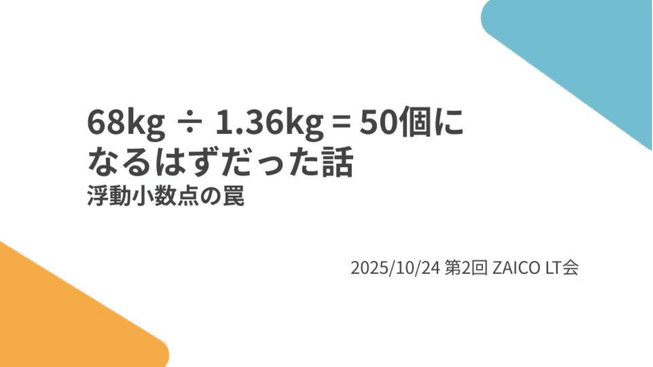
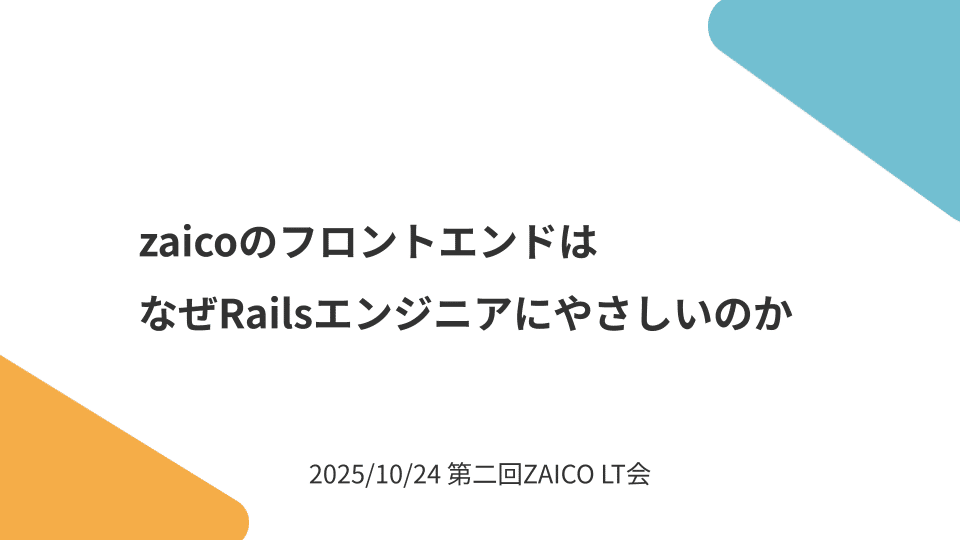


/assets/images/9769741/original/983753bf-ea12-4574-a215-8c144be95f3c?1656291198)
/assets/images/9769741/original/983753bf-ea12-4574-a215-8c144be95f3c?1656291198)

