建築部工事課 工事主任 中村 洋輔
「全部、お前に任せる」 そう声をかけられたのは、入社6年目の春。場所は福島、南相馬。ボランティア施設の建設現場だった。 形式上の“所長”ではなかったかもしれない。 でも、現場に立つのは自分ひとり。図面も工程も調整も、誰かが代わってくれるわけじゃない。 その日から、“自分で決めて、自分で動く”仕事が始まった。 今回のストーリーは、入社16年目の中村さんが語る“初めて現場を動かした日”と、 建築の仕事に向き合い続ける中で見えてきた「責任」と「誇り」に迫ります。
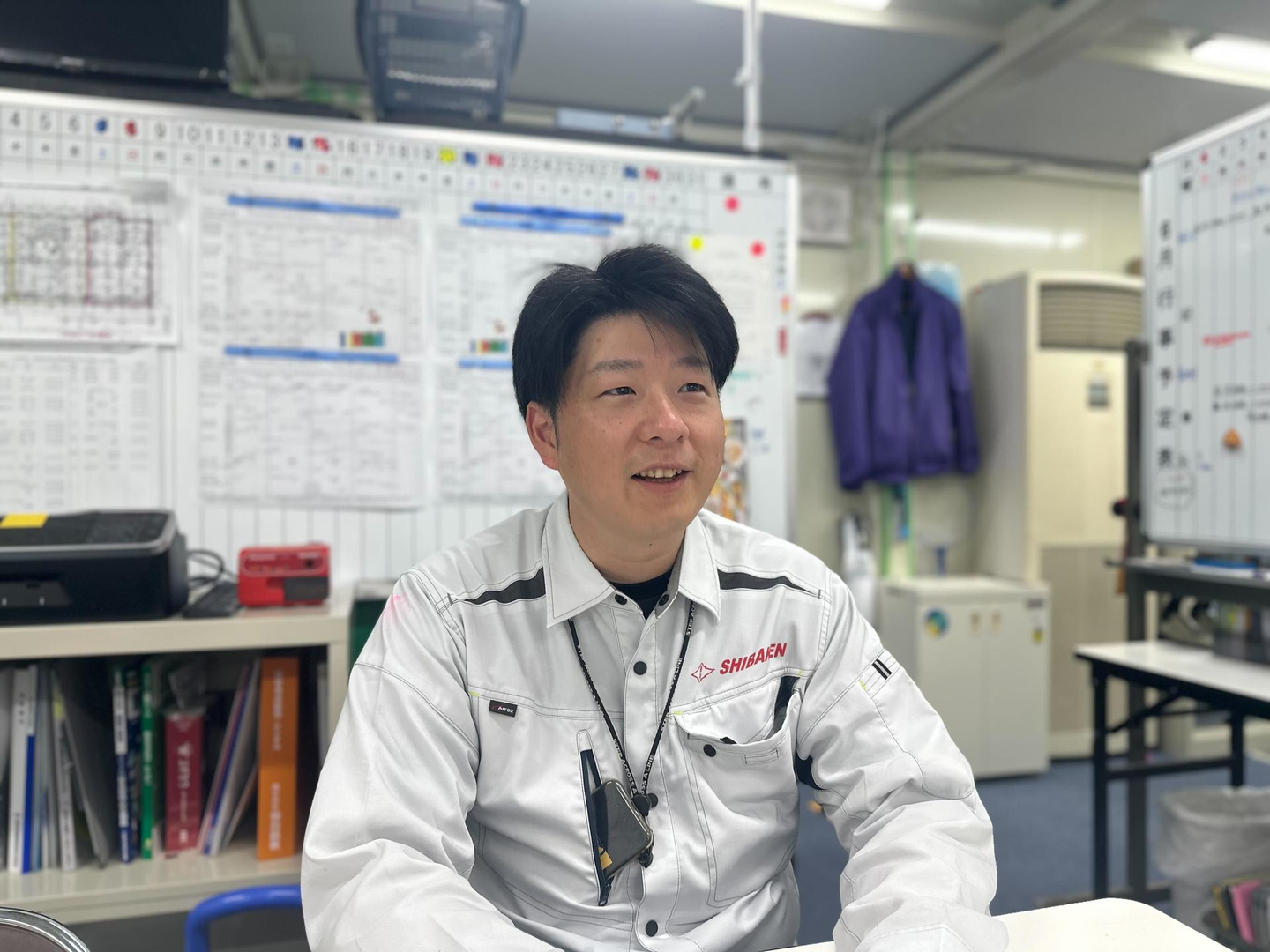
6年目、初めて“現場を動かした”日
入社して6年目の春。 場所は福島の南相馬。ボランティア向けの宿泊施設を建設する、数ヶ月間の現場だった。
「ちょうど自分の家を建て始めたタイミングだったんですよ。そんなときに、建築部の部長が現場事務所にふらっと来て、『中村、ちょっといいか』って。今でも覚えているんですが桜の木の下で、“こういう現場があるんだけど、お前に任せたい”って言われました」
驚きと同時に、どこかで来ると思っていた瞬間でもあった。それまで主に補佐的な立場で現場を動かしてきたが、いずれは自分も前に出なければならない。その“いつか”が、思ったより早く、自宅の新築を始めたタイミングでやってきた。
当時は妻と小さな子ども、そして両親と同居。福島への長期出張は決して軽い決断ではなかったが、妻は背中を押してくれた。
「行ってくれば?って、あっさり言われたんです(笑)自分としてはやってみたいという想いはあったんですが、反対されることも想像していました。家族は察してくれたのかもしれませんね」
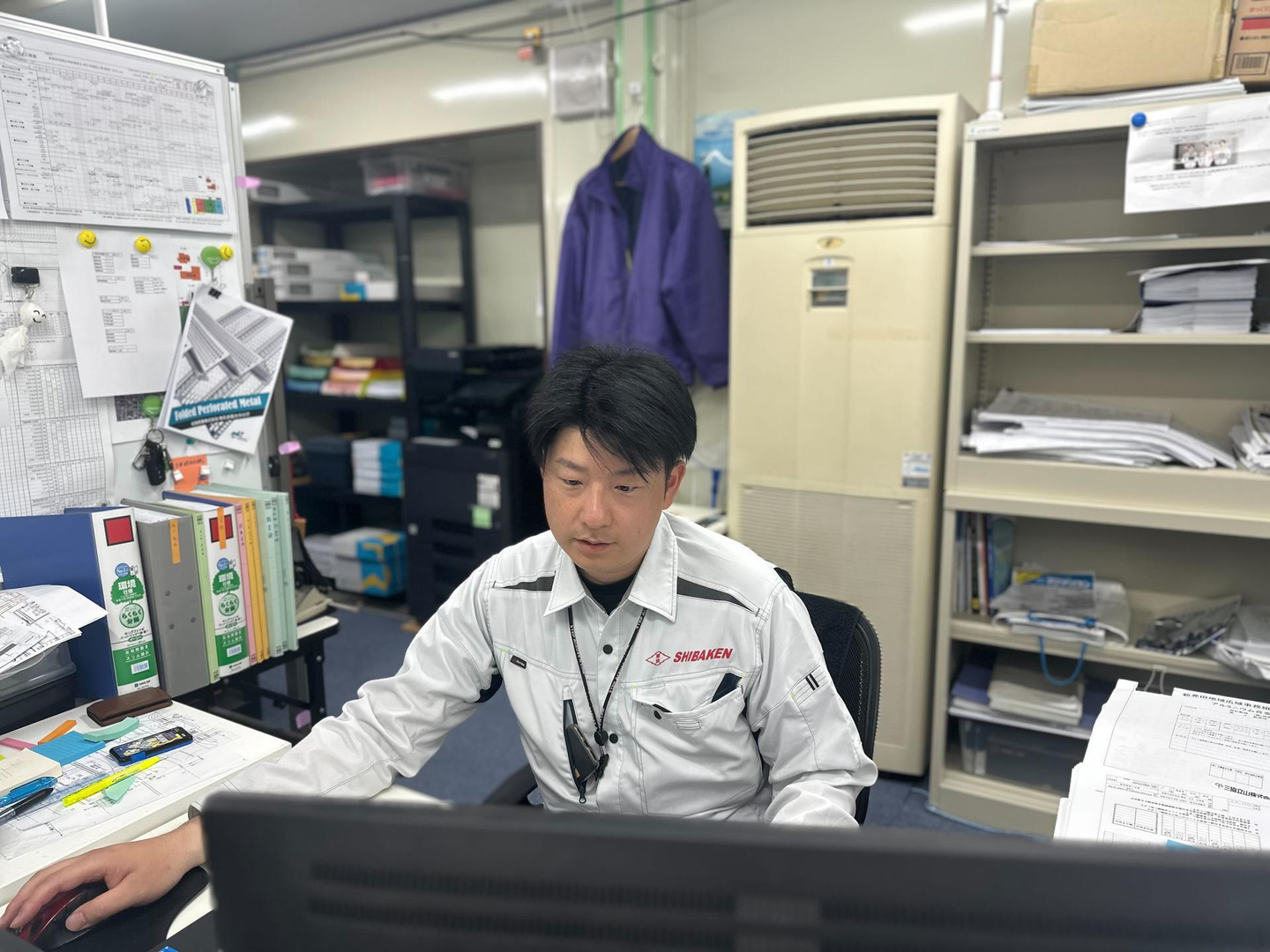
実質的にすべてを任された現場
形式上、所長という肩書きがついたわけではない。けれど、現場に常駐し、実質的な業務をほぼ一人で担当した。東日本大震災で被災した地域に建てられる、ボランティア施設の新築工事だった。
図面の作成、工程の立案、協力業者との調整まで、日々の判断と対応はすべて自分が担った。
「もちろん、社内の担当部署や協力業者さんのサポートもありました。でも、現場にいるのは自分だけ。図面を描いて、工程を組んで、職人さんと打ち合わせして…よくも悪くも、全部自分次第だったんですよね」
現場で初めて顔を合わせる協力会社も多く、距離を縮めるまでには苦労もあった。けれど「ちゃんと説明できるように」「信頼してもらえるように」――一つひとつ丁寧に積み重ねた結果、現場は大きなトラブルなく完了した。
「振り返ってみると、もっとこうしたいとか思う点はあります。でも、当時の自分としては“よくやったな”って言える現場でした」
自分の力で収めきったという経験が、中村さんにとってのひとつの“転機”になった。そして何より、自身が学生時代を過ごした福島県に、かたちは違えどもう一度足を運び、そこで役割を果たせたことに特別な思いが残った。
「市域は違うけど、4年間お世話になった福島に少しでも貢献できたとしたら嬉しいですね」
ものづくりを仕事にするきっかけ
新発田市の中央高校出身。高校生の頃は、まだ建設業に進む明確な意思はなかったという。
「通学路に新発田建設の社屋があって『新発田建設あるな』くらいの印象でしたね(笑)」
進路を決めたきっかけのひとつは、父親の存在だった。自営業で建設業を営む父の背中を見て育ち、気づけば“ものをつくる仕事”に自然と興味を持っていた。
「図工とか技術の授業が好きだったし、小さい頃から工作もよくやってました。なんか、“建物をつくるって、かっこいいな”って思いました」
そのまま日本大学建築学科へ進学。福島県の郡山で、建築材料(特にコンクリート)を研究する研究室に所属した。自ら配合を変えながら実験を重ねる日々は、ものづくりの面白さを再認識する時間でもあった。
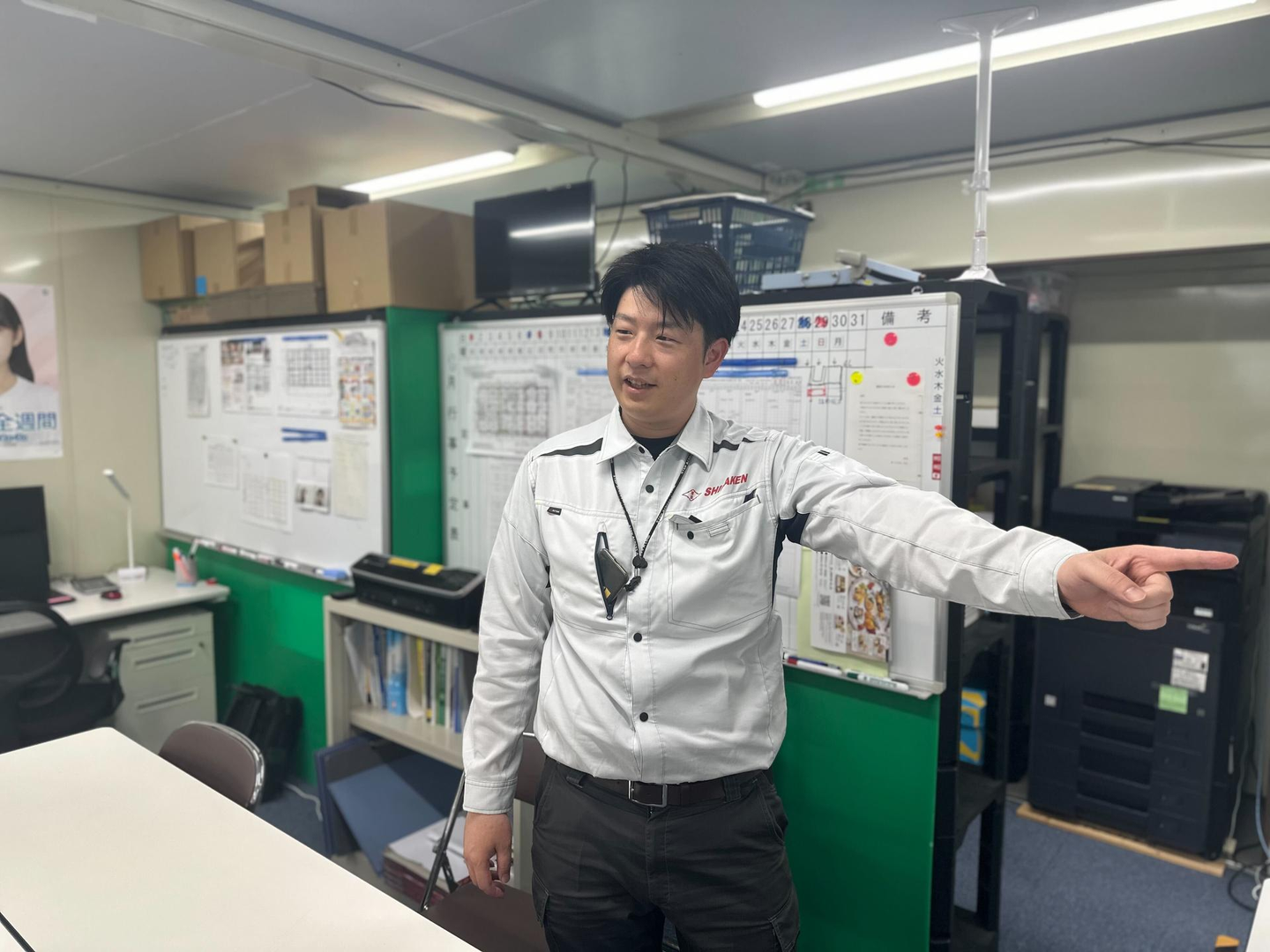
“真面目な会社”が少しずつ変わっていくなかで
新発田建設への入社は、地元志向が強くあったからこそ。 県外で学んだ4年間を経て、「やっぱり地元で、建物を建てたい」という想いが決め手になった。
「当時、会社についてすごく詳しかったわけじゃないんです。でも、就活で調べていくうちに、“あの建物も、これも新発田建設なのか”って分かって。街のランドマークみたいな建物をいくつも建てている会社って、すごいなって思いました」
入社当初の印象は、「真面目な人が多い会社」ただ、それだけでは終わらない変化も、ここ数年で感じている。
「社長がいろんなことを発信してくれるようになって、社風もどんどん変わってきましたよね。新しいことにも前向きに取り組む雰囲気になってきたなって」
研修制度も大きく変わった。 中村さん自身は“ほぼOJTオンリー”の世代だったが、今は入社後も手厚く座学やICT研修を受けられる仕組みが整っている。
「自分たちのときにはなかった制度ばかりですけど、“いい変化”だと思ってます」“今は2番手”でも、任されるときは必ず来る
心は熱くとも冷静に次代に向けての準備を
現在の中村さんは、現場において“ナンバー2”の立場が多い。所長を補佐しつつ、若手のフォローにも気を配るポジションだ。
「いま、僕の世代ってすごく薄いんですよ(30代の社員数が相対的に少ない)僕が入社したあと、2~3年くらい誰も新卒が入ってこなかった時期があって。その下の世代が増えてきたから、なおさら“自分が中間”って意識が強くて」
いずれ来るであろう、自分が“先頭に立つ日”に向けて、準備はしている。
「長きにわたって会社を支えてくれている先輩達も沢山いらっしゃいます。でも、あと5年もしたら入社年次でいっても自分が上から数えた方が早くなる。極端な話、上の人が全員いなくなったらって考えたら、自分が所長として会社を引っ張らなきゃと思っていますし、そのときはやってみせます。今はその時に向けてしっかり力をつけたいなと思ってます」
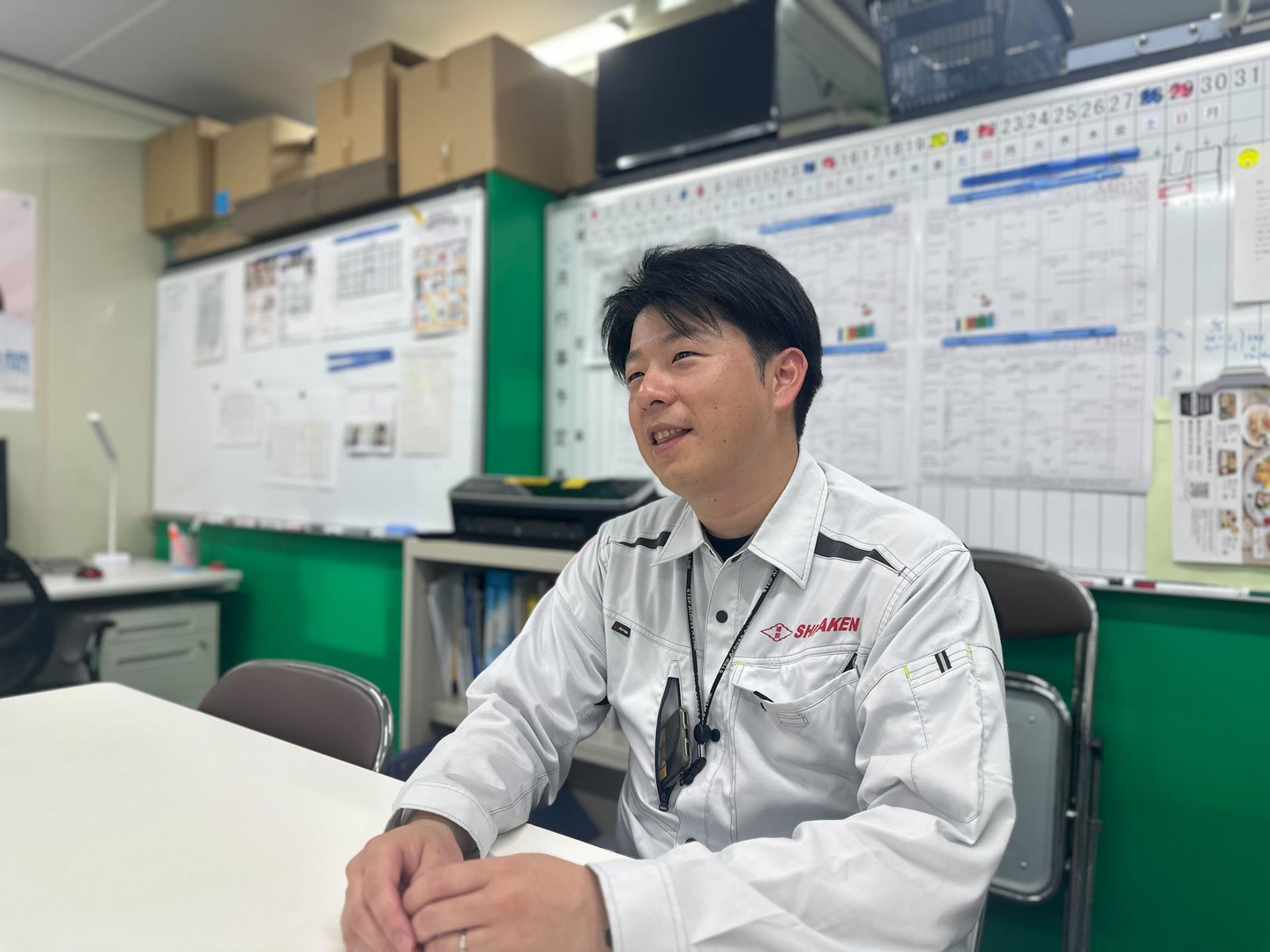
一緒に働くなら、ポジティブなやつがいい
インタビューの最後に、「一緒に働きたい人って、どんな人ですか?」と聞いてみた。
「元気で、ポジティブな人がいいですね。現場って、どうしても辛いことも多いですから。寒い、暑い、時間に追われる……そんな中でも前向きにやってくれる人がいると、雰囲気が良くなるんです」
現場はチームで動く、誰か一人の姿勢が、現場全体の空気を変えることだってある。
「辛くても、事務所の中の雰囲気が良ければ、なんとかなる。だからこそ、そういう“空気をつくれる人”って大事なんですよね」
建物は、誰かの覚悟で建っている。
一人で現場を背負うこと。自分の判断が、建物のかたちを決めていくこと。建築という仕事は、技術と経験の世界であると同時に、「腹をくくる」仕事でもある。今、中村さんはその“覚悟”を自分なりに形にしようとしている。
次に、誰かに「全部、任せる」と言われたとき、彼はきっと、まっすぐにその言葉を受け止めるだろう。



/assets/images/20327582/original/30bcb485-ea9b-4d48-8182-ca8545e8dd86?1738504457)
/assets/images/20327582/original/30bcb485-ea9b-4d48-8182-ca8545e8dd86?1738504457)

