建築部工事課 佐藤 陽
入社9年目にして現場監督として着実に経験を積み重ね、現在は現場の次席として日々奮闘している佐藤さん。近年、建設業界に働き方改革やDX(デジタルトランスフォーメーション)の波が押し寄せるなかで、若手としての柔軟な発想と現場で培った現実感覚のバランスに優れた佐藤さんは、そうした変革の中で確かな存在感を示し「次の新発田建設」を形づくる一員として歩みを進めている。
新発田建設を選んだ理由
現在の新潟市西蒲区で生まれ育ち、地元の公立の総合高校に通っていた佐藤さん。そこでCADや木材加工等、建設業界にも大きくかかわる技術を学んだことで、建設業に興味を持ったという。
「ちょっとした建物模型を作ったんですけど、その時面白いなと思って。これを仕事にしてもいいのかなと思いました」
その後、建築について学ぶため自身の高校から初めて職能短大へ進学した。進学後は建設現場の見学会へ足を運び、そこで新発田建設が取り仕切る大規模な建設現場の様子に驚いたという。そして、同じ短大のOBで、当時件の現場にいた新発田建設の社員や、新発田建設に入社が決まった先輩たちの話を聞いて、佐藤さん自身も新発田建設の入社試験を受けることを決めた。
「新発田のゼネコンではOBが1番いる会社と聞いて、環境が良く、自身の出身学校とのつながりも深く安心感がありました」

現場をまとめる責任
入社から9年を数え、着実に現場で職務を遂行してきた佐藤さん。なかでも特に印象に残っているのは、ここ数年の自らがナンバー2として監督してきた現場だという。自身を「まだ一人前とは言えない」と謙遜しつつも、少しずつ成長してきた実感があり、現在は次席としての責任を持って現場を取りまとめている。
「やはり最近次席という、現場のナンバー2を任せてもらって、施工図、発注物、工程、施主対応であったり、仕事の幅が広がってきたことに責任もそうですが、やりがいも大きくなってきています」
経験がすべて - 若手現場監督の本音
「経験って現場やっていて、本当に大事だと思うんです」
佐藤さんが仕事をする上で大事にしているのは、経験と信頼関係の積み重ねだ。改修や新築を問わず、同じような納まりや施工が出てくるたびに、過去の経験が“引き出し”として生きる。ときには専門業者の知見に助けられることもある。だからこそ、現場で大切なのは「自分の知識だけで判断せず、協力会社や設計者の声をきちんと聞くこと」だと語る。
コミュニケーションも、若手時代には苦労したという。初対面の職人から軽く見られがちな1~2年目を経て、4年目を過ぎた頃からようやく「指示が通るようになってきた」と感じられるようになった。その背景には、繰り返し現場を共にすることで育まれた信頼感と、言い方・伝え方を磨いてきた彼の努力がある。
「仕事以前に『ちゃんとしているかどうか』って見られますよね」
そう話す彼は、現場事務所の掃除や開け閉め、先輩より早く出社しての準備を欠かさなかった。それは、先輩たちの姿を“見て覚える”という、建設業界の伝統的な学び方の中で育まれてきたものだ。自身の経験から、後進には「遅刻しない」「現場の準備を先輩に任せない」といった基本姿勢を大切にするよう伝えている。実直に、着実に。数をこなし、現場で学び、仲間と歩む。その繰り返しの先に、佐藤さんは確かな成長を積み上げている。
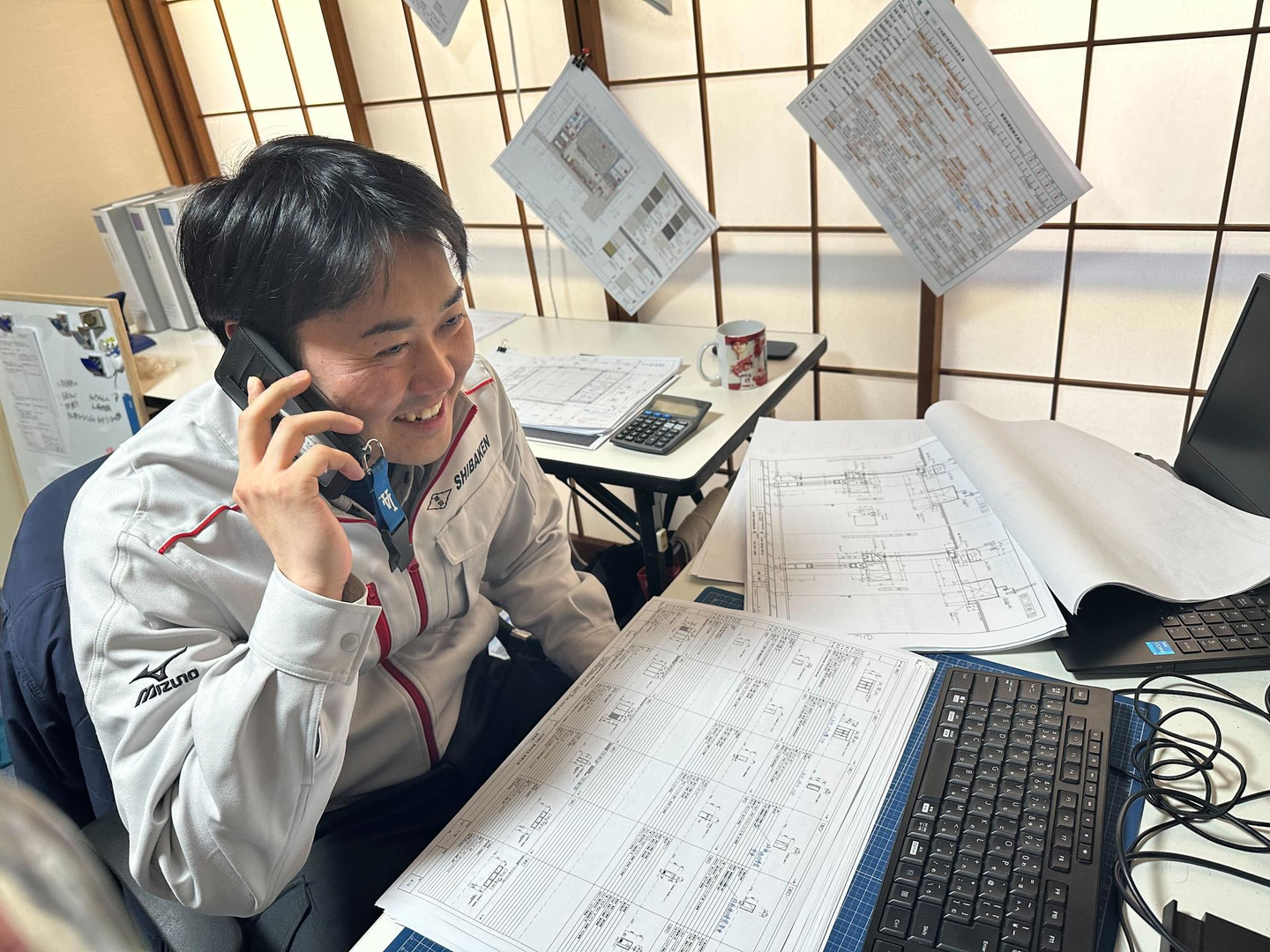
この会社が、次の時代に選ばれる存在であるために
変革が進む建設業界だが、次代に向けて課題も当然に存在している。
「今の時代ってやっぱり職人さんが不足していると思います。今まで通りの工期で契約をしちゃうと土日だけでなく、祝日も現場を動かさないといけないし、それでも工期に間に合わせることが正直厳しい現場があるのも事実です」「いまは仕事がある。でも5年後、10年後も同じとは限らない」
地域に根ざした建設会社としての強みとともに、彼が見据えているのは「この先も選ばれる存在であるために、何をすべきか」という問いだ。
「正直、新発田市内では建てる場所も少なくなってきていて、新築の大型案件も減ってくる可能性がある。だからこそ、新潟市など他地域への進出を見据えた準備が必要だと思います。新発田建設には生産システム室といった、業務効率化やDXの専門部署もあるが、学生や子ども達が業界で働きたくなるような環境を自分たちでも実現させたいですね」
働き方や価値観が大きく変わる今、会社として何を守り、何を変えていくべきか。その問いに向き合いながら、佐藤さんは一人の現場監督として、現場の最前線から「次の時代に選ばれる会社」を形にしようとしている。理想論だけでは語れない建設業のリアルに向き合い、仲間とともに持続可能な未来を築いていく。その姿は、確かに次代を担う存在だ。

/assets/images/20327582/original/30bcb485-ea9b-4d48-8182-ca8545e8dd86?1738504457)


/assets/images/20327582/original/30bcb485-ea9b-4d48-8182-ca8545e8dd86?1738504457)
/assets/images/20327582/original/30bcb485-ea9b-4d48-8182-ca8545e8dd86?1738504457)

