PROFILE
保積 雄介 広告系ベンチャー企業でセールスやマーケティング、新規事業立ち上げ、マネジメントなど幅広く経験。2013年に株式会社DeNA Games Osakaに入社し、大型ゲームタイトルのプロデューサーやPM、マネジメント業務を担当。2015年に同社代表取締役社長に就任し、採用から組織づくりまでプロダクト開発組織のマネジメントを経験。2018年2月にタイムラボを創業し、自社で複数のカレンダーソフトウェアを開発。2025年にソフトウェア開発に特化したスペシャリストチームPenguin Studioを設立し、外部クライアント企業の開発支援も行っている。
「35歳で起業」リアルな課題感から生まれたプロダクト開発
──今までのキャリアについて教えてください。
大学時代、就職活動の型にはまることに違和感を覚え、新卒採用には応募しませんでした。卒業後はビジネススクール進学も検討しましたが、「何事も経験しないと自分の力にならない」という思いから、中途採用で京都の広告系ベンチャーに入社。社員10〜20名規模の環境で、営業・人事・マーケティングなど幅広い業務を経験し、「頼まれたらNOと言わない」を信条に、20代は経験の“量”を重視して走り抜けました。
4年勤めた後、スマホゲーム市場の急成長に衝撃を受け、29歳でDeNA Games Osakaに転職。大型ゲームタイトルのプロデューサーやPM、マネジメント業務を担当し、経験を重ねました。マネージャー昇格後に組織の課題を目の当たりにし、その改善に本格的に取り組むため、代表取締役社長を務めることになりました。採用から組織づくり、プロダクト開発組織のマネジメントを担い、組織方針の明確化や採用の主導を行いました。
──DeNA Games Osakaを退任後、どのような経緯で起業されたのでしょうか?
DeNA Games Osakaの社長として「世界一のゲーム会社にする」という思いで本気で取り組んでいました。しかし、親会社の吸収合併が決まり、事実上1つのゲーム事業部に組み込まれるという意思決定がなされました。僕自身はゲーム開発よりもビジネスや組織、仕組みを作るのが得意だったので、吸収合併後の組織のトップはゲームを作れる人間の方が良いだろうと思い、DeNAを離れる決意をしました。学生時代から考えていた「35歳で起業」というタイミングと重なりました。2018年に株式会社タイムラボを創業し、まずは自分が解決したい課題を探しました。その中で「時間」の使い方が生産性に大きく影響することに気づき、僕自身も複数の予定管理に苦しんだ経験から、共同創業者と複数のカレンダーを同期するカレンダーソフトウェア「Lynx」を開発。2025年にはソフトウェア開発支援に特化したPenguin Studioを設立し、自社プロダクトと外部企業の支援を行っています。
「時間」を軸に描くデジタルキャンパス構想との出会い
──クロステック・マネジメントのプロジェクトには、どういった経緯で参画されたんですか?
きっかけは、現クロステック・マネジメントのCDO齋藤さんから「開発プロジェクト推進に参画してほしい」と声をかけてもらったことでした。そんな中、クロステック・マネジメントの話を受けて現クロステック・マネジメント代表の小笠原さんや京都芸術大学職員の木原さんと面談した際、僕がタイムラボで“時間”をテーマにプロダクトを開発してきた話をしたところ、小笠原さんの描く瓜生山学園のビジョンと強くシンクロしました。
たとえば、履修登録や成績証明書の発行など、大学の機能をすべてスマホで完結できるような「デジタルキャンパス」をつくりたいという構想。その基盤には「時間」が重要なインターフェースになるという話を聞いて、「これは自分たちの知見が活かせる」と直感しました。最初は大学の基幹システム開発と聞いていたので、もっと堅いプロジェクトかと思っていたんですが、実際は非常にビジョナリーで、スタートアップ的な熱量がありました。アジャイル開発で挑戦する姿勢や「アジアNo.1の大学へ」といったスケール感にも衝撃を受けて、「ここでなら本気で挑戦できる」と思い、参画を決意しました。
履修登録から学習環境を自動構築──大学業務を変えるLeaPlaの挑戦
──現在はどのような業務に取り組んでいますか?
現在は、プロジェクト「LeaPla(ラプラ)」において、エンジニアチームのサポートやリソース調整、トラブル発生時の後方支援などを担当しています。LeaPlaは、大学での履修登録を起点に、学生情報と授業データを基に学習ツールを自動連携させるプロダクトです。
また、定期的に開催されるオフサイトミーティングを通じて、プロジェクト全体の進捗・課題・リスクを俯瞰的に把握し、関係者間の認識を共有しています。このミーティングには初回から継続して参加し、全体の方向性や優先順位の調整、必要なアクションの明確化を担ってきました。
──LeaPlaは具体的にどのような業務を自動化して、職員の負担を軽減しているのでしょうか
LeaPlaは、履修登録データを活用し、授業ごとに必要なZoomリンクやSlackチャンネルの設定、Google Classroomの作成を自動生成・連携する仕組みを提供しています。従来は、職員が膨大な授業や学生数を前に、手作業でこれらの環境を準備していたため、かなりの労力がかかっていました。その点、LeaPlaが担う役割は非常に大きく、現場の業務負担を軽減するための重要なソリューションとなっています。とはいえ、まださまざまな課題があり、正直まだ発展途上の部分もありますが、「人間がやらなくていいことはソフトウェアに任せるべき」という考えのもと、今後さらにアップデートを重ね、最適化されていく予定です。問い合わせも増えており、初期の試行錯誤を経て、より強固なプロダクトに成長していけると感じています。
壮大なビジョンに挑戦できる「スタートアップ×豊富なリソース」の環境
──今の仕事のやりがいや魅力は何ですか?
クロステック・マネジメントの魅力は、スタートアップのようなスピード感と柔軟性を持ちながら、通常のスタートアップではできない戦い方ができる点にあります。瓜生山学園が持つ安定した財務基盤や的確な投資判断、そして成長中のスタートアップとしては類を見ないほど優秀なメンバーが集まるDXプロジェクトがあることで、他にはない規模で物事を推進できると感じています。こうした強力なアセットを活かしつつ、常にスタートアップ的な攻めの姿勢を崩さず挑戦できる環境は非常に魅力的です。大胆な意思決定や新しいアプローチが可能なのは、しっかりとした守りの土台があるからこそ。資金やリソースが確保されているため、安心して挑戦できる基盤が築かれているのです。だからこそ、チャレンジの幅も成長の可能性も大きく広がっていると実感しています。
──クロステック・マネジメントの組織カルチャーや働き方の特徴は何ですか?
クロステック・マネジメントのもう一つの大きな魅力は、組織のカルチャーや制度が非常にユニークで、なおかつ個人の働き方にフィットする点です。クロステック・マネジメントでは、業務委託を中心にフルリモートで全国から優秀なメンバーが集まり、自律的に成果を出す仕組みが機能している。これは、自分自身が理想とする「時間やリソースの使い方を自ら選択できる働き方」に非常に近く、参考になることが多いです。また、定期的な合宿やコミュニケーションの工夫など、オンラインでのつながりを保ちながら信頼関係を構築する仕掛けも面白く、組織づくりや運営において学びが多いです。単に「働く」ということにとどまらず、「どう生きるか」という視点を持ちながら、共鳴できる仲間と共に挑戦できることが非常に魅力的です。



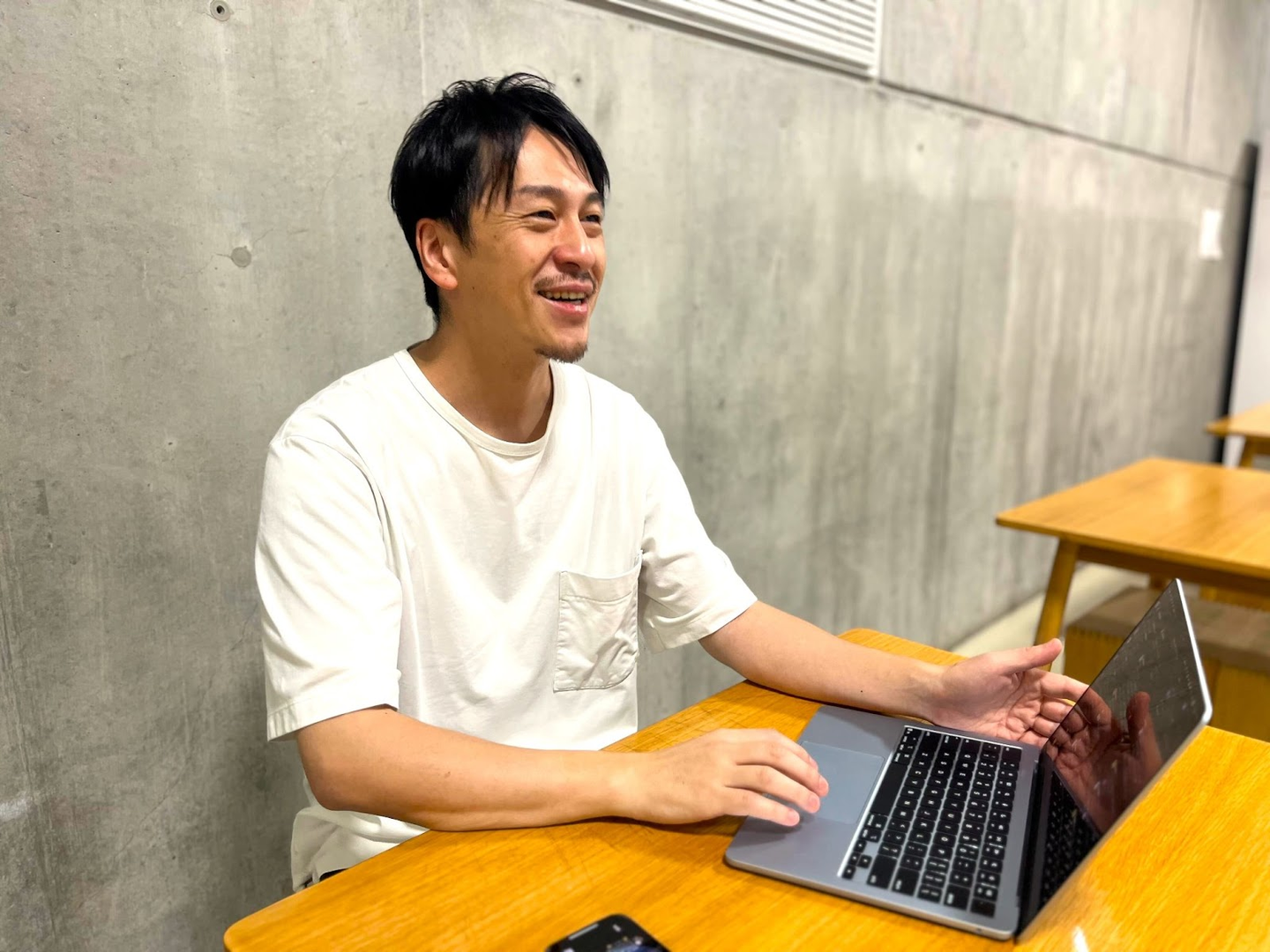
/assets/images/17505905/original/3d188f27-efbd-4a3d-814a-71a1218c42e2?1712163922)


/assets/images/17505905/original/3d188f27-efbd-4a3d-814a-71a1218c42e2?1712163922)


/assets/images/17505905/original/3d188f27-efbd-4a3d-814a-71a1218c42e2?1712163922)

