昨日、高校時代の友人と食事をしました。
最近は会う機会も増えましたが、それまでは長い間まったく会っていませんでした。卒業からもう15年。久しぶりでも、会った瞬間にあの頃の空気に戻れるのは不思議なものです。
この出来事から、ふとコロナ禍を思い出しました。
2020年、人との接触は避けるよう呼びかけられ、緊急事態宣言が発令され、街には「自粛警察」と呼ばれる人たちが現れました。
あの時期に「昨日友達に会ってきた」と言えば、批判を浴びたかもしれません。
コロナ禍がもたらした変化
もちろん、悪いことばかりではありませんでした。
会食や飲み会は減り、商談はオンライン化。1日の商談件数は倍増し、生産性も向上しました。しかも下はパジャマのまま仕事ができる気楽さもありました。
しかし、緊急事態宣言が解除されると、「一度顔を見て話さないと」という理由で対面打ち合わせを求められることが増えました。
僕はできるだけ断っていましたが、「会う」という文化は簡単にはなくならなかったのです。
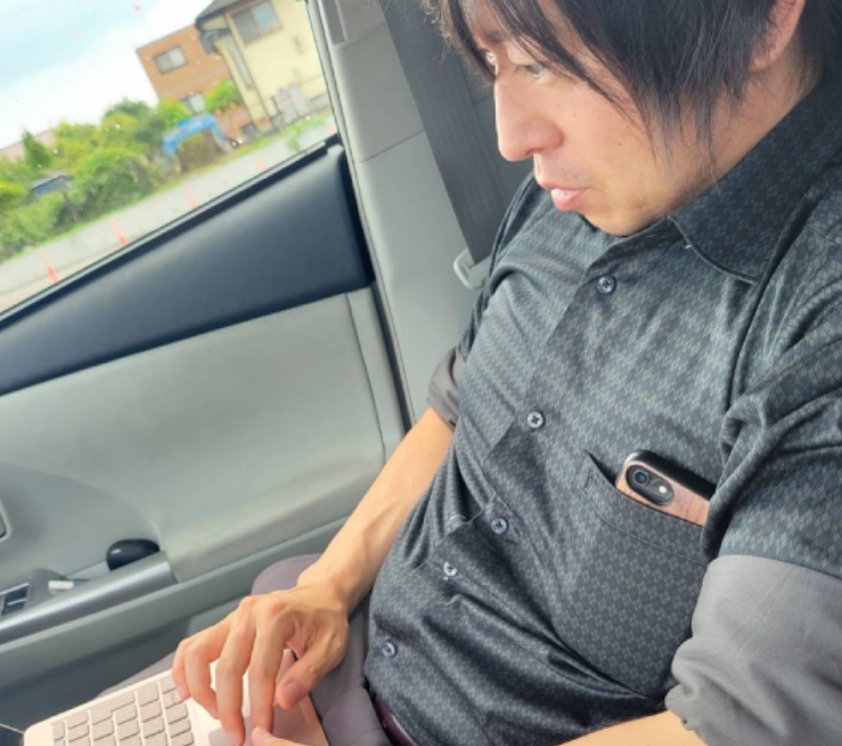
「会わないと信頼できない」は本当か?
さらに、「一緒に酒を飲まないと本音がわからない」や「喫煙所での雑談が重要」といった話もあります。
正直、僕はこれらが必ずしも真実だとは思っていません。
もちろん、対面は情報量が多いという利点があります。
ただ、人類の歴史のほとんどは、今のオンライン以下の希薄な手段で関係を築いてきました。
大陸間の移動が命がけだった時代、国同士の条約は手紙で交わされていました。
国内でも移動は大変で、子どもが親元を離れると「今生の別れ」に近い感覚だったのです。
わずか30年前でも、遠距離は「辛いもの」という認識が当たり前でした。

SNS時代の「久しぶり感」の消失
インターネットやSNSが普及する前、年賀状は数少ない関係維持の手段でした。
年に一度、一行程度の挨拶でつながっていたのです。
今では、何年も会っていない友人の近況がSNSで簡単にわかります。
子どもの顔も、キャンプに行ったことも、恋人ができたことも知ることができます。
だから、久しぶりに会っても「久しぶり感」がほとんどないのです。
SNSやLINEはほぼ無料で使え、これほど密につながっている時代はありません。
そんな中で、わざわざ対面を選ぶ意味は何なのか―僕はそこを考えるべきだと思います。
これから必要になる力
これからは、リモートで伝える力、電話で感じを届ける力、SNSで温度感を伝える力が必要です。
過去の偉人たちは手紙だけで重みや熱を伝えてきました。
今の僕らは「言葉にできない」とスタンプでごまかしてしまう――それでは足りません。
何語を話せるかよりも、何を話せるか。
そして、どんなツールを使っても同じ温度と空気を届けられる能力こそが求められています。
ちなみに今日は祖母のお見舞いに行きます。
こればかりは、どの時代でもやっぱり「対面」が一番です。

最後に
ここまで読んでくださった方は、きっと「人とのつながり」や「伝えることの大切さ」に共感してくれたのではないかと思います。
僕たちプラス・ピボットは、介護業界をはじめとした社会課題に正面から向き合いながら、その中で働く人や企業を支える仕組みづくりをしています。
もちろん、僕たちも完璧じゃありません。日々試行錯誤しながら、「どうすればもっと良くできるか?」を一緒に考え、行動しています。
そういう仲間が、まだまだ必要なんです。
経験やスキルは問いません。
必要なのは、誰かのために力を使いたいという想いと、自分ごととして課題を考えられる姿勢だけ。
少しでも興味を持ってくれたなら、まずはカジュアルに話してみませんか?
ぜひあなたの想いを聞かせてください。
その時間が、これからの未来を一緒につくる第一歩になるかもしれません。


/assets/images/20686404/original/dd702fe7-d950-4ef5-9a87-b0cd9c190d8e?1742282212)


/assets/images/20686404/original/dd702fe7-d950-4ef5-9a87-b0cd9c190d8e?1742282212)
/assets/images/20686404/original/dd702fe7-d950-4ef5-9a87-b0cd9c190d8e?1742282212)

