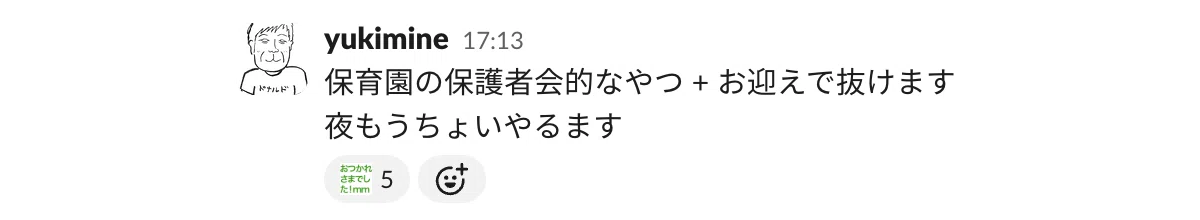株式会社REGALI の求人|シニアソフトウェアエンジニア|HERP Careers|転職のためのスタートアップ図鑑
株式会社REGALI が公開中の シニアソフトウェアエンジニア 求人の情報です。募集概要、必要とされるスキル、給与、働き方について確認しましょう。
https://herp.careers/v1/regali/ZwFQbLE5nZEn
REGALIでフルスタックエンジニアとして活躍する林さん。REGALIが3社目となる彼は、これまでWeb系事業開発会社やスタートアップでバックエンド開発を中心に、その技術力を磨いてきました。
現在は、プロダクト開発全般に携わりながら、最近ではレビュー機能の開発をリードするなど、事業成長の中核を担っています。
今回は、そんな林さんに、これまでのキャリアやREGALIへの入社の経緯、そしてREGALIの開発文化や働きがいについて、詳しくお伺いしました。
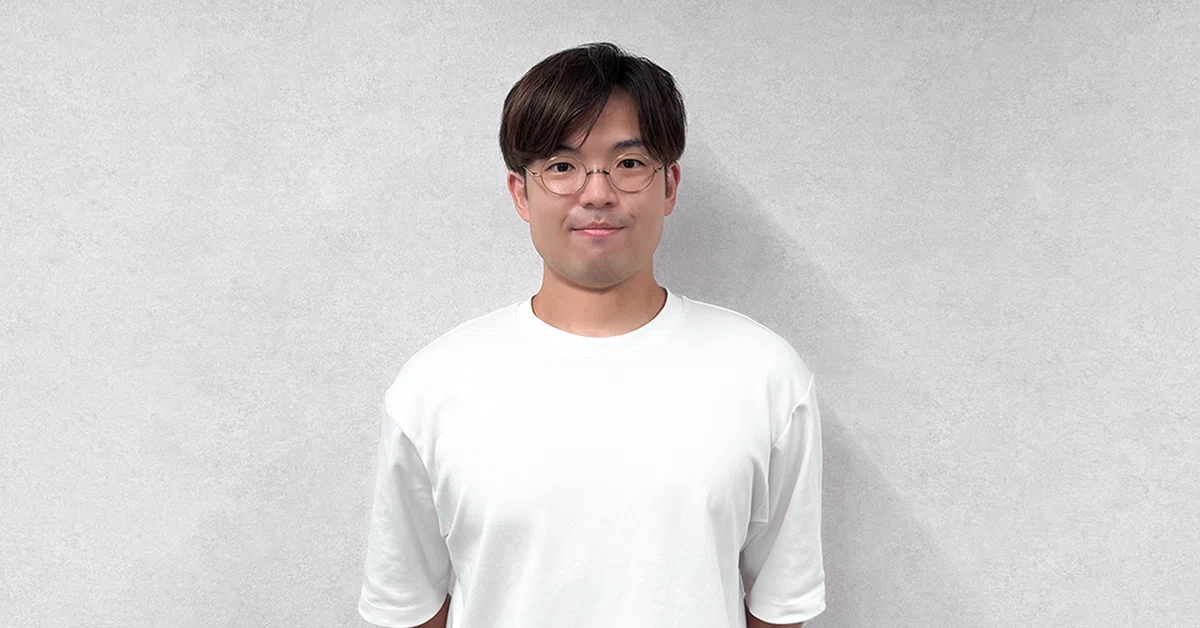
株式会社REGALI 開発部 林志嶺さん
林:キャリアとしては、REGALIは3社目になります。新卒で入社した1社目はWeb広告やWebメディアを扱う一部上場企業で、システムの開発・保守や新規プロダクトのリードエンジニアを経験しました。その後、2社目のC向けサービスを展開するスタートアップでは、少人数のチームでバックエンド全般の責任者として、1社目で培ったノウハウを活かしながら、かなり自由に改善などを進めさせてもらいました。
林:前職の環境に大きな変化があり、自分が望んでいた働き方とは少し合わなくなってきたと感じていた時期がありました。 そんな悩みを抱えていた時に、本当にタイミング良く、代表の稲田から「元気?ご飯行こうよ」と声をかけてもらったのがきっかけになりました。その場で会社や事業の話を聞いて、その後、正式に応募し、ジョインすることになりました。
まだ5名だったREGALIへの入社が決定し、歓喜する他メンバー
林:REGALIのエンジニアは特定のプロジェクト専任という形ではなく、事業インパクトやスケジュールなどの優先度に応じて、複数のプロジェクトを横断的に見ています。なので、一言で言うと「全般」というのが一番近いですね。
その中でも、最近特にコミットメントが大きかったのはレビュー機能の開発です。 開発の調査段階から設計、実装の大部分を任せてもらいました。
当時、代表の稲田や他のエンジニアメンバーが多忙だったこともあり、競合調査や要件定義なども積極的に引き受け、スプレッドシートにまとめてチームで議論しながら進めていきました。

リリースから続々と導入いただけているレビュー機能
(株式会社セストセンソ様の導入イメージ)
林:学生の頃から、特定の技術に特化するよりは、幅広く技術に触れていたいという思いがありました。 ありがたいことに、新卒で入社した会社がそうした考え方がベースの環境だったので、そこで基礎を叩き込んでもらいました。
2社目では、バックエンドの責任者という立場で、プレッシャーを力に変えながら知識を深めることができました。
REGALIに入社してからは、周りのメンバーにとても良い影響を受けています。 みんなフルスタックに動きながら事業に大きなインパクトを与えていて、その仕事っぷりがかっこいいなと思い。彼らに感化されて、「自分もこのスタイルを突き詰めていこう」と改めて強く思うようになりました。
林:新しい機能を作る際のデータベース設計からサーバーサイドの実装までが特に得意な領域です。
今後挑戦したいこととしては、事業の成長スピードにプロダクトやチームがしっかりとついていけるように、スケーラブルな状態にしていくことです。 REGALIのプロダクトがこれからどんどん多くの人に使われていく、その進化のフェーズを支える経験は今まであまりなかったので、非常に興味がありますし、挑戦していきたいです。

林:営業やCSなど、エンジニアではないチームからの要望を、本質を捉えて技術仕様に「翻訳」する作業は、プロダクト開発で最も難しい部分の一つだと思います。
REGALIでは、エンジニアのバックグラウンドを持つ代表の稲田が、その翻訳作業の中心を担ってくれています。 これにより、エンジニアとしては非常に動きやすい環境が作られています。
もちろん、彼だけに頼るのではなく、最近ではPdM(プロダクトマネージャー)に興味がある他のエンジニアが役割を分担するなど、チームとしてスケールしていくための挑戦も始まっています。
林:自分が担当する機能や得意な技術領域だけで境界線を引かず、「プロダクトや事業全体にとってどうなのか?」という視点を常に持つよう意識しています。プロダクトを成功させることが最優先なので、そのために必要なことであれば、自分の専門領域にこだわっている場合ではない、という考えです。
とはいえ、全てを一人で抱え込むのではなく、チームには仲間がいますから、自分より得意なメンバーがいれば、積極的に頼ることも大切にしています。この「抱えすぎずに頼る」バランスが重要だと感じています。
面白いことに、最近メンバーが順番に育休を取得しているのですが、これが期せずして、特定の人に依存していた知識をチーム全体で分散させる良いきっかけにもなっていて、結果的にチーム力を高めていると感じます 。
林:定期的なAI勉強会なども開催していますが、技術的な議論や知識共有は、その都度行われることが多いです。その代わり、一つ一つの議論がとても深いんです。
例えば、ある実装に対して「こっちの方がいいよ」だけで終わらせてしまうと、次に活きませんよね。魚の釣り方を教えるじゃないですけど、なぜそう考えるのか、事業やプロダクト、エンジニアチームとしてどういう方針があるから、こうじゃなくてこの方がいい、というところまでセットで話すようにしています。
議論の内容によって、プロジェクトを横断してメンバーを集めることもありますし、時には代表の稲田に入ってもらって、事業の将来を見据えたフィードバックをもらうこともあります。常にプロダクトにとって最善な形で議論できるよう心がけています。

林:正直に言うと、育休取得を報告する時は、進行中のプロジェクトのこともあり「本当に申し訳ない」という気持ちでいっぱいでした。
でも、会社側に相談した時は、「もちろん、いいよ!」という反応で、本当にありがたかったです。代表の稲田が普段から「family first」という言葉を口にしていますが、これが建前じゃなくて、本当にそう思っているんだなというのを、すごく感じました。
チームメンバーも「当然取るでしょ」という雰囲気で、快く送り出してくれました。
林:はい、とてもスムーズでした。 1ヶ月でものすごくプロダクトが成長していて驚きましたが、コードや設計に関する議論はGitHubやSlackに記録として残っているので、キャッチアップで苦労することはありませんでしたね。
林:この制度には本当に助けられています。今年二人目が生まれたんですが、例えば上の子が体調を崩して妻が病院に連れて行く時も、リモートワークだからこそ、下の子を横目で見守りながら仕事を続けることができます。
具体的な1日の流れとしては、朝子どもを保育園に送ってから9時半頃に勤務を開始し、18時頃に一度抜けて迎えに行き、19時頃からまた少し仕事をするという感じです。育児が大変な時は、子どもが寝た後や翌朝に作業することもあります。 非常に柔軟に働けるので、本当にありがたいですね。
slackで一時抜けを報告する林
林:「事業の成長を面白がれること」だと思います。 そういう方であれば、自然と自分のタスクの範囲を超えて、プロダクトや事業全体に対する責任感が生まれるはずです。 「これは自分の担当領域ではない」と線を引くのではなく、お互いの領域に良い意味で干渉し合いながら、チーム一丸となってより良いものを創り上げていける人だと、すごく楽しく働けると思います。
林:大きく2つあります。1つ目は「開発を阻む余計な壁がないこと」です。例えば大手企業によくある「これは別部署との調整が必要だから、来週まで待って…」みたいな理不尽な待ち時間が全然ないんです。何か議論したいことがあれば、すぐにDiscordで声をかけて解決できる。このスピード感で開発を進められるのは本当に大きいです。
2つ目は、「追い風が吹いている、今このフェーズを体感できること」です。 スタートアップが成長軌道に乗り、事業が勢いづいている状況って、実はかなりレアな機会だと思っています。 この貴重なフェーズを、当事者として一緒に乗りこなしていきたい、そう思ってくれる方には最高の環境だと思います。
▼ 一緒に働いてくれるメンバーを募集しています!▼