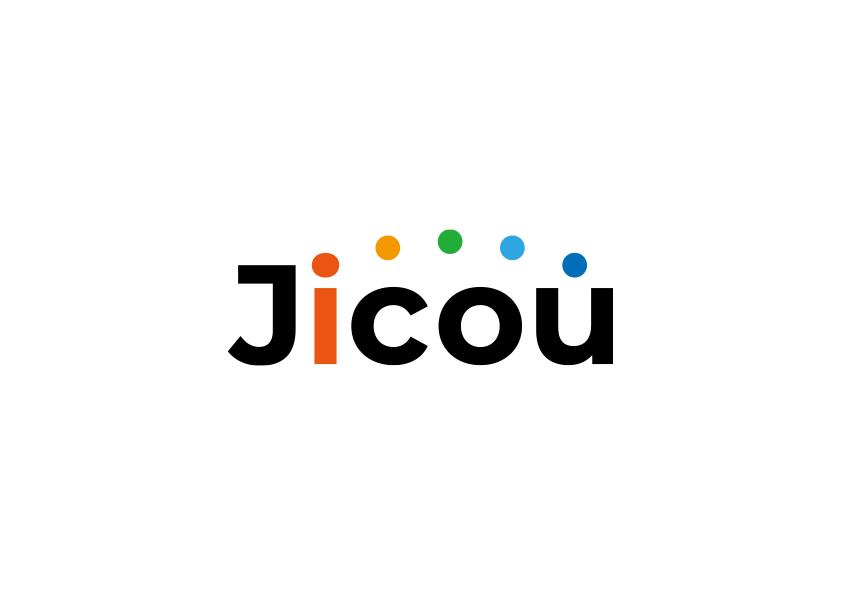こんにちは、ジコウです。
このnoteでは、私たちの会社がどんな価値観で動いていて、どんな想いで“はたらく”をつくろうとしているのかを、少しずつお届けしていきます。
名前は【ジコウでの“はたらく”を解剖してみた】。
この連載では、株式会社ジコウが
「中で本当に大切にしていること」
「今まさに悩みながら決めていること」
そんな話を、できるだけありのまま言葉にしていきます。
初回となる今回は、ジコウで大切にしているカルチャーの考え方です。
目次
- なぜ、ジコウは「学び方を学ぶ場」を掲げるのか?
- 成果よりも、プロセスに意味を持たせたい
- ジコウは「どんな人にとって心地よい場か?」
なぜ、ジコウは「学び方を学ぶ場」を掲げるのか?
私たちは今、働くことの意味が問い直される時代を生きています。
与えられた仕事をこなすだけでなく、自分の人生にとってどんな意味があるのかを考えながら働きたい。 そんな想いを抱える大人たちが増える中で、株式会社ジコウは「学び方を学ぶ場」というカルチャーを掲げています。
「学び方を学ぶ」とは、単に知識やスキルを習得することではなく、問いを立て、仮説を立て、試行錯誤を繰り返す中で、変化に向き合う力を育むこと。その姿勢を、個人ではなく組織として育てるというのがジコウのユニークな試みです。
なぜ、今それが必要なのか?そしてどんな背景や想いがあるのか?
今回は、そのコンセプトの根幹をつくったジコウ平田さんに、最近入社した永尾が話を聞きました。
「学び方を学ぶ場」という一見ちょっと抽象的な言葉の背景に、どんな思いや経験があるのか。まだ社内のことを手探りで知ろうとしている永尾の目線から、素直な疑問をぶつけていきます。
永尾: 「学び方を学ぶ場」と聞いて、少し抽象的だと感じる人もいるかもしれません。まず、なぜジコウという組織が、あえてこのコンセプトを掲げているのでしょう?
平田: 確かに、抽象的だと言われることもあります。でも僕にとっては、むしろ「これがなければ人は幸せになれない」とすら思っています。 根底にあるのは、「自分の人生は、自分の手でよくしていけている」と実感できるかどうか。その実感があるとき、人は静かに幸福でいられると思うんです。
永尾: それは、いわゆる「成長の実感」ということでしょうか?
平田: そうです。昨日より今日の自分が少しでも前に進んでいると感じられること。他人との比較ではなく、自分との対話から生まれる感覚ですね。
永尾: でも、それって個人の話に聞こえます。なぜそれを、会社という組織でやる必要があるのでしょう?
平田: 僕はむしろ、組織こそがやるべきだと思っています。組織って、結局は“人の集まり”じゃないですか。個人が変わらないのに、組織だけ変わるなんてことはありえない。だからこそ、人生をよくしたいと思える人が集まったら、組織も自然とよくなっていくはずなんです。
永尾: ただ現代の企業って、どうしても成果主義や効率重視が前提になっていますよね。
平田: 成果主義自体を否定するわけではありません。成果はもちろん大事です。でも、成果だけを追いかけると「成果を出せない自分には価値がない」と思い込んでしまう人も出てくる。 だからこそ「成果までのプロセス」にどんな意味を持たせるかが、組織づくりでは非常に重要だと思うんです。
成果よりも、プロセスに意味を持たせたい
永尾: あらためてお聞きします。「学び方を学ぶ」とは、具体的にどのようなことを指すのですか?
平田: それはたとえるなら“魚の釣り方”を学ぶこと。もっと言えば、どんな釣り竿でも、どんな水辺でも魚を釣る力を身につけることです。 つまり、自分で問いを立てて、仮説を立てて、試して、振り返って、また挑戦する。 このプロセスの繰り返しで、人は「学びの筋力」を鍛えていくんです。
ジコウ: 誰でも、そのプロセスを身につけることはできるんでしょうか?
平田: できます。ただし、“簡単”ではありません。 でも、子どもが歩けるようになるのって、何度も転びながらも、立ち上がり続けることでしょ? あのプロセスこそが「学び方を学ぶ」ことそのものなんです。
永尾: その“立ち上がり続ける力”を、大人が取り戻すために必要なものは何でしょう?
平田: まずは“柔軟性”です。知らなかったことを知る、できなかったことができるようになる。それを受け入れられるかどうか。 「今の自分」にこだわりすぎると、変化を拒んでしまうんですよね。
永尾: でも、それを組織で実践するのは、ハードルが高そうです。
平田: だからこそ、まず自分がやるんです。私はリーダーであると同時に「実験者」でありたいと思っています。正解がないからこそ模索し、問い直し、また立ち上がる。 その姿を“空気”として、組織に伝えていけたらと思っています。
永尾: 「主観的な豊かさ」という言葉が、話の中で何度か出てきました。それはどんな意味でしょう?
平田: 物質的には満たされていても、心が豊かだとは限らない。SNSなどの影響もあって、人と比べてしまいがちな世の中だからこそ、他者ではなく「自分の中にある幸福感」を信じる力が大切です。
主観的豊かさとは、自分が「今、自分の人生を生きている」と感じられる状態のこと。それを実現するには、自分の人生を自分の手でよくしているという実感が必要なんです。
ジコウは「どんな人にとって心地よい場か?」
永尾: では、ジコウという会社は、どんな人にとって“心地よい場”なんでしょう?
平田: 「自分の人生は、自分の手で変えていきたい」と本気で思っている人ですね。 誰かに与えられたレールじゃなく、自分で問いを立てて進みたいと思っている人。 そういう人にとって、ジコウは“最高の遊び場”になると思います。
永尾: 逆に、ジコウが合わない人は?
平田: 「答えをすぐにほしい」「教えてくれなきゃわからない」という姿勢の人には、ちょっとしんどいかもしれません。
永尾: 最後に、読者へメッセージをお願いします。
平田: 「なぜ働くのか?」という問いに、自分なりの答えを持ちたい。 そんなあなたと一緒に、“問い続ける組織”をつくっていきたいと思っています。
永尾: ありがとうございました。次回は、「学び方を学ぶ場」を支える4つの実践方針について、もう少し具体的に掘り下げていきたいと思います。