こんにちは!BabyJam採用チームです。
今回は、エンジニアとしてだけでなく、ビジネス視点も兼ね備えた黒川和馬さんにご登場いただきました。
「なぜ今AIを選んだのか?」「BizDevとの最適な連携とは?」「どんな人と一緒に働きたいか?」など、普段なかなか聞けない話をじっくり伺いました!
BabyJamとの出会い
── BabyJamとはどうやって出会ったんですか?
当時は京都に住んでいて、業務委託として、フルリモートで開発に関わり始めたのが最初でした。ちょうど就活も並行してやっていた時期でしたね!
──実際、業務委託のときはどんなお仕事をされていたんですか?
リモートで関わっていた当時は、大きく二つの仕事を担当していました!
一つは、既存アプリのバグ修正や小さな機能追加です。ちょうど「NORDER」の前身にあたるプロダクトで、CTOの古瀬さんの開発をサポートする形で携わっていましたね。
もう一つは、社内で出てきた新規アイデアのプロトタイプ開発です。「こういう課題を解決できたら面白いのでは?」といったアイデアに対して、MVP(Minimum Viable Product)をサッと作って、実現可能性を検証する試作開発もいくつか任せてもらっていました。
── なるほど。その中で「ここに入りたい」と思った決め手は?
就活をする中で、多くの企業は、「エンジニアは開発だけ」「ビジネスはビジネスチームがやる」といった分業構造がほとんどだなと感じたんです。でも、自分は両方に関わりたいという気持ちも強くて。そうなった時に、BabyJamなら、どっちも関われる環境だと思ったので、入社を決めました。
──そこから実際に上京されたわけですが、それも入社を決めたタイミングで?
そうですね。リモートで仕事を進めていると、どうしても東京とのスピード感のギャップを感じる場面が出てきて。だったらちゃんと上京して、本気でやろう、と決めました。

開発の中心で「全部やる」ということ
── 実際、現在はどのような業務に携わっているのでしょうか。
現在は、NORDERの国内版アプリ開発を担当しています。要件定義(=「こんな機能を作ってほしい」というビジネス側の要望を整理するプロセス)から、基本設計、実装、テスト、リリースまで、ほぼ一人で進めています。
フロントエンド(=ユーザーが触れる画面)からバックエンド(=データの処理や保存を担う裏側の仕組み)まで広く手がけており、UIのモック(画面の試作図)の作成やデザインも自分で、行っています。
いわば、プロダクトの設計から開発・運用まで、一通りの工程を担っているような形ですね!
── まさに開発の中核を担っている存在なのですね!
AIが書き、人が設計する──「今」の開発スタイル
── ちなみに、最近は、開発プログラミングにおいても、AIを導入しているとお聞きしました。実際、業務の中でも使うことは多いのでしょうか?
めちゃくちゃ使ってますね。実のところ、コードを書くという作業そのものは、ほとんどAIに任せていて、人間はその「フロー」を設計する役割にまわっている感じです。
「こういう動きにしたい」「こういう構成にしたい」という意図を明確にして、それをAIに伝えて、出てきたコードを調整・検証していく、というのが今のスタイルですね。
だからこそ、「どう書くか」より「何を作るか」「なぜそう作るか」を考える力が、これまで以上に大事になってきています。AIが頼れる存在になったからこそ、人間が担うべき役割も、どんどんアップデートされているなと実感しますね。
── なるほど、それこそが “今の開発”って感じですね。時代の変化をリアルに感じます。

「ビジとデブの真ん中で。」──両視点でプロダクトを磨くということ
── いろいろ担当されている中で、BizDevチームとの関わりも多いと聞きました。そのあたり、実際どんな風に進めてるんですか?
(BizDev=Business Developmentの略。主に事業開発や、プロダクトの価値をユーザーに届けるための施策立案などを担うチーム。)
そうですね、まずNORDERをもっと多くの人に知ってもらうためのマーケティングや広告周りは、西山さんと後藤さんが担当しています。あわせて、ユーザーインタビューも彼らが行っていて、実際の声やフィードバックを共有してもらうんです。それを自分がアプリに反映していく、という流れですね。
── BizDevチームとの関わりの中で、印象に残っているエピソードはありますか?
そうですね、最近で言うと、まさに今取り組んでいる、AIチャットですかね。
── 「NORDER」のAIチャット機能って...?
「NORDER」のAIチャットは、音楽活動を支える“マネージャーの代わり”として、ユーザーの悩みや相談内容に応じて最適な回答や提案をしてくれる機能です。
ただのチャットではなく、利用者の好みやニーズに応じて、適切なアドバイスやサポートをエージェント的に提供する役割を担っています!
「自分に合ったAI」との出会いをつくるために
── どのような仕組みを検討されているんですか?
現在は、AIチャットがより「自分ごと」として使えるように、オンボーディングの仕組みを見直しているところです。
── オンボーディング、ですか?
はい。オンボーディングとは、サービスの利用開始時に、ユーザーの理解や定着を助けるプロセスのことを指します。
NORDERでは特に、「この人はどんな目的で音楽活動をしているのか」「今どんな課題を感じているのか」「どれくらいの時間や予算をかけられるのか」といった情報を最初にヒアリングし、その内容に応じてAIのサポート内容やトーンをパーソナライズしていく設計を目指しています。
── いきなりAIが出てくるよりも、自分に合った関係性を築いた上で始めるほうが、安心感がありそうですね。
そうなんです。ただ情報を投げる存在というより、「目的や課題を知ってくれている友人」に近い距離感の方が、ユーザーにとっても相談しやすくなるんじゃないかと。
── そもそも、なぜそうした改善が必要だと考えたのでしょうか?
もともと、ユーザーの音楽活動には大きなばらつきがあるのに対して、プロダクト側が統一的なソリューションを提供してしまっていたという課題がありました。
BizDevチームと話す中で、「ユーザーの音楽活動のフェーズや課題がバラバラなのに、提供するソリューションが一律なのはよくないよね」という課題感が共有されていて。そこから、「じゃあ、最初にユーザーの状況を聞いて、それに合わせてサポートの形を変えられたらいいんじゃないか」という方向で話が進んでいきました。
── それをAIに組み込んで、もっと柔軟に対応できるようにしたと。
はい。最初にヒアリングすることで、ユーザーにとっての相談ハードルも下がりますし、プロダクトとしてもよりフィットした情報を提供できますから。
このアイデアは僕一人で出したというよりも、BizDevチームと一緒に、ユーザーのファクトをもとに課題とソリューションを議論しながらつくっていったものです。
エンジニアが、要件を「受け取る」側ではなく、一緒に定義するところから関われるって、実はなかなかないことなので。僕としてもすごく印象に残っている取り組みですね。

ユーザーのために考え、動く。今、BabyJamが求めている人とは?
── 最後に、どのような人がBabyJamには向いていると思いますか?
そうですね。
まず何より、音楽という領域に熱を持っている人にとっては、すごく面白い環境だと思います。メンバーそれぞれが本気で取り組んでいる分、熱量が高くて、自然とその空気に引き込まれるんですよね。
あとは、自分で手を動かして、結果を見て、検証して、改善していくというサイクルを、ちゃんと自分の手で回せる人ですね。大手だと分業されがちなところも、ここではまるっと任せてもらえるので、実践力がすごく鍛えられると思います。
── 特にエンジニア部門に興味がある人に向けてのメッセージはありますか?
「この技術だけやりたい」という人より、「この課題を解決したい」「このプロダクトをこうしたい」という野望を持っている人に来てほしいですね。
特定の技術領域にとらわれず、ビジョンに向けて自分で選び、自分で動いていく。そんな人が一番輝ける環境だと思います。良いツールも自由に使えるし、挑戦したい技術があればどんどん学べるし、技術的な支援も惜しまれません。
── AIを活用する時代であるからこそ、いろんな領域に広く挑戦できる人が、やっぱり向いているんですかね。
そうですね。もちろん特定の言語や技術に強みを持つのは素晴らしいことなんですが、それだけだと難しい場面も多くて。
どちらかというと、「ユーザーにとって何が一番いいのか」を起点に考えて、柔軟に手段を選べる人のほうが、今の環境には合っているのかなと思います。
── エンジニアチームについても、少し教えてください。
今は、僕と古瀬さんの二人で開発を進めています。小さいチームですが、その分一人ひとりの裁量が大きいですし、何より「アーティストにとって良い社会をつくる」という思いを強く持ったチームだと思っています。ユーザーの声に真摯に向き合いながら、プロダクトを磨いていく、そんな熱い気持ちを持った人に、ぜひ仲間になってほしいですね。
エンジニアとして開発の最前線に立ちながら、ビジネス視点も持ち合わせてプロダクトの価値を磨き続ける黒川さん。
「技術のための技術」ではなく、「ユーザーのためのものづくり」を追求する姿勢が、とても印象的でした。
次回は、BabyJamの事業部の取り組みについてご紹介していきます。どうぞお楽しみに!

/assets/images/14239976/original/6d033615-fc1e-4f2c-ab45-b42d0b5a0807?1692612458)
/assets/images/14239976/original/6d033615-fc1e-4f2c-ab45-b42d0b5a0807?1692612458)

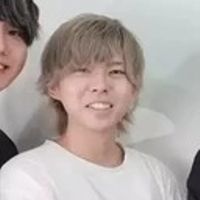

/assets/images/14239976/original/6d033615-fc1e-4f2c-ab45-b42d0b5a0807?1692612458)
