こんにちは!Contrea株式会社のMedicalチームでインターンをしているMinorinです。コントレアのエンジニアは、医療現場に足を運びながら開発をしています。なぜ現場に行くことにこだわっているのでしょうか?今回はプロダクトチームのお三方にお話を伺いました。最後まで読んでいただけると嬉しいです。
現在のお仕事内容も含めて、自己紹介をお願いします。
moya:
私はテックリードというポジションでチームのメンバーがいかに効率よく開発し、リリースを早くできるかに責務を持っています。あとは、MediOSが新しく医療現場で使われるときに、バグが出たり、レスポンスが遅くなったりしないように、品質をしっかり保つための取り組みをしています。
amu:
MediOSの機能開発と運用を担当しています。何を作るか、どう改善していくかを決めるために、実際に医療機関へ足を運んで、医療従事者の方々と直接お話しています。薬剤師のバックグラウンドを活かしながら、現場で得た声をもとに、開発して届けては検証というサイクルを回しています。
hiryu:
開発責任者として、MediOSを今後どう成長させていくか、市場にどうフィットさせていくかを考えることと、プロダクトチームを成長させていくために、採用活動やメンバーの目標設計等のマネジメント業務が主な役割です。みんながもっと役割に集中できるように、障害を取り除くのも自分の仕事です。最近は、AIを活用して開発だけではなく社内全体の労働生産性を上げることもミッションとして取り組んでいます。
コントレアにジョインするまでの経歴について軽く教えてください。
moya:
新卒からエンジニアをしています。1社目は大手のメーカーでシステムエンジニアとして働いていたんですが、もっと技術力を高めたいなという思いから東京のWeb系のスタートアップに転職しました。そこではバックエンド側のコードをまるっと任せてもらってひたすらに開発していました。少ないリソースで成果を出すためにいかに必要なもののみフォーカスするかみたいな思考が身についたと思います。あとは拡張性が高いシステムの作り方も学びました。その後、フリーランスとして独立した中で1つの業務先がコントレアでした。半年ほど業務する中で川口さんから正社員として働いてほしいとオファーを受けて業務委託から正社員になり今に至ります。
amu:
大学で薬剤師免許を取得後、新卒で製薬企業のMRとして働いていました。配属先の北海道で、色々な医療課題を目の当たりにしました。例えば、豪雪地域では患者さんが病院に行くのが難しかったり、医師が治療法の説明をしても、患者さんが納得できずに適切な治療を受けられないケースがあったりします。ただ、営業の立場だとそういった課題に直接アプローチするのが難しくて、もっと自分の手で課題解決をしたいと思うようになりました。そのための手段として「ものづくりをやりたい」と思い、エンジニアに転身して、コントレアに入社しました。
hiryu:
大学生の時に、父と一緒に起業したのがエンジニアを始めたきっかけです。父が営業、自分が開発を担当して、色々作って売っていました。でも、展示会に出してもなかなか売れなくて、、。それが本当に悔しくて、家に帰ってひたすら作り直しては、また売りに行って、を繰り返していました。そうやって改善のサイクルを回して少しずつ売れるようになっていくのがすごく楽しかったんです。そこから、もっとエンジニアとして技術を磨きたいと思い、新卒でヤフーに入社して、3年ほど金融系の新規事業立ち上げを経験しました。その後また医療系で1からやりたいと思い、コントレアにジョインし、新規事業開発を経て、今は開発責任者として働いています。
実際に現場に足を運ぶということがコントレアの中だと普通によくあることになっていますが、それが始まった経緯やきっかけについて教えてください。
hiryu:
もともと、創業当初からプロダクトを現場に届けることに強い関心を持つエンジニアが多かったのが大きいですね。それに、特に当初は動画説明というソリューションが医療業界に一般的でなかったので、そもそも何を作ればいいかがわからなかったんです。どうすればプロダクトが売れるのか、正解がなかったんですよね。だから、実際に現場に行って、お客さんの生の声を聞くしかなかった。それが、現場に行く文化が始まったきっかけだと思います。
現場に行くことを今も続けてる理由はありますか?
hiryu:
競合優位性をどう築くかという話になりますが、我々が作っている様なSaaSのプロダクトは、最終的にはソフトウェアを真似することができると思っています。じゃあその中でどうやって競争に勝っていくかというと、お客さんが求めているものを、早く作って届け続けることができるかが非常に重要だと思っています。そのためには、高品質なものを早く届ける役割と、どれだけ確度の高い施策を打ち続けられるかという2つのミッションが必要だと思っていて、その確度の高い施策を打ち続けるためには、やっぱり現場に行くのが一番確実で、精度の高い話になる。そういった開発組織こそがMoatであり、この文化はこれからも残り続ける必要があるのかなと思ってますね。
amu:
現場に行き続ける根本的な理由は、お客さんが抱えている課題をどれだけ解決できるプロダクトを提供できるか、というところにあります。でも、その課題って現場の方が全部教えてくれるわけじゃないんですよね。例えば、業務改善をしたいと思っていても、その課題感がちょっとフワッとしていることがあります。そのフワッとした課題をそのまま作ってしまうと、本当に解決すべき課題とずれてしまったり、現場の方々と齟齬が生まれてしまう。開発としては、一度作ったものをまた作り直したり、改善したりするのは、ものすごくカロリーを使う作業です。だからこそ、作る前に、その真の課題が何なのかを正確に捉えることが重要だと考えています。僕たちはスタートアップなので、限られたリソースの中で、いかに早くプロダクトを届けられるかが勝負になります。そのためには、作るものを間違えずに、スピーディーに提供する必要があるので、自分の目で現場を見て、一次情報を獲得することがすごく大事になってくるんです。
moya:
現場に訪問すると、開発者自身のモチベーションが上がりますね。机上の空論で開発していると、「これって誰のために作ってるんだっけ?」って思う瞬間が出てきます。でも、現場に行って、「〇〇病院の〇〇さんのために作ってる」と考えながら開発すると、最後のひと踏ん張りが全然変わってくると思います。あとは、意思決定とデリバリーのスピードが上がりますね。営業メンバーと一緒に病院を訪問した時に思ったのですが、営業メンバーだけだとお客さんから求められている課題がどれくらいの工数でできるものなのか、すぐに判断できないと思うんです。1度会社に持ち帰って、開発メンバーに確認しないといけないのは、すごくもったいないなと思いました。開発者が直接現場に行けば、その場で「それくらいだったら1日でできますよ」などと即座に判断できますよね。デリバリーの速度を上げるという意味でも、開発者が現場に行って、その場で課題を解決していくことにはすごく価値があることだと思っています。
hiryu:
確かにそうですね。言われてみれば、作ったものがどう使われているか、どう喜んでもらえているかって、意外と知る機会がないエンジニアも多いんですよね。でも、それってすごく大事で、使われている風景を見るとモチベーションに繋がりますよね。逆に、お客さんが触ってしんどそうにしているのを見て「これは改善できるな」って思えるのも、醍醐味ですね。
実際に、医療現場に足を運んだことで、具体的に解決の糸口となったようなエピソードはありますか?
hiryu:
MediOSが入院や麻酔の領域で使われているシーンを話せればと思います。病院の患者支援センターで、入院の持ち物や注意事項を説明するのに使われることが多かったんです。そこで、患者支援センターが実際にどんな業務をしているのか見学させてもらった時、看護師さんが患者さん一人ひとりに、入院までの期間に「お薬を飲むのをやめてください」とか「禁煙してください」といった指導をしている場面を目にしました。そこで、「もし、患者さんのスマートフォンにLINEで通知を送れば、この指導内容を忘れずに済むんじゃないか?」と思ったんです。そこから生まれたのが、今の入院支援という機能パッケージです。
amu:
他にもありますよ。MediOSは入院患者さんに対して動画視聴と問診票の回答をしてもらい、入院日や次の来院日までに必要な情報がリマインダーとして飛んでくる、というサービスを提供しています。運用を続ける中で、ある病院のスタッフさんから、「入院した患者さんが、数ヶ月後に再入院するケースがある」という話を聞いたんです。その再入院の際も、初回と同じように問診票に回答してもらう手間が発生していて、患者さんからすると「前回と同じ問診票をまた入力するのか…」という負担がありました。そこで、一度入力された問診票のデータを活用して、再入院の際は前回の回答データを表示し、患者さんの入力の手間を大幅に減らす機能を開発しました。この機能を提供して半年ほど経ちますが、再入院された患者さんからは「問診の入力がすごく楽になった」と喜んでいただいています。最初の開発当初は、1回の入院しか想定していなかったのですが、現場に足を運んで再入院される患者さんがいる事実を知ったからこそ、患者さんの負担を減らす改善ができたのは、現場に行くメリットかなと思っています。
MediOSはすごく実臨床に沿ったサービスですよね
hiryu:
MediOSの面白さはマーケットインで拡大できることにあります。MediOSが最終的に目指すのは、医療者と患者さんのコミュニケーションプラットフォームなので、動画をきっかけに、どういう業務や作業、コミュニケーションをシステムで置き換えることができるのか、という観点で考えれば、発想がすごく自由になります。エンジニアとしても面白いと感じる部分ですし、現場に行く理由になるのかなと思いますね。
コントレアのプロダクトチームの強みとは何でしょうか
moya:
メンバーがお互いをすごく尊重しているなと思っています。みんな経歴もバックグラウンドも違うんですけど、「あなたはこれがダメだ」みたいなコミュニケーションがなくて、お互いに改善し合えるんです。エンジニアは、思想が強い人が多くて「これはOK、これはダメ」みたいなことでぶつかることが結構あるんですけど、コントレアはそれが圧倒的に少ない。それは、お互いをリスペクトしているからこそできることなのかなと感じています。
amu:
チームの雰囲気でいうと、2つ感じているところがあって。1つは、とても前向きであること。コントレアのValueにもある「Go V Flight」にも通じるのですが、誰か一人が先頭に立って困難なプロジェクトを引っ張っている時も、周りが「どうすればこの困難な状況を抜け出せるか」と前向きに捉えて議論してくれます。チャレンジして失敗しても、周りがしっかりフォローしてくれるので、安心して動けるチームです。もう1つは、コミュニケーションがとても密であること。困った時にすぐに相談できる文化が根付いているんです。プロダクトチームとしてはメンバーの役割が分かれている部分もあるのですが、それぞれの強みを生かして、お互いにフォローし合い、相談し合えるので、安心して自分の動きができるんじゃないかなと思っています。チームの雰囲気以外では、やっぱりやりたいことができる環境ですね。言われたものを作るだけではなく、現場に行って 自分の見つけた課題を解決できる、その課題に対してチームで議論ができるっていうところが良い文化だと思っています。
hiryu:
2人が話していないところで言うと、「みんなが自分ごと化して取り組む環境」が強みかなと思います。ソフトウェア開発はチームスポーツなので、常にボールが転がっていて、誰かが拾わないといけないんですよね。誰も拾わなければ、システムはどんどん悪くなっていきます。そんな時に、「これは自分がやらなきゃダメだ」と思って、自然と一歩踏み出せるメンバーが多いんです。それが、お互いが気持ちよく働ける大きな要因になっていると思います。自分の役割を超えて、ちょっと飛び込んでみることができるメンバーには、すごく働きやすい環境だと思いますね。
どういうこだわりをもって日々開発されているのでしょうか。
moya:
「その場限りで開発しない」ということをすごく意識しています。どういうことかというと、一つの機能を作る時も、将来的に他の機能にも応用できるような、汎用性のある部品として開発するんです。例えば、LINEでメッセージを送る機能を作る時も、他のパターンで使えそうなら、後々の開発が楽になるようにモジュール化しておく。特に自分は開発チームの生産性を向上させるというところに責任を持っているので、開発メンバーが楽になるように今のうちに機能をモジュールすることを強く意識しています。開発しているとどんどん複雑化していってバグが多くなるという技術的負債が生じがちです。それを起こさせないために一定の開発のルールを整備したり、メンバー間で密なコミュニケーションを取ることで無駄なものを作らないように心がけていますね。
hiryu:
MediOSを使ってくださるお客さんが増え、機能もどんどん増えていく中で、より持続的な成長が求められています。とにかく大切なのは、お客様の要望を高品質な状態で、どれだけ早く定常的に届けられるかというところなので、定常的に届けるためにしっかり時間をかけて開発に取り組む時期が来ていると感じています。もやさんも話していましたが、一年後、二年後もMediOSが成長し続けられるような土台作りを、大事にして取り組んでいます。
amu:
1つは違和感を見過ごさないことだと思っています。例えば、画面の表示が少しずれているとか、ボタンの押し心地がイマイチだとか、本当に細かい部分です。でも、そういった細部へのこだわりが、医療従事者の方々に「良いクオリティのシステムだね」と評価されることに繋がってきますよね。また、患者さんの使いやすさも常に意識しています。入院や手術を控えて不安な気持ちの患者さんにとって、使いやすいシステムであることは開発やQA時に意識していることかなと思います。もう一つは、手段に固執せずに、課題に立ち返ること。自分たちが拾ってきた課題が、解決できる解決策を立てた時に、それがいかにスマートであろうが努力作品なのだろうが、やっぱりどっちの方が課題を解決できているのかが提供する価値としては大事なわけです。例えばAIを使ってすごく魅力的な機能を制作しても、それがちゃんと課題を解決できていなかったら意味がないと思うので、その解決策妥当性と課題がちゃんと見合っているのかっていうのは、細かく目を入れてやっています。
hiryu:
確かにね。新しい機能を作る時に「これ、実際使うとするとお客さんしんどいよね?」とか、「このレスポンスじゃ現場で使えないよね」という視点を、開発フローの中で必ずメンバーが言ってくれるっていうのが、いいなと思っています。
今後の展望として、目指している理想のプロダクトはどんなものか教えてください!
hiryu:
私たちが目指すのは、医療者と患者さんのコミュニケーションプラットフォームを作ることです。海外ではすでに当たり前になっていますが、日本ではまだ診察室などという限られた空間でしか医療者とコミュニケーションが取れないのが現状です。今後はより効率的で質の高い医療が求められる時代になっていくと思っているので、MediOSというメディアを通して、医療者と患者さんがお互いに質の高い医療を提供・享受できるようにコミットしていきたいです。具体的には、現在の動画を中心に、受診前の問診や、受診時の問診、自宅に帰ってからのメッセージ機能など、時間軸を広げていくイメージです。入院前から退院後まで、患者さんと医療者の生活をトータルでサポートし、お互いがより便利に楽になれるようなシステムを作っていきたいですね。
moya:
多くの病院で導入されるようになると、朝の受付時間などアクセスが集中する時間帯にシステムが遅くなる、といったことが起こりがちです。身近にいろんな方が使ってくださるためには、そうしたストレスなく使える、安定性が必要だと思っています。いつでも使える、使いやすいプロダクトにしたいなと思っています。
amu:
自分は、患者さんの記憶に残るサービスにしたいです。患者さんが病院に行ってMediOSを使うのは、入院や手術など人生の一大イベントなわけですよ。その不安が大きい状況で、MediOSが患者さんにポジティブな影響を与えられたら、きっと記憶に残ると思いますし、「このサービス、また違う病院でも使いたい」とか、「身内の患者さんにも勧めたい」と思ってもらえると信じています。患者さんの大きな人生の節目を、より手厚くサポートできるサービスにしていきたいなと思っています。
hiryu:
大事な視点ですよね。
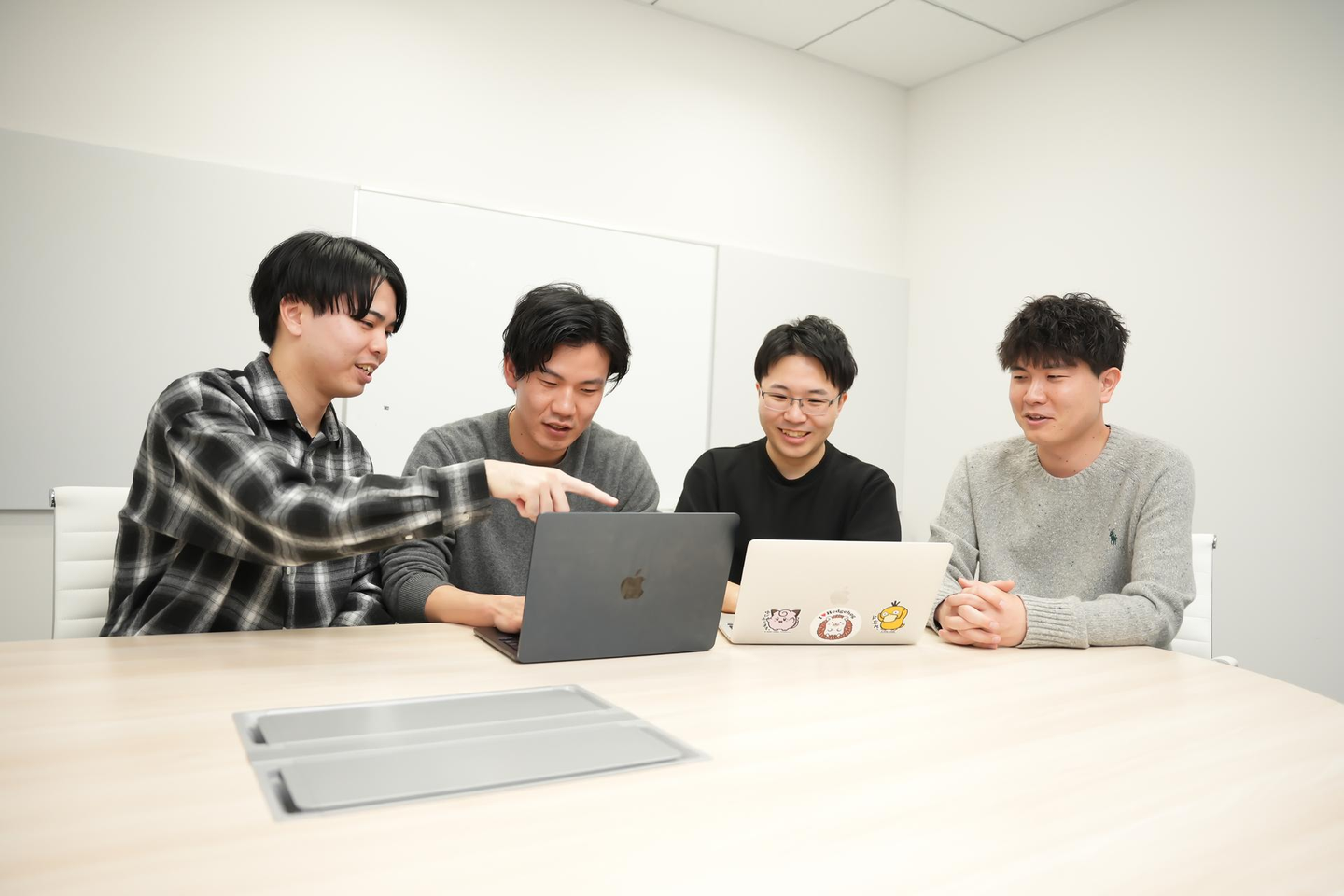
moyaさんは最近入社されたと思いますが、どのようにしてチームに溶け込んでいきましたか?
moya:
hiryuさんに「開発基盤を支えてほしい」と言われて入社しました。その際に一番意識していたのは、いきなり何でもかんでも改善しないことです。いきなり「この仕組みはダメだから変えましょう」と言うような人が入ってきたら、チームはなかなか受け入れようと思わないと思うんです。だから、報連相をしっかりする、アウトプットをしっかり出すなど、チームに対して信頼してもらうために意識していました。既存の環境をリスペクトしつつ、徐々に信頼を得ていくことで、自然と雑談も増え、チームに馴染んでいけたのかなと思います。
hiryu:
moyaさんが入社したタイミングは、初期の検証を抜け、プロダクトやチームを成長に耐えうるように改めて構築していく時期でした。その中で、もやさんはシステムやプロセスにおいて改善していくべき部分と、チームに言うべきことに対してとても誠実に向き合ってくれました。他のメンバーも、そういう姿勢を正面から受け入れてくれたので、うまくチームに溶け込んでいったんだと思います。お互いをリスペクトし合える人は、すぐ馴染めるんじゃないかなと思いますね。
amu:
そうですね。私もそうでしたが、チーム全体に新しい人を受け入れようとする雰囲気があるのが大きいと思います。困ったことをSlackで発信すると、すぐに誰かが拾ってくれたり、スタンプで反応してくれたり、他にも、朝のミーティングで雑談から入るなど、ウェルカムな姿勢で接してくれます。チーム自体に新しい人を受け入れる土壌があったので、私も入りやすかったのを覚えています。
最後に、どういう組織であり続けたいと思っていますか?それを踏まえた上で、どんな人にConteraに来てほしいかも教えてください!
amu:
課題にずっと向き合い続けるチームでありたいなと思います。私たちのチームは、課題を見つけて解決し、それを届けるサイクルをいかに早く回せるかで価値を出しています。このサイクルをフルに活かし、開発チームがもっと縦横無尽に課題に向き合えるようなチームでありたいです。他のチームと連携をしながら、プロダクトチーム主導で会社の社内全体に対してまだまだ影響を及ぼせると思っているので、そこはもっと伸ばしたいですね。
そんな環境で、失敗を恐れず何事もチャレンジできる人に来てほしいですね。ひたむきに課題に向き合うチームなので、トライ&エラーを繰り返せる人は向いていると思います。お互いを高め合いながら、チームを強くしていけたらなと思っています。
hiryu:
まさにamuさんがいう組織の形であり続けたいなぁと思います。あとは、常にワクワクできる組織にしたいです。新しい問題に直面した時でも、「面倒だな…」ではなく、「これをどうやって解決しよう?」とワクワクしながら、それを自分の成長の糧とできる好奇心がある組織でいたいです。課題を解決することがエンジニアの楽しさだと思うので、それをみんなで共有できるのが理想ですね。
どういう人にきて欲しいかは、とにかく好きなことがある人に来てほしいです。現場に行くことが全てではなくて、それぞれ役割が分かれていて良いと思っていて。技術的な課題、組織的な課題、どんな課題でも良いですが、何か課題を見つけて、それを自分ごととして取り組み、解決することを楽しめる人。そういう人と一緒に、ワクワクしながら働きたいですね。
moya:
他責にしないチームでありたいですね。不具合や、他のチームからの依頼に対しても、めんどくさがらずに、自分ごと化して前向きに取り組める。その姿勢が当たり前のチームでありたいです。自分の専門分野だけでなく、少しはみ出して他の人を助けることで、全員が高め合えるチームになれるといいなと思っています。
hiryuさんの言うとおり、課題を自分ごと化できる人に来てほしいです。誰かに解決してもらうのではなく、自分で課題を見つけ、人を巻き込みながら楽しんで解決できる人。そうして、お互いに成長できれば自分も楽しいです。開発が好きで、技術的な議論を楽しめる人であれば、さらに嬉しいですね。
編集後記:
最後までお読みいただきありがとうございました。
今回のインタビューを通して、コントレアのプロダクトチームの方々が、医療現場の課題だけでなく、その先にいる患者さんのことを第一に考えて開発されている姿がとても印象的でした。私はMedicalチームでインターンをしているので、完成したシステムを普段見ているのですが、開発の秘話や、皆さんの熱い想いを今回知ることができ、とても嬉しく思います。医療現場だけでなく、こうして患者さんのことを一生懸命考えてくれる方々がいる。そんなコントレアでインターンをできていることを、改めて誇りに感じました。インタビューを受けてくださったお三方、ありがとうございました!













