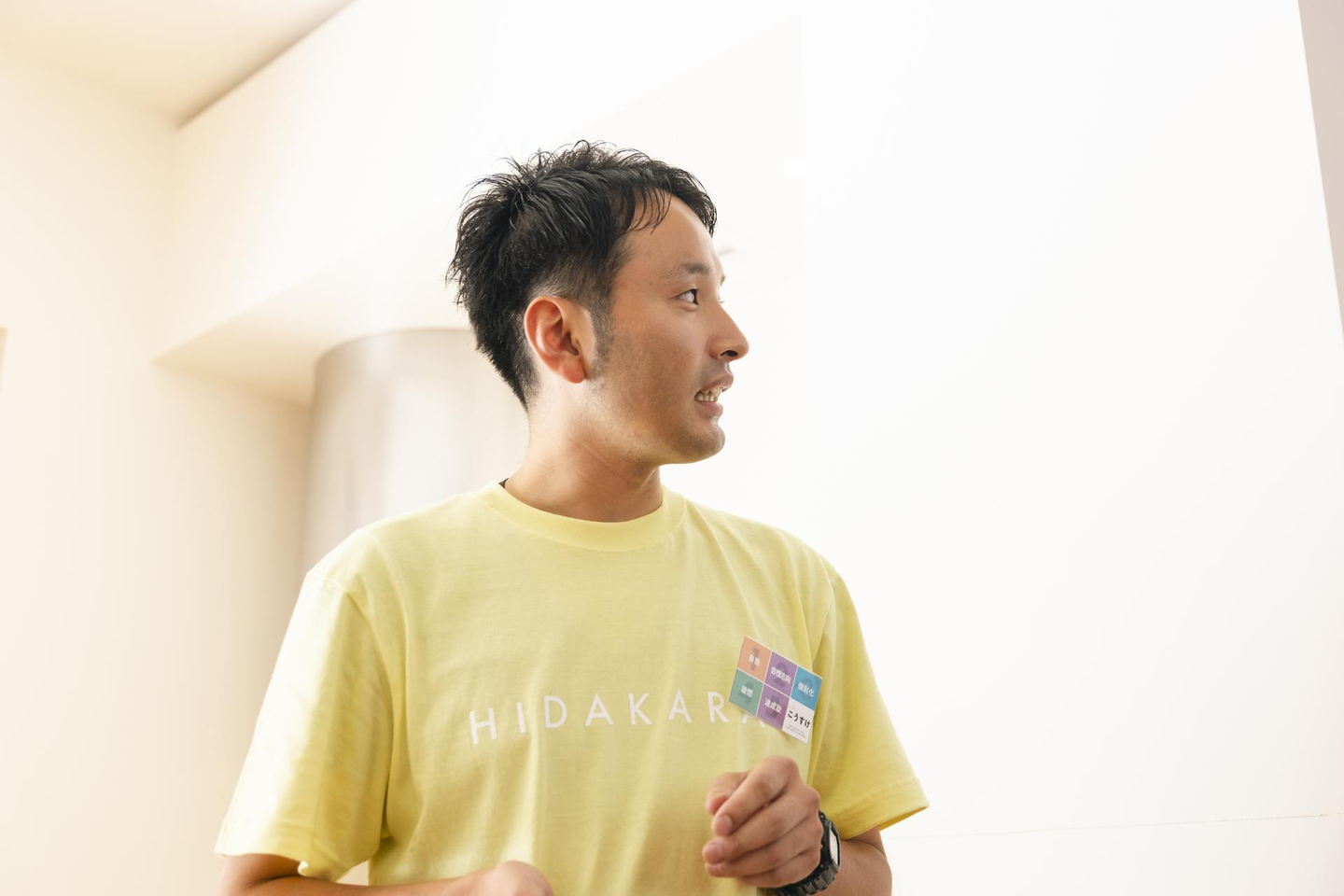【共同代表インタビュー後編】マーケ力で地域を元気に!飛騨で実現する地域貢献とキャリアアップ | 株式会社ヒダカラ
ヒダカラ共同代表インタビュー後編です。今回は、マーケティング力やスピードの秘訣、そしてこれからのヒダカラの挑戦について、インタビューしていただきました。前編はこちら「この商品は売れる!」――経験...
https://www.wantedly.com/companies/company_6183316/post_articles/954636
「地域のタカラモノを見つける」と言葉で言うのは簡単。でもタカラモノを見極める目と育てる実行力がなければ成しえないことです。加えて、地域創生には地域の人たちを動かす熱量も必要不可欠。
楽天出身でECマーケティングに強い代表二人をはじめ、スタッフ全員が「地域を元気にしたい」「地域の本当に良い物をより多くの人に知ってほしい」と本気で思い地方創生に取り組んでいるヒダカラ。
都市部ではできない地方だからこそできる面白さがあり、地方の手触り感を味わいながら、成長を目指しています。
今回は、どのような想いで地域と向き合い、何を想っているのかを深堀すべく、共同代表の舩坂康祐と舩坂香菜子へインタビューをしてもらいました!
ふるさと納税の寄附金合計額が60億円超え!地域への伴走で本気で取り組む地方創生
Uターンして初めて気が付いた、眠れる飛騨の魅力
桃農家との同級生との会話から始まった「飛騨のたからもも」が“地域の変化”につながる
ーーヒダカラは、一言でどのような会社なのでしょうか。
舩坂康祐(以下、こうすけ):
「“おいしい”と“オモシロい”未来を創る」をミッションに、「地域のタカラモノを見つけ、輝かせて、広めていく」会社です。岐阜県飛騨市を拠点にし、地域に深く入り込み、地域や事業者さんの成長にコミットして伴走することが私たちの特徴です。
船坂香菜子(以下、かなこ):
加えて、輝かせるものを私たちが作り出すのではなく、もともと地域にあるタカラモノを見つけ、地域のみなさんと一緒に輝かせることに重きを置いている会社です。
得意なWebマーケティングのノウハウを生かして、地域のタカラモノを見つけて輝かせるというスタンスで事業に取り組んでいます。
ーーヒダカラがこれまで支援したなかで、特に印象に残っていることをを教えて下さい。
こうすけ:
まずは、2022年に支援するふるさと納税の寄附金合計額が60億円を突破したことですね!自治体によっては私たちが支援を始めて、寄付額が100倍に増えた自治体もあります。
こういった結果が出せるのも、地域の皆さんが素敵なものを作っているからこそ。地方には、まだまだ世の中に知られていないたくさんの魅力があります。これからも私達は、地域の魅力を最大限輝かせるサポートをしていきたいと思っています。
かなこ:
最近は、たった数日で立ち上げた500万円を集めた製麺所のクラウドファンディングです。飛騨で9代続く製麺所がアクシデントに見舞われて困っていて。
もともとふるさと納税で関わりがある事業者さんなのですが、私達が関わってからとあるサイトの麺類カテゴリーで、何十週も連続して1位になるほどの人気に。あっさりしていてすごく美味しいんです!これまでその経緯を見てきているので、「緊急事態です」とご相談があった瞬間に、「なんとかしたい!できることをすぐにやる。」と決めました。
それで、クラウドファンディングを提案し、わずか4日で立ちあげることに…!スピーディーにクラファンを実施したことが功を奏し、支援総額500万円という想像以上の結果になりました。
今回の結果には、製麺所のみなさんも喜んでくれましたし、私たち自身が驚きました。
https://www.hida-kankou.jp/
こんなふうに、地域と私たちの距離感の近さと課題解決のスピードがヒダカラの強みだと思っています。
「ヒダカラが言うことなら全部やろう!」と言ってくださる地域の方々がいるのは、本当にありがたいですね。一生懸命やっていることが認められ、さらに仲間ができていき、やりがいと喜びを感じながら日々の仕事がほんとに楽しいんです。
ーーどのようなことがきっかけでヒダカラを立ち上げようと思うようになったのですか?
こうすけ:
僕の場合、地元が飛騨で、30歳の時にUターンしたのですが、最初は飛騨で事業を立ち上げるつもりはありませんでした。飛騨に住んでいたのは高校生までで、当時は地元の良いところを知らず、Uターンするまでは「都会のほうがいいかも」くらいの感覚でした。
でも改めて地元に帰ってみるて、今まで知らなかった地元のすごさに気づいたんです。飛騨はものづくりをしている方がとても多いんですよ。たとえば、1000年の歴史を持つ飛騨の匠と呼ばれる木工職人、自然豊かな環境で農作物を育てる農家、味噌醤油などの調味料、日本酒、工芸品の職人…。本当に素敵なもの、価値あるものを作っている方がたくさんいます。
でも、地元の人にとってはそれが当たり前すぎて、以前の僕のようにすごさに気づいていなかったり、良いものであることはわかっているけれど、売ること、伝えることまで手が回っていないという状況だったりして...。本当にもったいないなと思いました。
僕たちが販売や広報の部分をサポートできれば、地域のタカラモノが今よりもっと多くの人に届き、生き残っていけるのではないかと思い、ヒダカラを立ち上げることにしました。
ーーかなこさんはいかがですか。
かなこ:
私の場合は、出身も飛騨ではありませんし、最初は正直、夫のUターンにしぶしぶついて来た形でした。
でも来てみらた飛騨はすごくいいんですよね。私はヒダカラを立ち上げる前の3年間、楽天から飛騨市役所に出向する形でふるさと納税の仕事に従事したのですが、飛騨では暮らしと仕事がつながっていて、人のあたたかさもシビアさも感じられる、ほどよい町だなと思いました。
たとえば、一緒に仕事をしてる方と町でばったり会ったときに世間話ができるし、その方のご家族とも当たり前のように親しくなっていく。そういう関わり方が私にはとても楽しくて。自分の仕事が誰かのためになっていることを実感できる、地に足をつけて人との関わりのなかでリアルな仕事をしてるという手触り感がすごくあり、それがめちゃくちゃいいんですよね。仕事をしてると『あったかい』だけじゃなくてプライドを持って向き合ってる地域の皆さんから刺激ももらえる、この飛騨ならではの環境にハマりました。
ーー「地方を元気にできた」と思った具体的な事例や印象的なプロジェクトはありますか?
こうすけ:
ヒダカラ創業時からお手伝いしている「飛騨のたからもも」です。高校まで一緒だった幼馴染が、飛騨にUターンして、実家の桃農園を継いだんですよ。飛騨地域は桃の産地ですが、そのなかでも同級生の農園がある高山市国府町の桃は特に美味しいと地元では以前から知られていました。ですが、量があまり多く採れないため、当時は全国的な知名度が低く、後継者もいないという課題があったそうです。
その幼馴染と食事に行ったときに、他地域の桃より地元の桃の価格が安いことがとても悔しいと話していて。実際、他の桃産地と比べても遜色がないほど糖度が高いにも関わらず、有名な桃産地の半値でしか売れない、そのために後継者もいないという現実を初めて知りました。
地元の居酒屋で、「これはちゃんとやれば絶対もっと売れるよ!」と熱く語ったのを覚えています(笑)。「地元の桃をなんとかブランド化して売りたい!」と、一緒にブランドを立ち上げて販売することにしました。
ーー桃をどのようにブランディングしたのですか。
こうすけ:
飛騨の桃はポテンシャルがとても高く、飛騨という地域の魅力を凝縮したような商品だとだと改めて感じたので、幼馴染を含め、みんなで考えて「飛騨のたからもも」というブランド名にしました。
僕自身、桃を通じて飛騨の魅力を改めて強く感じ、こだわりを持ってひたむきに桃づくりに取り組んでいることに感激したので、「飛騨の人里離れた場所で真面目につくった桃」であることを伝えたく、その想いをブランド名に反映しました。このネーミングを軸に、写真やページ、パッケージ、同梱物、また品質面で基準を設けて訴求をしました。ネット通販やふるさと納税を活用したところ、全国から熱い反応をいただいています。
発売から5年経過した今、桃の値段は1.5倍から2倍になりました。売れたこと自体ももちろん嬉しいのですが、それ以上に、この取り組みが一時的な取り組みやブームで終わるのではなく、持続可能な形で根付いていることが何より嬉しいと感じています。
最初は「なんとかブランド化しよう!」と勢いで始めたプロジェクトでしたが、今では桃の品質の高さが認められ、食べチョクで評価されたり、ファンも増えてきました。
特に、幼馴染の農園が家族経営から法人化し、若い世代を雇用するまでになったのが大きな変化です。雇用に関しては私たちが何かをしたわけではないですが、家族運営から持続的に農業を続けられる体制を築いている姿を見ると、この取り組みが地域の未来にもつながるものだったのだと実感します。
この1~2年でも、関連した桃のアイスが商品化したり、桃のお酒を作ったり、農園でのリアルイベントを開催したり…といろいろな取り組みが双方から生まれています。
この「飛騨のたからもも」の取り組みが、今後も地域の誇れるブランドとして成長し続けるよう、これからも一緒に挑戦していきたいと思っています。
ーー今はヒダカラさんも実績がありますが、事業を始めたばかりの頃は信頼してもらえたのでしょうか?
かなこ:
創業当時のヒダカラは実績もなく、事業者さんは半信半疑だったと思います。思い出深いのは「こくせん」という飛騨の伝統的な和菓子を作っている、とある和菓子屋さんです。「こくせん」は100年続く飛騨高山の銘菓なのですが、そのなかで私が特別惚れ込んだこくせんがありました。
しかし、基本的には卸売りをしないというスタンス。でもどうしてもヒダカラの自社通販で取り扱いたくて職人でもある社長に直接会いに伺い、「本当においしいから、こういう商品をこんなふうに展開していきたい!」と私たちの想いを何度も伝えて。
その結果、ヒダカラで取り扱いさせていただくことになりました。最近になって「あのときは詐欺かと思ったわ」と社長に言われました(笑)。でも、ネット展開したことで、反響が大きくなったと喜んでいただき、熱意を持って取り組んで良かったと思っています。
ーーヒダカラが関わることで地元の商品の売上を伸ばす一方、職人さんから「これ以上の数はつくれない」といった反発などはないのでしょうか。
かなこ:
2020年にヒダカラを創業してからこれまで、そのような反応をいただいたことはありません。
私たちは一方的に「売りたい」「売ってあげる」ような感覚はいっさいなく、事業者さん自身が「売りたい、全国の人に知って欲しい」と思うところからスタートするようにしています。私達だけが頑張るのではなく、一緒になって本気で考えてもらって、そこにヒダカラが伴走することが大切だと思っています。
ーーヒダカラが関わることで地域の事業者さんにはどんな変化があるのでしょうか。
こうすけ:
ありがたいことに、僕たちがお手伝いをして売上が伸びることで商品価値に気付いたり、新たな取り組みに目を向けて挑戦している事業者さんがたくさんいます。新たな設備投資や雇用ができるようになったという嬉しい声も聞き、そういった変化に少しは貢献できていると思うと、励みになります。
ーーまさに、伴走を通じて地域の方と想いをひとつににしているのですね。
私もヒダカラも飛騨の方々に育ててもらったという思いがあります。これから事業を通じて、飛騨にもっと恩返しをしていきたいです。
ここまで前編では、ヒダカラの本気の地方創生への想いや実例を伺ってきました。後編では、成果を出せる秘訣である「楽天仕込みのマーケティング力」についてさらにお話しを聞いていきます!
後編はこちら↓