- AIプロダクトマネージャー
- テックリード
- Customer Success
- Other occupations (25)
- Development
- Business
- Other
「攻め」を支える「守り」の哲学。管理部長が語る、スタートアップを急成長させる組織の作り方。
「このままでは、自分の市場価値は無くなってしまう」。安定した大企業で確立された業務に取り組む日々に、彼は強い危機感を抱いていた。会計事務所、おもちゃメーカー、上場企業。多彩なキャリアを通じて彼が追い求めたのは、自らの手で組織の血肉を創り上げ、事業の成長を根幹から支えるという挑戦だった。
今回は株式会社SHINSEKAI Technologiesの管理部長・矢内賢一に、安定を捨ててスタートアップに飛び込んだキャリアの転換点から、事業のスピードを止めない管理部門の哲学、そしてIPOを見据えた強固な組織基盤の作り方について、話を聞きました。
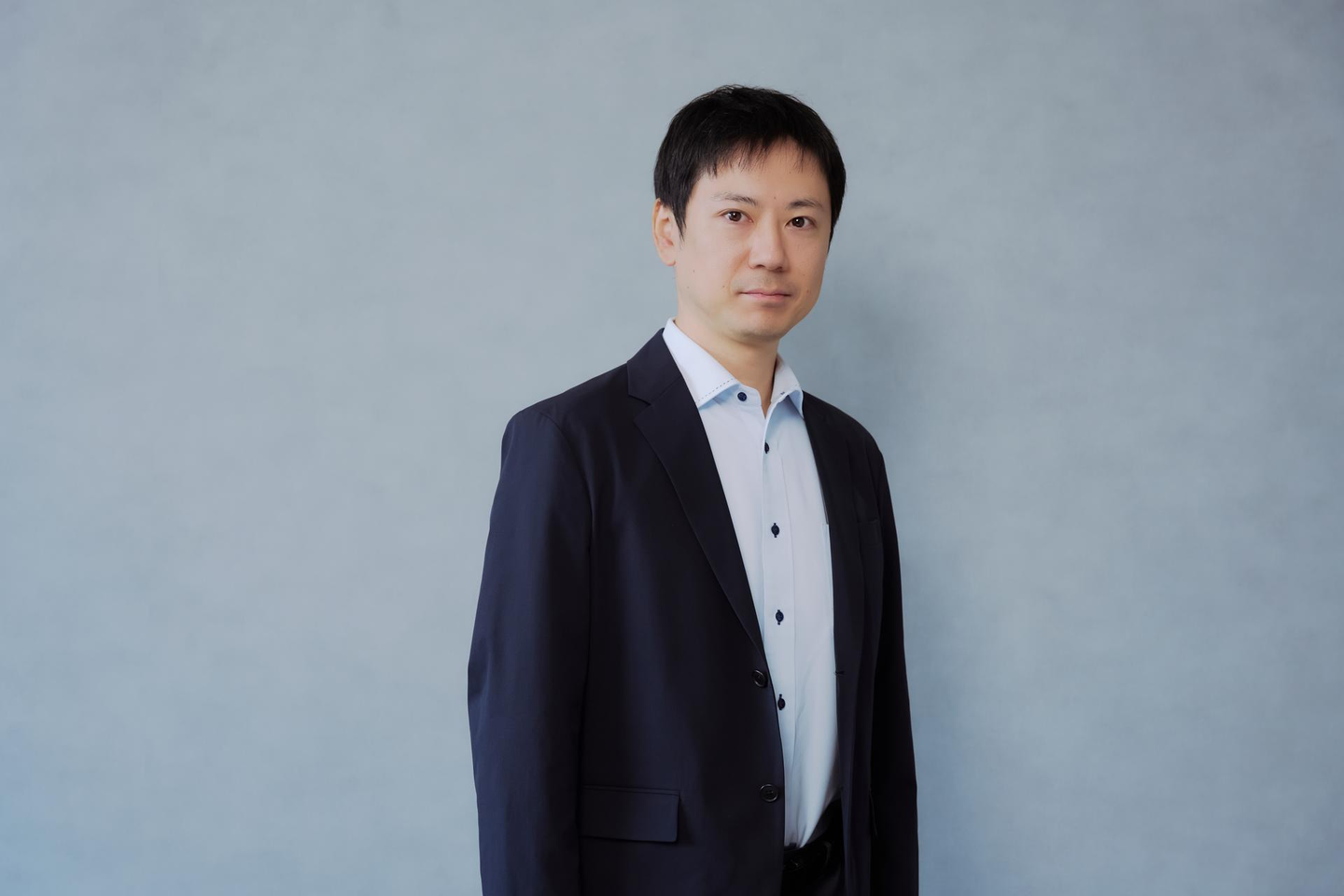
株式会社SHINSEKAI Technologies
管理部部長
矢内 賢一
「危機感」がすべての原動力。安定を捨て、ベンチャーへ
──はじめに、矢内さんのこれまでのキャリアについて教えてください。
新卒で会計事務所に入社し、6年間、個人の確定申告や法人の決算、労務手続きなど、バックオフィス業務の基礎を学びました。その後、ご縁があって大手おもちゃメーカーに転職しました。
そこでは経理・財務担当として、グローバルな経理業務から資金調達、為替リスク管理まで幅広く経験させていただきました。安定した環境で着実にキャリアを積むことができましたが、次第に、確立された業務範囲の中だけでなく、より裁量権を持って新しい挑戦がしたいという想いが強くなっていきました。
このままでは自分の市場価値は無くなってしまう、という危機感もありましたし、終身雇用が当たり前ではない時代に、一つの会社に留まるのではなく、どんな環境でも通用する専門性を身につけたいと感じたんです。
──それが、ベンチャー企業を目指すきっかけになったのですね。
はい。経理だけでなく、労務や総務など、バックオフィス全般を広く見て会社の成長に貢献したいと考え、スタートアップへの転職を決意しました。ただ、私には上場企業での経験がなかったため、まずは修行として上場企業に転職し、そこで1年半、経理と労務を担当しました。
37歳での転職だったので、とにかく時間がありませんでした。周りの若いメンバーが成果を出していく姿に煽られ、毎朝8時に出社して23時まで仕事と勉強に打ち込む毎日でしたね。電車で吐きそうになるくらい大変でしたが、この1年半でやりきったという自信が、次のステップに繋がりました。
──安定した環境からベンチャーへ移ることについて、ご家族の反応はいかがでしたか?
大反対でしたね。おもちゃメーカーを辞めること自体が大反対でしたから。ですが、「家族を支える責任は自分がしっかり持つから、この挑戦をさせてほしい」と熱意をもって伝え、最終的には理解を得ることができました。

最後の決め手は「社長の情熱」。シンセカイテクノロジーズへのジョイン
──数あるベンチャーの中から、なぜシンセカイテクノロジーズを選んだのでしょうか?
転職活動では、経理職の転職市場が活発だったこともあり、エージェントから企業を100社ほど紹介されました。しかし、なかなか「成長産業だ」という実感が湧くものがなかったんです。そんな中で、シンセカイが「コミュニティ」という新しい領域にチャレンジしていることを知りました。この領域の可能性と、面談で感じた社長の熱意に強く心を動かされたんです。
最後は2社で迷っていましたが、決め手は社長の人柄と事業にかける想いでしたね。周りを巻き込む力というか、その求心力がすごいんです。それでまずは業務委託から、という形で関わり始めました。
守りだけでなく「攻めを助ける」。スタートアップ管理部門のミッション
──現在、管理部門の責任者として、どのようなことをされていますか?
バックオフィス全般です。経理・財務・総務・法務・労務、そして上場準備や広報・IRなど、非常に幅広い領域を担当しています。
──チームに課せられているミッションは何でしょうか?
スタートアップの管理部門は、守りだけでなく「攻めることを助ける」のがミッションです。会社の急成長を支える羅針盤として、そして縁の下の力持ちとして、組織の基盤を支える存在でなければなりません。具体的には、以下の3つをミッションとして掲げています。
- 経営判断を支えるための正確な情報提供
- 成長に耐えうるオペレーションとコストの最適化
- 安心して事業活動に専念できる環境整備
事業のスピードを止めないように、事業部との「橋渡し」をすることが最も重要だと考えています。
──現在のフェーズで、最も重要視している業務は何ですか?
シンセカイは現在、事業成長とIPO準備を両立させなければならない非常に重要なフェーズにあります。そのため、管理部門としては「守り」を固めつつも、「攻め」を加速させるための仕組み作りが急務です。
特に重要視しているのは、「資金調達」と「ガバナンスの強化」です。スタートアップは常にキャッシュとの戦いですから、コストを下げ、利益を最大化し、外部から資金を調達することが会社の生命線になります。
同時に、上場を見据えたガバナンス体制の構築も不可欠です。具体的には、予算実績管理体制の整備、迅速な意思決定を支えるワークフローの設計、そして契約・与信管理などのリスク管理体制の確立などです。インサイダー取引のリスク管理や、ハラスメント防止など、見落としがちな部分のルールを整備し、会社全体に周知徹底していくことも大切な仕事です。
3年後の理想と、AIが変えるバックオフィスの未来
──3年後、シンセカイテクノロジーズの管理部門は、どのような理想の姿になっていると思いますか?
3年後ですね。組織としては、CFOと共に私がコーポレート全体を統括し、経理、財務、総務、経企など、各分野の専門的なリーダーがいる6〜7人規模のチームになっているのが理想です。
これは、将来のIPO(株式上場)をしっかりと見据えた上で、その先のプライム市場へと成長していくための強固な基盤となる組織です。管理部門が弱いと、何かあった時に会社全体が揺らいでしまいます。逆に、ここが強固であれば何があっても大丈夫。自分の手で、そんな最強の組織を作りたいですね。
将来的には、バックオフィスが個人の経験や勘に頼るのではなく、複数のAIエージェントの従え、リアルタイムのデータを活用できる「経営の推進機能」を実装し、オペレーションから解放されたメンバーが「羅針盤」として付加価値の高い業務に集中できる体制を目指します。
──ご自身の役割については、どうお考えですか?
私自身がチームの核として組織を支えていくことはもちろんですが、それ以上に、私と同じ、あるいはそれ以上のリーダーを育てていくことが重要だと考えています。社長が目指す、日本を代表するような企業規模になるには、一人では限界がありますから。自分と同じレベルで考え、動けるリーダーを何人も作っていく。それが3年後に向けた私の大きな目標です。
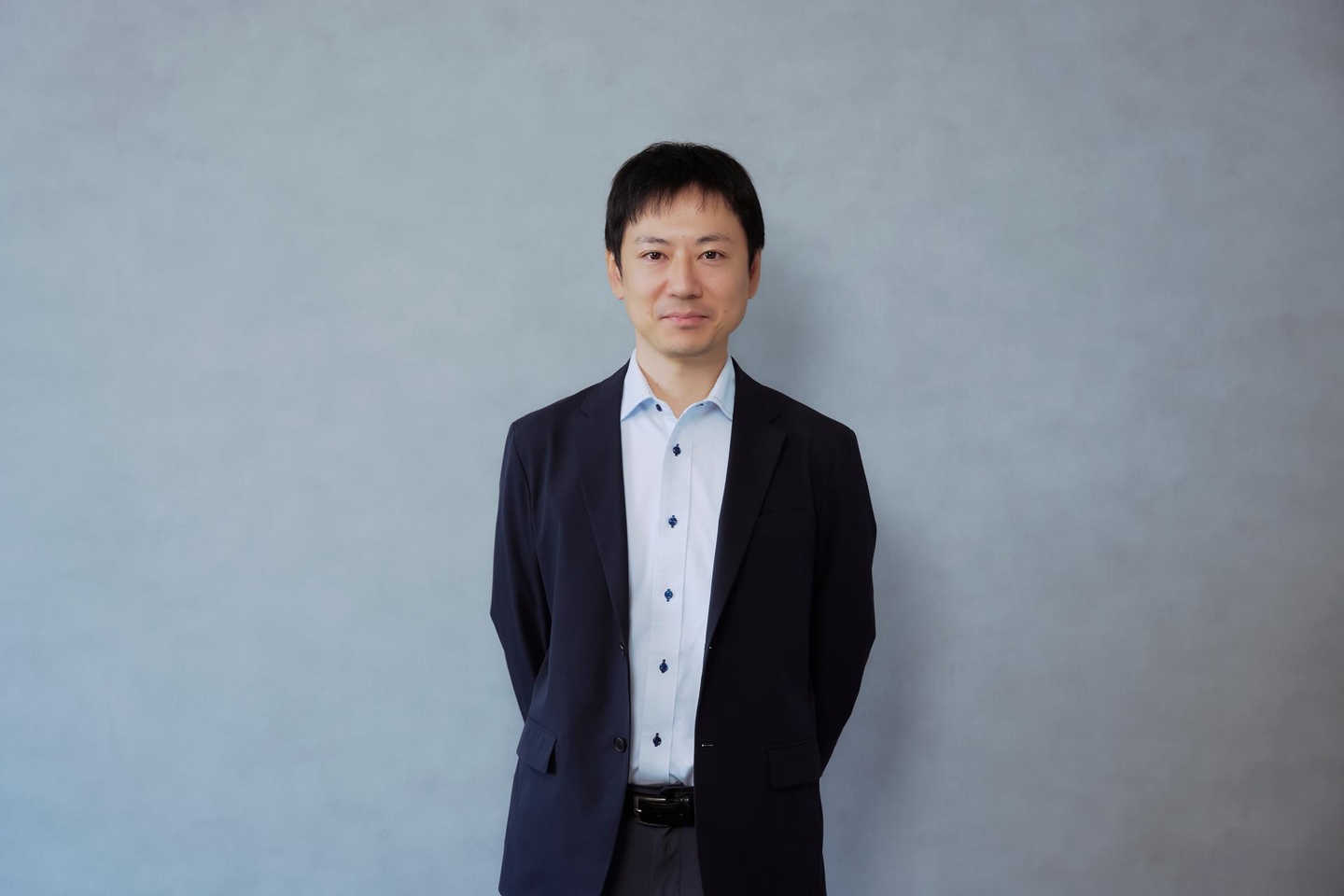
未来のメンバーへ。自ら価値を創り出す、挑戦者求む。
──シンセカイテクノロジーズで働くことの魅力と、逆に大変さを教えてください。
大変なこととしては、事業の成長スピードと、それに伴う変化の激しさですね。スタートアップでは、事業計画のピボット(方向転換)も起こり得ます。事業の舵が切られる時、管理部門はそれを支えるために猛烈なスピードで動かなければなりません。新しい計画に合わせて予算を再策定し、資金繰りを考え、法務・労務面でのリスクを洗い出す。会社の未来を左右する判断を、限られた時間と情報の中で下していく。その責任の重さとプレッシャーは、安定した組織では味わえない大変さだと思います。
また、まだなにも整っていないこと、そのものも大変さであり、面白さでもあります。例えば最近のオフィス移転一つとっても、ただ引っ越すだけではありませんでした。引っ越し業者など複数の業者と同時に交渉を進め、コストを最適化する必要がありました。諸手続きも自身で行います。移転後も、ゴミ箱やトイレットペーパーの補充といった細かなルールから、個人情報保護観点でのセキュリティレベルの維持まで、文字通りゼロから会社の「当たり前」を創り上げていかなければなりません。決められたレールがない分、大変さはありますが、それこそがこのフェーズの魅力だと感じています。
──最後に、未来のメンバーに期待することを教えてください。
AIの登場で、もはや「専門性」だけを突き詰めることに価値がなくなりつつあります。「自分の領域はここまで」と線を引くのではなく、自分の専門領域にプラスして、周辺領域にも積極的にチャレンジしたいという意欲のある人と一緒に働きたいですね。
自分自身で目標を設定し、必要なスキルを習得し、会社にインパクトを与える。その結果として会社が成長し、自分の評価も上がる。そして、チームも同様。私自身できないことはたくさんあります。それをチームでお互いに補完し合いながら、切磋琢磨して高みを目指していける仲間を求めています。
シンセカイテクノロジーズでは、「メンバーが働きやすい環境づくり」にもスピード感を持って挑んでいます。共にシンセカイテクノロジーズを盛り上げてくれるメンバーを募集中です!カジュアル面談も実施中ですので、下記のリンクからお気軽にお問い合わせください。

/assets/images/22290701/original/8e172b49-6671-4362-b83c-9dafe46e1e61?1760679533)

/assets/images/22311234/original/e2cab252-4481-4550-9c20-35df55e5dae5?1761014586)

/assets/images/22311234/original/e2cab252-4481-4550-9c20-35df55e5dae5?1761014586)

