2025年1月、TYPICAのヨーロッパチームに新たなコミュニティマネージャーが加わった。10代の頃からコーヒー生豆のサプライヤーとして働くことを夢見ていた、アメリカ・ミネソタ州出身のジャクソン・ブースだ。
アメリカの大学で国際ビジネスについて学んだ後、コロナ禍において期間限定のオンラインストアを5ヶ月ほど運営。その後、フランスの大学院でのMBA取得、日産自動車やフリーランスでのマーケティング経験を経て、TYPICAの一員となったジャクソンは今、4年ほど住んだフランスを中心に新規顧客の開拓、既存顧客との関係深化に努めている。
高校生時代にコーヒー店でバリスタとして働く中で、コーヒーを取り巻く世界の広さや深さに魅せられてから約10年。その情熱を空回りさせることのないスキルやノウハウを身につけたうえでTYPICAで働くようになったジャクソンを突き動かしているものとは?
夢中になれる人生を
人生、好きだったものが嫌いになることもあれば、何かの拍子に大して興味がなかったものを好きになることもある。
人口100人程度の田舎町で生まれ育ち、16歳のときにミネソタ州のロースターでバリスタとして働き始めたジャクソンにとって、コーヒーは「特別な思い入れがない」存在だった。それこそ「給料を上げたいなら、焙煎士の資格を取って焙煎するという道もあるよ」というオーナーの提案が、熱を上げて取り組もうと思った最初のきっかけだったのだ。
だが、ほんの軽い気持ちで足を踏み入れたことで、世界は一変する。100時間の実習をする傍ら、書籍や動画を通してコーヒーについて学ぶ過程で、ジャクソンはすっかりコーヒーの世界に魅せられていた。

「焙煎の仕方によってはカップの味やプロファイルまで調整できるところにワクワクしたんです。要は、自分のクリエイティビティを発揮できる余地があるということ。
これは後々気付いたことですが、意図したものであれ、意図しなかったものであれ、コーヒーは一杯ごとに違う味を体験できる。そしてその違いには必ず理由があって、掘り下げようと思えばいくらでも掘り下げられる終わりなき世界なんですよね。
加えて、世界の遠いところからはるばるやって来たものを飲んでいるという実感も刺激的でした。いずれは世界を旅して生産者とつながり、素晴らしいコーヒーをカフェやロースターに届けたいという思いが自然と湧いてきたんです」
とはいえ、ジャクソンの中には、地に足をつけて物事を考える冷静な自分がいた。世界を股にかけてコーヒーに関わる仕事をするなら、信頼されるラベルが必要だろう。そう考えたジャクソンは、国際ビジネスを学んだ学士課程を終えた後、MBAを取得するためにフランスに渡って修士課程へと進んだ。
修了後はアメリカに戻る予定だったが、「人も、食も、文化もすべてが気に入った」ジャクソンはフランスに残ることを決める。しかしコーヒー生豆に関わる仕事は見つからず、結局、修士課程中にインターンをしていた日産自動車に就職。マーケティングマネージャーとして、担当する2台の車種のマーケティング施策を統括するなかで、データ分析や予算管理、部署を超えたマネジメントなどのスキルを体得した。
「日産で働けてよかったのは、情熱や愛着を持って仕事をしている人に囲まれていたこと。僕自身は車にあまり情熱を持てなかったけれど、彼らからはいい刺激やエネルギーをもらうことができた。チームの一員として自分の役割を全うしようと考えていたので、2年間は転職のことも考えず目の前の仕事に集中していましたね」
そんなジャクソンに“目覚めの時”が訪れたのは2024年のことだ。長期休暇中に、親友と一緒にスペインの9つの街を巡ること2週間。その一つひとつがまっさらな記憶として心に刻まれていくような美しい風景や友人と過ごす時間、旅先で出会った人々との触れ合い……。旅の魔法は、潜在意識の中で眠っていた願望を呼び起こした。
発見と情熱に満ちた日々をこの先もずっと味わい続けられるように、もう一度コーヒーの世界に戻ろうーー。転職に向けて本格的に動き出したジャクソンは、もともとつながりのあったTYPICAのスタッフに連絡を取ったのである。
「日産時代も、同僚たちの姿を見ていて羨ましかったんですよね。僕もこんなふうに何かに夢中になれる人生を送りたいと思わずにはいられなかった。とにかくずっとコーヒーの世界に戻りたいという気持ちはあったけれど、いつ、どんな形でそれを実現できるのかはわからなかったんです」

いわばロースターのコンサルタント
「遠回り」とも言える形でTYPICAに入社し、再びコーヒーとがっぷり四つに向き合うようになったジャクソンだが、人生に無駄はない。日産自動車時代にマーケティングマネージャーとして磨いたスキルは、TYPICAでも確実に役立っている。フランス、ドイツ、ベルギー、スイスのロースターとの関係深化や新規開拓を進めていくうえで、「数字に強い」ことが強みになっているのだ。
「常日頃から心がけているのは、お客さんが必要としている情報を聞かれたらすぐに提示できる状態にしておくこと。たとえば生豆の購入代金の支払い方法は複数あるのですが、すべての選択肢ごとの支払い総額や支払いスケジュールなどをあらかじめ資料にまとめたうえで商談に臨んでいます。『後でご連絡します』『ウェブサイトで確認してください』と返答していたら、機会損失につながりかねませんからね。
ロースターは基本的に、とても忙しい人たちです。規模の小さな事業では、一人で複数の業務をこなしているような状況だし、規模が大きく、ある程度分業化されているところでも、生豆の調達に関わる責任の重い仕事を任されている人は膨大な仕事を抱えている。だからこそ、お客さんが『知りたい情報』をできるだけシンプルかつ迅速に届けることに価値があると思うんです」
その甲斐あってか、ジャクソンは入社後半年未満ながら、フランスでは順調に新規顧客を獲得している。
「自分が加わるより前にTYPICAが積み上げてきた信頼があること、フランスに4年ほど住んでいてフランス語を話せること、フランスの人たちの商慣習や暗黙知的なところを肌感覚で理解していること。そういった基盤があるのは前提として、各ロースターとの対話やヒアリングにじっくり時間をかけたことが一番大きいと思います。
基本的に、新しい人と出会うときはいつも、その人のことをもっと知りたいという思いが真っ先にあります。相手のことを深く知れば知るほど、彼らのニーズに合わせた提案や対応ができて、ビジネスの成果にも結びつきますしね。
たとえ現時点で彼らのニーズにマッチするものがなくても、彼らが何を欲しているか、何を望んでいるかを認識していれば、それが手に入ったときにすぐに彼らの顔が思い浮かんで、連絡を入れられる。そういう個別ニーズに寄り添った働きかけが、信頼関係につながっていくのかなと。彼ら自身が成功できるように最大限サポートすることが自分の役割。彼らのコンサルタントになっている感覚はあるんですよね」

誰もがキーパーソンになるコーヒーの世界
ジャクソンが人生ではじめて抱いた夢は、「有名なミュージシャンになること」だった。両親や姉をはじめ、家族皆が楽器の演奏や歌唱を楽しむ環境で過ごしていたからである。
だが誰もが一度は抱くような淡い夢は、10代始めの頃には消えていた。突出した才能があるわけでもないうえに、表舞台でスポットライトを浴びる生き方が自分には合ってないと感じたのだ。
「コーヒーのおもしろいところは、目立たなくても成功できることかもしれません。バリスタやロースターのチャンピオンにならなくても、クリエイティブでいられます。特にスペシャルティコーヒーの領域では、サプライチェーンにおいて重要な役割を担っていない人なんていませんからね。
生産者はどんな品種を選ぶか、農園をどう管理するか、どう精製するかといったことを自分たちで決められる。焙煎士は焙煎度合いやプロファイルによって、バリスタは淹れ方や抽出レシピによって、コーヒーの味をコントロールできる。要は、一人ひとりの意思や創意工夫が、コーヒーの価値を左右するんです。
僕にとって、マーケティングとコーヒー、そして今でも趣味でやっている音楽に共通しているのは、創造性を発揮できて、自分自身を表現する手段でもあるということ。特にコーヒーは自宅のキッチンで淹れるだけでも、クリエイティブな要素がありますからね。
逆に言えば、自分で何かを創り出している感覚がないと、人生は退屈になってしまう。前職時代、仕事が時々、目の前の数字を追いかけるだけの作業と化していたことも、コーヒーの世界に戻るべきだという動機づけになったんです」

2020年、学士課程を終えてから修士課程が始まるまでの5ヶ月間、コロナ禍でのオンライン購買に商機を見出したジャクソンは、自分で焙煎したコーヒーを販売する期間限定のECサイトを立ち上げ、運営した。口コミの活用や見せ方の工夫、期間限定をうたう販売戦略など、自身の創造力を駆使することで、たとえまったく同じ商品でも顧客のワクワク度は変わり、購買行動に結びつくのだ。ゼロイチを生み出すそのプロセスに、ジャクソン自身が誰よりもワクワクしていた。
「昔から何かにつけて可能性を見出そうとするというか、今の状況でできることはないかと考える習慣はあると思います。学校の生徒や先生、近所の住人を相手にポップコーンやソーダを売り歩いていた10代の頃には、人と関係性を築くことが売り上げにつながるという成功体験を得ることができた。生活必需品ではないけれど、あると嬉しいし、人が笑顔になる。その点では、ポップコーンやソーダとコーヒーは同じですよね」
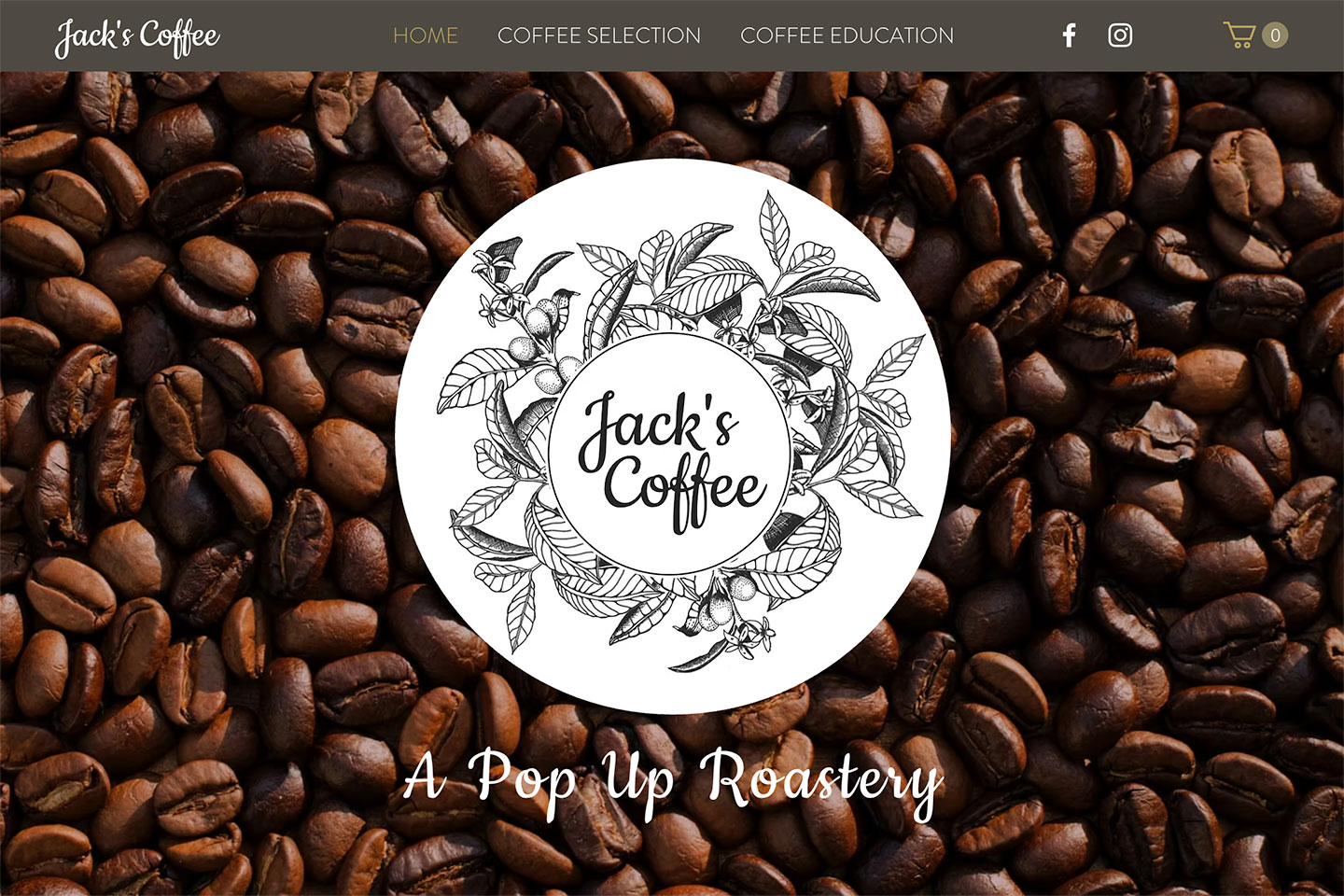
つながりが新しいつながりを生む
ゼロイチをつくり出す手段は、必ずしも起業や創作活動だけには限らない。「一人ひとりが経営者である」組織を目指しており、個々の裁量が大きく、社内起業をしているような感覚を味わえるTYPICAは、ジャクソンにとって自然と肌が合う環境だった。
「相手が望んでいる場合に限りますが、ロースターを相手に商談する場合、生豆のことに限らず、焙煎やカフェの運営に関しても、彼らのチームの一員になった感覚でアイデアを出しています。彼らも自分でビジネスを始めたアントレプレナー。僕と似たようなマインドセットを持っているから、対話するのはとても刺激的で楽しいんですよ。
つくづく思うのは、ロースターが誰から/どこから生豆を買うかという決断もつまるところ、個人的な関係に大きく左右されるということ。フランスがよい例ですが、この人は信頼できる、この人に共感する、この人が好きだ…といったごくシンプルな感情から生まれたつながりが新しいつながりを生んでいるし、そのネットワークは加速度的に広がっていくと信じています。
TYPICAは、Webサイトや人を媒介して、『語るべきものを持っている生産者』や『注目されるべき生産者』のコーヒーや彼ら自身にスポットライトを当て、その魅力を広める拡声器の役割を果たしている。それぞれのコーヒーが名もなき存在にならないように工夫されているんです。だから僕には、できるだけ解像度高く、生産者についてロースターに伝える責任がある。
TYPICAで働いていると、“何か大きくて意味のあるものの一部になっている”という感覚を得られます。2030年までに(質・量ともに)世界一のコーヒー生豆のダイレクトトレードプラットフォームになるという目標の達成を目指す過程で、僕たちの価値観を世界に広めていきたい。だからこそ目の前のお客さんと丁寧に向き合って、信頼と成果を積み上げていくことが大切なんです」

/assets/images/6505701/original/9e0a8c36-3eba-422d-8ed3-710a498969dd?1617521362)


/assets/images/6505701/original/9e0a8c36-3eba-422d-8ed3-710a498969dd?1617521362)
