目次
KPI進捗ミーティングとは? 〜数字を追うだけではない"対話の時間"〜
裁量はある。でも「投げっぱなし」じゃない。
「思考の深度が増した」長の変化
「数字を見るって、ちょっと面白い」久保田の気づき
「成果を出せるデザイナーに近づいている!」米倉の喜び
「いつでも相談できる」早坂が感じる安心感
「目標達成を当たり前の文化に」〜社長が描く、ミーティングの先にあるもの〜
この環境が合うのは、こんな人
"任せる"だけじゃなく、"信じて、支えてくれる"環境
SNS運用・広告制作・WEBサイトのディレクションなど多様なプロジェクトを支えるデジゴリのメンバーたち。その共通点は「自分の仕事が、ちゃんと成果につながっている」と実感できていること。
でもその裏には、"ただ任せる"ではなく"信じて育てる"カルチャーがあります。
今回は2週に1回行われる「KPI進捗ミーティング」を通じて見えてきた、裁量と支援のバランス、そして「あたたかくて、ちゃんと成長できる」デジゴリの魅力をご紹介します。
【メンバー紹介】
- 長 拓也:マーケティングDX事業部 ディレクター/二郎ゴリラ
- 米倉 幸花:マーケティングDX事業部 デザイナー/ヌマゴリラ
- 早坂 祐人:マーケティングDX事業部 ディレクター/はちみつゴリラ
- 久保田 真拓:業務改善DX事業部 ディレクター/生成AIコンサルタント/源ゴリラ
KPI進捗ミーティングとは? 〜数字を追うだけではない"対話の時間"〜
デジゴリでは2週間に1回、メンバーが社長の菊池と1対1で行う振り返りの時間を設けています。
一般的なKPI管理とは異なり、このミーティングでは「数字」だけでなく「思考プロセス」が重視されます。メンバーは自分の担当業務のKPI(重要業績評価指標)について、その数字に至るまでに考えたこと、次にどうするかを考え、社長と対話します。
社長はメンバーの思考に寄り添い、時には新たな視点を提示し、時には背中を押す。若手が多いデジゴリでは、この「考える習慣」を身につけるための仕組みとして、KPI進捗ミーティングが機能しています。
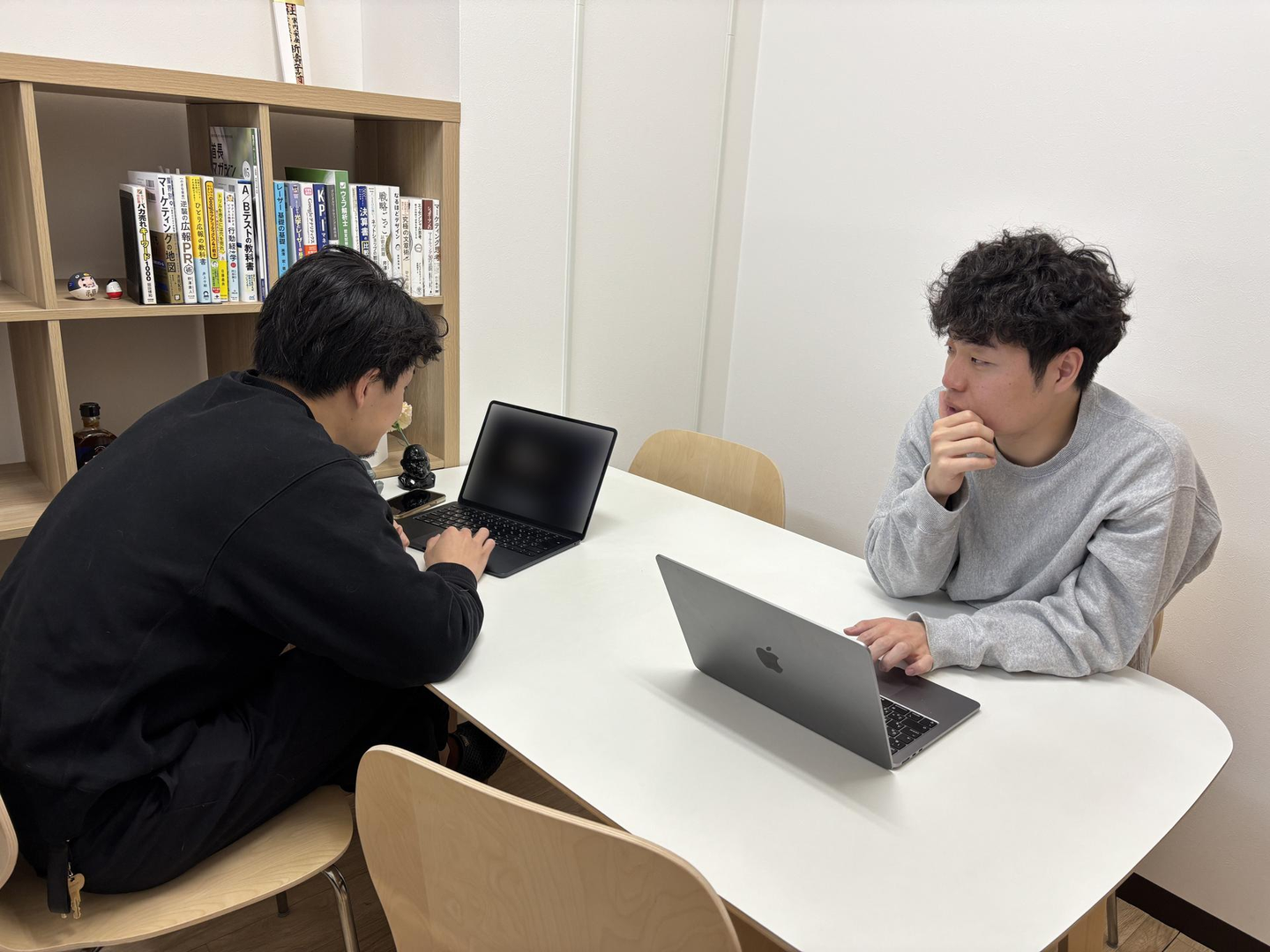
KPI進捗ミーティングの様子
裁量はある。でも「投げっぱなし」じゃない。
創業5年目を迎えるデジゴリでは、若いメンバーにも大きな裁量が与えられています。これは単なる「若いから頑張って」という丸投げではなく、一人ひとりの成長を信じる文化から生まれています。
長「デジゴリでは挑戦の連続です。前の会社は組織として形が整っていて、やることもある程度決まっていましたが、ここでは自分の裁量で新しいことにチャレンジできる自由があります。その分責任も大きいですが、やりがいを感じています」
しかし、大きな裁量があるからこそ、迷いや不安も生じやすい。そんな時に支えになるのが、2週に1回のKPI進捗ミーティングなのです。
久保田「強制で1時間相談できる時間があるのがありがたいです。振り返りが大切だと頭では理解しているんですが、日々の業務に追われると時間を作るのが難しく…。でも定期的に設定されているおかげで、振り返る習慣ができています」
「思考の深度が増した」長の変化
ここからは、各メンバーがKPI進捗ミーティングを通じてどのように変化したのか、それぞれの視点から詳しく紹介していきます。まずは二郎ゴリラこと長 拓也に話を聞きました。
長「KPI進捗ミーティングが始まってから、『自分の成果によってコントロールできるKPIってなんだろう?』と考えるようになりました。
特にSNS運用では、フォロワー数やリーチ数などの表面的な数値だけでなく、クライアントのビジネス目標に適した指標は何かを考え抜くようになったんです」
前職では与えられた業務をこなすスタイルだったという長。デジゴリでの裁量の大きさに最初は戸惑いつつも、徐々に「考えて仕事する」感覚を掴んでいったといいます。
長「以前は『ふわっと考えて、とりあえずやってみよう』という感覚が強かったのですが、思考の深度が増し、論理立てて考える習慣がついてきました。
リサーチでも『なぜこの動画は伸びて、似た構成の動画は伸びないのか?』と原因を追求するようになり、より効果的な施策を提案できるようになったのは大きな変化です」
社長との対話から得た気づきが、仕事の質を変えることもあったといいます。
長「あるクライアントのSNS運用で悩んでいた時、KPI進捗ミーティングでのきくしゅーさん(社長・菊池の愛称)との対話で『そもそも今回のターゲットが、このプラットフォームにいないのでは?』という視点を得ました。この気づきがなければ、効果の出ない施策を続けていたかもしれません。
ご依頼いただく以上、私たちはコンサルの立場であり、要望を聞くだけでなく最適な落とし所を見つける役割があるのだと実感しました。
事実を集め、仮説を立て、論理的に結論を導く。難しいですが、今までよりも仕事に手応えを感じられて楽しいです」
「数字を見るって、ちょっと面白い」久保田の気づき
続いては、源ゴリラこと久保田の変化を紹介します。久保田はKPI進捗ミーティングを通じて、「数字を見る」という行為自体に面白さを見出すようになったといいます。
久保田「SNS運用の案件を担当しています。入社当初は投稿するまでの工程で手一杯で、その先の効果検証まで頭が回りませんでした。でもKPI進捗ミーティングが始まってから、少しずつ俯瞰で見られるようになりました。1週間単位で振り返り、達成できなかった原因と打ち手の考え方をきくしゅーさんから教わっています」
—— 具体的にどんな変化がありましたか?
久保田「以前は『達成した/していない』だけだったのが、『じゃあどうするか』まで考えるようになりました。『気合!』ではなく具体的な方法を決めるんです。少し高い目線から仕事を見るきっかけになっています。
KPIって面白いですよ。同じ案件に対しても、KPIをどこに定めるかによって達成のための行動が変わってくる。奥深いなと感じています。
以前はお題目的に置いている数字だと思っていたけど、そんなことなかったんですね。自分の行動を変えるきっかけにもなる、大事な指標だと知りました」
「成果を出せるデザイナーに近づいている!」米倉の喜び
次に紹介するのは、ヌマゴリラこと米倉の変化についてです。デザイナーとして入社した米倉は、「成果につながるデザイン」を追求したいという思いがありました。
米倉「バナーの成果が気になるようになり、3日に1回は必ず広告の管理画面を見に行く習慣ができました。
また、制作案件では『最適解』という視点を得ました。クライアントのご要望をただ受け取るだけでなく、『クライアントのご要望を、スケジュールに影響を及ぼさずに実現するために、今どうアクションすべきか』という納期意識が加わり、『本当に効果的な提案とは?』とひと呼吸おいて考えられるようになったんです」
KPI進捗ミーティングは、米倉にとって「制作物と成果の関係」を学ぶ絶好の機会となりました。
米倉「クライアントとの定例会で成果や改善策を報告する際、根拠を持って数字で説明できるようになりました。これまでは見た目など感覚的な理由を伝えるのみだったので、『仮説』を立てる思考が備わり始めたことは、成長を感じています。
また、菊池さんは今まで管理画面を見てこなかった私でも理解できるように端的な例でいつも解説してくれます。知識不足ですみません…と最初は恐縮していましたが、優しく教えてもらえて分からないことを素直に質問できる環境がとてもありがたいです」
そして、実際に自分の仮説から行動して成果につながった経験も。
米倉「KPI進捗ミーティングが始まり、今までは指示をもらって修正していたバナーを自分で仮説を立てて差し替えたところ、コンバージョンを半月で2つ獲得できたんです!『2個とれてるー!』ってはしゃいじゃいました(笑)。
それから管理画面を見るのが楽しくなりましたね。私が理想としている、成果を出せるデザイナーに一歩ずつ近づいているのが嬉しいです」
「いつでも相談できる」早坂が感じる安心感
2025年2月に入社したばかりの、はちみつゴリラこと早坂にとって、KPI進捗ミーティングは貴重な相談の場になっています。
早坂「定期的に社長と1対1で話せる時間が確保されている点が何よりの価値だと感じています。KPI進捗ミーティングは1on1のように雑談も交えながら、自然に相談できる雰囲気があります。なのでもし些細な課題ができたとしても、『KPI進捗ミーティングで相談しよう』と思えます。気軽に相談できる場があるため精神的な支えになるという点がとてもありがたいです」
――KPI進捗ミーティングでは、どのような話をしていますか?
早坂「現在はWEBサイト制作のディレクションを担当しているため、私のKPIは案件のスケジュールに対する進捗度合いに置かれています。なので必然的に、どうすればクライアントの満足度が上がるのか、を話し合うことが多いです。
KPIに基づいて行動を振り返ることで、要因の深堀りができるし、気づけなかった要素は指摘していただけるんです。話していて状況が整理できて、『どうすればいいのかわからない』を潰せるのが大きいですね」
「目標達成を当たり前の文化に」〜社長が描く、ミーティングの先にあるもの〜
KPI進捗ミーティングを設計した社長・菊池は、このミーティングにどのような思いを込めているのでしょうか。
菊池「組織として目標達成を当たり前の文化にしたいという思いで始めました。会社に利益を残すための行動を習慣化することはもちろん、メンバーの目標達成に向けた行動プロセスを可視化したいんです。
数字では見えづらい『頑張り』も、きちんと評価していきたいという意図もあります」
――KPI進捗ミーティングの中で特に心がけていることは?
菊池「『役割の明確化』と、『仮説思考』の促進ですね。
メンバーが自分のプロジェクトにおいて、どのような役割が求められているかを明確にするよう意識しています。会社視点とクライアント視点、両方の観点から自分の役割を理解できるように。メンバーがその部分を見失っていたら、問いを投げかけて一緒に考えることは心がけていますね。
また、すべての数値には意味があるので、『なぜそうなったのか』という仮説を立てる習慣をつけてほしいと思っています」
――取り組みを通じて、「この人が変わった!」と実感した具体的な事例があれば教えてください。
菊池「ヨネ(デザイナー・米倉 幸花)は、わかりやすく変わってきたんじゃないかな?『インプレッション』や『クリック数』などの発言が増えた気がします。
実際にクライアントとの定例会でも、米倉がクリエイティブ改善の提案をしてくれるようになりました。数字に対する苦手意識がなくなり、自信を持って話せるようになったのは大きな成長だと感じます」
――KPI進捗ミーティングを通じて、どんな人材に育ってほしいと考えていますか?
菊池「目的や目標からの逆算思考ができる人材、論理的に課題解決できる人材、そして何より『数字に強い人』に育ってほしいですね。この業界だけでなく、どんな仕事においても価値を発揮するスキルだと思うからです」
KPI進捗ミーティングは単なる数値チェックの場ではなく、デジゴリの組織文化そのものを形作る重要な取り組み。菊池の言葉からは、メンバー一人ひとりの成長と会社全体の成長を重ね合わせる思いが伝わってきます。
この環境が合うのは、こんな人
社長が育てたいと考える「目的から逆算思考できる人材」「論理的に課題解決できる人材」「数字に強い人材」―。
そんな環境で奮闘しているメンバーたちは、どんな人にこの環境が合うと考えているのでしょうか?
長「成長したいけれど方向性が見えていない人に、特に価値があると思います。まさに、少し前の自分みたいな人ですね!
仕組み化された環境で、『作業』することに慣れている方にはギャップも大きいと思うんですが、成果に直結する考え方を身につけられると、僕が自信を持って言えます!」
米倉「『自分が担当した仕事がどう成果につながっているのか』に興味がある人。成果を追いたいけどどうすればいいか分からない、もっと自分の考えに自信を持ちたい!という人にぴったりだと思います」
"任せる"だけじゃなく、"信じて、支えてくれる"環境
デジゴリのKPI進捗ミーティングを通じて見えてきたのは、「数字を追う」という行為の先にある可能性です。
それは単なる業績管理ではなく、メンバー一人ひとりの「考える力」を育む仕組み。裁量と支援のバランスが取れた環境が、自然と「成長している実感」をもたらしているようです。
思考の深度が増したという長。数字を見ることの面白さに気づいた久保田。コンバージョンを獲得する喜びを知った米倉。相談できる安心感を得た早坂。
それぞれの変化の裏には、「任せっぱなし」ではなく「信じて、支える」というデジゴリのカルチャーがありました。
デジゴリはまだ、金ピカな福利厚生がある会社ではありません。でも、「ちゃんと育つ仕組み」なら、ここにあります。
あなたの仮説を、行動に変えてみませんか?
/assets/images/19861808/original/a747c2a3-e681-4ff5-b336-d080829a5b23?1733219330)






/assets/images/19861808/original/a747c2a3-e681-4ff5-b336-d080829a5b23?1733219330)
/assets/images/19861808/original/a747c2a3-e681-4ff5-b336-d080829a5b23?1733219330)
