- Webディレクター
- 中途_デザイナー
- 業務委託_広告コンサル
- Other occupations (4)
- Development
- Business
- Other
どうも、ラシン株式会社の藤永です!
今回のテーマは、最近YouTubeで目にした「子ども食堂」に関するニュース番組についてです。
毎晩、食事をしながらiPadでYouTubeを見る習慣があるのですが、ニュースやドキュメンタリーを選ぶことが多く、その中でおすすめに出てきたのが「子ども食堂」を取り上げた番組でした。
番組の中でまず衝撃を受けたのは、
「日本では今、9人に1人の子どもが貧困状態にある」という現実です。
そうした状況の中で、子どもに食や居場所を提供する「子ども食堂」が全国で増え続け、
昨年にはついに1万カ所を突破しました。これは全国の公立中学校の数を上回っており、
その広がりの大きさにびっくりしました。
番組では、例えば家庭の事情で食事が十分に用意できない子どもが学校の先生の紹介で子ども食堂を利用するケースや、夏休みの間、共働きの両親が日中不在のため、毎日お昼ごはんを子ども食堂で食べている子どもの姿などが映し出されていました。
子ども食堂の運営は主に民間のNPOなどが担っており、その多くが企業や個人からの寄付、
さらには運営者自身の貯金を切り崩して日々の食費や運営コストをまかなっているという現状も知りました。(退職金を切り崩しながら運営される方もいるそうです、、)
かなり多くの部分が「人のやりがい」や「善意」によって支えられており、そうした仕組みでここまで広がっていることに驚きますし、国のシステムではこれらの問題に対処できていない事実にもショックを受けました。
そして、そういった脆弱な運営基盤に拍車をかけるように、近年では米不足や食費・物価の高騰、さらには光熱費の上昇などが重なり、子ども食堂は自分自身の生活とは比べ物にならいほど、大きなダメージを受けているのだろうと容易に想像できました。
ここからは、私自身の感想を少し書きたいと思います。
もともと「子どもの貧困」や「子ども食堂」という存在があることは知っていました。ただ、今回改めて番組を見て、自分が30歳を前にする今のタイミングで深く考えさせられる機会となりました。
これから運が良ければ自分にも子どもができるかもしれないし、同世代の友人や兄弟にはすでに子どもがいる、そんな背景の中で、未来を担う子どもたちがお腹を満たせていないという現実を目の当たりにして、大きなショックを受けました。そして同時に、「自分には何ができるのだろうか」と強く考えるようになりました。
もちろん、貧困の問題は子どもだけに限られるものではありません。
高齢者や働く世代の中にも経済的に苦しんでいる人はたくさんいます。また、国の経済発展や国防、外交問題、ジェンダーの平等や人種差別など、私たちが向き合わなければならない課題は数えきれないほどあります。
しかし、そのような大きな課題に目を向ける前に、
私はまず「日本に生まれてきた子どもたちが、今まさに食べるものに困っている」という事実にこそ最優先で向き合うべきではないかと感じました。
小さな体を支えるための最低限の食事すらままならない状況など、社会として決して許されることではありません。
ただ、とはいえ「子ども食堂」という取り組みが、根本的な解決策になっているわけではないことも重々承知しています。あくまでもその場しのぎであり、例えるなら怪我をした傷口に絆創膏を貼って一時的に血を止めているようなものだとも感じています。
もちろん、子ども食堂という仕組みや活動そのものを批判したいわけでは決してありません。むしろ、多くの子どもを救っている大切な取り組みであり、その存在には心から敬意を抱いています。
ただここで伝えたいのは、「ではこの問題を本当に解決するために、社会として何から手を付けるべきなのか」という視点を、もっと多くの人が持つ必要があるのではないかということです。
個人レベルでできることを考えても、正直なところ現時点で私の頭の中には具体的な答えがあるわけではありません。それでも、まずは「子どもの貧困」や「子ども食堂の存在」といった課題を、自分ごととして捉える人が少しでも増えていくことが、解決への大きな第一歩になるのではないかと強く思います。
「自分は子供がいないからどうでもいい」
「自分の身の回りは裕福だからよかった」
こういった考えの人が少しでも減り、社会全体の課題として考えていきたいと思います。
とはいえ、今の自分に個人レベルで何ができるのかと考えると、やはりすぐには明確な答えは出ません。まずは自分が住んでいる地域で、どのような子ども食堂の取り組みがあるのかを知ることから始めたいと思います。そして、ほんの少額かもしれませんが、自分の持っているお金を寄付という形で託していく。そうした小さな一歩を通して、子どもの貧困問題をより自分ごととして捉える意識を育んでいきたいと考えています。
また今回の経験を通して、自分の中で「仕事をしてお金を稼ぐ意味」に一つ大きな軸を見つけられたように感じています。
資本主義の社会において、自分や家族の生活のためにお金を稼ぐことは当然大切ですし、私自身も趣味や身近な人のために稼ぎたいという思いがあります。けれども、それだけではどこか虚しさや違和感を感じることがあります。
今回の気づきを通して、自分が稼ぐ意味の一つとして「その日を生きることに困っている人を支える」という選択肢を持てるようになったことは、大きな前進だったと感じています。
さらに、「子ども食堂」という素晴らしい取り組みをより効果的に支えるためには、個人だけでなく、会社という単位でも何かできることがあるのではないかと感じています。むしろ、お金を生み出す企業だからこそ、社会的意義のある活動を支えていく役割があるのではないか――そんな思いが最近強くなっています。
このあたりのアイデア/想いについては、折を見て経営層にも相談をしてみたいと思っています。自分自身の小さな行動から始めつつ、会社としても社会的な貢献につなげていけるように、今後も考えていきたいです。
そして、このような取り組みを進めていくことは、結果的にラシン株式会社をより魅力的な企業へと成長させることにもつながるのではないかと、現段階でも確信しています。
少し打算的な視点かもしれませんが、社会的意義のある活動に積極的に関わることで、多くの求職者から「働きたい」と思われる魅力的な会社になれるはずですし、取引先からも信頼され、選ばれる企業になっていくのではないかと思います。
まとまりのない文章になってしまったかもしれませんが、ここまで読んでくださった方がいらっしゃったら、ありがとうございます。
僕自身、もっと「自分のためだけではなく、誰かのために自分の命や時間をどう使うのか」ということを、きれいごとではなく真剣に考えていきたいと思っています。そして、もしここまで読んでくださったあなたがいらっしゃるなら、ぜひ一緒にこの課題について頭を使って考え、ともに小さな一歩を踏み出していただければ嬉しいです。
以上、真面目モードの藤永でした。また来月!

/assets/images/22011847/original/51c1b5fc-8b86-4a70-9e4a-a525ff21cc83?1757389301)

/assets/images/21346716/original/e0a9ab04-81a3-4f9f-b0a2-b596761a0748?1749793058)
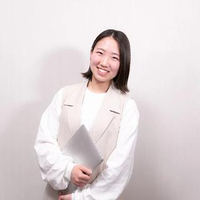

/assets/images/21346716/original/e0a9ab04-81a3-4f9f-b0a2-b596761a0748?1749793058)

