- フロントエンドエンジニア
- PM
- NestJSの経験者
- Other occupations (3)
- Development
- Business
社内報から生まれた、AIに関する熱い議論
みなさま、こんにちは!
Lboseで採用人事を務める小笠原です。当社では、メンバーの知見や取り組みを社内に共有する目的で、週に1度、社内報を制作しています。今回は、最近社内で大きな反響を呼んだ特別回を、Wantedly読者の皆さまへ向けて再構成しました。テーマは「AI」。
代表の小谷と、CTOの南ナリット、そして私の3名で、LboseのAI活用に対する考え方や、これからのエンジニアに求められる役割について語り合いました。
この対談が生まれたきっかけは、開発部門で行われた別の「AI合宿」でした。その話を聞いた代表の小谷が「ずるいぞ、僕もやりたい!」と南に持ちかけたことから、この企画はスタートしました。
今回は、このAI合宿の全貌と、そこから見えてきた私たちの組織の未来について、前後編の社内報を一本の記事にまとめてお届けします。
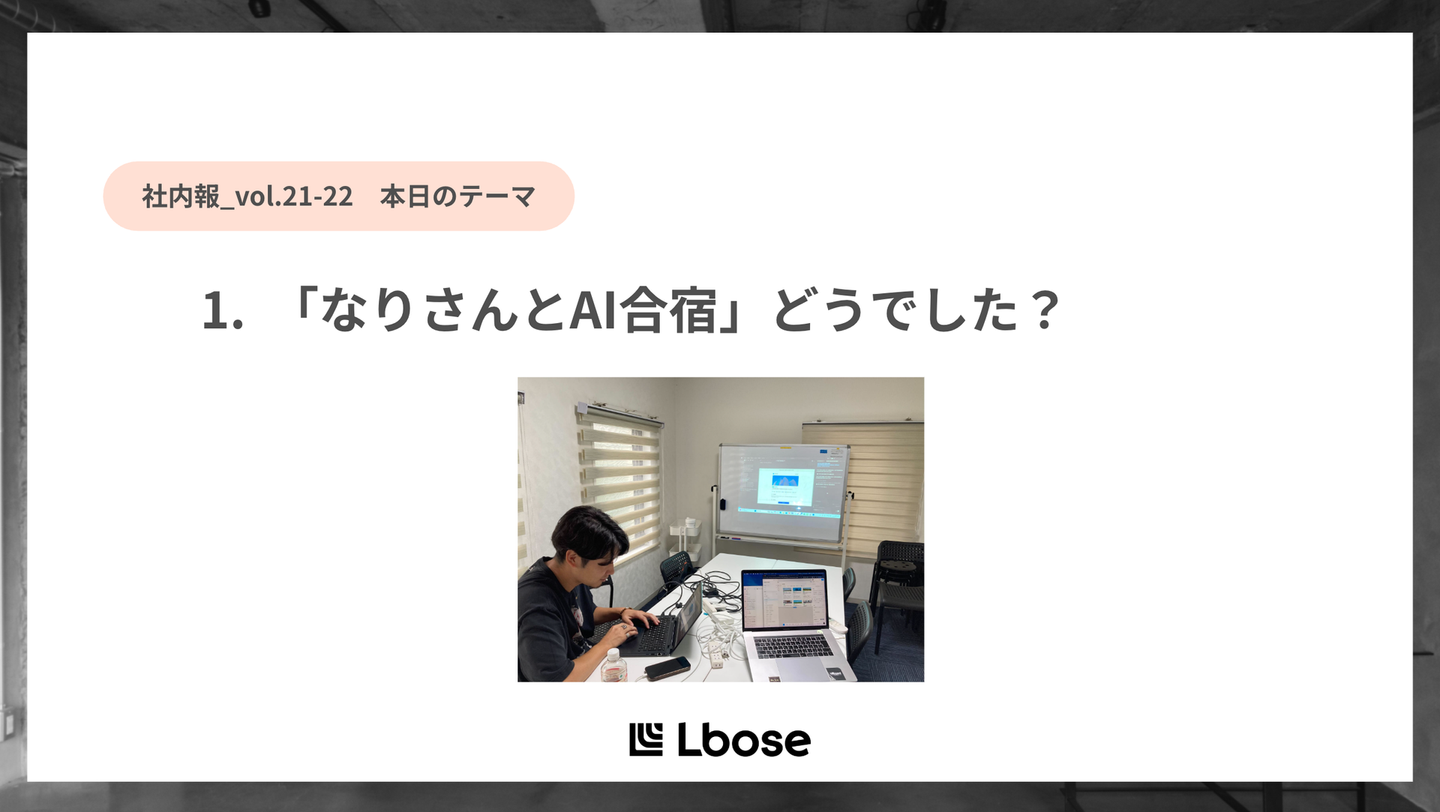
目次
社内報から生まれた、AIに関する熱い議論
1. Cursorで「モックアップ開発」を実践
2. 業務自動化への挑戦と、エンジニアの専門性
3. AIが作る時代、価値を生む「ラストワンマイル」とは
4. AIを使いこなすための「組織のルール」と個人の役割
5. Lboseが目指す、AIと共創する未来
1. Cursorで「モックアップ開発」を実践
合宿の最初のテーマは、AI開発環境の「Cursor」を試すことでした。
普段はビジネスサイドにいる小谷が、南のサポートを受けながらAIとの対話だけでモックアップを作成。その過程で、非エンジニアでもプロンプトの工夫次第で高い品質の成果物を出せることを体感しました。
「APIキーの探し方」「再現してね」といった具体的な指示によって、試行錯誤しながらもモックアップを効率的に作成できたことは、大きな発見でした。
この経験は、「無形の商材を扱う際にイメージを伝えるのが難しい」というビジネスサイドの課題を、AIが解決できる可能性を示しています。
AIによってアウトプットの回転数が上がれば、よりスピーディーに検証を進められ、学習型のアプローチが可能になります。これは、クライアントへの価値提供を最大化する上で非常に重要なことです。
2. 業務自動化への挑戦と、エンジニアの専門性
Cursorでの成功体験を基に、次は業務自動化ツール「Dify」を使い、会議アジェンダの自動作成に挑戦しました。
しかし、一見シンプルなタスクに見えたこの挑戦で、私たちは「壁」に直面しました。
DifyとNotion、Slackの連携を試みるも、APIの仕様や認証の壁に苦戦。
この経験は、ツールの特性を深く理解し、適切な設定を行うことの重要性を浮き彫りにしました。
南は、NotionのAPIに「データベースにページを追加する」機能がないため、テンプレートの複製による自動化が難しかったという技術的課題に触れ、ツールの仕様を理解した上での設計力が、やはりエンジニアには不可欠であると語りました。
AIツールは進化を続けていますが、それを最大限に活かすためには、やはり人間側の専門スキルや判断力が求められることを再認識する機会となりました。
3. AIが作る時代、価値を生む「ラストワンマイル」とは
2つのツールを試した経験から、私たちはAIが担える部分が増えたからこそ、人間に残された最後の3割(ラストワンマイル)が持つ本当の価値について議論を深めました。
小谷は、「AIが7割を自動化しても、残りの3割が全体の価値の7割を占める」という見解を示しました。
例えば、プロジェクトの傾向と人の傾向から最適なアサイン候補を出すような複雑なロジックを解決するのは、やはり人間が作るラストワンマイルの部分であること。
これに対し、南は、AIは多機能なコードを生成しがちだが、「本当に必要なものを判断し、引き算ができること」が人間の価値であるという視点を補足。AIによって仕事は効率化されますが、その分、ルール作りや品質管理など、新たな仕事も増え、エンジニアのポジショニング自体が変わってきていると語りました。
4. AIを使いこなすための「組織のルール」と個人の役割
AIを単なるツールではなく、組織全体の力として活用するために必要な考え方も掘り下げました。
南は、AIの精度はプロンプトや事前情報に大きく左右されるため、個人による品質のバラつきをなくすための「ルール作り」が不可欠であると強調。そして、「AIはインフラ」であり、電気のように誰もが当たり前に使いこなすべきものだというメッセージを投げかけました。
小谷もまた、効率化や生産性向上だけでなく、「ユーザーやクライアントへの価値を最も高める」という軸でAI活用の方針を決めることの重要性を語りました。AIを活用することでアウトプットの回転数が上がり、より良いものを作るための検証や学習に時間を費やすことができる。AIは、より良いサービスを作るための強力なパートナーなのです。
5. Lboseが目指す、AIと共創する未来
Lboseは、AIをインフラとして使いこなし、エンジニアがコアな価値に集中できる環境を目指しています。複雑な課題解決や、ユーザーへの価値提供といった「ラストワンマイル」にコミットできる開発メンバーを求めているのです。
AI時代におけるエンジニアの役割について、あなたはどう考えますか?
Lboseで共に、AIと共創する未来を創りませんか?



/assets/images/7090636/original/2c35b0cf-93c5-41c2-b827-d30f7f86f96f?1624716118)


/assets/images/7090636/original/2c35b0cf-93c5-41c2-b827-d30f7f86f96f?1624716118)



/assets/images/7090636/original/2c35b0cf-93c5-41c2-b827-d30f7f86f96f?1624716118)

