- 生産管理・資材調達
- セールス|BtoB|お菓子缶
- パッケージデザイナー|お菓子缶
- Other occupations (1)
- Development
- Business
- Other
「会社の雰囲気はどうしたら良くなるのでしょうか」というご質問をいただくことが頻繁にあります。「どうすればもっと理念を会社に浸透させられますか」という聞き方をされることもありますが、これも結局のところは同じことを聞かれているのだと認識しています。
雰囲気って大事ですよね。誰しもが良い雰囲気の会社で働きたい、会社の雰囲気を良くしたいと思いながらも中々うまくいかないので、冒頭のような話がよく話題に上がるのだと思います。僕自身もそんな偉そうに高説垂れる立場にはないのですが、5年前は最悪な雰囲気で全員下を向いてお互いの悪口を言っていたような老舗中小企業で、今はご来訪いただいたみなさまから「どうしてこんなに雰囲気が良いのですか」と聞かれるくらいにまでなった企業の当事者として、改めて思うところを書いてみます。
雰囲気が悪いのを直そうとしても無意味
結論から言うと”雰囲気”そのものを課題として組織風土改革に取り組んだとしても、根本的に良い雰囲気に改善されることはないのではないかと思います。雰囲気とはいわば”架空の申し合わせ”によってできているものです。なんとなく手を上げづらいからやらない、意見を言ったら反対されるのが怖いから言わない、という空気を読んだ消極的な意思決定の集合体が雰囲気の正体だと考えると、「組織風土改革!」というような外圧的な力学で変化を煽り続けても、根っこの部分から変わることがないのではないかというのが持論です。強烈なカルチャーに共感した人が集まっているベンチャー企業や強固な文化形成がされている企業でない限りは、人の意思決定の根底にある思想に触れるのは簡単なことではありません。
空気を読むのは防衛本能
雰囲気が悪いと生産性が落ちます。誰かの顔色を伺ったり、あえて意見を言わなかったり、誰にも見えないところで会話をしたり、本来1分で終わるようなことを何時間もかけて遠回りするような挙動が増えます。そういう仕事の濃度を薄める行動が増えれば増えるほど消極的な意思決定が指数関数的に増えていくという負のスパイラルに陥って、ますます非生産的な力学が強化されていきます。そうやって生まれてしまった雰囲気を何とかしようと経営者が躍起になり、心理的安全性の確保に努めたりパーパスやMVVといった指針を策定したり1on1をしたりするわけなのですが、どれも実際うまくいかないことが多いのが実態なのではないかと感じます。
うまくいかない原因は各社各様だとは思うのですが、個人的に良く感じるのは「雰囲気が悪い」という問いの根底に真剣に向き合わないまま、心理的安全性だとかパーパスだとかソリューションらしきものに逃げてやしないか、ということです。そもそもこのような消極的意思決定をする背景には「自分が損するのではないか」と防衛本能に基づく感情があるからです。誰もやってないし、自分が目立つと周りから非難されるのではないか、自分の立場が危うくなるのではないか、と脅かされた状態にあっては、いくら手を変え品を変え外圧的に「こういう行動をするのが正しい」「安心して発言しなさい」と指示命令をしたところで不安が解消されることはないわけです。
「心理的安全性をつくる」という歪んだ発想
雰囲気を良くするために心理的安全性(と言われるモノ)が大事であることに異論はありません。しかし、心理的安全性とはそもそも何でしょうか。もっともらしい科学的な言葉を持ち出したところで、人間の感情はもっと原始的なところにあるのではないかと思います。「これが正解だ」という思想や行動規範の見本を示し報酬と制裁でコントロールしたところで、防衛本能が強く働いている人の感情は「損しないように言われた通りにしよう」となるのが関の山です。表面的に多少の改善がみられたとしても雰囲気を変えるまでには至らず、相当にコストや時間をかけた割にはあまり変化が実感できなくて暖簾に腕押しのような無気力感を感じる人が多いからこそ、組織開発や経営改善の悩みが枯渇しないのだと推察します。そもそも、心理的安全性を意図的に作ることなんて叶わないのではないか、と僕は思います。
「ありがとう」「ごめんなさい」を一番口にしているのは誰なのか
雰囲気を変えるための特効薬もハウツーもないと思うのですが、一つだけその道に続く方法はあると僕は思っています。それは「ありがとう」と「ごめんなさい」の総量を極限まで増やしていくことです。
「なんだそんなことか」と思われるかもしれません。しかし、僕はこれが雰囲気のすべての原点だと信じていますし、逆にこの2つの言葉があまりにも軽んじられてやしないかと思うわけです。例えば、自分の所属している組織のことを想像してみてください。相談を受けた上司の方はどのように話すでしょうか。
「相談してくれてありがとう」
「教えてくれてありがとう」
「忙しいところ時間とってくれてありがとう」
「考えてくれてありがとう」
このように感謝の気持ちを示す言葉を会話の始めや終わりに言えているでしょうか。「できているときもある」とかそういうレベルの話ではなく、一度たりとも欠かさず必ず言えてると自信を持って言えるでしょうか。どれだけ内容が至らなかったりシャビーだったとしても、「ありがとう」と言える点を見つける努力を上の立場の人が徹底してできているでしょうか。感謝の言葉を率先垂範で示す努力はできているのでしょうか。人間のコミュニケーションの原点にあるこの言葉を、経営者が心から大事に想って日々使い続けていなければ、閉ざされた人の心の扉が開くことはありません。
人を変えるという烏滸がましさは捨てよう
いつから人は、人を支配して変えることができると誤認するようになるのでしょうか。会社組織という話になると、マネジメントというものが当然のように正義のような面構えで君臨し、いかにして人をコントロールすることが出来るかという議論になりがちです。「パーパスやMVVを”浸透”させれば人の思想は変わる」「心理的安全性を確保すればもっとポジティブに行動するようになる」、このように書かれている本や広告もよく見かけますね。しかし、僕は個人的にはこういう発想自体が根本的に歪んでいるのではないかと思います。そもそも組織という人為的なものを利用して人が人を変えようということ自体あまりに烏滸がましいわけです。優越的地位を利用してどれだけ他人に力を加えたことで塑性は働きませんし、人が根本的に変わることはありません。
唯一出来ることがあるとすれば「共感」を呼ぶことだけだと僕は思っています。「ありがとう」「ごめんなさい」という言葉を大事にして、清く善い行いだと信じることをやり抜き続けていれば、少しずつ共感する人は現れるはずです。それは人を変えるということではなく、防衛本能と諦観で心の奥底にしまわれていた良心を改めて表に出すことに他なりません。感謝したり謝ったり、人と人とのコミュニケーションで当然なされるべきことが充実して初めて「ここでは自分の心の声に従って行動して良いんだ」という安心感が生まれるのではないでしょうか。
少し極論的に乱暴な書き方にはなりましたが、僕はもっと組織というのは人間が自然な姿で心の声に従うことが出来る場所であるべきだと思います。「ありがとう」と「ごめんなさい」を大事にできる会社がふえれば、世の中はもっと優しくなると信じています。

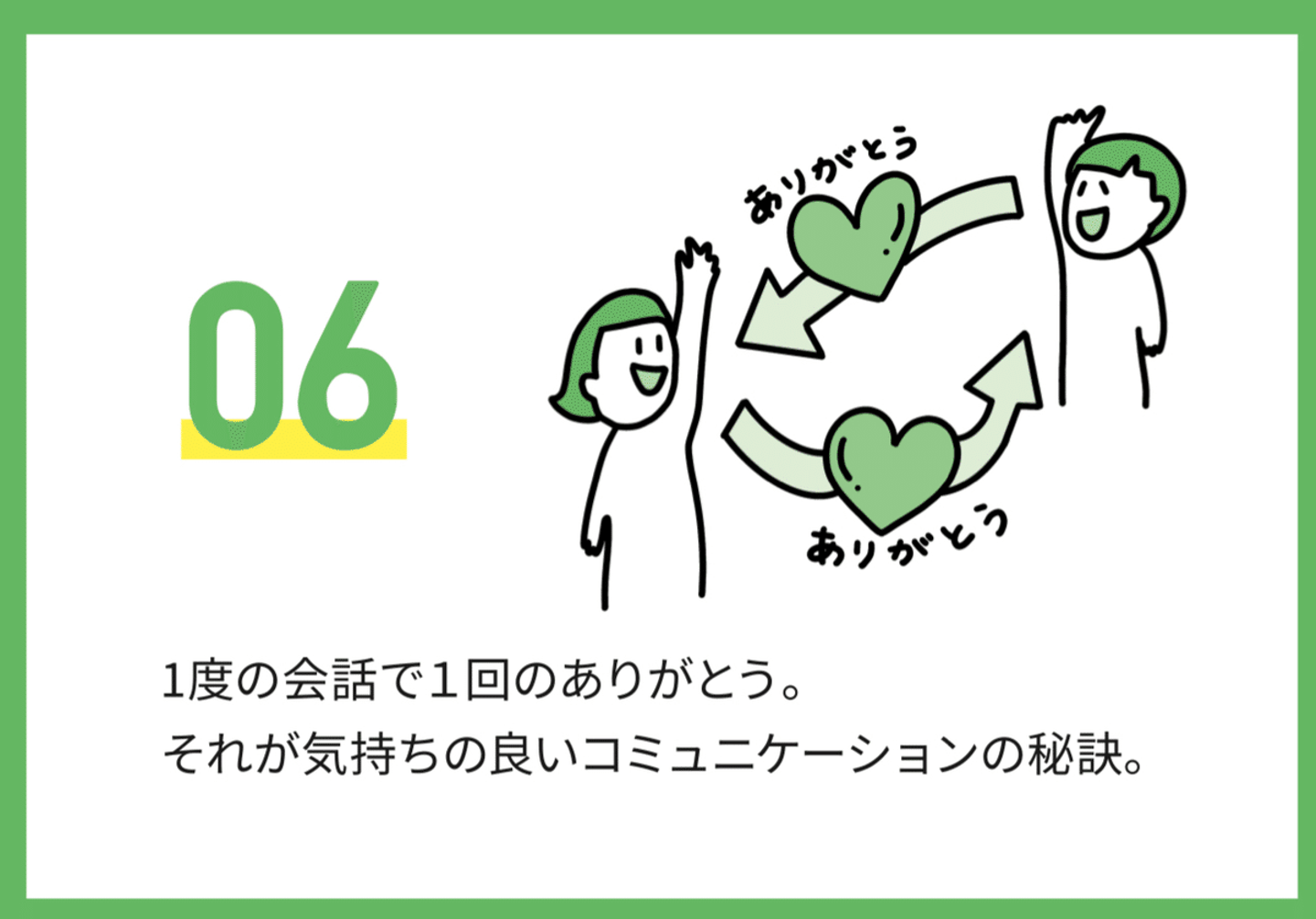

/assets/images/9549171/original/61bc10ef-9b0d-412c-85ba-b7aefd96d00a?1653524238)
/assets/images/9549171/original/61bc10ef-9b0d-412c-85ba-b7aefd96d00a?1653524238)



/assets/images/9549171/original/61bc10ef-9b0d-412c-85ba-b7aefd96d00a?1653524238)
