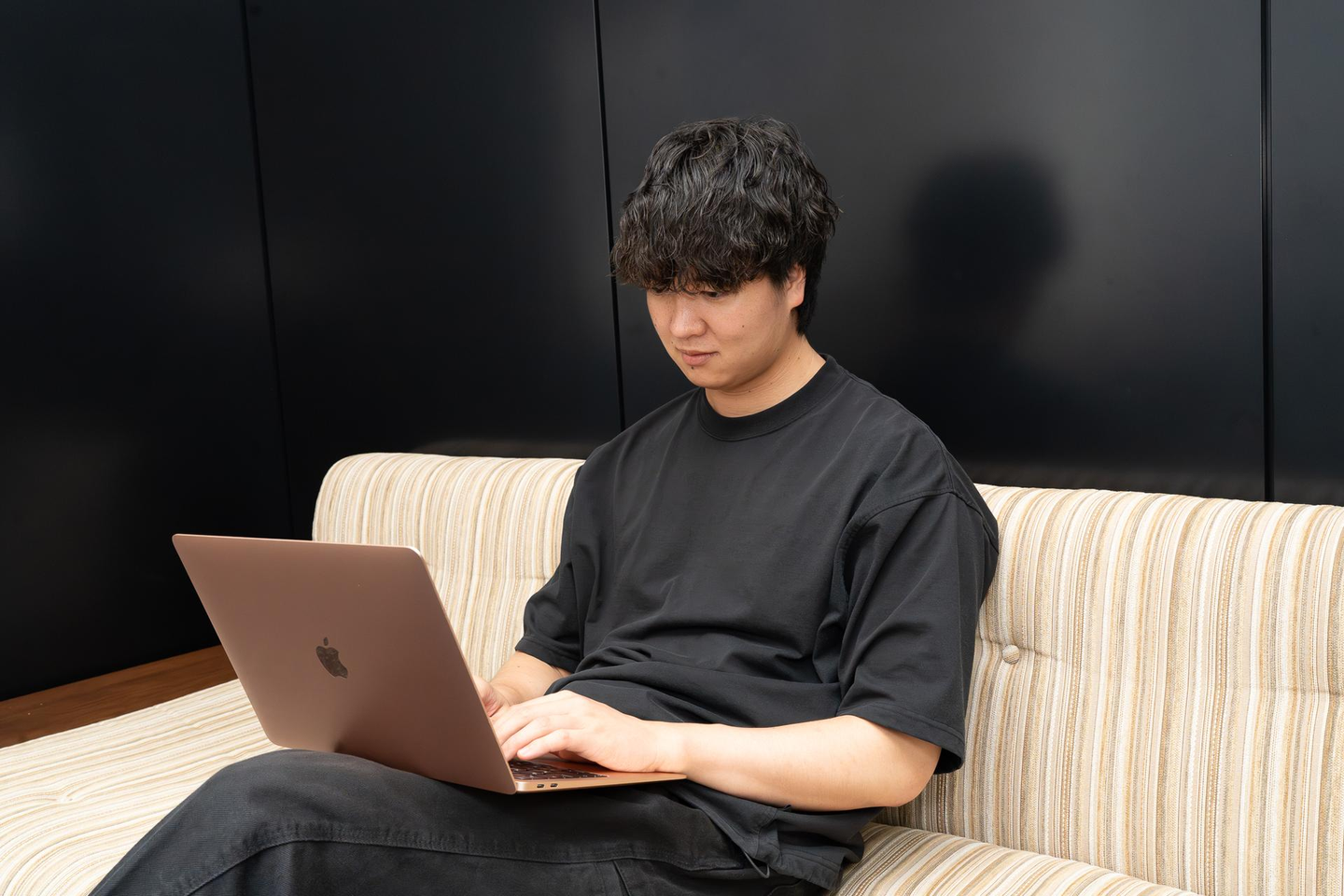「3年で辞めます」と宣言して入社した僕が、4年目の今、退職するまでの話~後編~【社員インタビュー】 | 株式会社ALBONA
インタビュアー:酒井 / 人事企画 ALBONA人事部にて、 採用ブランディングや組織開発・制度設計などを担当しています。プロフィール・名前:中村さん・職種:C2C Webプラットフォーム事業責...
https://www.wantedly.com/companies/albona/post_articles/1002633
インタビュアー:酒井 / 人事企画 ALBONA人事部にて、 採用ブランディングや組織開発・制度設計などを担当しています。
プロフィール
・名前:中村さん
・職種:C2C Webプラットフォーム事業責任者
・社歴:3年9ヶ月
・勤務地:東京支社――そもそも、新卒でベンチャーに飛び込もうと思ったのはなぜだったんですか?
元々は、国際問題や、海外における地域支援の分野に関心があったんです。 学生時代には実際に現地のプロジェクトに関わったり、医療支援をしたりしていました。
将来的にもその領域で働いていくつもりで、国際機関への加入に修士号が条件になることもあり、まずは大学院への進学を予定していました。
でも進路を考える上で、強く感じた違和感があって。
――どんな違和感だったんですか?
支援の現場で感じたのは「目標はとても偉大なのに、それを叶えるための武器が全然足りていない」ということでした。
現場で小さな成果を積み重ねても、大国やグローバル企業の動きひとつで一瞬にして押し流されてしまう。結局、人の行動や意識を変えて社会を動かしているのは、支援業界やアカデミアが避けがちな“資本主義のロジック”なのでは、と強く思ったんです。
でも、そのまま大学院に進んで支援の道に行っても、そうした力を学ぶチャンスはほとんどない。だからその前に一度真逆のサイドに振り切って、マーケティングの現場で「人を動かす力」を徹底的に身につけたいと思いました。
――そんななかで、ALBONAに出会ったと。
初めての面談で、社長の野下から「こんな事業を立ち上げようとしてる。一緒にやらないか?」と話してくれたんです。
当時の僕は、あえて“着実に育ててもらえる会社”を避けて就活していました。
というのも、最初から3年働いたら大学院に進学するつもりだったからこそ、“時間をかけて成長する環境”より、“とにかく早く自分を鍛えられる環境”を求めていたんですよね。
そんなときに、「新卒・未経験でも、いきなり社長直下で新規事業の立ち上げに関われる」なんて提案をもらって、もう他は見えなくなりました。
「これはALBONA一択だ」と、即決に近い感覚でした。
――入社当時、会社やチームはどんな編成でしたか?
僕は5人目の社員で、全体でも他に業務委託やインターン生が数名が居るだけで、合わせて10人程の会社でした。そして新規事業立ち上げチームは社長、エンジニア、僕の3人体制。「ああ、何でも全てが自分次第の環境に本当に来たんだ」と実感したことを覚えています。
――最初の業務は、どんな感じでしたか?
入社初日から、いきなり「新規事業の立ち上げメンバー」としてアサインされました。
もちろんマーケの知識なんてまったくない中で、社長の野下にがっつり張り付いて、議事録作成、リサーチ、企画、仮説検証…UIUXやプロダクト設計…とにかくやれることは全部やる日々でした。 初めてのことだらけで、全て手探りで、見様見真似。ただ、短期間で多くのことを学べた期間であり、この時の経験は今なお活きていると感じます。
そのまま半年も経たずに「事業部長」という肩書きがついて、現場の最前線に立ってました。
――新卒半年で事業部長って、相当なスピード感ですよね。
ほんと、普通に考えたらあり得ないと思います(笑)。
でも当時の自分にとっては、それが「やりたかったこと」そのものでした。 支援業界に行く前に、資本主義のど真ん中で結果を出す。圧倒的な早さで"人々の感情・行動に変化を起こす力"を身につける。
そういう本物の経験をしたくてALBONAに来たので、裁量の大きさもスピード感も、むしろありがたかった。
──任せられてきた裁量の大きさも、信頼の象徴ですよね。
本当にそう思います。
最初から新規事業のPMを任されて、事業部長という肩書きももらって。
自分の実力が全然追いついていないことは分かっていましたが、それでも「やってみたらいいよ」と任せてくれる。
どんなに未熟でも、チャンスを渡し続けてくれた。だけじゃなく、個人の成長に驚くほど投資してくれる。「実力がないなら伸ばせばいい」「その為のサポートは惜しみなくする」というスタンスが、社長や会社にはありました。
――事業部長として働く上で、困難だった事はありますか?
“悔しかった経験”ですが、「自分に見えていた未来を、チームに見せられていなかった」ことです。
立ち上げ期の事業って、本当に泥臭いことばかりで。
スピードを優先して、とにかく数を打って、小さな改善を繰り返して、ようやく少しずつ前に進んでいく。そんな中で、僕は社長と日々やり取りをしていたこともあって、事業の構想やゴールのイメージがかなり具体的に見えていたんです。
「今の積み重ねが、〇ヶ月後に未来を切り開いている」という確信と期待を持って日々向き合っていた。 でも、それが見えていたのは自分だけだった。
—―メンバーはそうじゃなかったと?
現場で手を動かすメンバーにとっては、目の前のタスクが“何に向かっているのか”が見えづらくなっていたと思います。 日々の忙しさに飲み込まれていく中で、知らず知らずのうちに、チームの中で視点がズレていってしまってる事にも、メンバーが疲弊している事にも気づいた。
そのとき、焦りもあったし、悔しさもありました。
「なぜ伝えられないんだろう」「なぜ同じ方向を向けていないんだろう」と自問しながらも、
結局は“言葉にして伝える努力”を怠っていたのは自分だったなと、思い知らされたんです。
—―リーダーにはどんな姿勢が求められると考えますか?
ALBONAは、「自分で選んで動ける」場所です。
だからこそ、リーダーには“選ばれる覚悟”が求められる。正しさだけを振りかざしていても、人はついてこない。同じ方向を向いてもらうためには、”ただの行動・アクション”を伝えるだけじゃ足りなくて、「どんな景色を一緒に見たいのか」という物語を語り続けなきゃいけない。
“この先に何があるのか”を想像できるからこそ、そこに誠実であるべきなのがリーダーなんだと、あの経験を通して痛感しました。
—―「リーダー」をどう捉えるようになりましたか?
今では、「リーダーは視点を揃え続ける仕事なんだ」と思っています。
同じゴールに向かっているはずでも、立場が違えば見える風景は違う。 そのズレに気づかずに走り続ければ、誰かが置いていかれてしまうかもしれない。だからこそ、何度でも立ち止まって、言葉にして、共通のビジョンを描き直すことが必要なんだと思います。
振り返ると、“教科書には載っていない、組織のリアル”を痛感する経験でした。
――聞いていると、苦労はあれども高く成長した過去が伺えます。
そう思います。
大きな裁量と事業部長という立場を渡され、がむしゃらに走っていたら、いつの間にか高く・遠いところまで来ていたような感覚もあって。
“仕事”の進め方、事業をゼロイチからスケールさせていく過程、チームメンバーという”人”に対する在り方やアプローチ、本当に数多く経験させてもらいました。
――入社前に描いてた成長ができていた感覚もありますか?
そうですね、間違いなく成長していたと思います。
「3年で大学院に行く」という前提があったから、限られた時間の中でとにかく“力をつける”ことに集中していました。 未経験からマーケを覚えて、新規事業の数字も動かせるようになり、「新卒3年間にしては色々経験できている。順調だな」と思えていた。
でも、その一方で——どこか「あぐらをかいている自分」が居ることにも、気づき始めていました。
「3年後には会社辞めるって決めて入社してるんですよ、僕。」 中村さんが一緒に帰り道を歩きながら、そう迷いなく語っていたのを、未だに鮮明に覚えています。聞いた瞬間から今日まで、中村さんが辞めてしまう日のことを寂しく思う自分がずっとありました。
飄々としていてどこか掴みどころがなく、でも一度話し出せば熱く、深く話してくれる中村さんが、チームを拡大し、メンバーの成長にも全力で向き合っていた過程を見てきました。 正直、「いや中村さんが辞めたら会社どうなると思ってるん!?」ってずっと思ってました(笑)。
人を巻き込む難しさ、人を動かす難しさ——でもその中で見つけた「導く人」としての背中は、紛れもなく“中村さんにしか出せない輝き”を持っています。 前半では、その“背中を背負うまで”のリアルさが詰まっていました。
そして次回、後半では「なぜいま卒業するのか」、 あのとき一度は延期した“旅立ち”の理由とその先の想いを、代表野下と交わした言葉の数々や関係性をとことん語ってもらっています。
ぜひ最後まで読んでください。
※記事内の情報は2025年8月時点のものです。