高品質なデジタルサービスをデザインするために欠かせない、質の高いUX調査サービスを目指したら、人類学の調査にヒントがありました。このシリーズは、UX調査サービス開発を担当する2人がそれぞれの経歴を活かしてより質の高い調査を追求する議論を記録したシリーズ。第二回目は「インタビュー調査の人選とまとめ方」をお送りします。
第一回目はこちら:インタビュー調査とエスノグラフィは、組み合わせて使うもの
登場する人
川北奈津:UXディレクター
静岡大学情報学部卒業。情報科学芸術大学院大学(IAMAS) メディア表現研究科修士課程修了。作品制作・展示活動、広告制作会社勤務を経て、現在に至る。UX/IA部マネージャー。UXリサーチサービスの品質を上げるべく日々奮闘しています。
比嘉夏子:人類学者
北陸先端科学技術大学院大学 知識科学系 助教。京都大学博士(人間・環境学)。人類学者/エスノグラファー。オセアニア島嶼をフィールドとして人間の行動や価値観を研究してきた傍らで、広くデザインやリサーチなどの業界にも関わりつつ、人間理解を深める手法を探究中。
気づきを逃さないよう、調査対象の絞り方を疑ってみる
川北 前回はインタビュー調査の方法についての話でした。今回はインタビューやエスノグラフィの調査対象者の人選について。どんな条件の人をどんなバランスで何人位を調査対象とすればいいのかいつも悩ましいんですよね。
比嘉 プロジェクト毎の制約もあるので難しいですよね。
川北 そうなんです。予算と時間の制約から調査対象者を絞るわけですが、こうすると的確なユーザー像とマーケットを把握できなくなってしまう危険も感じます。
比嘉 欧米の企業に比べて日本では調査に予算と時間をかけない傾向がありますからね。
川北 比嘉さんは人類学者としての経験の中でこうした問題にどう向き合ってるのでしょうか?
比嘉 そうですね。まず違和感があるのは、細かい属性や条件によって最初から対象を絞りきってしまうことなんです。確かにターゲットを絞って調査するのは当然だと思うんですけど…
川北 けど?
比嘉 そもそも対象プロジェクトの本当のターゲットが見えてこないから定性調査をしようとしているわけじゃないですか。なのに調査対象を年齢や性別や仕事、趣味などの属性によって最初から絞らないといけないというのは矛盾ですよね。
川北 確かに…そういえば幅広いターゲットを抱える観光サイトや検索サービスなんかだと、気づけば調査対象が増えて定量調査のようになったり…
比嘉 ただ、ちょっと糸口はあります。人類学者のフィールド調査と違って、A.C.O.の抱えるプロジェクトはオンラインサービスがほとんどですから、その特性を考えてみるといいかもしれません。
川北 定量が得やすいということですかね?
比嘉 そうですね。
ポータル的なサイトだと、世界中のみんながターゲットということなので、そもそもWebなのにそんな対象者を絞ってしまっていいのかっていう不安があると思うんです。例えば、ネット証券のサービスだと投資に興味がある人からターゲットにしていく。必ずしも間違っていないのですが、調査対象の絞り方を疑わずにいると、大切な気付きの機会が失われますから。

ペルソナを決めず、まずはパイロット調査から
川北 それでも対象者の属性を決めることが必要な理由はなんでしょうね? 予算と時間を守ろうとすることでしょうか。
比嘉 おそらくひとつには、リサーチの方法や規模との兼ね合いもきっとあって。例えば一般的な定量調査は、対象者が1000人だったら500人ずつ男女のアンケートになったりする。世代も、日本の人口の世代の分布に合わせたような比率で取りましたよ、とか。東京だけだと偏るから、全国の都道府県から取ってますよ、とか。偏りをできるだけ無くした計的なデータに私たちは普段からよく触れてると思うんですね。
かといって、それと同じようなイメージで10人を選んでインタビューをしてみようとすると、それは何となく違う。やっぱり定量調査は目的や方法が違うものなので、そういう統計的な考え方をそのままにはあてはめられない訳です。
川北 そうですね。定量と定性の調査の違いってすごくありますもんね。
比嘉 例えば以前A.C.O.のプロジェクトでもやりましたが、まずはごく簡単にでも「パイロット調査」を実施してみることです。試しに身近な人を対象者にしてみる。オフィスの仲間や家族でもいいので。パイロット調査をしてみると、その先の調査で必要なことがだいぶわかってくるはずなんです。
川北 最初からターゲットとか属性とかペルソナをガチガチに決めずに、まずはパイロット調査を実施するんですね。
比嘉 そうです。パイロット調査で感覚を掴んだら、じゃあもっとこういう人に聞いてみようという話になるはずです。思い込みでつくった属性やペルソナよりも遥かに早く掴めて来るはずです。それを元に本格的な調査設計をするということですね。
川北 開発の初期段階にまずプロトタイプをつくると気づきが多いという効果に近いですね。
比嘉 そうですね。最初からガチガチに決めずに段階に分けて、とにかく手を動かして少しずつでも前進させることで、早い段階で芯をつかみ、次の段階に影響を与えていくデザイン思考を調査段階から取り入れていくというイメージです。
川北 実際にやってみると、クライアントと一緒に小さい段階を共有しながら進められるので、それがやっぱりいい感じなんです。同じ目線で進められるので変な気の使い方をしなくていい関係になる。ただ、そういう帯同型の進め方にはなかなか予算が付かないという課題はあるんですけどね。
比嘉 最近でもそうですか?
川北 最近はだいぶご理解いただけるお客様も増えましたが、そういう方はどんどん事業を成長させていますね。やはりユーザーへの理解が深まっていたりチームでの見解が一致していることが大きな効果となっています。

調査結果の分析は、経験と理論の往復運動
川北 エスノグラフィ調査で観察して得た情報や画像を結果から見えたデータをレポートする際、この目で見て感じたことを言葉にしたとたんに単純化されてしまって、調査で得られた気づきや奥行きが失われてしまう感覚があります。比嘉さんはこういう感覚ってありますか?
比嘉 川北さんが気にしていることはよくわかります。実際には複雑で多様な出来事を、単純な言葉に落とし込んでしまうことの違和感は、たぶん多くの人が抱えていますよね。以前のポストイットの記事の話ではないですけど、ビジネスでのリサーチの分析プロセスを見ていると、やはり過度に単純化してしまっていることがいっぱいあるんですね。本当はもっと別の言葉で語られていたことや、人それぞれに違っていた表現を、わかりやすい一言でポンと表してしまう。
川北 人類学の研究や論文を書くときなどはどうしてますか?
比嘉 人類学の研究では、「ことば」の取り扱いはもっと厳密だと思います。例えば「苦手、嫌だ、好きじゃない」といったさまざまなニュアンスを「嫌い」の一言でくくってしまうようなことがよく分析のなかで起きていると思うのですが、そういったまとめ方、抽象化のプロセスはもちろんある段階では必要になるにせよ、元々の言葉のニュアンスをすぐに捨ててしまうような分析は、やはり危なっかしいなと思います。
たとえば人類学者がわざわざ長い時間をかけて調査地の「現地語」を習得するのは、もちろんコミュニケーションの手段が必要だからというのもありますけど、ことばに対する感度を上げて、その人たちの認識や感じ方をつかもうとしているからなので。インタビューデータの取り扱いなんかも同じことで、一語一句を丁寧に取り出すこともできれば、「○○の話」のようにざっくりと要約されてしまうこともあるし、その精度はさまざまだと思うんです。
論文執筆の話に戻ると、現場で得られたさまざまなデータを整理し、分析して論文という形にするとき、それは簡単に言うとデータと理論の往復運動みたいなことをやっています。おそらく一般的には具体的なデータから抽象的な理論へと階段を上がっていく、というイメージをされそうですが、たしかにそういう部分もありますけど、でもやはりずっと往復しつづけるというか、限りなく具体的な事例や生のデータと、より抽象的で概念的な説明というのは、ちゃんと互いに紐づいているべきなんですね。その意識がないと、ただの事例の羅列になってしまうか、あるいは根拠のない宙に浮いた話になってしまう。両者がちゃんとつながっていて、そして必要に応じてたどれるような状態になっていることが理想的だと思ってます。
/assets/images/1813/original/8a25edbc-7309-44b6-b82f-a6ad4515c59b?1651126270)



/assets/images/1813/original/8a25edbc-7309-44b6-b82f-a6ad4515c59b?1651126270)



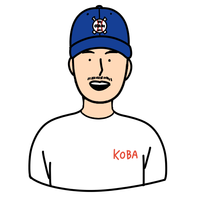

/assets/images/546723/original/66674948-a2f7-40ec-98d9-4d622f4e6cd1.jpeg?1473061080)

