こんにちは。JOYCLE代表の小柳です。今回は、当社に出資いただいているベンチャーキャピタルANOBAKAの小田紘生さんとの対談をお届けします。
JOYCLEは、全国の自治体や医療・介護施設が直面する「ごみ処理」という社会課題に対して、新たな分散型インフラで解決を目指しているスタートアップです。VCの立場からどんな点に可能性を感じてくれたのか、実際に現場を見て何を考えたのか、率直な声をお聞きしました。
「難しそう、でも面白い」──最初の出会いと投資判断
小柳:まずは出会いのきっかけ、覚えてますか?
小田:広島県ゆかりのスタートアップイベントでしたね。僕の地元ということもあって参加していて、JOYCLEの事業内容を初めて聞いたのがそこでした。
正直、最初は「参入障壁がめちゃくちゃ高そう…」と思いました。でも、その分「これは社会に必要とされているし、誰もやってないことだ」とも感じたんですよね。
小柳:そう言っていただけて嬉しいです(笑)。産廃って地味だし、「市場としてわかりやすい」ものでもないので、見つけていただけただけでもありがたかったです。
小田:いや、地味だけど本質的な課題なんですよ。とくに医療や介護の現場での廃棄物処理って、もう持続不可能な水準まで来ている。地域のインフラが崩れているのに、代替手段がない。
そうした現場にフィットするソリューションを開発してるのがJOYCLEだった。これは一発花火じゃなく、社会の基盤を支える事業になると思って投資を決めました。

事業じゃなくて「人」に賭けた
小柳:「事業より人で決めた」と言ってくれたのも印象的でした。どういう意味だったんですか?
小田:装置の良さや技術のポテンシャルも大事なんですが、実現までの道のりがあまりにも複雑だからこそ、“走りきれる人かどうか”が最も重要になると思っています。
小柳さんは、とにかく足を使う。自治体や病院に直接会いに行って、ピッチに出て、巻き込んで、言語化していく。あの巻き込み力と行動量は、本当にすごいです。
あと、知らないことを素直に学びに行けるところも強い。産廃のプロじゃなくても、誰よりも速く情報を集めて、知識を武器に変えていける。それができるから「難しいインフラ事業でもきっと形になる」と確信を持てました。
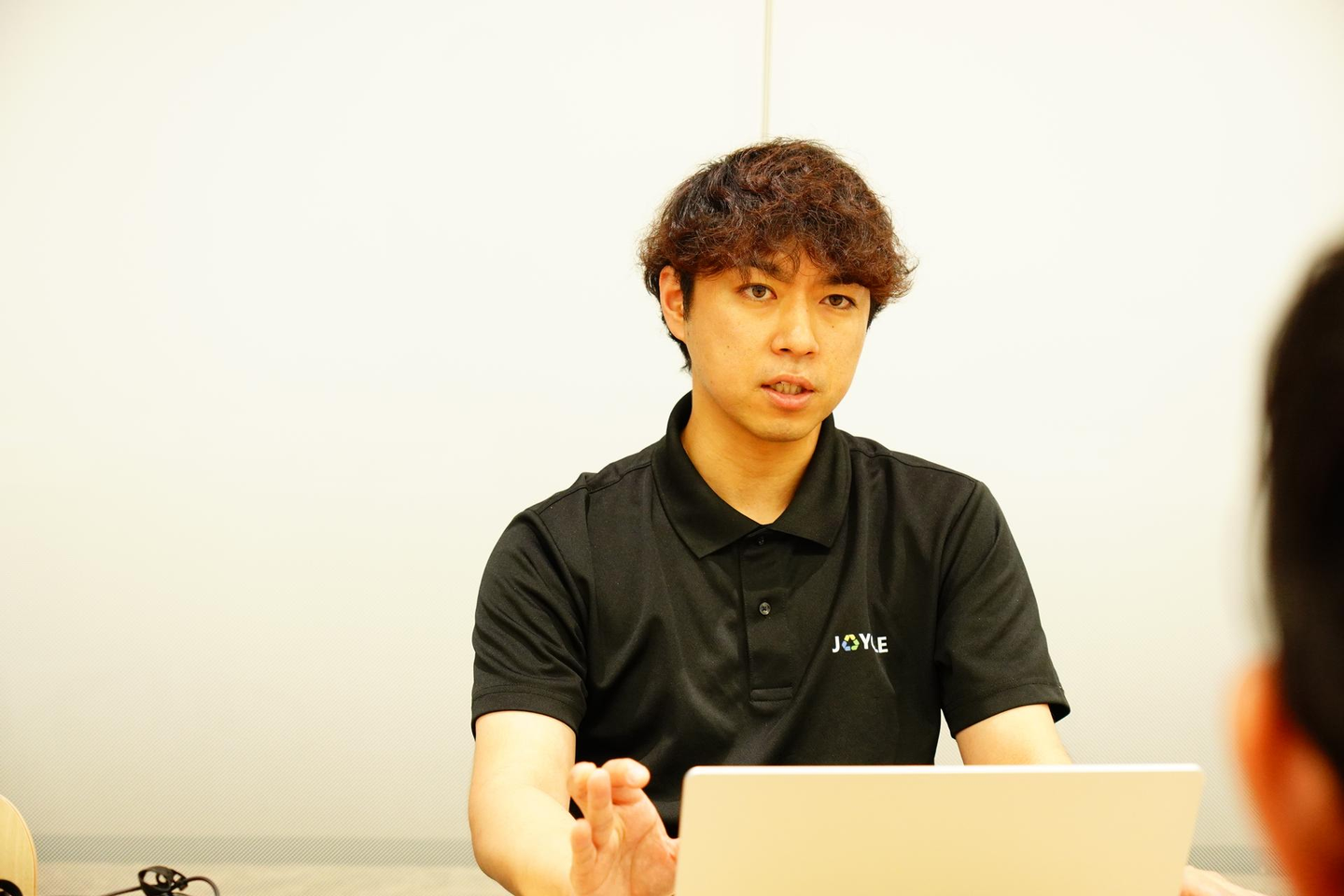
売り切りじゃなく、次世代のインフラをつくる
小柳:VCの方からはよく「装置ビジネスってスケーラビリティあるの?」と聞かれます。正直、その視点にモヤモヤすることもあります…。
小田:分かります(笑)。でもJOYCLEは、装置を売って終わりじゃない。むしろ、装置は“入り口”に過ぎなくて、データの可視化や稼働管理、保守、制度連携まで全部つなげていく仕組みをつくっている。
長期的には、「社会インフラとしての新しいモデル」を提案できると思うんです。装置、ソフト、制度、すべてを統合して最適化していく。その視野の広さが、他のハードウェア系スタートアップとは一線を画していると感じています。

現場のリアルが、確信に変わった
小柳:装置の見学にも来て、ご一緒した石垣島の産廃処理企業さんのお話も聞いてくださいましたよね。
小田:はい。あのお話は衝撃でした。ごみを運べない、処理できない、最悪ビーチに埋めてる──それが現実だと知ったとき、本当に「今すぐ必要なソリューションなんだ」と痛感しました。
現場の方が「これが欲しかった」と言ってた言葉が、何よりの証拠でしたね。
VCとの関係って、こんなに近くていいんだ
小柳:ANOBAKAさんとご一緒してから思ったのは、「VCってこんなに近い存在なんだ」という驚きです。
小田:僕らは「伴走型VC」でありたいと思ってるんです。株や契約の設計から、次の資金調達まで一緒にやりますし、社内メンバーのようにSlackでやり取りもしています。
特にJOYCLEのように、構造を変えるチャレンジには「何でも相談できる土壌」が必要なんですよね。JOYCLEには、そういう“遠慮なく本音で話せる関係”が築けていると思っています。

未来をともにつくる仲間を、探しています
小柳:JOYCLEって、まだまだ未完成なチームだと思っています。でも、その分“自分の意志”で動ける余白がある。正解のない挑戦が好きな人には、最高の環境かもしれません。
小田:社会課題って、構造ごと変えないと解決できないものばかりなんですよね。でも、それに真正面から挑めるスタートアップって実は少ない。JOYCLEは、その稀有な存在です。
「仕組みから社会を変えたい」──そう思える方には、ぜひ仲間になってほしいと思っています。

/assets/images/13963574/original/0edcf844-b366-4332-a5bb-afc3b6294418?1690149691)


/assets/images/13963574/original/0edcf844-b366-4332-a5bb-afc3b6294418?1690149691)

/assets/images/13963574/original/0edcf844-b366-4332-a5bb-afc3b6294418?1690149691)

