HIKIFUDAは、「ものづくりから世界を拡張する」というミッションのもと、エンターテインメント業界に特化した課題解決型のサービスを展開しています。現在はOEM事業を基盤に、製造業におけるBPOサービスと業務DX支援を組み合わせた独自のアプローチで、業界全体の変革を目指しています。
今回は、創業に至った原体験や今後のビジョン、そしてHIKIFUDAが大切にする価値観について、入澤社長に語っていただきました!
【プロフィール】
入澤 翔太郎
代表取締役社長。大学卒業後、複数の業種で経験を積みながら、独立志向を持ってキャリアを築く。バックオフィス支援事業を展開する中で、エンタメ業界が抱える構造的な課題に直面し、2021年に株式会社HIKIFUDAを創業。
変えたかったのは、業界の“当たり前”だった
僕はもともと、エンタメ業界に強いこだわりがあったわけじゃないんです。でも、ひとつ強く感じたのは「この業界はまだまだ変わる余地がある」ということ。
きっかけは、バックオフィスのBPO支援をしていたときに出会った顧問の会社でした。現場では、納期やクライアント優先の働き方が当たり前で、従業員の労働環境が整っていなかった。制度も慣例も古く、変化が止まってしまっていたんです。
日本は“ものづくり大国”なんて言われてきましたが、裏側の仕組みがこれではもったいない。もっと合理的に、もっと持続可能にできるはずだと。最新のテクノロジーやDXを取り入れれば、今まで業界に入れなかったような人たちも参加できる。つまり、バックオフィスを支援する仕組みを整えたら、ものづくりの社会構造を変革できるんじゃないかと思ったんです。
もともと僕は、いくつかの業種を経験してきていて、父もずっと自営業を行っていたので、自分で何かやってみたいという思いはずっと持っていました。で、実際に会社を立ち上げてみたのですが……想像以上に大変でしたね(笑)。
会社は「理想を叶えるための場所」になると思っていましたが、現実はそんなに甘くありませんでした。でも、それでも信じてくれる仲間が1人、また1人と増えていって、小さなワンルームから始まったHIKIFUDAは、今では銀座にオフィスを構えるまでになりました。
事業そのものの軸は変えていないけれど、世の中のニーズに合わせて、サービスの設計や伝え方はどんどん進化している。たくさんの人と力を合わせることで、理想が形になってきた感覚があります。

モノを作るだけではない。持続可能なエンタメの基盤を生み出したい
僕たちのミッションは「ものづくりから世界を拡張する」。これは「誰でもやりたいことを形にできる社会をつくる」という意味を込めています。
エンタメ業界は、慣例や職人技が価値になりがちで、属人性の高い世界です。それが、新しい人が参入しづらい原因にもなっている。だから、契約の標準化やプロセスのオープン化を進めて、誰でも再現できるようにしたいと考えているんです。
当社のOEM事業では、グッズ製造を通じて、IPホルダーやアーティストとファンの間をつないでいます。これは、単なる“モノを作る”という行為ではありません。いわば、エンタメの「延命装置」なんです。
エンタメには流行り廃りがあり、どんなに良い作品やアーティストでも、収益の仕組みがうまくいかなければ、続けていけないことがあります。でも、例えばグッズの売上が安定すれば、アーティストの活動そのものが長く続けられる。ファンも、自分の応援が意味を持つと実感できる。そういう循環をつくることこそ、僕たちがこの事業で届けたい価値なんです。
そもそも、エンタメって商慣習の中では“立場の弱い”ジャンルなんですよね。だからまずは、グッズの見た目を変えるところから始めました。そこから、僕の得意な領域である「仕組みづくり」や「要件定義」といったPMO的な視点を加えて、事業を進化させていきました。
今はOEMが売上の大半を占めていますが、それだけにとどまらず、最近では在庫の管理や配送の体制も強化しはじめています。さらにこれからは、グッズの買取に関するサービスも広げていく予定です。
このような一つひとつの積み重ねが、業界のあり方そのものを変えていく。そんな手応えを感じています。
裏側から支える力が、未来のエンタメをつくる
これから先、僕たちが本気で目指しているのは、 エンタメ業界における「バックオフィス文化の常識化」です。
例えば今、某プラットフォーム運営企業様と一緒に取り組んでいるプロジェクトがあります。支援者へのリターン品の製造・配送・各種対応まで、HIKIFUDAが担っているのですが、このようなアライアンスは、エンタメの世界ではかなり珍しい。そもそも「組みにくい」とされてきた業界なんです。
でも僕は、こういう座組みこそ“常識”にしていきたいと思っています。「エンタメをやるなら、バックオフィスを整えて当たり前」―― そんな認識が業界全体に広がれば、もっと健全で、持続可能な土台がつくれるはずです。
実際にエンタメ業界は、華やかなイメージもあり、裏側で支える人たちがやりがい搾取になってしまうような状態も起きています。だからこそ、僕たちはバックオフィスを“固定インフラ”として組み込んだ新しいビジネスモデルを、業界のスタンダードにしていきたいんです。
これは、僕の中でずっとブレずに持ち続けてきたロジックですが、そこに“情熱”の部分が乗ってくると、もっと未来が広がると思っていて。
例えば、僕たちが展開している学生団体「UNION」。これは、エンタメ業界に入りたいと思っている若者たちに、実際の現場で「何をどう始めたらいいのか」を体験的に学んでもらう場です。そういう意味では、HIKIFUDAは“エンタメの教育機関”のような存在にもなっていきたいんです。
業界の入り口として、まだ何も知らない人にも門戸を開く。 土台を育て、裾野を広げていく。それが、業界そのものを厚く、強くしていくことにつながると思うんです。

「実行力のある、いいひと」が新たな“常識” を生み出す
僕たちが大切にしている人物像は、「実行力のある、いいひと」。 “挑戦”という言葉は響きはいいけれど、それだけじゃ社会は回らない。大事なのは、ちゃんと“やるべきことをやる”実行力なんです。
「いいひと」とは、要は素直な人のこと。自分を主語にするのではなく、まずは相手、特にお客様の立場に立って考えられる人のことです。バックオフィスの仕事って、主観じゃできないんですよね。だからこそ、誠実に向き合える人に来てほしいと思っています。
あと、よく「HIKIFUDAはベンチャーですよね?」と言われますが、正直、僕はそう思ってなくて。 というのも、僕の中で“ベンチャー”って、まだ整ってない、雑多な状態というイメージが強いんです。でも今のHIKIFUDAは、もうそういうフェーズじゃない。誰が入ってきても、一定のクオリティで安心して働ける環境があります。
だから、「ベンチャーっぽさ」は求めていません。でも、成長したいとか、社会に貢献したいと思っている人。 そういう気持ちを持った人に仲間になってほしいですね。
僕は本気で、業界の構造を変えられると思っているし、それに向けたビジョンも描いています。 8年前にバックオフィスの仕事を始めた頃は、今みたいに認知もされていませんでした。でも今では、ビジネスモデルとして確立されてきて、逆にバックオフィスが整備されてない業界は自然と淘汰されるような時代になってきました。
だからこそ、僕らが掲げているミッションやビジョンを、ただの理想論で終わらせたくない。 当たり前に、業界の「常識」にしていく。それが、持続可能な世界をつくることにつながるし、誰が抜けてもちゃんと回っていく仕組みにもなると思うんです。
このような価値観を共有できる人と、未来を形にしていきたいですね。
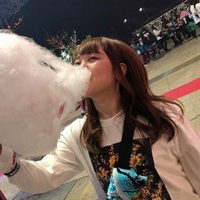

/assets/images/19703393/original/b2504a9f-3fde-4438-8fff-37f5ed855202?1731570926)


/assets/images/19703393/original/b2504a9f-3fde-4438-8fff-37f5ed855202?1731570926)





/assets/images/19703393/original/b2504a9f-3fde-4438-8fff-37f5ed855202?1731570926)

