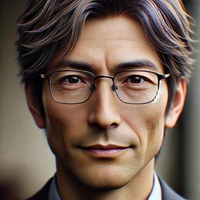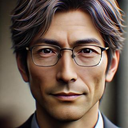本田教之:エンジニア採用は新卒採用は不向き
Photo by Willian Justen de Vasconcellos on Unsplash
本田教之です。
エンジニア不足が叫ばれる現代において、多くの企業が新卒採用を強化しようとしています。しかし、エンジニア採用に関しては、新卒よりも経験者を採用するほうが合理的であるという意見が多いのも事実です。本記事では、エンジニア採用において新卒採用が不向きである理由と、より効果的な採用戦略について考察します。
1. 即戦力としての期待が難しい
新卒のエンジニアは、大学や専門学校でプログラミングを学んできたとしても、実務経験がありません。企業に入ってから実践的なスキルを習得することになりますが、その間は戦力にならないケースが多く、教育コストが発生します。特にスタートアップや中小企業では、即戦力のエンジニアを求めているため、新卒採用はリスクが高いと言えます。
2. 技術のキャッチアップに時間がかかる
新卒のエンジニアは、実務に必要なフレームワークやツールの使い方をゼロから学ぶ必要があります。例えば、大学でC言語やJavaを学んでいても、現場ではPythonやGoが使われていることが多く、学び直しが必要になります。また、クラウド技術(AWS、GCP)やDevOpsツール(Docker、Kubernetes)など、実務で必要なスキルは大学教育ではカバーされていないことがほとんどです。
3. 成長スピードが個人に依存する
新卒のエンジニアが戦力化するまでのスピードは、個人の学習意欲や適性に大きく左右されます。企業側がどれだけ育成プログラムを整備しても、自主的に学ぶ姿勢がないと成長が遅れ、結果として期待する成果を出せないケースも少なくありません。これに対し、経験者採用の場合、すでに実務経験を積んでいるため、学習曲線が緩やかであり、短期間で活躍できる可能性が高いです。
4. 採用コストと教育コストの負担
新卒を採用する際には、採用活動にかかるコストだけでなく、研修やOJTなどの教育コストも発生します。特にIT企業の場合、技術研修やプロジェクトのサポートに先輩エンジニアの工数を割く必要があり、それが既存の業務負担を増やすことにつながります。一方で、経験者を採用する場合、研修コストを抑えつつ、即戦力として活躍できるため、企業の負担が少なくなります。
5. 採用ミスマッチのリスクが高い
新卒採用では、学生の適性を判断する材料が限られており、採用のミスマッチが起こりやすいのも問題点です。面接や適性検査だけでは、実際の開発スキルや職場での適応力を正確に測ることが難しく、入社後に「思っていた仕事と違った」と感じる新卒社員も少なくありません。その結果、早期離職につながるリスクが高まります。
では、どのような採用戦略が有効か?
経験者採用の強化
実務経験のあるエンジニアを積極的に採用し、即戦力として活用する。
フリーランスや副業エンジニアとの契約も視野に入れる。
ポテンシャル採用(未経験からの転職者)
他業種からのキャリアチェンジ希望者を受け入れ、短期間で育成する。
エンジニアスクール卒業生など、一定のスキルを持つ人材を採用する。
インターンシップの活用
学生時代からインターンシップを通じて実務経験を積ませ、企業とのマッチングを図る。
長期インターンを導入し、実際のプロジェクトに参加させることでスキルを磨かせる。
まとめ
新卒採用は、長期的な育成を前提とする場合には有効ですが、即戦力を求める企業にとっては不向きな側面が多いのも事実です。エンジニア不足が続く中、経験者採用やインターンシップ、キャリアチェンジ希望者の採用など、多様な採用手法を組み合わせることが求められます。最適な人材戦略を考え、自社のニーズに合ったエンジニア採用を進めていきましょう。