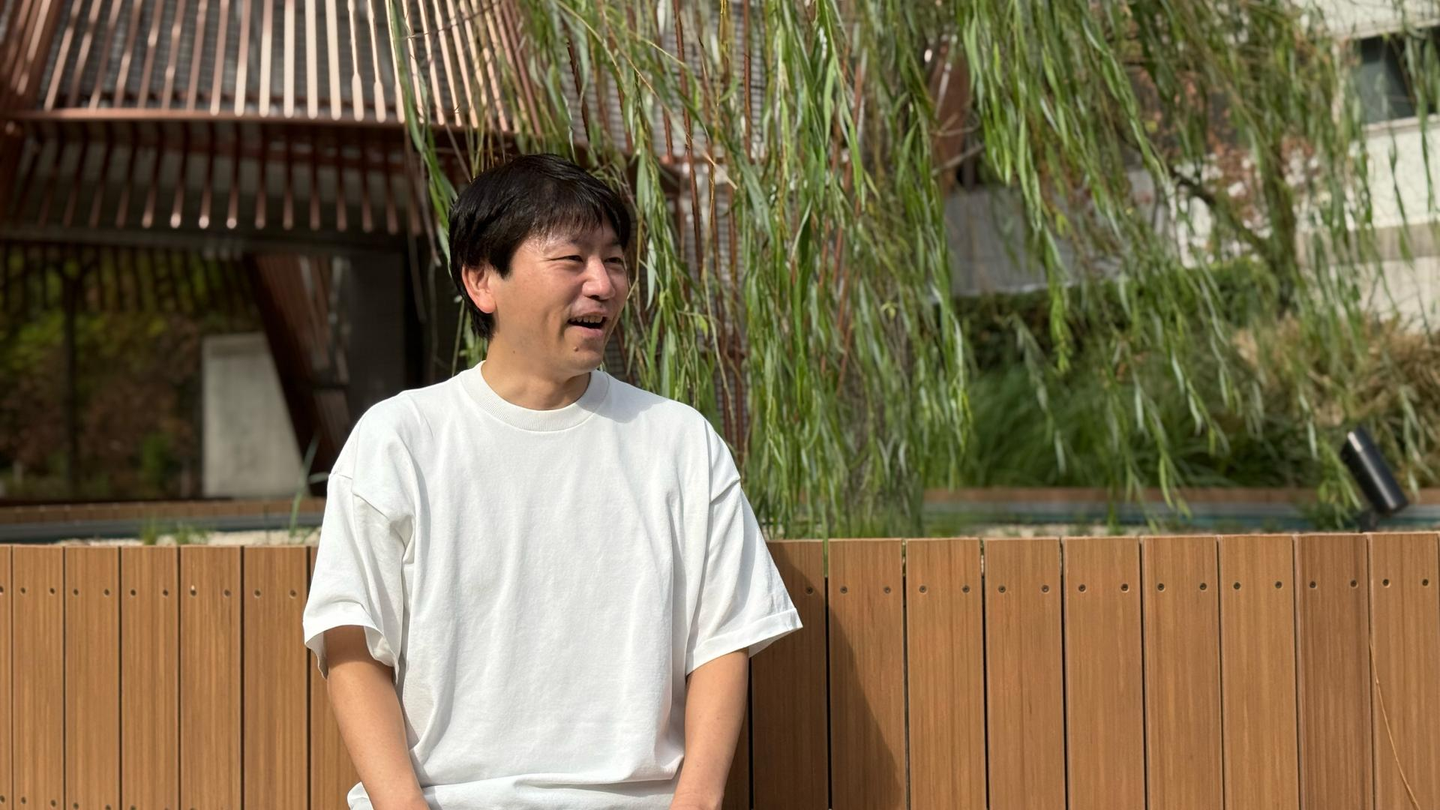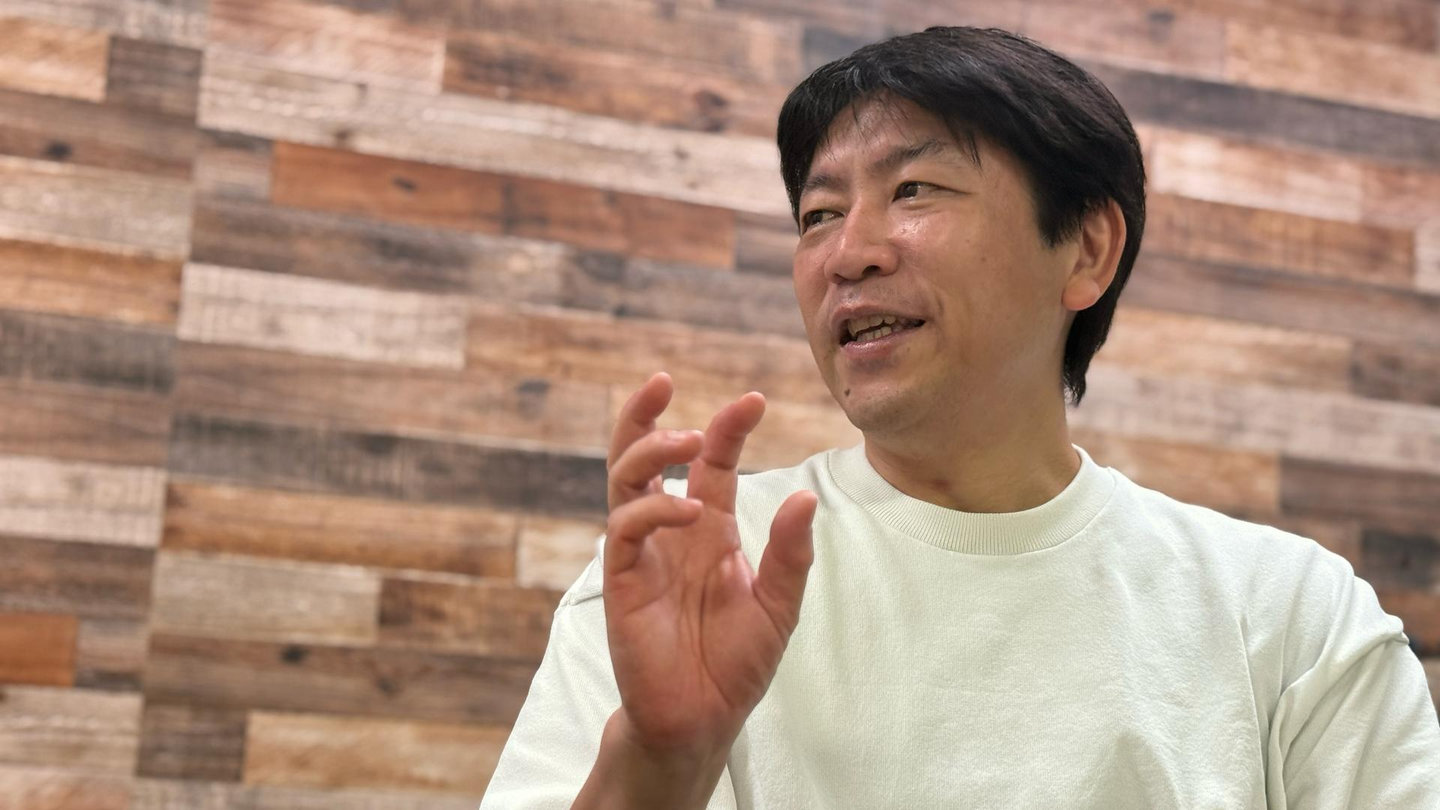トンガルマンの社長って、ほんとはどんな人? | トンガルマン株式会社
社員匿名座談会「村松さんを語る」登場メンバー(匿名)ディレクター/デザイナー/バックオフィス※発言は読みやすさのために編集・要約しています。採用サイトの真面目な社長インタビューはよくあるけど、も...
https://www.wantedly.com/companies/tongullman-co-jp/post_articles/1009838
──今日は会社紹介を通して、社長の村松さんがどんな人で、どんな価値観で会社を動かしているかをうかがいたいと思います。よろしくお願いします。
村松: はい、お願いします。
──さっそくなんですが、自己紹介とトンガルマンに関わり始めた経緯からお願いします。
村松: 13年くらい前ですかね。グループ会社のGPオンラインに入社したタイミングで、ちょうどトンガルマンが設立される時期でした。GPオンラインの面接で「(トンガルマンと)どっちに行きたいですか?」と聞かれて、僕は「どっちも楽しそうです」って答えたんです。
同時期に入ったエンジニア2名はトンガルマンへ行って、僕はなぜかGPオンライン側に(笑)。でも入社2日目くらいにトンガルマンの社長がやってきて「手伝ってくれ」と。しばらくはGPオンラインに席を置きながらトンガルマンを手伝っていました。
それで半年後くらいに「正式に入らないか」という話になって。僕はアプリ制作の経験も少しあったので、創業から半年くらいでジョインして、そこからエンジニアをやりつつ、会社の成長とともにディレクターグループやデザイナーグループを作るみたいな組織づくりも一緒にやってきました。
──もともとはどんな領域のエンジニアだったんですか?
村松: 入社前は高速道路の換気ファンを回すシステムとか、保険の契約システム、新聞を作るシステムとか、どちらかというとかっちりとして仕事でした。
その頃はクライアントの顔があまり見えない世界だったんですけど、GPに入り徐々にWeb系に近づいて、トンガルマンでスマホアプリの時代が来てエンドユーザーに近いところへ移っていきました。流行っているシステムをそのときどきでやってきた感じですね。実は今もシステムや作ること自体は大好きです。
──なるほど、どんどんクライアントやユーザーの顔が見える世界へ寄っていったわけですね。
村松: そうです、反応が見えるのが楽しいんですよ。
──もともと管理職や社長になりたいと考えていたのですか?
村松: できればずっとエンジニアでいたかったです(笑)。前の会社でも、年齢や経験でやらせてもらう役目は増えたんですけど、やっぱり自分の手を動かして作るのが楽しかった。転機でいうと、トンガルマンに入ってからですね。
──マネージャーや社長に至る流れは?
村松: 当時は社長+エンジニア数人みたいな体制で、ディレクターがいなかった。社長が仕事を取ってきて、エンジニアが作る感じでした。
で、「ディレクターは必要だよね」となってグループを作ったり、チームがまとまってないと感じたら自然とまとめ役をやったり。そうすると今後はデザイナーを採用したらそこを見る人が必要で、みんながこっちを見るから「わかりました」と(笑)。少しずつマネジメント業務にシフトしていきました。
これがやり始めると結構楽しい。エンジニアではない考え方に触れるのが面白くて。望んでプラン通りというわけでは全然ないですが、必要なことをやっていくうちに今に至っています。
──なるほど、必要なところに入り続けた結果としての社長(笑)。
村松: そんな感じですね(笑)。
──とはいえ、マネージャーと社長では大きな違いもあると思いますが、就任して一番「ここは違うな」と思ったところは?
村松: よりみんなのことを考えるようになりますし、「自分がキー」という感覚が強くなりました。ただ、自分一人で何とかなるものではないとも強く実感しました。結局メンバーがいてこそなんだなと。そこは思っていたより変わらない部分もありました。
──なるほど、責任とチームの両輪ですね。
村松: そうですね。
──経営者としてたいせつにしている意思決定の進め方などはありますか?
村松: 考えるときはまずいろんな角度から分析して、なぜ迷っているのかまで掘ります。だいたい迷いの枝がたくさん出るんですけど、とことんまで考え抜いて、判断材料を出し尽くして、最終決断は感情に切り替える。みたいな二段階構造です。
──なるほど、2面性がありますね。その経験はどこで培ったのですか?
村松: 前半はエンジニア時代、後半はトンガルマンでの「突然の部署立ち上げ」みたいな正解がわからない状況をやってきた経験から。最後は後悔しない方を選ぶのが良いです。自分で選べばやり切れるし、他責にしないので。
社内でサイコパス説が出ているそうですが、モードがいくつかあるのは確かです(笑)。
(村松さんのサイコパス疑惑はこちらで詳しくメンバーが語ってくれています)
──少しプライベートも。最近のマイブームは?
村松: 万博が楽しくてしょうがないです。何回も行ってます。家族でも一人でも、メンバーとも。展示そのものだけじゃなくて、作った人の顔を思い浮かべて見たり、国の思惑や国民性まで含めて楽しむのが好きで。
──それは楽しそうですね。おすすめのパビリオンとかありますか?
村松: UAEパビリオンが結構好きです。全体の適度な脱力感がよくて。話しかけるとめちゃくちゃ喋ってくれるんですよ、運営の人たちが。でも呼び込みはしない。そのギャップが面白い。人も含めてコンテンツなんですよね。
──視点が“作り手側”ですね。
村松: 職業病かもしれません(笑)。
──会社のことも教えてください。ミッション・ビジョン・バリューは就任時に?
村松:
はい、新たに言語化しました。詳しくはぜひトンガルマンのWebサイトを見ていただきたいですが、バリューにしたのは「協調・責任・情熱」。これは僕自身が日々大切にしている姿勢で、仕事に真摯であってほしい、という思いを込めています。
──TOPページに出てくる「まだ見ぬ世界を、ご一緒に」というメッセージも印象的です。
村松:
そうですね。受託制作という形態は自分たちのサービスではないぶん、作り終わったあと見えづらくなることもある。距離が生まれがちなんですよね。でもそのマインドだといいものはできない。自分ごととして一緒に作るのが大事で、クライアントにも我々をベンダーではなく仲間と思ってもらいたい。その両方向のスタンスを一言で示すのが「まだ見ぬ世界を、ご一緒に」というメッセージです。
──クライアントや社会に対して、どんな課題を解きたいと考えていますか?
村松: 僕たちは専門性が高いことをやっていると思っています。やりたいことはあるけど実現方法がわからない、わかるけど謎の空白があって踏み切れない、そういう場面が多い。
そこを僕たちが解像度を上げて、到達したいところまで一緒に行く。それが一番求められていることで、僕らが力を発揮できるところだと思います。
──なるほど、クライアントが実現したいが方法がわからないような世界を、ご一緒するということですね。
村松: そうです。
──その中でトンガルマンの強みや、今後伸ばしたいところは?
村松: 強みは技術力もありますが、時代的にここだけで差別化は難しい。最終的にものづくりを分けるのは中の人の姿勢で、協調・責任・情熱というフレーバーが大きい。一緒のパートナーとして作り上げるところは強いと思っています。
逆に課題と言うと、受託ゆえに責任やポジションを守ろうとしてしまう瞬間があること。実は行儀がよすぎる、真面目すぎる状態になると「ご一緒に」感が薄れることも。社内には個性的で面白い人が多いのに、仕事の場だと抑えめになることもある。そこはもう少し出していけると、むしろ喜ばれると思っています。
── マインドや文化の土台はできてきているので、その先の個を出していくフェーズということでしょうか。
村松: はい、そんなイメージです。
──そんなトンガルマンですが、社内の雰囲気は村松さんから見て一言で言うとどんな感じですか?
村松: みんながみんなのことをよく見ているなと感じます。誰かがへこんでいれば「話聞いてきます」と自然に手が伸びる。忙しくても自然と人のことは見ている。逆に自分のことは見えてない人もいるくらい(笑)。部署やポジション関係なく、会社全体で似たパーソナリティはあるかもしれません。
──社長と社員の距離はどんな感じですか?
村松: 僕はプロジェクトで困っていると呼ばれることも多いし、日常でもフラフラ歩きながら「今何やってんの?」って話します。社長と社員の距離は比較的フラットだと自分では思います。
──社長に就任されてから組織文化作りとして意識したものはありますか?
村松: 僕が社長になってから数字の話をすごくするようにしました。制作会社ですが、アーティストではなくビジネスの視点を持ってほしい。そうでないとお客さんと長く良い関係は築けない。
最近は社内でもかなり会社の数字やプロジェクトの数字に対する意識が強くなってきて、「この数字を達成するためにこうしよう」「この予算感ならこのアイデアのほうが効果が高い」みたいな、現実的で再現性のある会話が増えました。チームが強くなってきているポイントだと感じています。
──永続的な関係性を築くためにも数字意識は重要ですよね。
村松: そうなんです。本当にご一緒にするためには、自分や相手のどちらかが無理をしている状態は結局長続きしないので。
──たしかにメンバーの数字の意識はかなり高まっていると感じています。でも数字至上主義にはなっていないですよね。社内も決してピリピリしているわけでく自然な感じですが、この辺りのバランスやコツは?
村松:
実は僕には良い仲間がいまして。必要なタイミングで必要な数字の話をうまく落とし込んでくれる人がいたり。それから恐ろしいほどの仕組みを作る数字の鬼みたいな人もいます(笑)。見た目は数字で語るタイプじゃないのに、数字を楽しむ人です(笑)。
どんどん組織内で対話を重ねるうちにいろんな人が必要性を理解してくれて、いまは各グループのミーティングや現場でも自然に数字の話が出る。トップダウンというより草の根的に広がっていきました。
──他にもメンバーの自慢できるところを教えてもらえますか?
村松: 止まらないとこかな(笑)。挫折しても座り込まず、歩きながら考え続けるところ。止まりそうな人がいたら周りが抱え上げて歩き始める(笑)。これは風土だと思います。
最初からそういう人だけを採用していたというより、大多数がそうだと自然とそうなる。トンガルマンに入るとそういうキャラになっていく面もあります。
──たしかに、支え合って前に進む姿勢がありますね。
──他社との違いや特徴ってありますか?
村松: 制作会社って個人商店的になりがちですが、うちはチームをすごく大切にしています。チームだと高め合いが起きるし、へこんだときに補い合える強さがある。
だからコミュニケーションや関係性は大事にしています。基本的なことでいうとオンラインMTGでも相手の顔を見ながらちゃんと話す、など。外からは個性の強いクリエイター集団に見えるかもですが、実態はチームの力が強い。これからは個性ももう少し前に出して、チームと個のバランスを取りたいです。
──トンガルマンで活躍する人の共通点は?
村松: 目の前の仕事を楽しみつつ、中期も見るという二段階の視点がある人は成長が早いです。
あとはラストマンシップが大事ですね。僕らのプロジェクトでは、自分が最後の防波堤という気持ちが成功と失敗を大きく左右することがある。そういう意識が根づけば、時代やフィールドが変わっても成功できるようになると思います。
入社後は協調性を発揮しながら、テンプレないい子で終わらずに個性で勝負してほしい。出すべき場面では出す、求められていない局面では抑える。この切り替えができる人はぐんと伸びます。
──一方で、向いていないのは?
村松: すごく安定して毎日きっちり定時で、不安は一切抱えたくないという人は向いていないと思います。
その代わり、創造的なことがやりたい、変化や初見を楽しめる人にはチャンスがたくさんあります。僕らにとってもまだ見ぬ世界がめちゃくちゃあるので、飽きないことだけは保証できます。あと最後は根が真面目で作り切る人が合います。
── 最後に、応募を迷っている方へひと言お願いします。
村松: 名前のインパクトや外からのイメージで、変人集団で近寄りがたいと思われるかもしれませんが、全然そんなことはなくて。実態は真摯にやり続け、悩んで悩んでアウトプットするチームです。
この仕事を本気でやりたいと思えたなら、ほぼ何とかなると思ってます。飽きない毎日は約束できるので、ビビらずに一度、応募してみてください。ご一緒にやりましょう。
──背中を押されます。今日はありがとうございました。
村松: こちらこそ、ありがとうございました。