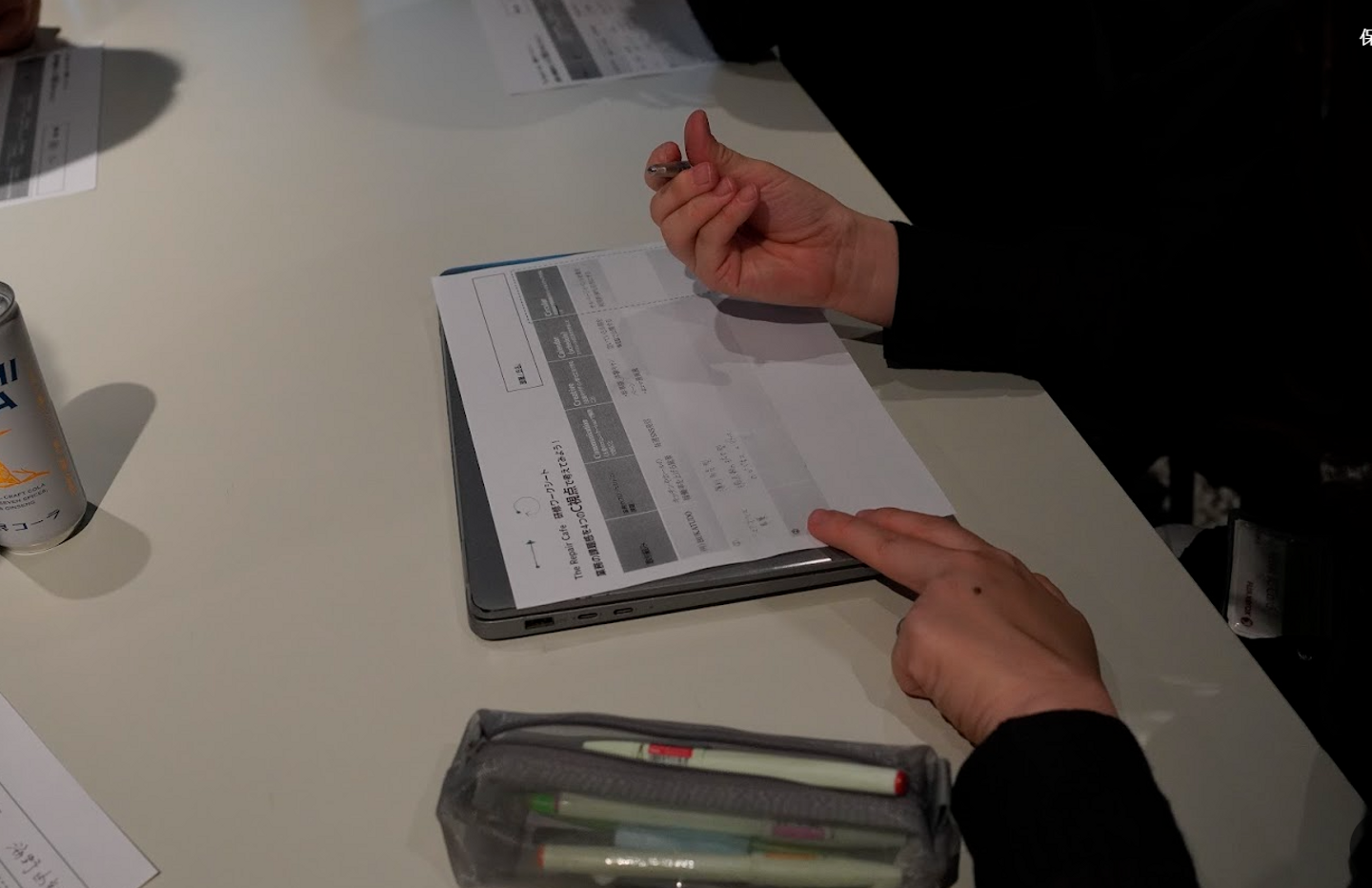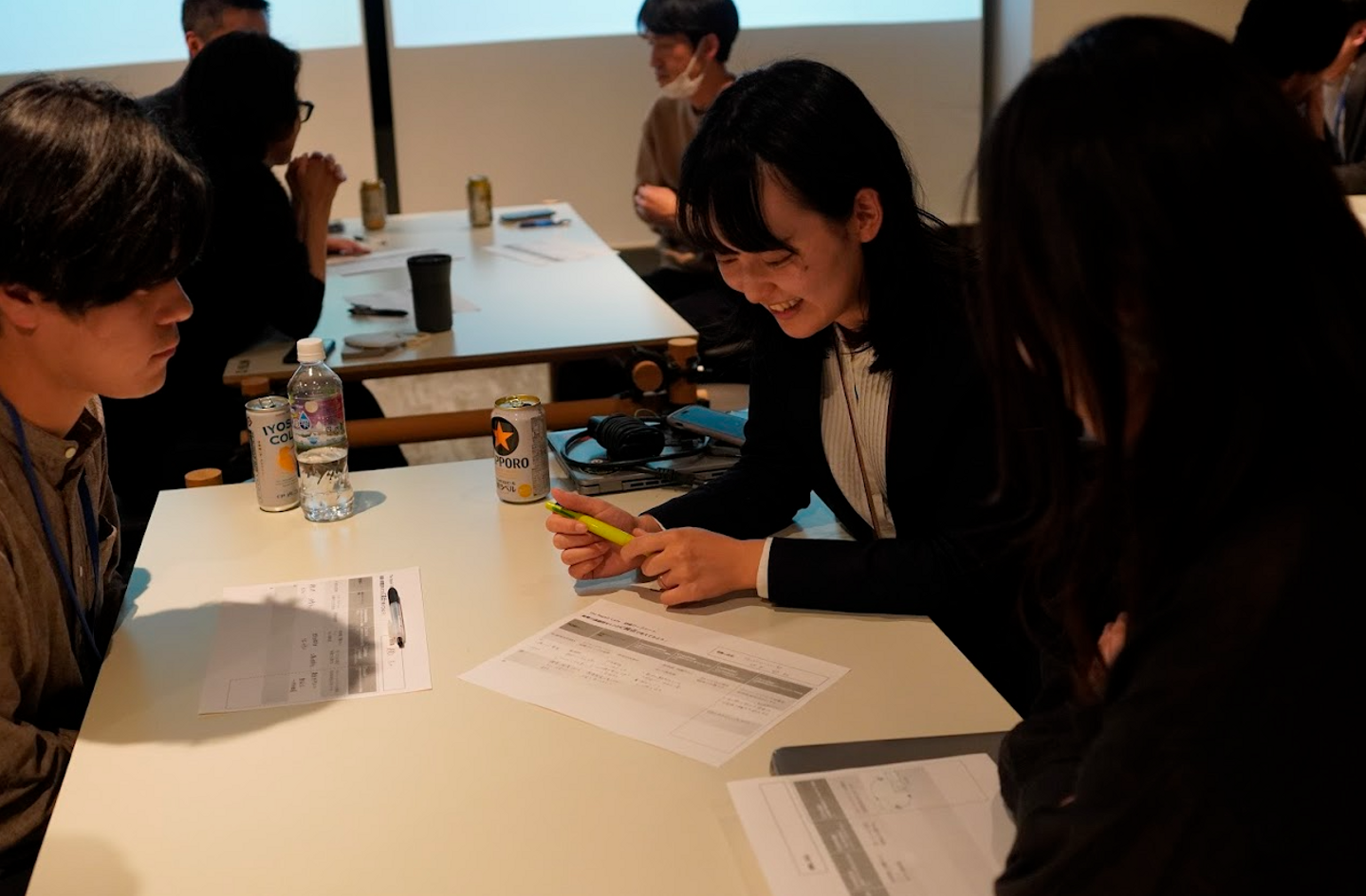豊かな未来のために | リノベーションの株式会社リビタ
リビタはリノベーションで、暮らしとコミュニティをデザインする集団です。企業社宅や中古マンションなどの既存建物を再生し、お客さまの本当に住みたい住まいをご提供します。
https://www.rebita.co.jp/vision/csv.html
リビタでは、これまで/これからのプロジェクトやリビタが定める「くらしのスタンダード‐ReBITA Sustainability Standard‐」に関する分野について、さまざまな角度から考える場として「リビタの夜会」を定期的に開催しています。リビタ社員だけでなく、日ごろからお世話になっているお取引先の方や卒業生、内定者などを招待し、トークと懇親会をセットに共に学び、会話を楽しむセミオープンな場です。
今回は「サーキュラーエコノミー」をテーマに、ショートドキュメンタリー『The Repair Cafe』を鑑賞し、ゲストそれぞれの視点でのサーキュラーエコノミーの潮流についてお話しいただきました。
鈴木高祥さん|株式会社カゼグミ 代表取締役 合作株式会社 取締役
一般社団法人大崎町SDGs推進協議会 クリエイティブディレクター/一般社団法人Think the Earth 推進スタッフ/一般社団法人 Work design Lab パートナー
茨城県水戸市や鹿児島県大崎町での仕事に従事。リビタとは「BUKATSUDO」や「the C」など利用いただいていた関係から茨城県のお仕事などで関わる。プロジェクトデザイナーとして、企画の立案から、最終のアウトプットまで関わる。
加藤 佑さん|ハーチ株式会社 代表取締役
1985年生まれ。東京大学教育学部卒業後、2015年12月にハーチ株式会社を創業。英国ケンブリッジ大学サステナビリティ・リーダーシップ研究所 Sustainable marketing, media and creative 修了。慶應義塾大学SFC研究所所員。
ゲストの鈴木さんは、普段プロジェクトデザイナーとして行政や民間企業と仕事をする中で、「サーキュラーエコノミー」という概念は、地域に切り離せないものだと感じているそうです。
鈴木さんが関わる鹿児島県大崎町は、「サーキュラーエコノミー」に先進的に取り組む町として注目されています。代表例として、住民が分別しきれいに資源化されたプラスチックやペットボトルや缶は、高値で出荷され、ごみ売買の益金を地域に還元する仕組みとして「リサイクル未来創生奨学金制度」を導入しています。鈴木さんは、ワークショップを実施し、視察に訪れた人が「サーキュラーエコノミー」をより身近に感じてもらえるような体験を提供しています。
今回鑑賞した『The Repair Cafe』は、加藤さんが代表を務めるハーチ社が企画制作を手掛けたオリジナルショートドキュメンタリーです。
リペアカフェとは、家電や服、自転車など、あらゆる壊れたものを地域のボランティアの方から教わりながら修理ができる場所です。発祥の地であるオランダ・アムステルダムを舞台に、日々、直したいものがある人が訪れる様子が描かれています。
この場所で生まれるコミュニケーション、身の回りにあるモノと人との関係性、そして「真の豊かさとは何か」を見つめ直す姿が印象的でした。
リペアカフェでは、誰かのものが直るとその場に居合わせた人は一緒に喜びます。一方、ムービー内で「アムステルダムの人は忙しすぎる。友達以外の人と話す機会がない。」とある人が言っていました。そんな忙しい地だからこそ、普段出会うことのない人と日常生活や仕事ではしない「リペア」を行うことで、人々の居場所にもなっているのだと感じました。
続いて、サーキュラーエコノミー含むソーシャルグッドなアイデアを集めたウェブマガジン「IDEAS FOR GOOD」を運営している加藤さんより、海外の事例や様々な研究内容などサーキュラーエコノミーについての最近の潮流についてお話しをしていただきました。
とある研究によると、環境負荷の8割はデザインや設計段階で決まってしまうのだそう。デザイナーとして物作りの裏側まで想像をすること、そして、ユーザーの心に寄り添うエモーショナルな物を作ること。このようなことが永く物を使ってもらえる、という話が印象的でした。
各テーブルにて、サーキュラーエコノミーの視点をどのように事業に落とし込んでいけるのかアイデアワークショップをしました。
以下、参加者からの意見
リビタ社員の多くが関心の高いサーキュラーエコノミーについて、参加者全員で考えるよい機会となりました。
役職や部署を超えて、関心事をもとに学び合える場として今後も様々なテーマで夜会を実施していきます。レポートの発信もしていきますので、お楽しみに!
撮影:古末拓也