はじめまして。株式会社ナンバーナイン、クリエイティブ局長の澤と申します。
新卒入社したIT企業で、人事部長や子会社代表を経験し、ナンバーナインにジョインしました。現在は、横読み漫画・タテ読み漫画の編集者を抱える「編集部」、制作進行や作家さんへの原稿料・印税支払いなどのやりとりを束ねる「コンテンツ統括部」、そして主にタテ読み漫画の制作を行う「クリエイティブ部」の3つの部があるクリエイティブ局の局長をしております。漫画IPパブリッシャーとして、時代と国境を超えるような作品を生み出すため、日夜組織の整備を進めています!
今回のnoteは、3つの部の中でも、作品制作の要を担う「クリエイティブ部」について、ご紹介させていただきます。webtoon制作における作品のクオリティを左右する重要な部署の仕事に興味がある方はぜひご一読ください。
国産webtoonNo.1を生み出したその先に何を目指すのか?
ナンバーナインでは、タテ読み・フルカラー漫画であるwebtoonを、漫画というよりはアニメに近いチームでの制作を行っています。
原作・ネーム・線画・背景・着色をそれぞれ工程ごとに担っていただく外部作家さんはもちろん、社内でも、編集・制作進行(PD)・アートディレクター(AD)・クリエイターといった役割に分かれ、「誰か一人の力」だけでは連載できない、高いクオリティの作品を、毎週制作しています。
制作プロセスの一例。各工程に担当者がいるケースもあり、チーム力が問われる現場です
制作フローの詳細に感しては以下のnoteもご参照ください。
なかでもクリエイティブ部が担う役割は、コマごとの演出を最大化したり、作品世界に奥行きを生むためのクオリティアップの部分です。
各作品を担当する社内のADは、編集者と作家さん(原作者・ネーム制作者)が作成した細かく指示の入ったネームを受け取り、線画、着彩、背景、エフェクト、仕上げといった、作品の絵的なクオリティを決定づける制作工程の全てを監修しています。
デッサンの崩れがないか、ネームの演出意図と合っているか、キャラクターの感情がきちんと表現されているか、場面にあった描写になっているか……などなど、過酷な週刊連載の中でも、作品の細部に神を宿らせる責任を負っています。それを支える社内クリエイターたちもADの判断を軸に、週刊連載の過酷なペースに合わせた作業を、高いクオリティをキープしながら行っていきます。
いわば、才能ある作家さんたちの情熱が込められたバトンを受け、最高の形で読者の元へ届けるための「アンカー」を担っているのが「クリエイティブ部」です。
そのような社外の作家さんの力と社内制作のハイブリッドな制作体制で生まれたのが、「LINEマンガ 2024年間ランキング(連載)」にて、国内制作として最高位の5位と9位にランクインした『神血の救世主~0.00000001%を引き当て最強へ~(以下『神血の救世主』)』と『俺だけ最強超越者~全世界のチート師匠に認められた~(以下『俺だけ最強超越者』)』です。
ありがたいことに、この2作のヒットにより、スタジオとしては、これまで「なんとかガムシャラに良いものを作る!」というフェーズから、「2つのヒットを通じて得られた仮説を基に、しっかりとした体制で、多くの作品をリリースしていく」というフェーズに突入できるようになりました。8月7日に配信開始が決まっている『ゴッドオブキラーズ』はじめ、リリース準備中の複数の作品でも「これは!」という手応えがチーム内で生まれてきてもいます。
「最強のプロダクションチーム」になるために必要な3つの進化
その一方で、課題もでてきました。
多くのクリエイティブチームが抱える問題のような気もしますが、より安定的に高品質の作品をつくっていくために、「個々のスキルの集合体」から「最強のプロダクションチーム」への進化が求められるようになってきました。
現在のクリエイティブ部が成し遂げなければならない進化は、以下の3つです。
進化1:「感覚」を「言語」へ。作品のクオリティをさらに高めるための共通言語化。
「このキャラクターのハイライト、もっと"キラッと"させて」 制作現場では、こうした感覚的な言葉が飛び交います。もちろん、その感性はクオリティの源泉です。また、制作本数や、部のメンバーの人数が少ない場合は、感覚のままでも、阿吽の呼吸で作品に反映することは難しくないかもしれません。
しかし、チームとして、ある程度たくさんの作品数を制作していかなければならないとなると、安定的に高品質な作品を生み出し続けるには、「感覚」を「再現可能な技術」に翻訳しなければなりません。
- どの作品の、どの表現で、なぜクオリティの課題が発生したのか?(課題の特定)
- 例えば「キラッとさせる」とは、具体的にどのツールを使い、どの数値をどう調整することなのか?(言語化・数値化)
- そのTIPSを、今後どうチームの制作マニュアルに反映し、誰が責任を持って展開するのか?(仕組み化・アクションプラン)
こうした議論を構造化し、チームの共有財産となる「ナレッジ」として蓄積する。このプロセスが、特定個人のスキルに依存しない、組織全体の制作レベルを底上げすると考えています。
現状でも、個々の「作業」のマニュアルはあるのですが、どうやって「勝ち筋」を見出し、その方向にアウトプットを改良していくのかは、もう「型にはめる」以外のやり方で仕組み化できそうだと考えています。
進化2:週刊連載の生命線。制作パイプラインを司る「リレーの交通整理」
webtoonの制作現場は、秒単位でバトンが渡されていくリレー競技です。
作家さんから「線画」データが届く →「着彩」担当へ →外部の「背景」チームが描いた素材と合成 →「エフェクト」担当が演出を加え、仕上げる。このパイプライン上で一つでも遅延や手戻りが発生すれば、その影響はあっという間に全体へ波及し、週刊連載という絶対ルールを守れなくなります。
私たちが今まさに求めているのは、この複雑なリレーを円滑に進めるための「交通整理」、つまり生産管理の視点です。
- 各工程の標準作業時間(リードタイム)はどれくらいか?
- ボトルネックはどこに発生しやすいか?
- 各担当者のスキルや負荷状況をどう可視化し、最適にリソースを配分するか?
次にデータを受け取る担当者が、一切迷わず、最高のパフォーマンスで作業を開始できる環境を整える。そのための緻密なフロー設計と進捗管理こそ、クリエイティブの質と速度を両立させるための要です。
スケジュールの安定を、制作進行だけに任せるのではなく、個々人が次工程の担当者にパスするにあたって、コミュニケーションの取り方や、業務領域の細かい分担調整の改善をすることで、より効率的な制作ができるはずです。
進化3:「職人」を「チーム」へ。ナレッジを掛け算にする越境の文化
クリエイティブには、デッサン、着彩、エフェクトなど、各分野のスペシャリストが在籍しています。当然、彼らの専門性は非常に高いのですが、その知見が個人の「タコツボ」に留まっていては、組織としての力は最大化されません。
「男性向け作品で使用した"雨の表現"のテクニック、女性向け作品でも応用できるのでは?」 「第1スタジオで取り入れた制作ルール、第3スタジオでのあの作業も効率化できるかもしれない」
こうした「ナレッジの横展開」を、偶発的なものから意図的な仕組みへと昇華させることが急務です。
部署横断の勉強会、ツール活用法の共有会、成功事例の共有フォーマット作成など、私たちは組織の壁を壊し、知見を掛け合わせるための文化づくりに本気で取り組んでいきたいと考えています。
「最強のプロダクションチームをマネジメントする」という挑戦
ここまでで、3つの進化を紹介させていただきました。クリエイティブ部ではもちろん、自らのスキルで、作品のクオリティをアップさせていただけるプロフェッショナルなクリエイターの方を常に求めています。
一方で、クリエイターたちが持つ才能を最大限に、かつ安定的に引き出し続けるための「事業基盤」と「仕組み」を構築できるマネジメント力を持った方にもジョインいただきたいと考えています!
- プロセスを分析し、ボトルネックを解消することに喜びを感じる。
- 個人の感覚やスキルを、「再現可能な仕組み」に落とし込むことが得意だ。
- 高品質な作品を、安定的に、数多く世に送り出すための「最強の制作ライン」を、自分の手で構築してみたい。
もしあなたが、そうした想いを持つ方であれば、これほどエキサイティングな挑戦の場はないと断言できます。
クリエイティブ業界に経験がない方でも、自らクリエイティブについて学ぶ姿勢を持って改善ができる方、メーカーの生産管理、IT企業の業務改善、コンサルティングファームなどで「再現可能な仕組み」を構築してきたような方々にもご活躍いただける環境だと思います。
私自身も、新卒の時に叶えられなかった「漫画の編集者になる!」という夢を、業界未経験ながら、違った形で叶えられる環境にワクワクしています。これまで培ってきたビジネススキルを、漫画に関わる環境で発揮してみたい!とお考えの方、漫画で待ち遠しい未来を共に創っていく覚悟のある方からのご連絡を、心からお待ちしています。
是非一度、気軽にお話ししましょう!
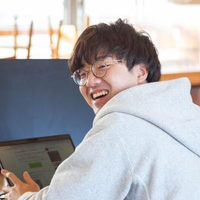

/assets/images/13374899/original/1e06fd85-0e16-41e8-a204-ef593374cc59?1684923565)


/assets/images/13374899/original/1e06fd85-0e16-41e8-a204-ef593374cc59?1684923565)

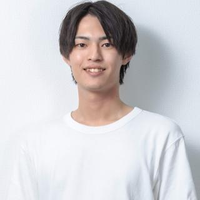
/assets/images/13374899/original/1e06fd85-0e16-41e8-a204-ef593374cc59?1684923565)

