ストーリーでは、現在neoAIで活躍するメンバーを紹介しています!
今回ご紹介するのは、LLMを用いた実プロダクト開発の中心で活躍する春日愛実(かすが まなみ)さんです。
2024年8月にneoAIへ参画。東京大学システム創成学科Cコース4年として学業と両立しながら、1年で最前線で価値を生むエンジニアへと成長を遂げています。コードを書くことにとどまらず、クライアントミーティングでの要件擦り合わせや説明も担い、技術とビジネスの両輪で成果を出しているのが春日さんの持ち味です。
本稿では、春日さんのneoAIでの働き方や、プロジェクトの面白さ・学びについて聞いていきます。
目次
――自己紹介をお願いします。
――neoAIに入社するまでの経緯を教えてください。
――入社前のイメージと実際に働いてみてのギャップはありましたか?
――現在はどんなプロジェクトを担当されているんですか?
――クライアントミーティングでの経験について詳しく教えてください。
――この1年間で一番成長したと感じる部分は?
――そういった成長を支える仕組みはどんなものがありますか?
――neoAIの雰囲気やカルチャーについて教えてください。
――今後の目標を教えてください。
――最後に、読者に向けて一言お願いします。
――自己紹介をお願いします。
こんにちは!東京大学システム創成学科Cコース4年の春日愛実です。2024年8月にneoAIにジョインして、約1年間AIエンジニアとして働いています。

――neoAIに入社するまでの経緯を教えてください。
大学に入ってからAIに興味はありましたが、専門的な知識はありませんでした。そこでAIトレンドも踏まえ、人工知能をメインで学べるシステム創成学科を選びました。学科に入ってから、授業でデータ分析を行ったり周囲がインターンを始めている姿を見て、AIの実務スキルを身につけたいと強く感じていました。
そんな矢先に、学科の先輩であるひろとさん(現neoAI Enterprise部長)に声をかけてもらいました!正直、最初は「自分にできるかな?」という不安もありました。ですが、実際の活動の様子や活躍している同年代の学生の話を聞いているうちに、「ここでなら成長できそう」という直感があって。
特に印象的だったのは、エンジニアといってもコードを書くだけではなく、クライアントとのミーティングに出るなど、ビジネススキルも身につけられるという話でした。「技術もビジネスも両方学べる環境」というのが、非常に魅力的に感じました。
――入社前のイメージと実際に働いてみてのギャップはありましたか?
正直、エンジニアってずっとコードを書いているイメージが強かったです。机に向かって黙々とパソコンで作業する感じかなって。
でも実際に入ってみると、いい意味で自分が想像していたエンジニア像とは異なりました!実際に自分で手を動かしてAIを実装していくのはもちろん、クライアントとのミーティングに参加したり、ビジネススキルも身につけられる環境だったんです。技術的なスキルだけではなく、コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力も同時に磨けるのは、想像以上でした。
それに、先輩や同期がとても優しく、個性的なメンバーが多いのも印象的でした。エンジニアというと寡黙なイメージがあったんですが、みんなユーモアがあって面白い人ばかりです!責任感が強くて、常に「どうしたら成長できるか」を考えている人たちに囲まれているのは、本当に刺激的です。

――現在はどんなプロジェクトを担当されているんですか?
入社してから最初は、教育企業向けに、LLMで業務効率化を図るプロジェクトで活動していました。クライアントと生成内容について擦り合わせをして精度向上を図ったり、実際にシステムに実装したりする中で、自分の作ったAIが学生の学習を支援していることに社会的な意義を感じています。これはneoAIの行動指針(※1)にある「家族・友人に誇れる仕事をする」にも通じており、世の中を良くする仕事をしているという意識を持って働けています。
最近は、チャットボットのAI回答サービスの開発に携わっていて、特にその回答の精度評価を自動で行うAIの開発を担当しています。評価方法自体が決まっていない状態から、「どうやったら正しく評価できるか」を考えながら進めています。LLMのファインチューニングを行ったり、論文で発表されたスコアの高いプロンプトエンジニアリングを試したり、まさに最先端の技術を実際のプロジェクトに扱うことができています。
また、両方のプロジェクトを通じて実感しているのは、一つひとつの仕事が持つ影響力の大きさです。クライアントが日本を代表するようなエンタープライズ企業だからこそ、手掛ける仕事のインパクトも非常に大きいんです。これほど社会に大きなインパクトを与えるプロジェクトに、学生という立場でありながら裁量を持って価値創出に貢献できるのは、neoAIだからこそ得られる貴重な経験だと感じています。

――クライアントミーティングでの経験について詳しく教えてください。
最初は本当に大変でした(笑)。先方のミーティングで自分の担当分を話すこともあるのですが、クライアントは必ずしも技術に詳しいわけではないので、技術的な内容をどうわかりやすく、しかも簡潔に伝えるか本当に悩みました。
ミーティング後にはマネージャーから、「間の取り方を意識すると相手が理解しやすくなるよ」であったり、「技術を知らない人に説明するときは、相手が理解できているか確認しながら進めるといいよ」といったアドバイスをもらいました。そうした具体的なフィードバックを受けて次に活かす、というサイクルを続けるうちに、次第にうまく伝えられるようになりました。何度もmtgに出てフィードバックをもらい、ブラッシュアップを重ねる中で、実践的なスキルが身についたと思います。
一番嬉しかったのは、精度向上の成果をクライアントに認めてもらえた時ですね。「実際の業務でそのまま使用できるレベルになった」とクライアントに褒められた時は、本当に達成感がありました。自分が作ったものが実際に世の中で使われて、誰かの役に立っているんだなって実感できる瞬間です。
――この1年間で一番成長したと感じる部分は?
技術面では、Pythonを授業でやった程度だったのが、今では実際にプロダクトを動かせるレベルまで成長しました。Azure等のクラウドサービスも触れるようになったし、LLMの活用から実装まで一通りできるようになりました。
でも、一番成長したのは「抽象的な大きなタスクを自分で分解して期限内に終わらせる力」だと思います。最初は抽象的な大きなタスクを任されても、何から手をつけていいか分からなかったのですが、今では自分でタスクを構造化して、優先順位をつけて進められるようになりました。
この成長には、「全員がPM」という行動指針が背景にあると思います。それぞれが自分の仕事に対して責任感を持って、オーナーシップを発揮することが求められる環境だからこそ、こういう力が身についたんだと思います。
そして、この1年間の成長を先日「JobGrade(※2)が1から1+に上がる」という形で評価していただけたのは、自分のアウトプットを認めてもらえた気がして、すごく嬉しかったです。 1と1+の違いは、簡単に言うと「自分のタスクを遂行できる」から「他のメンバーのリードもできる」へのステップアップですね。1の段階では、必要な場合は周りのサポートを受けつつ、基本的に自分のタスクをやり切る力が求められます。1+になると、自分のことをやりつつ、周りのメンバーをリードする力が必要になってきます。 次のステップに向けては、もっと視野を広げて、プロジェクト全体を見渡しながら動けるようになりたいです。
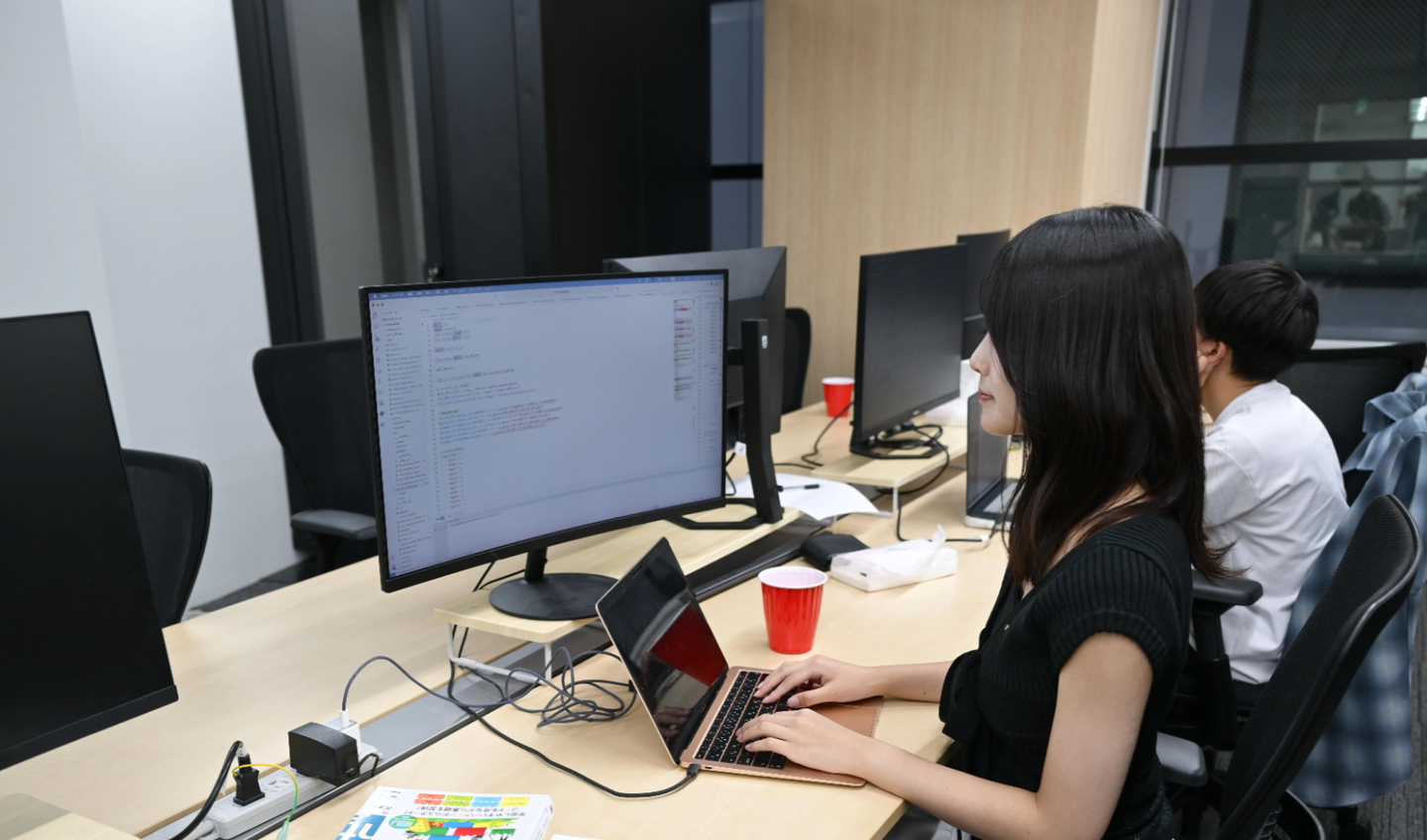
――そういった成長を支える仕組みはどんなものがありますか?
まず、入社後1ヶ月間の研修期間がすごく充実していました!コンテンツが日々アップデートされていて、深層学習の基礎から最新の画像生成モデルの理論まで体系的に学べます。また、LLMを使用した簡単なアプリケーションの開発も行なったりします!実際のプロジェクトで使う技術を体系的に学べる環境が整っていて、過去のプロジェクトのTipsがまとまった「AIナレッジ」というものもあり、困った時はそれを参考にできる環境が整っています。
そして何より大きいのが1on1制度ですね。neoAIには、直属の上長や部長と1on1をする機会があります。普段の業務でのGood/Moreを振り返る機会になっていて、これが成長に不可欠だと感じています。 印象に残っているフィードバックは、業務の進め方についてです。「決まったことをやり切ることはできているけど、それだけではなく課題解決の考察を次のアクションまで繋げられるともっと良くなる」と言われました。ただタスクをこなすだけじゃなく、なぜその課題が起きたのか、次はどう改善できるかまで考える視点を持てるようになりました。 上長が本当に親身になって相談に乗ってくれるので、安心して挑戦できる環境があります。失敗を恐れずにチャレンジできるのは、こういったサポート体制があるからだと思います。

――neoAIの雰囲気やカルチャーについて教えてください。
エンジニア集団というと堅いイメージがあるかもしれませんが、みんな優しくて面白い人が多いんです!責任感が強くて、「どうしたら成長できるか」を常に考えている人たちが集まっています。
例えば、「改善点をこまめに見つけて、タスクをダラダラしない」とか「1on1をガチる」とか、みんなが基準値を高く持って働いていることが伝わってきます。でも堅苦しくなくて、楽しみながら成長できる雰囲気があります。
特に好きなのが週一回のあした会議(※3)です。プロジェクト報告や学び発表(※4)があるんですが、ただ真面目に語るだけじゃなくて、それぞれの発表にユーモアがあるんですよ。ベストプレゼンテーター賞とかもあって、楽しみながら学べる場になっています。
年に一回のワーケーションも最高でした!普段の業務で関わらない人とも交流を深められて、前回は「行動指針をアップデートしよう」というワークショップをやったり、自由時間には花火やBBQをしたり。仕事も遊びも全力で楽しむ文化があるのがneoAIの魅力だと思います。

――今後の目標を教えてください。
技術力、マネジメント力どちらも磨いて将来的にはマネージャーとしてPJを進められるようになりたいです!今までは自分の担当範囲をしっかりやることに集中していましたが、もっと視野を広げて、チーム全体の生産性を上げられるような動きができるようになりたいですね。 例えば進んでいないタスクのつつきのような、まだ手がつけられていない「落ちているボール」を積極的に拾いに行く姿勢も大切だと考えています。これは行動指針の一つでもあり、実際にそれを実践することで評価されるのは、とてもやりがいを感じます。
技術的にも、LLMの最新技術やRAG(Retrieval-Augmented Generation)などの実装にもっとチャレンジしていきたいです。neoAIには「時代の最先端であり続ける」という行動指針があるので、常に新しい技術にキャッチアップしながら、それを実際のプロダクトに落とし込んでいきたいです。
――最後に、読者に向けて一言お願いします。
Wantedlyを見て「レベルが高そう...」とハードルを感じる人もいるかもしれません。でも、スタート地点に関わらず誰もが成長できる環境が整っています!私も最初はPythonを授業でちょっとやった程度でしたが、1年間で本当に多くのことを学び、成長することができました。技術的なスキルだけじゃなく、ビジネススキルも身につけられる環境で、優秀で面白い仲間たちと一緒に働けるのは、本当に貴重な経験です。
何かに本気で打ち込みたいと考える学生にとって、ここは濃密な経験ができる最高の環境です。「どうせやるなら全力コミット」という行動指針の通り、本気で成長したい人にとっては最高の環境だと思います。
私たちと一緒に、最先端のAI技術で世の中を良くする仕事をしませんか?きっと、想像以上の成長と充実感が待っています!
※1. 行動指針:メンバーが大切にしている「行動する上でのOS(=Operating System)」のこと。10個の項目からなる。

※2. JobGrade : 従業員が担当する仕事・職務・業務によって等級分けする制度のこと。
※3. あした会議:週一回行われる全社会議のこと。neoAIで一番熱い場所にするというミッションのもと、プロジェクトの進捗共有などの情報共有をはじめとした、さまざまな取り組みを行なっている。
※4. プロジェクト報告・学び発表:前者は、各プロジェクトの進捗共有や、終了報告など。後者は、メンバーが業務で得た成長と学びを発表する場のこと。







