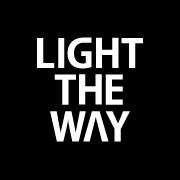はじめまして。2025年4月に新卒で入社しました、藤井玖光(ふじい くみ)です。
出身は兵庫県神戸市。そんな私が関西から東京に出てきて、映像の仕事を選んだ理由をお話ししたいと思います。
その原点には、かつての自分が抱えていた「言いたいことがあるのに、うまく伝えられない」という感覚がありました。たとえば、友達と話しているときに、なんとなく会話が噛み合わなかったり、自分なりに大切に思っていることを言葉にしても、うまく届いていない気がしたり。真剣に話しているつもりなのに反応が薄かったり、話題をすぐ変えられてしまったり。そんな経験を何度か重ねるうちに、いつの間にか「伝えること」に慎重になっていた気がします。
時間をかけて話せば、きっと気持ちは届く。わかり合える。そう思っていても、その一歩手前で気持ちがすり抜けてしまうような感覚がありました。もっとスムーズに、自然に、思いを伝えられたら。そんなもどかしさが、ずっと心の奥にあったんだと思います。
人前で話すのが極端に苦手なわけではありません。ただ、自分の考えや気持ちを言葉にするのが難しくて。話しているうちに何を伝えたかったのか分からなくなったり、相手の反応が気になって途中で言葉を飲み込んでしまうことも、少なくありませんでした。でも、それは「伝えたいことがない」わけじゃない。どうすれば、自分の思いをちゃんと伝えられるのか。その答えを、ずっと探し続けてきたように思います。
今回は、そんな私が「映像で伝える」という手段に出会い、この仕事を選ぶまでの過程を振り返ってみたいと思います。
思考することからはじまる、私のものづくり
私にとって中学校は、初めて「自分の外側に広がる世界」を意識しはじめた場所でした。
小学生の頃までは、似たような感覚や価値観を持つ友人たちとだけ過ごす、穏やかで心地よい日々が続いていました。自分の考えがそのまま「世界の当たり前」として通用する、ある意味で守られた空間の中にいたのだと思います。
けれど中学に進学すると、少しずつ目に入ってくる世界が変わり始めました。自分とは異なる価値観や考え方、ふだんのふるまいや発言から見える「他者のふつう」に直面するなかで、私の中に漠然とした違和感が生まれました。以前は、自分が良いと思うものは誰かと共有できるのがあたりまえだと思っていたのに、あまり興味を持ってもらえなかったり、「へぇ〜」で終わってしまったり。そんな「共感されない」という感覚だけが残ってしまう。
今思えば、思春期の真っただ中で「他者と自分の違い」に敏感になっていったのだと思います。けれど当時の私は、その違和感の正体がわからず、「違う考えを持つことは、きっと間違っているのではないか」と、心のどこかで思い込んでいたように思います。その思い込みは、やがて自分の考えや気持ちを外に出すことへの苦手意識やコンプレックスにつながり、「表現すること」の見えないハードルになっていました。
その一方で、自分の考えや感じたことを、誰かに知ってほしいという気持ちも心の中にはあり、そのふたつの思いのあいだで、私は揺れていました。

そんな矛盾を抱えていた私に小さな変化をもたらしてくれたのが、所属していた放送部で取り組んだ中学卒業記念の映像制作でした。
同級生や先生へのインタビューを通して思い出をまとめるという内容で、企画から撮影、編集まで、すべてが初めての体験でした。SDカードからデータを取り込む方法すら分からず、「MP4ってなに?」という状態からのスタート。映像編集ソフトや機材の使い方も何もかも手探りの中で完成した映像。それを見た友人が「よかったよ」と声をかけてくれた瞬間、それまでうまく言葉にできなかった気持ちが、映像を通せば届けられることに気づきました。
言葉だけでは伝えきれなかった内面を思考を重ねて構成し、映像として外に出す。私を表現することへの手ごたえを感じることができた出来事でした。この経験をきっかけに、私にとって「映像」は単なる技術や表現手段ではなく、思考を通じて他者とつながるための、自分にとって自然で信頼できる「ことば」になっていったように思います。
映像制作から見えた、枠を飛び越えた先の世界
その後、映像制作を始めた私は、高校生のときに、あるIT教育のイベントに参加しました。それは、大学生のメンターたちが中高生にITスキルを教えてくれるというイベント…
記事の続きはこちら↓
https://light-the-way.jp/column/all/6343