- ディレクター
- CS(公共・医療領域)
- フロントエンドエンジニア
- Other occupations (37)
- Development
-
Business
- ディレクター
- PMM
- プロダクトマネージャー/PdM
- 法務(LegalOps)
- 経営企画・FP&A・PMI推進
- 経営企画・FP&A
- 法務担当
- 27卒ビジネス職
- FSMGR(ヨジツティクス)
- IS(ヨジツティクス)
- パートナーアライアンス/シニア
- IS(マネージャー候補)
- プリセールス
- アライアンス責任者候補
- オープン(コンサル経験者歓迎)
- 【27~29卒】長期インターン
- エンタープライズセールス
- ソリューションセールス
- セールス(ヨジツティクス)
- インサイドセールス
- パートナーアライアンス
- エンプラセールス(公共・医療)
- フィールドセールス
- エンプラセールス(シニア)
- マスマーケティング
- マーケティング・プランナー
- Other
Contents
・PHPエンジニアが次のステップを目指せるように。書籍に込めた思い
・日頃の発信活動がきっかけとなり、チームで挑んだ書籍執筆
・任せ合いと助け合い、エンジニア組織の文化が活きた執筆工程
・仲間と共に学び、挑戦できる環境がカオナビのエンジニア組織にはある
カオナビのエンジニアメンバー8名が共同執筆した技術書『TECHNICAL MASTER はじめてのPHP エンジニア入門編』が、2024年12月に発売されました。
本書は、PHPの基本知識を学んだエンジニアが、中級者へステップアップするために必要な知識をまとめています。
今回は、執筆メンバー8名のうち4名に、出版に至った経緯や完成までの道のりについて話を聞きました。インタビューを通して見えてきたのは、インプットとアウトプットを大切にするエンジニア組織の文化と、互いに学び合い、新たな挑戦を後押しするカオナビならではの環境でした。
Interviewee
プロダクトデベロップメント本部 サービスデザイン部 Strategy1グループ /TL
佐野 元気
大学卒業後、2017年に不動産会社向けのクラウドシステムを提供する会社でソフトウェアエンジニアとしてキャリアをスタート。バックエンドからフロントエンドまで担当し、売買仲介会社向け顧客管理機能を開発。2020年1月に株式会社カオナビへ入社し、バックエンドエンジニアとして履歴機能開発やパフォーマンス改善を行うだけでなく、エンジニアリングマネージャーとして横串の組織改善業務に従事。現在は開発チームのテックリードとして、分析関連の機能を担当する。
プロダクトデベロップメント本部 研究開発部部長
藤田 泰生
SIerとして10年ほど働いたのち、ゲーム系のベンチャー企業でエンジニア兼プロダクトオーナーを経験。2021年6月に株式会社カオナビに入社。カオナビでは、プロダクトロードマップの作成や新規事業の企画/開発を行いつつ、EMとして組織横断的な活動をしている。
CTO室/エキスパート
富所 亮
SIerでの受託開発を経験後、口コミ系の自社サービス会社でマネジメントに従事。さらにベンチャー企業などを経て、2020年11月にカオナビに入社。入社の決め手は、フルリモートでの働き方で可能で、かつエンジニアメンバーにゆとりが感じられたこと。
プロダクトデベロップメント本部 技術基盤部 アーキテクトグループ/Development Contributor
矢田 直
ソースコードは書くより消すのが好きなバックエンドエンジニア。複数の企業でWebアプリケーションの開発、運用保守を経験。2019年4月に株式会社カオナビに入社し、ソースコードの整理整頓を日々取り組んでいる。
PHPエンジニアが次のステップを目指せるように。書籍に込めた思い
──まずは、皆さんの担当業務とカオナビに入社した経緯を教えてください。
佐野:
現在は、バックエンドエンジニアとして「カオナビ」の分析機能の開発をメインに担当しています。前職ではサーバーサイドからフロントエンド、プロダクトマネジメントや顧客対応まで幅広い領域に携わっていたのですが、もう少しエンジニアリングの専門性を突き詰めたいと考え、2020年にカオナビへの転職を決めました。以降、さまざまなプロジェクトを経験してきましたが、入社から5年が経とうとしている今では、改めてエンジニア組織全体を見渡す視点から、部署横断の組織改善などに貢献していきたいと考えているところです。
藤田:
私は研究開発部の部長として、「カオナビ」へのAI導入や新規事業の立ち上げなどを担当しています。現・CTOの松下と前職で同僚だったことがきっかけで、2021年6月にカオナビへ入社しました。前職のゲーム開発・運営を行うベンチャー企業に所属していた頃は、ヒット作が生まれるまでプロダクトのリリースを重ねる日々を送っていました。カオナビの話を聞き、既存のサービスをより良くしていくミッションに興味を持ったことが、入社の決め手でしたね。
富所:
入社以来、プロダクトの技術負債解消に取り組んできました。複雑化したシステムの構造を整理し、開発スピードや生産性の向上を目指しています。前職では受託開発を行っていたのですが「次は自社サービスで長期的にアプリケーションを改善していく仕事がしたい」と考え、現在に至ります。面接の際に、CTOをはじめ社員の方々が楽しそうに仕事をされている様子が印象的で、良い環境だと感じられたことがカオナビを選んだ決め手でした。
矢田:
現在は、社内のエンジニアに対してPHPのコーディング規約の整備や静的解析ツールの導入などの技術的な支援を行いつつ、「カオナビ」で利用している開発言語のPHPやフレームワークのバージョンアップを進めています。前職はSES企業に勤めており、次は自社サービスを開発・提供する会社にチャレンジしたいと考える中でカオナビと出会い、面談、面接を通して面白そうだなと思って入社を決めました。
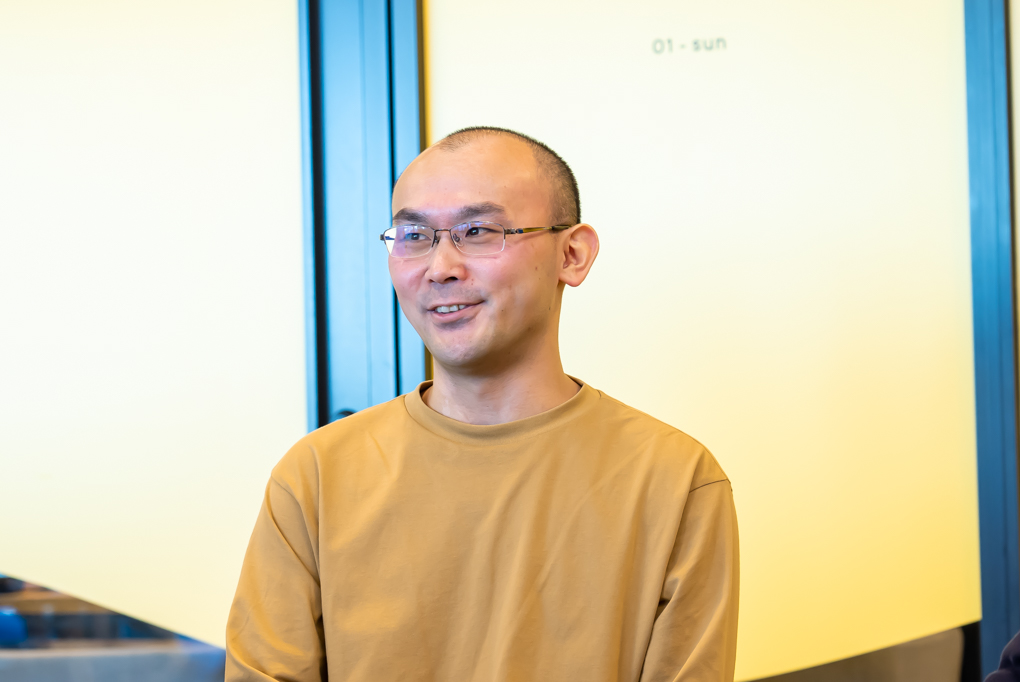
──今回出版された『TECHNICAL MASTER はじめてのPHP エンジニア入門編』は、どのような書籍なのでしょうか。
藤田:
本書は初心者の方向けというよりも、すでに2~3年ほどPHPに触れている、基本的な知識や実践経験を持つエンジニアを対象としています。実務に役立つ知識について解説し、読者の方が次のステップに進むために必要なことを1冊に詰め込みました。
矢田:
PHPの現状や最新動向についても詳しく紹介しているので、他言語での開発を経て、久しぶりにPHPに取り組む人の学び直しにもおすすめです。また、PHPについて知れるだけでなく、Web開発において必要な知識も得られる内容になっています。
富所:
現在、国内にあるPHP関連の技術書は、入門書か、ベテラン向けの難易度の高い解説書が多い印象です。一方で、その中間に位置するレベルの書籍がほとんど存在しないことに課題を感じていました。
エンジニアが現場に配属されると、その現場特有の手法を踏襲しながら業務を進めていくのが一般的です。しかし、こうした知識は特定の現場でしか通用せず、生きた知識にはなりにくい。そこで、本書ではPHPを用いてスムーズに開発するための体系的な知識について理解してもらうことを目指しました。
佐野:
普段の業務でも、新卒2~3年目の社内エンジニアメンバーに対してコードレビューを行うときに「もっとこうした知識が前提にあればスムーズに進められるのではないか」と感じる場面が多々ありました。そういったメンバーや、そのレビュアーの助けになればという思いも本書に込めました。
日頃の発信活動がきっかけとなり、チームで挑んだ書籍執筆
──本書の出版は、どのような経緯で決まったのでしょうか?
藤田:
最初のきっかけは、出版社の方から、PHPをテーマにした書籍の企画をカオナビに持ち込んでいただいたことでした。ここ数年、カオナビのエンジニアメンバーが外部カンファレンスでPHPをテーマにした登壇を重ねてきたことを評価していただいたようです。実際に、本書を執筆したメンバーの半数以上は継続的に登壇しており、こうした日頃の活動を通じて「カオナビのエンジニアはPHPに詳しい」という認知につながったのだと思います。
富所:
メンバーたちの発信によって、このように社外の方から注目いただけたことを非常に嬉しく思っています。

──今回、本書を執筆したのは総勢8名のメンバーだと聞いています。皆さんは、どのような思いから執筆に参加しましたか?
佐野:
社内で書籍執筆メンバーの募集告知が出た後、立候補制で執筆メンバーが集まりました。私自身は執筆未経験でしたが、「本を作る」という0から1を生み出すような経験をしてみたいと、好奇心から手を挙げました。
矢田:
私も執筆の経験がなかったので不安でしたが、こういった機会には今後いつ巡り合えるかわかりません。「だったら、今チャレンジしてみないと」と決心して参加しました。執筆経験のあるメンバーも立候補していたので、その点も心強かったですね。
藤田:
佐野さんや矢田さんのように、執筆が初めてのメンバーも多かったですよね。私は以前に2冊ほど、PHPとは異なる分野での共著の経験がありました。その経験を通じて執筆の大変さは理解していましたが、自分の名前が残る仕事ができたことがとても印象深かったんです。日頃から一緒に仕事をしているメンバーが集まっていたので「絶対に良い本ができるだろう」という安心感もあり、参加を決めました。
富所:
私は、以前から新しいチャレンジの機会には積極的に参加するタイプで、今回も迷わず立候補しました。8人という大人数での共著は珍しいですが、意欲的なメンバーが多く集まってくれたことで頼もしく感じましたね。これまでの雑誌や技術書の執筆経験を活かして、メンバーのサポートができればとも考えていました。
任せ合いと助け合い、エンジニア組織の文化が活きた執筆工程
──執筆はどのように進められたのでしょうか?
藤田:
まずは、5月の連休明けに各自が考えてきた目次案を持ち寄って、書籍の全体的な構成や章立てを決めるところからスタートしました。執筆範囲の分担と各章のアウトライン作成を経て、初稿の執筆に取りかかったのが7月から9月にかけてです。初稿作成後はレビューと校正の期間に入り、1冊の書籍として形が見えてきたのが11月でした。こうして振り返ると、発売日の12月まで本当にあっという間の執筆期間でしたね。

──日常業務と並行しつつ、集中して書き進めていったんですね。執筆を進める中で、工夫されたことはありますか?
佐野:
執筆期間中は「ひとまず全部書き切ること」を強く意識していました。最初からうまく書こうと自分の中でハードルを上げてしまうと、前に進めなくなると思ったからです。そこで、まずは担当箇所をざっくりと書いてみて、読み返しながら修正していくようにしました。
こうした進め方は、普段の開発スタイルと通じる部分があります。システム開発においても、慎重に作り込むのではなく、まずは動くものを短期間で作り、そこから改善を重ねていくケースが多いんです。そのマインドを持って取り組んだことで、初めてのチャレンジでもなんとかやり切れたと思います。
富所:
私は執筆経験者として、比較的大きなテーマを扱う章を率先して担当するようにしました。難しい内容だった分、プレッシャーを感じながらも粛々とテーマに向き合う日々でしたね。執筆ではAIも活用しながら、わかりやすい解説を心がけました。
藤田:
業務が多忙な時期は執筆を進めるのが大変でしたが、チームとして取り組めている感覚を持てて非常に心強かったですね。Slack上で執筆に取り掛かる際に宣言し合うチャンネルを設けたり、執筆物を共有するGitHubリポジトリを用意したりと、全体の進捗状況が見える仕組みを整備したことも大きかったです。今回の座談会メンバーでいうと、とくに矢田さんは先陣を切って執筆作業を進めてくれており「みんなが頑張っているから自分もやらねば」と、励まされる場面が多くありました。
矢田:
Slack上で「今から書き始めます」と宣言して、通常業務とのメリハリをつけて時間を確保したのがよかったのかもしれません。少しでも余裕を持てるように、とにかく「一行でもいいから毎日書く」を心がけていました。
──チームで1冊の書籍を書き上げて感じた手ごたえや、率直な思いについて聞かせてください。
佐野 :
普段のソフトウェア開発とはまた異なり、手に取れる形で自分の成果が残る体験が新鮮で、大きな達成感を得られました。
また、発売後には書籍を読んだ方から感想を直接いただけたことも嬉しかったですね。その方は数年ほどPHPに触れていなかったそうですが「すでに知っている内容が多い入門書と違い、新たな気づきも多く、学び直しにぴったりだった」との声をいただきました。「中級者へのステップアップを支援する」というコンセプト通りの1冊になったのではないかと思います。

藤田:
お互いに声を掛け合いながら、文字通り「全員で」ゴールに到達できたのが何よりも良かったですね。実は、目次案を決めたミーティング以降、執筆メンバー全員で話す機会はほとんどなかったんです。みんなが自律的に執筆を進めながら、この書籍が完成しました。お互いに信頼して任せながら、誰かがヘルプを出したときには助け合える。そんなチームプレーの形がカオナビらしいなと感じました。
仲間と共に学び、挑戦できる環境がカオナビのエンジニア組織にはある
──カオナビのエンジニア組織には、アウトプットや学び合いに意欲的な文化が根付いていると感じます。どのように形成されてきたのでしょうか。
富所:
私が入社した当初、カンファレンスで登壇するメンバーは限られていました。私を含め数名で登壇しながら、周りへアウトプットを働きかけてきた結果、だんだんとチャレンジする若手メンバーが増えていったんです。今では、どのカンファレンスでも、社内の誰かが必ずと言っていいほど登壇しています。
藤田:
もちろん、アウトプットの機会はカンファレンスへの登壇だけではありません。現在、富所さんが運営に携わっている「社内ISUCON※」をはじめ、社内ではさまざまな勉強会も活発に行われています。
※ISUCON:LINEヤフー株式会社が運営窓口となって開催している、ウェブアプリケーションの性能改善を競う日本発のコンテスト。カオナビではエンジニア育成を目的に2024年7月より社内でほぼ毎月開催中。

佐野:
現在、カオナビでは毎年12月の有志メンバーによるアドベントカレンダーや、カンファレンス参加者によるイベントレポートなど、ブログを書く文化も定着しています。決して強制ではありませんし、今後も強制するつもりはありませんが、何かしらアウトプットしようという意識を持っている人が社内には多いですね。
富所:
今回集まった書籍の執筆メンバーは、とくに普段から外部発信やカンファレンス登壇に積極的な人たちばかりです。
書籍の出版を通じて、エンジニアとして実績を積んだ先に「本を出す」というキャリアの選択肢もあるんだと、社内のメンバーに示せたことも良かったと感じています。出版はハードルが高いと感じるかもしれませんが、エンジニアとしての成長の延長線上にあると捉えてもらえたら嬉しいですね。
──組織の文化が、一人ひとりのエンジニアの可能性を広げることにもつながっているのですね。
藤田:
そうですね。インプットやアウトプットは、目の前の仕事のためだけに行うものではありません。自分のキャリアを考え、目指す姿を実現していくためのものだと思います。だからこそ、私たちは業務外での成長機会も大切にしています。今回集まった執筆メンバーも、同じ思いでさまざまな活動を行っているのではないでしょうか。
書籍の執筆は、あくまでアウトプットの一つの形です。他にもやりたいことがあれば、何でもチャレンジしてみればいい。そう背中を押してくれる環境が、カオナビにはあります。カオナビに来ていただければ、自分の可能性をきっと広げられるはずです。
佐野:
また、一緒に学びを深めたり、新しい形のアウトプットに挑戦したりする仲間を増やしたい、と考える方にも、カオナビの環境はぴったりだと思います。「カオナビなら、必ず仲間が見つかるよ」と伝えたいですね。
▼その他インタビューをご覧になりたい方はこちら
kaonavi vivivi(カオナビの「人」と「組織」が見えるメディア)





