jicTech FM「インシュアテックにおけるAIー開発と顧客体験、両輪での価値創造ー」
「ゆるめ社内ラジオ」として社内配信するjicTech FM。その内容を一部ご紹介しています!今回のテーマは「インシュアテックにおけるAI 開発と顧客体験-両輪での価値創造」。ゲストとパーソナリティはこちらのメンバー。
ー ゲスト:Engineer 中澤綾さん
SIerでフロントエンドエンジニアとして4年間経験した後、2022年3月に当社に入社。社内のフロントエンド関連プロダクト全般の開発を担当しつつ、AI導入の推進にも携わる。
ー ゲスト:Engineer 宮田木織さん
Web広告企業にて広告配信管理画面開発を3年間経験した後、2021年11月に当社に入社。保険SaaS基盤システム「joinsure」のバックエンド開発に従事。趣味ではスター1.2K超えリポジトリのメンテナーを務める。
ー メイン パーソナリティ:Engineer 高橋周平さん
通信・金融システムにて設計開発を約6年経験。2025年6月より当社に入社。共通基盤グループとして、保険SaaS基盤システム「joinsure」の横断的な開発に携わる。
ー アシスタント パーソナリティ:Public Relations 浮ヶ谷
大学卒業後、国内生保会社にて法人営業を担当。その後、保険業界紙の記者として13年間にわたり保険業界各所を取材した経験を持つ。2024年4月より当社にて広報を務める。
自己紹介
浮ヶ谷:皆さん、こんにちは。JICT FMアシスタントパーソナリティの浮ヶ谷です。今回は「インシュアテックにおけるAIー開発と顧客体験、両輪での価値創造ー」をテーマにお送りしてまいります。本日のゲストは中澤さんと宮田さんです。よろしくお願いいたします。また、今回は進行役を高橋さんにお願いしております。高橋さん、よろしくお願いいたします。
高橋(周):はい、よろしくお願いします。共通基盤グループに所属しているエンジニアの高橋です。今年6月に入社しまして、保険システムのjoinsure(ジョインシュア)のプロジェクトを横断的に見ています。本日はAIについて皆さんといろいろと語り合いたいと思っております。よろしくお願いします。ではまずゲストのお2人から、簡単に自己紹介をいただきたいと思います。初めに中澤さんからよろしくお願いいたします。
中澤:はい、開発グループに所属している中澤です。普段はフロントエンドの実装を担当しています。最近は社内の業務改善を目指して、代表の畑さんと協力しながらAIのトライアルをしたりしています。今日はよろしくお願いします。
高橋(周):よろしくお願いいたします。では続きまして、宮田さんよろしくお願いいたします。
宮田:はい、社内では普段、Kotlin x SpringBootでバックエンド開発を担当しています。趣味の方では、jackson-module-kotlinというOSSのメンテナーを務めております。
高橋(周):今日はよろしくお願いいたします。
AIの活用状況について
高橋(周):はい、ありがとうございます。それでは、早速質問に移りたいと思います。今回は、インシュアテックとAIがテーマとなっていますが、まずお2人は現在、AIをどのように活用されているのかというところからお話を伺っていきたいと思います。では宮田さん、よろしくお願いします。
宮田:業務におけるAIの活用としては、コード生成、特にテスト生成で活用しています。その他、自分の理解の浅い事柄をパッと検索したい時に、ChatGPTに質問を投げたりもしています。趣味のOSS活動でもテスト生成はやっていますし、あと、翻訳ですね。自分は英語が全然ダメなんですけど、AIの翻訳があるおかげで、世界中の開発者と繋がってOSS活動ができているなと思っています。ごく一部ですがコードレビューを依頼することもあったりします。
高橋(周):ありがとうございます。世間ではAIに乗り遅れているエンジニアがいるっていう話も聞いたりするんですけども、宮田さんは結構早くからキャッチアップして色々活用されているなっていう印象を受けました。続きまして中澤さんはいかがでしょうか?
中澤:はい、私は自己紹介のところでもお話ししたように、畑さんと協力しながら今AIをトライアルしている状況です。AIを使ってこんなことはできないか、あんなことはできないか、といった感じで、できる限り幅を広げながら探検しているような状況なので、業務の中でもかなりいろんなところをAIで賄っています。通常の実装の流れであれば、チケットに実装内容の説明が書いてあって、それを人間が読んでコードを書いて、プルリクエストを出して、みたいな流れがあると思うんですけども、チケットを読むところからコードの実装、プルリクエストを出すところまで全部AIに任せられるようなフローも試せるような状況になってきています。
高橋(周):AIの導入について、社内で率先して進めてくださっているのが中澤さんだと思っていて、そうした取り組みをされていることに私自身入社してすごく驚きましたし、そういう挑戦を後押しする文化のある会社なのだという印象を受けました。中澤さんご自身はAIの導入に関する社内の雰囲気や動きをどう見ていらっしゃるんでしょうか?
中澤:そうですね。私の場合、畑さんが社内のチャットツール上で「誰かChatGPT Proのトライアルしてみませんか?」って声をかけていたところで手を挙げたことからAI導入に取り組むようになりました。トップダウンで始まったこともあり、その後も色々なAIを試すことができている状況なので、その波に乗れたっていう意味ではラッキーだと思いますし、今はかなり裁量を持っていろんなことに挑戦させてもらっています。
高橋(周):ありがとうございます。やっぱり新しい取り組みをどんどん任せてもらえるっていうのはエンジニアにとっても嬉しいことですよね。中澤さんはAI活用に関する社内勉強会も実施されていましたが、勉強会はどういう経緯でやることになったのでしょうか?
中澤:AIって、今の業務に絶対に必要かって言われるとそうではない部分もあると思うんですよ。事実、今までAI無しで業務を継続してきたわけですし。その結果、AIを日常的に触る人もいれば、全く触らない人もいて、そこでどうしても差が広がってしまうので、その差を埋めるためにも、AIを触っている人間がAIについて紹介する勉強会があるといいのかなと思って開催しました。
高橋(周):エンジニアが率先してそういった勉強会を開いてくれるっていうのは会社としても良いことだと思いますし、1エンジニアとしても、そういった取り組みをみんなで頑張っていこうっていう雰囲気があるのはすごく嬉しいことだなと感じました。
今のAIの限界
高橋(周):それでは次の質問に移りたいと思います。今度は宮田さんにお聞きしたいのですが、業務でもプライベートでもAIを活用されているというお話でしたが、一方で今のAIの限界も感じたりしているのではないかと思います。その点についてのお考えを聞かせていただけますか?
宮田:そうですね。まず既存の業務に対してAIを取り入れようとする場合って、0→1、つまり全く知らないものについてなんとなく知ろうとするケースと、10→100、基盤が整っているものをスケーリングさせるみたいな場面に適用するっていうのが強いと思うんですけど、1→10のような、基盤を整えて拡大の基礎を作るみたいなところにはAIは適用しにくいなと感じています。なぜかというと、自分が携わってきたプロジェクトを考えてみても、設計方針にどうしても各所でブレが生じてしまっている状態なので、それを1からAIに触らせてうまいこと生成してもらって期待通りの成果を得るというのは難しいというのが実情です。実際に全部をAIにやらせようとしたら、かえって能率が落ちてしまったみたいなこともよく聞きますし、使えるシーンが限定されてしまうっていうところは1つ限界としてあるのかなと思っております。
もう一つ、間違ったものが出てきてしまった時にどうするかっていう問題は常に付きまといます。先ほど翻訳でAIを活用しているとお話ししましたけど、決して褒められた英語は書けていないだろうなっていうのが実感としてはあり、でも自分はそれを校正しきれないからそのまま使っているみたいなこともあったりします。これって業務であれば許されない態度ですよね。なので、自分が責任を持てるところに適用するっていう使い方がどうしても求められると感じています。
高橋(周):ありがとうございます。宮田さんのお話を聞いていて、いろいろな使い方や情報があったとしても、最終的な取捨選択に関しては人間側に求められるので、何でもかんでもAIを使えばいいっていうわけではないなっていうのはすごく感じました。今お話いただいたように、適材適所でAIを使っていくっていうことがエンジニアとしても求められる段階であり、AIに仕事を奪われるみたいな話を聞くこともありますが、まだまだエンジニアが主導してAIを使っていくことが重要なのではないかと思いました。
インシュアテックにおけるAIの可能性
高橋(周):ここまでAI活用にフォーカスしてお話を伺ってきましたが、当社はインシュアテック企業ということで、インシュアテック企業でのAI活用という観点からお話を深めていきたいと思います。
金融や保険領域のシステム開発で有名なのがウォーターフォール開発と呼ばれる開発手法になりますが、この分野でのAI活用の価値や可能性はどういったところにあると思いますか?ちょっと難しい質問だと思うんですけども、肌感覚で結構ですので、中澤さんお願いできますか。
中澤:ウォーターフォール開発っていうと、大きな設計がドンとあって、それを全て実装してくっていう感じだと思うんですけど、AIに関しては「コンテキスト ウィンドウ」っていう用語があるんですけど、AIが取り込める情報の総量っていうのはどのAIも今制限されている状態なんですね。だから大きなものを詰め込みまくるっていうのはどうしてもできないので、AIがそれをこなせるだけの量まで小さく小さく分解した上で、AIがこなせるような指令を出すといった形であれば生かせる場面はあるかなとは思います。
高橋(周):ありがとうございます。宮田さんはいかがでしょうか?
宮田:中澤さんのおっしゃっていることが「まさに」だと思っています。金融や保険のビジネスは多岐にわたる要素が複雑に絡み合っているため、そのシステムを少しでも変更しようとすると、他の多くの機能や関連するシステム、業務プロセスにまで予期せぬ影響が及ぶ可能性が非常に高く、その結果、開発が難しくなり、リスクも増大するという課題があります。ですから、これは人間にタスクを振るのと同じといえば同じなんですけど、ちゃんとタスクを区切って、消化できるように噛み砕いた上で、それを人間に対してよりももっとちゃんとやってあげなきゃいけないところは結構あるのかなと思います。
もう一つは、先ほどの、AIが間違った判断をした場合に責任を取らなきゃいけないのは人間だという話につながるんですけど、特に金融や保険領域って、ミスが許されない業界だと思うので、そのあたりの担保をすることが強く求められるっていう意味では、そもそも負えるリスクが小さいためにAIを活用する余地が他の業種に比べて少し小さくなるところはあるのかなと思っています。一方で品質の保証等はどんな開発でも絶対に求められることなので、良い感じに使ってちょっとずつ加速していけたらっていうふうには思っていたりします。
高橋(周):ありがとうございます。金融とか保険ってなると、数字がほんの少し違っただけでも大問題になってくるので、かなり難しい分野かなとは思います。ただ、この先お客様に納得していただけるものを作るという意味では、AIの活用というのはすごく大事かなっていう印象を受けました。
今後、挑戦したいこと
高橋(周):それでは、AI技術の進化を踏まえて、エンジニアとして、今後どのような挑戦をしていきたいか、という質問に移らせていただきます。いろいろなAIツールをうまく使って業務品質や効率を上げていきたいといった気持ちがあると思いますが、宮田さんはいかがでしょうか?
宮田:そうですね、業務に関して思っているのは、AIでもちゃんと開発できるようなレベルの開発基盤を整えることができたらいいなっていうことです。AIって情報のブレに弱いところがあったりとか、事前準備がちゃんとできていない状況だと、悪い言い方をすると、期待通りでないものが出てきてしまうんですよね。一方で、それって人間に対しても親切じゃない状況だと思うので、人間もAIも開発しやすいような基盤を作れたらなっていうことを考えています。
趣味の領域だと、自分はOSSのリポジトリのメンテナーとして、AIに学習させる情報を作っている立場みたいなところがあるので、新しい機能や、バグの修正、AIがちゃんと答えてくれないものがあったらそれに関するブログを書くとか、そういうことをやっていって、開発者がAIを使って幸せになれる未来に貢献していけたらと思っています。
高橋(周):確かに、人間もAIも、前提や方針といった情報をしっかり伝えないと、期待通りの結果が戻ってこないっていうところは共通しているのかなと思いました。社内でも今はそういったナレッジを整理していく段階かと思いますし、私自身も頑張っていきたいと思います。中澤さんはいかがでしょうか?
中澤:AIの進化が早すぎて、1年後どうなっているかも分からないような世界ではあるので、その時々に応じて適応していかないといけないな、っていうのが正直なところです。
私に限らず、AIについていけなくなったらどうしようみたいな焦りとかって誰しもあると思うんですよね。そういう意味では、エンジニアってキャッチアップが得意な職種だと思うので、その特性を生かして、エンジニア領域、例えばコード生成等にはもちろん生かしますが、エンジニア領域以外のところ、例えば社内の業務改善をAIを利用して加速するみたいなことも、色々とできる余地があると思うんですよ。そういうところにも取り組むことで、自分だけ、エンジニアだけじゃなく、社内全体の業務がもっとうまく回って、プロダクトをもっと早く世に出すことも可能だと思っているので、そういうところを今はやっていきたいなと思っています。
高橋(周):ありがとうございます。中澤さんはAIに関してかなりの速さでキャッチアップされていると思っているのですが、その中澤さんが焦るぐらい進化が速いっていうことなので、会社としても、皆でどんどんキャッチアップしていければいいなと思いました。お2人ともありがとうございました。
浮ヶ谷:当社では、エンジニアはもちろん、全メンバーにAI活用の基盤が提供されていますから、これからもますます知識を深め、活用していけるといいですね。
「こんな環境で働いてみたい」という方は、ぜひ当社の採用ページからお気軽にご応募ください!
jicTech FM、次回もお楽しみに!


/assets/images/19636006/original/e755afc6-ab61-4e4f-970d-7b313f2b6db8?1730888349)
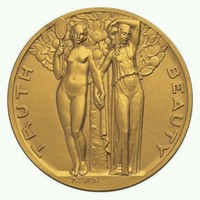



/assets/images/19636006/original/e755afc6-ab61-4e4f-970d-7b313f2b6db8?1730888349)

