目次
はじめに
ISTとの出会い
なぜISTへの入社を決めたのか
コンサル部設立の背景と意義
ISTにDXコンサルティング部ができたことによる変化
メッセージ
はじめに
今回は情報戦略テクノロジー(以下、IST)のDXコンサルティング部 部長であるM.Rさんにインタビューを行いました。なぜISTに入社したのか、そしてコンサル部が設立された背景について、率直にお話しいただきました。
ISTとの出会い
ーこの4月で入社から1年のM.Rさんですが、ISTに入るまでの経緯をお聞きしたいです
もともと前職ではスタートアップのCOOをやっていました。その会社の社長が僕の大学時代のゼミの友人だったんです。彼は大学の頃から、「いつか自分も起業する」と言っていて。彼が起業して4年ほど経ったタイミングで私が入社しました。
そんな彼は経営者界隈での繋がりが多く、ある日、「ISTの川原さん(IST執行役員)という人と食事に行くから一緒に行かないか」と誘われました。そこで我々と川原さんと他社の経営層の方の4人で食事をしたのが、ISTとの最初の出会いでした。
ーそれはいつ頃のことですか?
2023年の夏、7月か8月くらいですね。まだTシャツを着てテラス席でお酒を飲んでいたのを覚えています。その出会いから入社まで半年くらいでしたね。
ー展開が早いですね...!
(写真:M.R)
なぜISTへの入社を決めたのか
ーその後、どのような経緯で入社されたのでしょうか?
最初は営業同行を手伝わせていただいていて、ビジネスパートナーとして何社か一緒に回っていました。その頃、私は独立を考えていたので、自分が入れるプロジェクトを探していたんです。そのことを川原さんにお伝えしていました。
それからというもの、川原さんから月に1回くらい連絡が来て、「そろそろランチに行こう」と誘われるようになりました。そして恵比寿の中華料理店でフカヒレだったり美味しいランチをごちそうになるという...(笑)。「いつも美味しいご飯を食べさせてくれるお兄さん」という感じで川原さんを見ていました。
そういう食事を4、5回くらい重ねたんですが、実は入社の誘いは断り続けていたんです。
ー断っていたんですか?
はい。もともとコンサルをやる予定はなかったんです。コンサルよりも事業会社に入って、サービスやプロダクトを作ったり、組織マネジメントをしたりする方向にピボットしようと考えていました。
ー疑問なのですが、コンサルの方はゆくゆく自分で事業をやりたくなるものなのでしょうか。
そういう人は多いですね。辞める人は事業会社の企画部門に行ったり、小さなコンサルファームを作ったり、自分のプロダクトを作ったりする人が多いです。やはり「手触り感」が足りないんですよ。事業戦略や経営戦略を描いて終わりではなく、自分が主体となって意思決定して、「赤字だ、どうしよう」とか「これが売れない、どうしよう」といった体験をしてみたかったんです。
ーなるほど!では...最終的に入社を決めた理由をお願いいたします。
川原さんと飲みに出かけた際、その場に社長の高井さんも呼ばれていて。高井さんが焼酎をロックで飲みながら「よろしくな」と言って...そこで握手をした際に、「握手したということは入ることだからな」と言われて...気付いたら入社していました(笑)
ーえっ
もちろんそれだけではなく、縁を感じたんです。実は高井さんの前職は、私がいた会社の前身の会社で、瀧本さん、野沢さん(いずれも弊社役員)もそこにいらっしゃったんです。お互いに知っている人もいて、いろんな話で盛り上がり、そこに縁を感じました。
また、高井さんと川原さんのいる会社はいい意味で「やばそう」だなと思ったんです。すごくビジョナリーでやりたいことがあるけど、それを実際に絵にして実行できる人たちがいるのか、もしそれができているなら面白そうだなと。そして今後より一層成長していくのであれば、それを担っていくのはすごく面白そうだと思いました。
コンサル部設立の背景と意義
ー2024年8月に立ち上がったDXコンサルティング部ですが、なぜISTに必要だったのでしょうか?
真面目な話ですが、「0次DX」というテーマに沿って説明すると、システム開発のプロセスにおいては、要件定義やもっと前の「超上流」と呼ばれる部分、つまりどんなシステムが必要かというところから考える必要があります。
0次DXを実現するためには、そこから要件を詰めていったり、お客さんと整理していく必要があります。そういう観点で、SES形態ではなく上流のところからフォローできるコンサルタントの部署があった方が、ISTが掲げるミッションの達成に繋がるというのが、コンサルティング部署のミッションだと思っています。
また、ISTがIRで掲げているSPA(Speciality store retailer of Private label Apparel)という形で、自社で一気通貫でビジネスからITシステム開発まで、さらにその先の運用や人材育成、内製のフォローまでを自社で完結できるというのは、ビジネスモデルとして、また他社との競合優位性という観点でも必要だったと思います。
ISTにDXコンサルティング部ができたことによる変化
ー実際にDXコンサルティング部ができて、会社に変化を感じますか?
私が見ていて感じるのは、営業の質が上がったということです。出てくる案件の質もそうですし、フロントエンドとしてのコンサルがいることで、出てくる課題の粒度が2つくらい上がりました。以前はシステムを作るという話も一定数あったのですが、今はコンサル・企画など超上流から入る案件が増えた感じがします。
ーそれは大きな変化ですね。まさに求めている0次DXの姿に近くなったということなんですね。
そうですね。エンジニアからすると、今まで売っていたものはソリューション提案というよりは、パッケージレイヤーやツール寄りに近くて、「こういう課題を抱えているお客さんにはこういうものが売れる」というプロダクトアウト的な思考に、結果的になっていたこともある気がします。
しかし今は、「お客様が本当に止めているものは何なのか」というヒアリングの質であったり、ソリューション営業やコンサル営業と呼ばれる部分の質は高まったと思います。
コンサルは本質的には営業だと思っています。営業とは何かというと、クライアントやお客様が抱える課題やニーズは何なのかという、問題提起やニーズ定義から始まるものです。そこにクッションを一つ挟むだけで、お客様からの見られ方も提案の質も格段に上がります。
これはコンサルも営業も人事もエンジニアも同じだと思っています。私がよく言うのは、「コンサル」は枕詞だということ。すべての業務や業種に「コンサル型」や「コンサル的な」ものがつくだけで、動き方が変わっていくと思うんです。少しずつかもしれませんが、そういう変化が起きているように感じます。
メッセージ
ー最後に、一言お願いいたします!
続きは面接でお会いしましょう!
ー是非またインタビューのお時間いただければと思います(笑)
本日はありがとうございました!
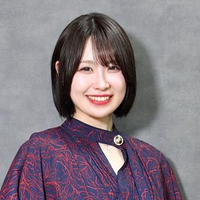






/assets/images/14287758/original/41aa6faf-6f8c-427c-9316-d03b39f542f1?1692955864)
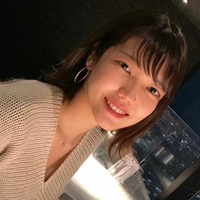

/assets/images/14287758/original/41aa6faf-6f8c-427c-9316-d03b39f542f1?1692955864)

