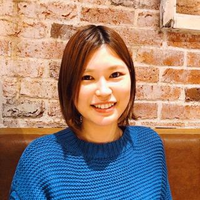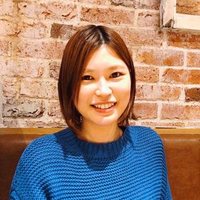こんにちは。株式会社ヒューマンテクノロジーズ 採用担当の源田です。
近年はコロナ禍をきっかけに、多くの企業でリモートワークが取り入れられるようになりました。
実は当社ではコロナ禍以前からリモートワークを取り入れており、リモートワークが始まったのは、10年以上前です。そしてコロナ禍が収束した現在もエンジニア組織はフルリモートで働いております。
今回は面接でも良くご質問いただく、エンジニア組織がフルリモート勤務になったきっかけや今後の方針などを、人事採用部門の責任者であり、かつて開発部門の責任者でもあった糸井にインタビューを行いました。
この記事では、
- エンジニア組織がリモートワークをはじめたきっかけ
- リモートワークでの文化づくり
- 今後のエンジニア組織における働き方
についてお話しして参りますので、「フルリモートでの働き方に興味のある方」や「当社のリモートワーク文化に興味をお持ちの方」はぜひ最後までご覧ください。
■エンジニア組織がリモートワークをはじめたきっかけ
ーまず、エンジニア組織のリモートワーク変遷を教えてください。
リモートワークが始まったのは2011年。きっかけは、東日本大震災でした。震災発生時の電車の運休や計画停電といった影響を受け、「どこにいても働ける環境を整える必要がある」と考えるようになったのが出発点です。
2011年〜2020年頃までは、週1回の在宅勤務を試験的に導入し、徐々に体制を整えていきました。そして、2020年の新型コロナウイルス感染拡大を機に、【フルリモート体制】へと移行しました。
当時は、一部のサポート職メンバーはオフィスで業務を行っていましたが、開発業務に関しては、すでに自宅でも対応できる体制が整っていたことが大きかったです。元々セキュリティの観点からVPNを導入していたため、それを活用して自宅から本社のデスクトップPCへリモート接続する形で業務が可能でした。
また、PCで電話の発着信ができるクラウド型ビジネスフォンを導入したり、サポート部門では遠隔地にあるコールセンターと契約を結んだりと、リモートワークが現実的な選択肢として社内に浸透し始めていました。
当時はまだ出社が主流ではありましたが、エンジニアに限らず、少しずつ全国各地へ分散していく動きが始まったのもこの頃です。
もちろん、ひとつの場所に集まって仕事をする方が効率的で、コミュニケーションコストも抑えられます。ただ、そうした集約型の働き方では、大災害が発生した際に継続的な事業運営が難しくなる恐れがあります。
「それではいけない」と、当時の社長が号令を出し、分散型でも機能する新たなコミュニケーションスタイルの構築を目指して、社内での“訓練”を始めたというのが、現在のリモート体制の原点になっています。
■リモートワーク試験運用時期の状況
ー当時、まだ世の中的にリモートワークが浸透していない時代だったと思いますが、導入にあたって不安はありませんでしたか?
もちろん、不安はありました。導入前からコミュニケーション自体は取れていましたが、実際にリモートを開始してみると、「仕事をやっているのかどうか」が見えにくくなる点は課題として感じていました。
ただ、リモートワークを導入した一番の目的は、「会社として、いざという時にも耐えられる組織になる」ことでした。その目的の重要性を考えると、一時的に成果が落ちることがあっても、それは想定内というか、必要なプロセスだと思っていました。
そういった背景もあって、当時のマネージャー陣に新しい働き方をどう受け入れてもらうか、というのは一つのハードルでした。
なかでも一番心配だったのは、生産性の低下です。たとえば、これまでスムーズに連携できていたサポートとのやりとりが、リモートによって崩れてしまうのではという懸念がありました。
ただ、当時から営業部門、サポート部門、エンジニア部門のマネージャー陣同士がそれぞれの部門間で日頃からしっかりとコミュニケーションが取れていたため、各部門で個別にフォローし合える体制がありました。もしこの土台がなかったら、うまくいかずに空中分解していたかもしれません。
また、開発者としては、リモートワークを導入したことで集中してコーディングに取り組める環境が整ったのは大きなメリットでした。
オフィス勤務時は、隣にいるからこそすぐに質問ができたり、クイックに対応できるという利点はありましたが、その反面「今は話しかけられたくない」というタイミングもあります。そういった場面では、リモートによって自分のペースで集中できるようになり、結果として生産性が上がるという声もありました。
■リモートワークでの文化づくり
ーリモートワークならではの文化はありますか?
そうですね、昔からコミュニケーションはとても大切にしていると思います。たとえば、チームによって毎日実施している「昼会」の時間はとても重視していて、時には1時間ほど話すこともあります。進捗や細かい相談ごとを共有しつつ、雑談を交えてその人のコンディションも確認できるような場にしています。……まあ、1時間はちょっと長いかもしれませんが(笑)。
また、試行錯誤を続けられる文化も根づいていますね。取り入れた仕組みがうまくいかなければすぐに改善を試みたり、別の新しいやり方にトライしたり。会社全体として従来のやり方に固執するのではなく、より良くしていくことに前向きだと感じます。
現在、人事採用チームでも取り入れている「チェックイントーク」も、エンジニア組織では以前から行っていました。もともとは、海外拠点立ち上げのためにシンガポールに滞在していたメンバーが、日本側にも共有してくれたのがきっかけです。
各メンバーがその日の状態や感情を共有し、それを見た同僚が「今日はちょっと調子が悪そうだから、配慮してあげよう」「今日は調子が良さそうだから、新しいタスクをお願いしてみよう」といったように、お互いのコンディションを自然に気遣いながら働くことができています。
また、リモートワーク環境でもコミュニケーションの機会が確保できるよう、年に2回、全社イベントとして「夏イベント」と「忘年会」をオンラインで開催しています。
さらに、当社では交流費補助制度があり、オンラインでのランチ会や飲み会、もちろんオフラインでの集まりにも一部補助が出る仕組みがあります。こうした機会を通じて、部署を超えたつながりや、より深いチームの結束も生まれています。
■今後のエンジニア組織における働き方
ーここまで、リモートワークをはじめたきっかけや、コミュニケーション文化など聞いていきましたが、今後もリモートワークは継続していく方針でしょうか?
はい、当社のエンジニア組織では今後も基本的にフルリモートの体制を継続していく方針です。現在のマネジメントラインにいるメンバーもリモートワークに慣れており、これまで大きな混乱もなく移行できた背景もあります。
また、私たちは「分散しても勝てる組織」を目指しています。もちろん、物理的に集まって働く方が効率的な面もあるのは事実です。ただ、どこにいても高い生産性を保てる仕組みやチームづくりを進めることが、今後の成長にとって重要だと考えています。
一方で、別部門では若手が多い組織もあり、そういった場合は対面でのコミュニケーションが必要になる場面もあるでしょう。ただ、エンジニア組織については比較的ベテランのメンバーも多く、かつ業務の特性上、在宅で完結できる仕事が多いこともあり、全国どこに住んでいても活躍していただける体制をとっています。「リモートにしない理由が今のところない」というのが正直なところですね。
もちろん、首都圏在住で「オフィスで働きたい」という方がいれば、出社も可能ですし、チームビルディングの一環として、年に数回ほど出社するような機会も設けているチームもあります。
■フルリモートの環境で求められる人材とは
ーリモートワークが続いていく中で、求められる人材はどんな人になりますか?
そうですね、積極的にアウトプットしてくれる人が向いていると思います。リモート環境ではどうしても物理的な距離がある分、発信しないと埋もれてしまうことがあるので、自分の考えや状況をきちんと伝えてくれることはとても大切ですね。
ただ、当社は発言に対して揚げ足を取ったり、否定したりするような文化はなく、心理的安全性が高い環境です。なので、安心して自分の意見を伝えてもらえると思いますし、「しっかり言いたいことを言える」というのは非常に重要だと感じています。
また、やはりリモートだからこそ、自己管理ができることも求められます。誰かが常に見ているわけではないからこそ、「自分で動かないと、自分に返ってくる」という感覚を持てるかどうか。
今ある良い文化を維持していくためにも、そしてより良くしていくためにも、自律的に動きながらチームや組織に貢献しようとする姿勢は必要だと考えています。
いかがでしたでしょうか?今回は、当社のエンジニア組織におけるリモートワーク導入の背景と、それに伴う日々のコミュニケーション文化についてご紹介しました。
当社では、リモートワークを早期に取り入れた経験があり、効率的な業務進行や円滑なコミュニケーションの方法を試行錯誤しながら築き上げてきました。その結果、現在ではリモート環境でも、チームワークの強化や生産性の向上が自然に実現できていると感じています。
リモートワークがもたらす柔軟な働き方に興味を持ち、当社の企業文化に共感していただける方にとって、きっと有意義な環境が整っていると思います。少しでも興味を持っていただけましたら嬉しく思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!