- PM・SE・事業開発
- サステナビリティコンサルタント
- バックエンドエンジニア
- Other occupations (20)
- Development
- Business
- Other
ゴーレムは、建設という「社会を支え続けてきた巨大産業」にテクノロジーの力で挑み、産業変革にチャレンジするスタートアップです。
その挑戦の背景には、日本の製造業の進化と停滞を間近で見てきた代表 野村の強い危機感と、建設だからこその希望がありました。
今回は、代表 野村に、建設に挑む理由、起業までの背景、そしてこれからの展望についてインタビューをしました。
目次
「変っていない産業」だからこそ、希望がある
各領域の専門家の暗黙知が支える産業
設計の「背景情報」までデータにする
難しいからこそ、誰も手をつけてこなかった
経営判断までの距離の長さに違和感があった
コンサルを経て「自分でやる側に行くしかない」
経験がなくても施工管理できる未来をつくる
「変っていない産業」だからこそ、希望がある
――ゴーレムは建設の領域をターゲットにして事業に取り組んでいますが、、なぜこの産業を選ばれたのでしょうか?

野村:
大きく2つ理由があります。1つ目は、純粋に「希望がある産業」だからです。僕は現在39歳で、ちょうど生まれた頃がバブル経済のピーク。その後は「失われた30年」と言われる時代をずっと生きてきました。
大学時代にヨーロッパに行ったとき、日本の電機製品が全く存在感を持っていなかったことに驚いたんです。当時はサムスンが全盛で、「日本から来た」と言うと「サムスンの会社?」と聞かれるような感じで。今だと当たり前ですが、当時国内ではまだまだ「日本のエレクトロニクスは世界一」というような空気だったので、とても驚きました。
そういう現実を見てきて、「じゃあ今、日本が世界と戦える分野ってなんだろう?」と考えるようになりました。
各領域の専門家の暗黙知が支える産業
――建設のどんな構造に、特に課題を感じたのでしょうか?
野村:
建設って、一見すると設計があって、発注があって、工事があって…というふうに順序立って進んでいきます。
実際に工事が始まるまでは、「壁を作る」というような、目に見える進捗ではなく、「仕様を決める」というような情報を作る工程なんですよね。
その進捗の成果として、設計書だったり見積書だったりがあるわけなんですが、前の情報から後の情報、具体的には「設計書」から「見積書」を作るロジックが人の頭の中にしかないんです。
だから専門家同士が毎回話し合う必要がありますし、時間もかかる。そのため簡単には仕事を理解するためには長い経験が必要で新人教育が難しいし、属人化も進んでしまうという課題があります。。
高度成長時代は成り立っていたけれど、今の社会情勢で、この課題が顕在化していて、もう仕組み自体を根本から変えないと、このままでは業界が成り立たなくなると感じています。
設計の「背景情報」までデータにする
――課題を解決するために、どのようなアプローチを取っているのですか?

野村:
情報を作る工程では、完成された情報しか残らないんですよ。でも本当は「なぜこう設計したのか」「なぜこの順番にしたのか」という“背景の意図”が非常に重要で、それが標準化や自動化の最大の障害になっているんです。
そこで、各工程の情報を標準化(データ化)し、情報間の背景情報を共通ロジックとして、整理していく。これができれば、誰でも同じ仕事ができますし、新人も早く戦力化される。さらに言えば、AIや工場生産などの自動化にもつながっていく。
工程の情報(データ)が、一気通貫でつながれば、建設のやり方を大きく変えられると思っています。
難しいからこそ、誰も手をつけてこなかった
――ここまで難易度の高い産業に、あえて挑もうと思った理由は?
野村:
建設は昔から「自動化が難しい産業」だと言われてきました。現場ごとに条件が違うし、標準化しづらい。だからこそ長年放置されてきた部分でもあります。
でも逆に言えば、今まで誰も本気で手をつけられなかったということでもある。もし簡単だったら、とっくに誰かがやっているはず。グどの国をみても、建設業の労働生産性ってずっと横ばいなんです。これはマイナスではなく、まだ日本が世界をリードできるチャンスがある領域だと捉いえています。
経営判断までの距離の長さに違和感があった
――野村さんご自身の原体験についても教えてください。
野村:
もともとはガラス工場で生産技術をやっていました。古い方式の技術を改良して性能向上させる仕事でした。
ただ担当者としては、「新方式のほうが優れている」「早く切り替えたほうが長期的にメリットがある」と感じていました自分が努力して技術開発するほど、「旧方式でも良い」という経営判断がされるという点に、違和感を感じていました。
自分自身が、その判断をできる立場になるには、何十年も経験を積まないといけない。50歳くらいまで、もやもやを続けるのは嫌だなって、転職を決めました。
コンサルを経て「自分でやる側に行くしかない」
――そこから起業にたどり着くまでの経緯は?
野村:
技術戦略コンサルに転職して、経営判断の支援をする側に回りました。でもいざやってみると、方向性を示しても、あくまで提案するだけで、当たり前ですが自分で決めるわけではない。。
だったら、自分で意思決定できる立場に行くしかない。自然と起業という選択になりました。
経験がなくても施工管理できる未来をつくる
――最後に、ゴーレムとして目指している未来を教えてください。
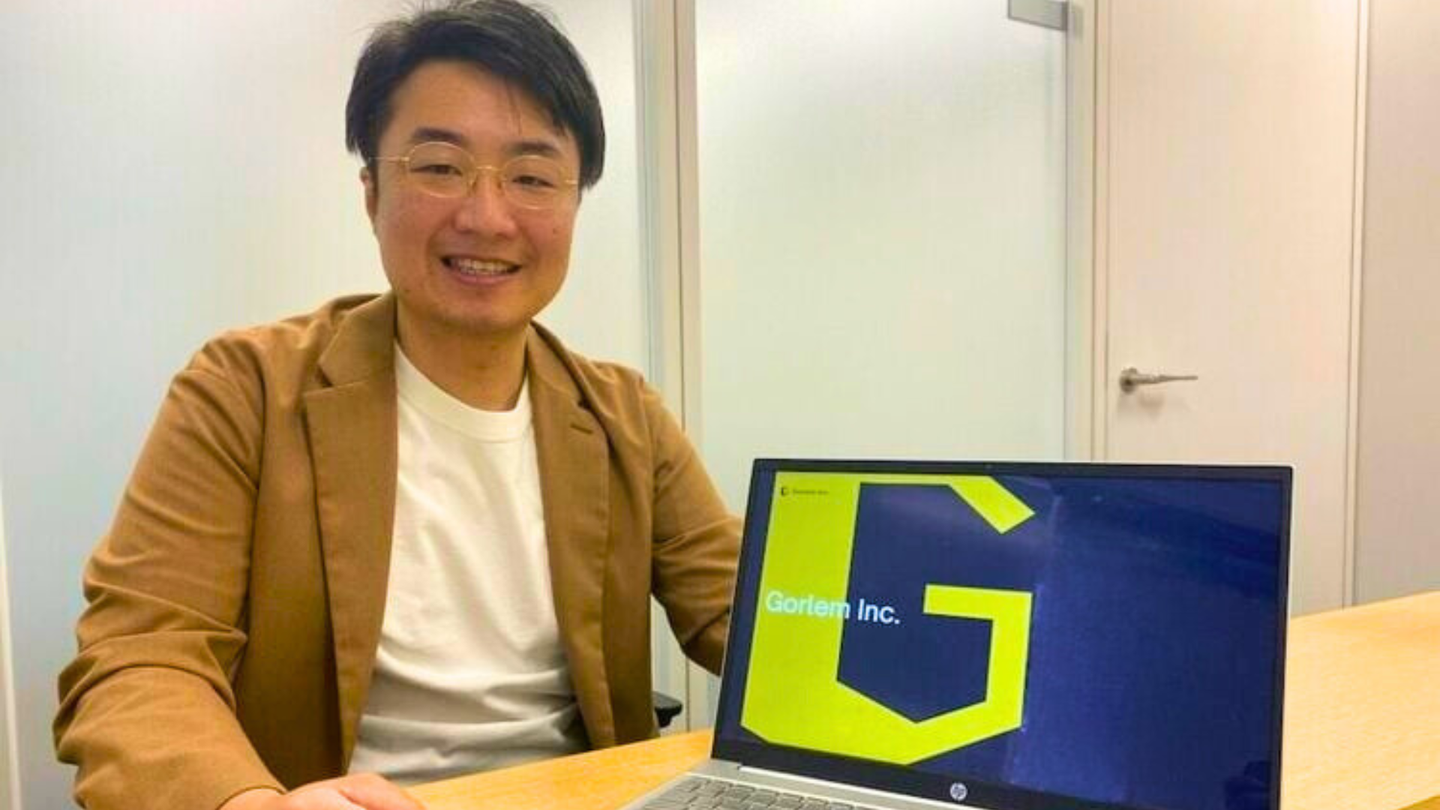
野村:
これまでの建設は、経験がある人にしかできない仕事だった。でも知識をデータに整理すれば、若手でも地方でも海外でも設計施工管理ができるようになる。
人口が減っても成立する仕組み。暗黙知に頼らず、仕組みで回る産業構造にしたい。
ゴーレムは、そうした新しい当たり前を作っていこうとしています。
「変わらない産業」にこそ、まだ大きな変革の余地がある──。 ゴーレムは、建設業界という巨大な産業構造の整理に挑戦しはじめています。
今後も、なぜこの産業に挑むのか、どんなチームで取り組んでいるのか、その裏側を様々な角度から発信していきます。ぜひ続くストーリーにもご注目ください!

/assets/images/9768410/original/3c08ea5d-14a1-40f2-bac9-1b7e9f0fe450?1703716670)


/assets/images/9768410/original/3c08ea5d-14a1-40f2-bac9-1b7e9f0fe450?1703716670)

/assets/images/9768410/original/3c08ea5d-14a1-40f2-bac9-1b7e9f0fe450?1703716670)

