繁忙期でございます。
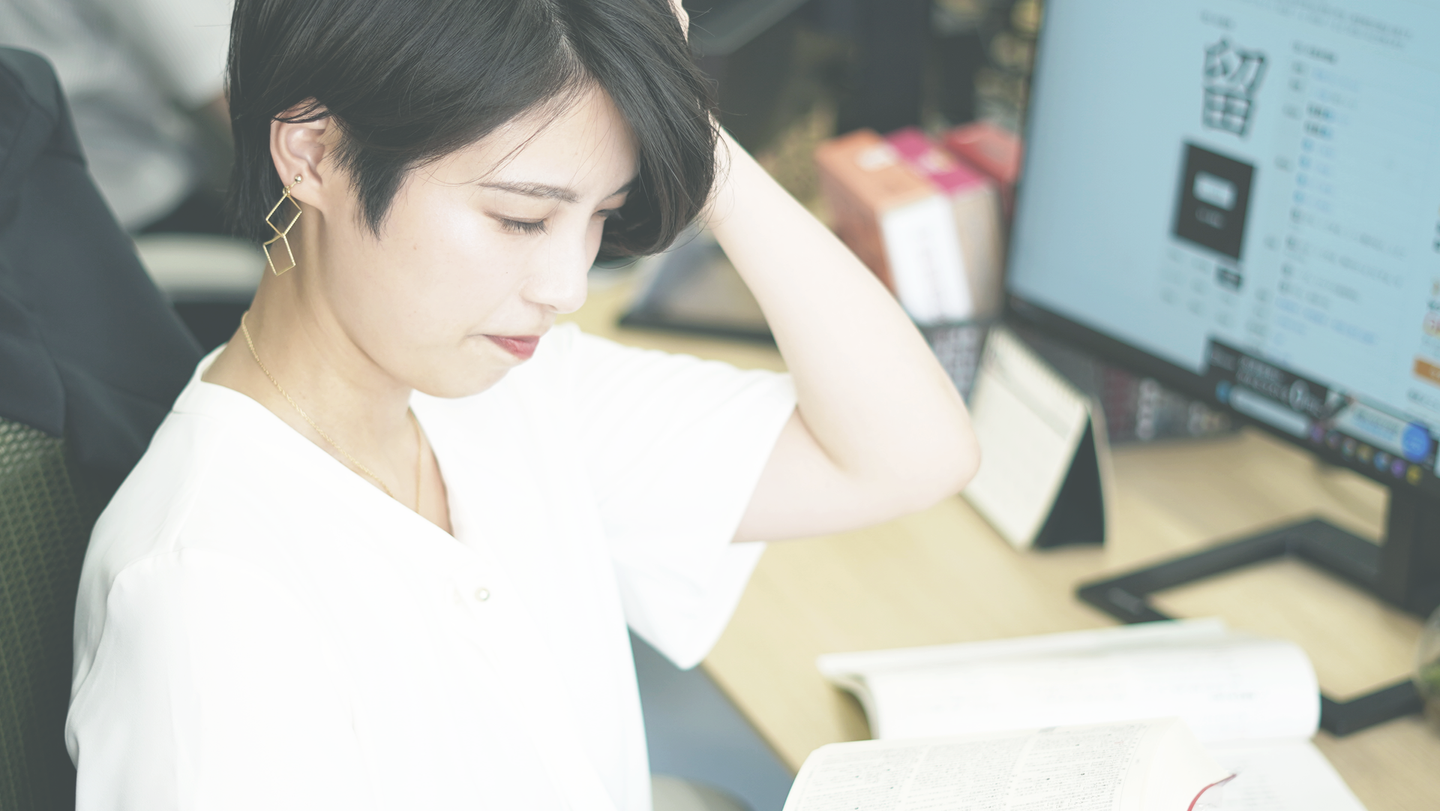
図:編集作業に追われる様子
今年のお盆休みは9連休でした。
休み明け、低速運転して仕事のリハビリをしたいところですが
編集部はまるで定期考査前の高校の図書室のように
いい感じの緊張感と静けさ(と逼迫感)でバリバリ仕事しています。
静けさ と書きましたが、校正作業は集中力が大事です。
そのため、ふつうは繁忙期というと てんやわんや!鳴り響く電話に追われる!のイメージですが
編集部はみんなの忙しさに比例して静かになっていきます。
校正作業を紙で行い、編集作業をwordで行い、調べ作業は本とネットで行うので、机上は賑やかです!
さて本題です。
佑人社の編集部に向いている人はどんな人か。
・一人で集中する作業が苦にならない人
・相手の気持ちや状況を推し量ってコミュニケーションを取れる人(社内外問わず)
・調べものや勉強が好きな人
この辺りが思い浮かびますが、今日は三つ目について。
調べものが好きな人って、学び続けられる人だよな~ と思います。
そういう向上心のある人、知的好奇心の強い人は向いてます。
最近の糸長の調べもの例。
古文に出てきた「具足」、中学生には分かんないだろうから注釈付けたいな~
「具足」っていうと、色んな荷物もった足軽とか武将が視覚的なイメージとして思い浮かぶけれど
安直に「鎧のこと。」って注釈つけてよいものかな~
鎧以外の装備一式も含む気がするんだよな~ 狭義には鎧?
よし辞書引くか!
~コトバンクで検索~
世界大百科事典
軍陣などに際しての用具を総括して,物の具,装束,調度などの名目と同様に広く用いられる。
具足は,武家の全盛期に至って,物の具の呼称と同様に鎧をさすことが多くなり,
ハイハイやはりそうなのね。日本国語大辞典様も見よう。
日本国語大辞典様
①物事が十分に備わっていること。揃い整っていること。
~中略~
⑨武具。甲冑。
よしよし問題なし。てか初出が続日本紀(722)なのか~意外と古いんだな
と、こんな感じでした。複数の辞書を引くと理解が深まるし、トリビアが増えて楽しいですね!
辞書以外を使った調べものだと次のような例も。
「鳥の目魚の目虫の目」という表現はどのぐらい人口に膾炙しているのか?
→よし、コーパスだ!少納言少納言!
漢文の「以為らく(おもへらく)」は、引用の「と」を伴わない場合があるのか?
→よし、文法書だ!新明説漢文!
もちろん、調べても正解がないものもあります。
「三宝の海に廻向して」 …これどう注釈つける?
三宝は仏・法・僧。廻向は供養を指す言葉です。
これをそのまま直訳すると 仏法僧の海(!?)を供養して(!?) となってしまいます。
ちなみに引用元の書籍では、ここの現代語訳は華麗にスルーされていました。
しかし、子どもの受けるテストに出てくる以上、編集者としては華麗にスルーはできないのです…
まあ仏教説話で出てくる一節なので、要するにここはレトリック的な表現で
仏の導きサイコー!的なことが言いたいわけですね。 ということで、少々アクロバティックな注釈ですが
三宝の海に廻向して(=海のように広大でありがたい仏と僧と仏法にお祈りして)
としておきました。こういうのは編集者のセンス(キラッ☆)です。
このように、調べものをしても正解が見つからない場合は、テストの教材としての性格を重視し、受験生に資するように編集方針を決めていきます。教材としてこの文章をどう読ませたいか ということですね。
また、たとえ正解が見つからなくても、調べ物の道すがらでは知識の収穫が多々あります。
こういう作業の楽しめる、知的好奇心のある人は、佑人社の編集者に向いてます!
自分は当てはまるかも、と思ったら応募ボタンをクリックしてくださいね。

/assets/images/19445053/original/e47185f0-785e-4ae3-ad9f-8e731054ab13?1729073171)


/assets/images/19445053/original/e47185f0-785e-4ae3-ad9f-8e731054ab13?1729073171)



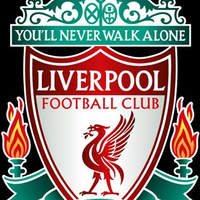
/assets/images/19445053/original/e47185f0-785e-4ae3-ad9f-8e731054ab13?1729073171)

