【部署紹介ーその2ー】現状の社会福祉を仕組みから変えていく!困難を抱える人々が自立して輝ける社会へ(公益事業部)
日本財団という名前は聞いたことがなくとも、「このマークがついた車を見たことある!」という人は多いのではないでしょうか。
これは、日本財団が全国の社会福祉法人などの団体へ送迎車両として助成したものです。
日本財団 公益事業部は福祉車両の配備を始め、ヤングケアラーや子ども第三の居場所、文化・芸術の振興など日本国内の福祉、その他の公益増進に資する幅広い業務を扱っている部署です。それでは、公益事業部が取り組んでいる事業を見ていきましょう👏
🧒子ども第三の居場所🧒
3人に1人が何らかの困難に直面していると言われる日本社会。親が共働きだったり、家庭や学校以外に自分の居場所がないと感じている子どもは多くいます。全ての子どもたちが、自分にとって安心できて、ワクワクできるような体験を送れるための拠点づくりを全国に拡げています。
🏗みらいの福祉施設建設プロジェクト🏗
どことなく暗く、閉鎖的なイメージがある福祉施設。そこをもっと開放的な場所にすれば、地域コミュニティも活性化し施設利用者と地域の人々の交流が増えるのではないか。そんな担当者の気づきから生まれた事業です。建築デザインを地域づくりの重要な要素として捉え、福祉事業者と建築家・設計者が協働して「みらいの福祉」について考える仕組みづくりを日本財団はサポートしています。
👪ヤングケアラーと家族を支えるプログラム👪
本来、大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもは「ヤングケアラー」と呼ばれています。普通に学校に通っていても、家に帰ると親の介護などで自分の時間が全く持てない、そんな見えづらい困難を抱えています。日本財団はヤングケアラーが子どもらしい時間を過ごし、その家族も安心して過ごせるよう官民連携でモデル事業や普及啓発活動を行っております。自治体と連携して子どもの居場所や相談窓口を設置し、ヤングケアラーとその家族両方が安心して生活できる環境を目指して取り組みを進めています!
🌈夢の奨学金プロジェクト🌈
現在、4万人もの子どもたちが社会的養護の下、生活をしています。子どもたちは原則として18歳を迎えると、経済的にも精神的にも自立することが求めら、毎年2,000人の子どもたちが社会に旅立ちます。その多くが生活費を捻出するため就労を余儀なくされていて、進学率も低いというのが現状です。「夢の奨学金」では、返済不要の学費全額や生活費の給付に加え、ソーシャルワーカーによる伴走などのサポートを手厚く提供しています!
🏞難病の子どもと家族を支えるプロジェクト🏞
医療の進歩により救える命が増えると同時に、医療的ケアを日常的に必要とし、病気と向き合いながら生きている子どももたくさんいます。現在、日本では自宅で医療的ケアを受けながら生活している子どもが全国で約2万、きょうだい児や家族を含めると25万人いるといわれています。このプロジェクトでは、難病と向き合う子どもと家族を対象としたイベントの実施や、拠点づくりを支援しています!
☕はたらく障害者サポートプロジェクト☕
福祉施設で働く障害者が得る月額工賃は全国平均2万円弱程度。この工賃のみで自立した生活を営むことは容易ではありません。障害者が「当たり前に地域で働く」そんな社会を実現させるため、このプロジェクトは始まりました。2015年から全国各地で約30の工賃向上モデル事業を実施し、脱福祉型のビジネスモデルを確立し障害者が自立して生活を組み立てていけるよう活動しています。
詳細はこちら!
🌳職親プロジェクト🌳
日本での刑法犯の検挙数は2004年から一貫して減少していますが、再犯者率は1997年から上昇しており、2000年では49.1%に上昇しております。犯罪は許される事ではありませんが、再犯を防がない限り犯罪被害で悲しむ方はなくなりません。そして、一度犯罪者というレッテルを張られた受刑者は更生しようと思っても社会に居場所がなく、自分が生きていく術が分からずに再び法を犯してしまうという現実があります。そのような人々がしっかりと己の罪と向き合い、そのうえで再び社会の一員として人の役に立つ。そんな社会を目指すため、このプロジェクトは生まれました。
~対症療法ではなく、根本からの解決を~
社会課題、特に福祉の分野では問題は無数にあり、ある人にとっては何でもないことが立場を変えると非常に大きな問題にもなりえます。
日本財団では
①社会で問題となっている課題を発見
②小規模でモデル事業を構築・実施
③効果検証したモデルを全国に波及させる
このようなステップを踏みながら、社会課題へアプローチしていきます。
民間団体だからこそ取れるユニークな手法で展開されるプロジェクトを、これからも是非ご注目下さい!

/assets/images/21065633/original/bbd6ddc2-437c-4000-a992-f60b39a7101c?1746689120)

/assets/images/18487803/original/26bc311c-b7c3-4ed7-a786-d20692f36e4b?1720299995)
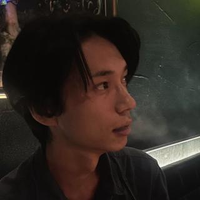

/assets/images/18487803/original/26bc311c-b7c3-4ed7-a786-d20692f36e4b?1720299995)

