- Project Manager
- 開発、PM両方をお任せします
- カスタマーサクセス
- Other occupations (15)
- Development
- Business
- Other
急成長中の注目スタートアップ、ランディットでは、現在組織拡大中につき、一緒に働く仲間を募集中です。
ランディットのビジネスについてもっと知りたい!
入社したらどんなメンバーと一緒に働けるの?
そんなご要望や疑問にお応えすべく、ランディットの事業開発本部とAIMO事業本部から、4名のメンバーが対談。COOの岡崎をファシリテーターに迎え、ランディットの開発チームの裏話から、AIMO事業本部の未来までを語ります。
自己紹介
岡崎:
今日は、ランディットのサービス開発を担う事業開発本部と、AIカメラを活用した駐車場管理システムを手掛けるAIMO事業本部の4名に話を聞いていきたいと思います。まずはそれぞれの役割について教えてください。
菊池:
私は、事業開発本部長として、メンバーが働きやすい環境作りや採用を担当しています。
櫻井:
すべてのプロダクトを見つつ、主にSYNC PORTとAIMOの技術面を詰めたり、他のプロダクトのサポートに入ったりしています。あとは、菊池のサポートとして一緒に組織作りや採用にも関わっています。
姜:
AIMOの事業本部長として、開発とビジネスの両方を見ています。開発面ではプロジェクトマネジメントや新規の試みも担当しています。
有山:
UIと会社のあらゆる販促物のデザインを担当しています。AIMOに関しては、姜のサポート役として、駐車場構築のための工事など、開発に必要な業務を担当することもあるので、社内では、現場仕事も手がけるという意味で、「フィールドデザイナー」「工事部長」って呼ばれています(笑)。
ビジネス部門との“近さ”が強みのチーム
岡崎:
早速ですが、この事業開発本部・AIMO事業本部ならではの魅力はどこにあると思いますか?
菊池:
ランディットって、ビジネス側と開発側がすごく近いんです。自分もいろんなスタートアップを経験しましたが、それこそが開発者としてワクワクしながらやれる環境だと思います。言われたことをやるのではなく、自分でがんがん作っていける人にとってはすごくいい環境だと思います。特に櫻井さんには、そこが生きてると思います。
櫻井:
どうしてこのような環境になっているのかというと、開発しながらビジネスにつなげていっているからだと思います。最初にランディングページを作って、提案しつつさらに開発していく。開発が作ったものをどうビジネスとして展開していくか、事業本部長たちと密にコミュニケーションをとって進めています。
岡崎:
まさに、ランディットが大事にしている「マーケットイン(Market in)」の考え方を実現させたもの作りですね。
菊池:
と同時に、ランディットの世界観にも合わせにいっています。その両軸ができているからうまく回っていると考えています。
岡崎:
有山さんは代表と同級生なんですよね。
有山:
中学から一緒ですが、社員になった時点で、“同級生”ではなく“社長”として見てます。
岡崎:
大成功してるバンドのメンバーって割と幼なじみだったりする。なので、有山さんのような人が会社にいることが、目に見えない大きな何かをもたらしている気がしますね。
有山:
開発チームの中でも私の役割は特殊で、「工事部長」って呼ばれるくらい、入社以来いろんなことをやってます。なので、自分の可能性を広げたり、いろんなところにやりがいを見いだせたりするというメリットがあります。自分次第で何でもできる、そんな組織になっているのはすごいと思います。
岡崎:
入社当初からそういう感じだったんですか?
有山:
最初からですね。私はデザイナーとして入社しましたが、PIT PORT(予約式駐車場運営サービス)のプロジェクトマネージャー的役割からスタートして、並行してデザインをはじめとするさまざまなことを経験し、今はAIMOのプロジェクトマネジメントも担当しています。エンジニアの上流工程に深く関われたのは自分自身にとっても重要な経験でした。
菊池:
私も入社以来、今までにない経験をしてきました。会社やビジネスのフェーズをふまえて、その時々で必要だと思ったころをやるスタンスでいます。それをプラスに捉えられる人にはぴったりな環境だと思います。
岡崎:
柔軟性が高いメンバーが多いですよね。
姜:
柔軟性があって、自分がやりたいことが会社から求められてることとマッチしてる感じですね。自分がやりたいものはアピールすべきだし、自分がやりたかったものでなくても、一度はトライする価値があると思っています。やってみて、それで合わなかったら相談する、というのがいいと思います。私は運が良かったのか、今までそういう局面はなかったのですが。
菊池:
逆に、指示されたい人や、受託開発が好きな人には厳しい環境かもしれません。ランディットは自社サービスを開発しているので、「自分がこうしたい」という思いを強く持って開発したい人に合っていると思います。
有山:
私は前職が受託開発会社だったのですが、クライアントからの開発依頼に対して、保守的な対応になりがちな傾向がありました。ランディットでは自分が作ったサービスを伸ばしていきたいという強い思いがあるので、入社してから、「できない」と最初に言わないようになっていきました。ランディットの開発やプロジェクトは、まず「できるにはどうするんだろう?」と考えることから出発するので、いつの間にかそういう思考になっていました。受託開発会社出身でも、それが意識できていれば問題ないと思います。
AIMOの事業の魅力と将来性は
岡崎:
そんなランディットが注力しているサービスの1つがAIMOですが、AIMO事業本部について教えてください。
姜:
AIMOは、“カメラとAIを組み合わせたサービス”であり、現状、建設と駐車場の2つの事業が柱となっています。両方とも従来のサービスに、コストを抑えつつプラスアルファの機能をつけるようなイメージで展開しています。
「AIMO Parking」は、駐車場に昔からある仕組みをAIを活用しながらDXするもので、既存の駐車場運営設備で出来ることは標準装備し、その上でコストが高かったり対応しきれなかったこと、例えばゴミの検知や違法駐車などの問題を、AIを導入することで解決できるようにしています。
「AIMO Construction」の場合は、防犯カメラという従来からある仕組みを、コストを上げずにプラスアルファの機能をつけれるような形で提供するものです。導入することで、例えば、足りなくなった資材を自動で発注したり、遠隔で指示したりできるようになります。
AIMOは、実はいろんな領域に活用できるビジネスであり、技術の横展開として現在進めている「AIMO Industrial(工場向け)」や「AIMO Real estate(不動産向け)」や「Live Biz(遠隔臨場)」はその最たる例です。駐車場や建設現場としてしっかりとしたサービスを供給しつつ、お客様のご要望に合わせて、さらなる0→1にも挑戦して成長させていきたいと考えています。
岡崎:
事業を推進していてワクワクするところはありますか?
有山:
特にコインパーキングという、車に乗る人なら誰でも使うところに自分が作ったサービスが入って、それが自分たちの頑張り次第で日本中の人が使う可能性があるのがすごいと思うし、作っていて楽しいです。AIMOの場合は、物理的なモノを触って使ってもらえるので、その実感が湧きやすいんです。何千とあるコインパーキングにAIMOが入って、どこに停めても自動精算されるという新しいユーザー体験が当たり前になる世界が近づいていると思うと、ワクワクします。
姜:
その上で、AIMOは次の世界も見据えています。将来自動運転が当たり前になった時、既存のシステムは通用しなくなります。そこで、自動運転と連携できるようなシステムの基盤になっていくというのが、AIMOが目指す未来です。
岡崎:
ちなみに、ランディットとしてAIをどのように活かそうと考えていますか?
姜:
AIを活用したビジネスって、データが核なんです。駐車場を起点にすることで、さまざまなデータを取得できるし、周辺の不動産の状況までわかるようになるので、他の領域にもビジネスを広げていくことができます。AIを活用したデータビジネスは大きな可能性を秘めていますし、それがランディットが目指す未来を作っていくうえで、欠かせないものです。
有山:
足元では、AIを業務の効率化にもどんどん取り入れています。AIMOのログデータの分析にも活用していますし、活用することでさらにAIが進化しています。そんな循環が今後もっと増えていくと思います。
鍵は視野の広がりを意識したコミュニケーション
岡崎:
スタートアップでこのサービスラインナップ、しかもハードもソフトも手掛ける会社って珍しいですよね。
菊池:
普通だったらこの人数では難しいと思います。サービス1つ開発して運営するだけでも大変なのに、どれにも手を抜かず走っています。
岡崎:
その第一線で活躍する櫻井さんはエンジニアとしてはどういうキャリアを積んできましたか?
櫻井:
学生時代から自分でサービスを作れるようになりたいと思い、独学でアプリを作っていました。大学4年生の時にランディットにインターンとして入社し、フロントエンドの担当になったのですが、両方やりたいと申し出てバックエンドも手掛けるようになりました。当時から、自分で考えて作って、他のエンジニアからレビューしてもらって、OKが出たらそのままサービスに反映されるという経験をしてきました。
ランディットのビジネスは、既存の仕組みがあるものをデジタル化していくために、新しい提案が必要になります。自分たちでルールを決めて作っていけるので、そういったところが面白いと思ってやり続けています。
菊池:
ランディットには、櫻井さんみたいな人がいるから強いんですよ。スタートアップで伸びるには、自分で切り開いていける環境が重要です。大手のような手厚いサポートは正直言ってないのですが、その代わり、質問したいと思えばいつでも聞ける環境が用意されています。業務委託のエンジニアも社員に積極的に教えてくれたりするような風土があるのもうちの強みです。
岡崎:
いつ頃からこういう雰囲気ができてきたんですか?
有山:
私は、創業から1年後くらいに、櫻井さんと同じ日に社員として入社したのですが、当時からすでに、少人数でも開発を広げてうまく回していくための基盤はあったように思います。
岡崎:
チームとして動くうえで何か工夫していることはありますか?
菊池:
チームメンバーの視野を広くすることを意識しながらコミュニケーションを取るようにしています。担当外のサービスの話も共有することで、会社として作っているサービスすべてを好きになってもらうように心がけています。
櫻井:
直接手掛けていないサービスについても自分ごとだと思ってほしいんです。日々の気軽な会話の中でも「隣の人がやっていることが、あなたのプロダクトにもこういう風に影響するかもしれないよ」というような話し方をすることで共感してもらえて、次の会話で視野が広がった反応、例えばビジネス視点での提案が来たりするんです。採用面接の際にもそこを意識して話していますし、そんなコミュニケーションが取れるように入社後もサポートしています。
有山:
エンジニアだけの会議でも、他のプロダクトについての質問がたくさん出ます。他での知見を生かそうとしているんですね。将来的に各プロダクトのデータを統合する必要があるっていう認識を皆が持っているのも、他のプロダクトへの興味が強い理由です。
菊池:
やはりビジネスと開発が近いというのも、興味が出てくる理由として大きいと思います。そこには代表の影響があり、プロダクトラインナップが増えてもそれがちゃんと浸透するようにメンバー全員が意識しています。
岡崎:
今後ランディットが成長し人数も増えるなか、どんなチームにしていきたいですか?
櫻井:
私たちのチームのエンジニアは、それぞれ自分のプロダクトを将来こういう風にしたい、という思いを持った上で、同じ方向を向いています。単なる作業者ではなく、一ビジネスマンでもあり、プロダクトも自ら作ることができる、そんな世界観の組織にしたいと思ってます。
菊池:
このカルチャーが途絶えないよう、強いチームを醸成していきたいです。今いるメンバーたちのような意識があれば、組織が大きくなっていってもそれが実現できると思います。会社が目指す方向が分からなくなるとメンバーの視座も下がってくるので、コミュニケーションの質と量は特に意識しています。
また、事業開発本部として、社外から見て良い意味でハードルが高い組織だと思われるようになることを目指しています。そのためにも、もっと外にも、自分たちのやっていることの面白さを発信していかなければと思っています。
将来の仲間へのメッセージ
岡崎:
最後に、ランディットへの応募を検討中の方々へのメッセージをお願いします。
菊池:
ビジネス部門と協力して世の中にないサービスを作ることにワクワクできる方と一緒に働きたいですし、そんな方に来ていただくことで組織も活性化すると思います。
有山:
もしランディットに興味を持たれたら、まずは近くの駐車場をちょっと意識して見てみてください。どういう機械があってどういうサービスなのか、見ているうちにもっと興味が沸いてくるかもしれません。
櫻井:
僕もそれが楽しいなって思います。ここのコストを下げるのにこういうサービスがあったらいいな、それを作る工数がこれくらいで、回収できるのにこれくらいかかるから、黒字にできるのはこれくらい、みたいなことまでイメージできるようになると相当楽しくなります。
岡崎:
これだけビジネスマインドがある25歳、楽しみだね!もともとの素養もあるけれど、ランディットだから誕生したという側面もあるのかな。
櫻井:
様々な個性を持ったメンバーを集めてていただいているので、そういう観点が生まれたっていうのもあります。ビジネスとエンジニアの壁がない。私はまさにその組織風土の影響を受けている例だと思っています。
COOからのメッセージ
私は、SBI証券の黎明期に約5年、アマゾンジャパンで10年以上にわたり各種デジタル事業の立上げに力を注ぎ、その間にも複数のスタートアップでビジネス創造に携わってきました。そんな経験を経て参加したランディットは、代表が描く大きなビジョンのもと、 創業からわずか3年で『at PORT事業』を確立し、『AIMO事業』を始めとする複数の関連事業を立上げ、お客様の課題に応じて組み合わせてご提供する新たな挑戦のステージへと歩みを進めています。
このグローバルスケールの可能性を秘めるスタートアップに、あなたの経験と情熱を注ぎ込んでみませんか?まずは気軽にカジュアル面談で、共に創り上げていく未来についてお話しましょう。

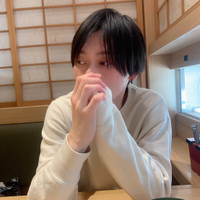




/assets/images/18101914/original/b014934c-4212-48a8-932f-5dd8abb2e58e?1717402969)
/assets/images/18101914/original/b014934c-4212-48a8-932f-5dd8abb2e58e?1717402969)

/assets/images/18101914/original/b014934c-4212-48a8-932f-5dd8abb2e58e?1717402969)
