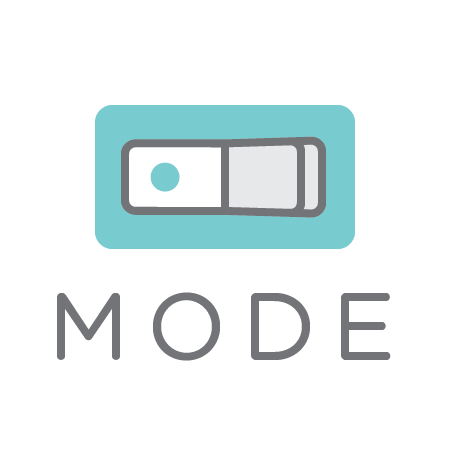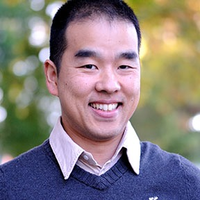MODEは、現場のリアルタイムデータや既存システムのデータを一元的に統合し、業務効率化や安全性向上を実現する「BizStack」を開発・提供する、シリコンバレー発のスタートアップ企業です。日々新しい挑戦に満ちたフィールドで、私たちは「次世代の社会を支える力」になりたいと願っています。
今回は、その進化を牽引するMODEのHead of Product、徳生 裕人さんにお話を伺いました。Googleや日本のデジタル庁を経て培ったキャリア、BizStack開発に込める想い、さらにはPMチームとの連携方法まで、幅広く語っていただきます。
目次
グローバルで磨かれたPMキャリア:Googleから政府機関を経てMODEへ
— 自己紹介とこれまでのキャリアについて教えてください。
— MODEでの現在のポジションと業務内容を教えてください。
IoTからAIへ:技術×強み×価値の追求
ー BizStackの開発にあたり、どのような面白さや難しさを感じていますか?
ー PMチームとは、普段どのように連携していますか?
ーどんなPMと一緒に働きたいと考えていますか?
MODEが挑むAI時代のプロダクトリーダー像
ー 今後、プロダクト全体の展望についてどのように考えていますか?
— スタートアップとしてのMODEの魅力はどこにあると思いますか?
— これから入社される応募者にメッセージをください
グローバルで磨かれたPMキャリア:Googleから政府機関を経てMODEへ
— 自己紹介とこれまでのキャリアについて教えてください。
徳生:徳生 裕人と申します。日本で生まれ、今はアメリカに住んでいます。キャリアとして一番長かったのはGoogleで、日本とアメリカの両方で、合計14年間PMとして働いていました。
2023年には日本のデジタル庁でチーフストラテジーオフィサーとして、政府内でのAI活用普及などに取り組み、そして2024年にUSに戻りMODEにジョインしました。
Google時代は、エンジニアたちと一緒に検索や YouTube の機能を開発する伝統的なPMの仕事のみならず、日本の製品開発本部長という立場で、Google の全製品について提言を行う組織横断的な仕事にも携わることができました。
PMとしてのキャリアの始まりは少し変わっていて、元々理系だったものの、大学卒業後は総務省に就職し国家公務員として働いていました。その後、日本の製造技術スタートアップのRD部門に移り、3年後に国内採用第1号のPMとして Google に入社しました。
ちょうどその頃のGoogleは、海外展開を加速させていた時期で、私はPMとして未経験ながらもチャレンジする機会を得ました。黎明期の Google で優秀な同僚たちからプロダクトマネジメントを学ぶことができたのは、私にとって非常に幸運でした。
— MODEでの現在のポジションと業務内容を教えてください。
徳生:現在は「Head of Product」として、BizStackという製品の開発全体を統括しています。PMチームのマネジメントを担いつつ、いちPMとしてはアメリカ市場向けのプロダクト施策にも直接関わっています。
私はPM歴やPMマネージャー歴は長いのですが、Googleではあくまで製品の一部分を見ていたにすぎません。これだけ多くの顧客に使われている プロダクト全体の方向性に責任を持つ役割はレアですので、責任とやり甲斐を感じています。
MODEのPMチームは、プロダクトビジョンの策定からロードマップ作成、ユーザーリサーチや要件定義、KPIの設定・分析、リリース後の効果検証まで、プロダクトライフサイクル全体をリードします。
他のプロダクトマネージャー、UXデザイナー、エンジニアリングリーダー、ビジネスチームなど多様な部門と密に連携しながら優先順位付けし、迅速な意思決定を行いながら、価値あるプロダクトの実現をリードしています。
IoTからAIへ:技術×強み×価値の追求
ー BizStackの開発にあたり、どのような面白さや難しさを感じていますか?
徳生:BizStackはもともとIoTの文脈でスタートしていて、いろんなセンサーをつなげて、データを管理・可視化しやすくするという点では、非常によくできたプロダクトだと思います。
今はその土台を活かして、新しい業界やユースケースに踏み込んでいくフェーズにあります。強みを活かしつつ、新しい方向性を模索する。そのバランスが難しくもあり、やりがいのある部分ですね。
IoTを通じてデータが集まるという基盤があるので、「じゃあそれを活かしてAIで何ができるか」というのは自然な発想です。ただ、その中で大事なのは、単に新しいことをやるのではなく、「AIなどの新しい技術」、「自分たちの強み」、「顧客にとっての価値」の3つがしっかり結びついたものを作ることです。
加えて BizStack は非常に拡張可能性が高いフルスタックのプラットフォームなので、同じ機能を実現するにも多くの方法があり、そのバランスをとるのが非常に難しい。けれど、だからこそチャレンジングで面白いフェーズだと思います。
ー PMチームとは、普段どのように連携していますか?
徳生:私を含めた3人のメンバーがいます。基本的に優秀なチームなので、マイクロマネジメントを避けるようにしています。それぞれのPMに対してスコープとKPIを明確に設定して、各自が自律的に創意工夫できるようにするのが私の大事な役割だと思っています。最低限の週次のミーティングや 1 on 1 はしますが、目的と方向性だけをしっかり握って、あとはある程度任せるスタイルですね。また、MODE全体ではAsanaというワークマネジメントプラットフォームを使ってタスクや進捗状況を管理しています。
私が就任してまもなく「ピラー」という小さなチーム単位の仕組みも導入しました。これは、チームをいくつかのビジネスゴールごと “柱(pillar)”として分けて、自走できるようにするための試みです。
各ピラーには、プロダクト・エンジニア・ビジネスのリードを設定して、基本的にはその3人で意思決定できるようにしています。MODEは US と日本にオフィスがありますが、地理的に近い人を同じピラーに集めています。
MODEはリモートファーストなので、自由度が高い一方で、他のチームが何をしているのか見えにくいという課題もあります。ピラーの導入は、それを補うための仕組みでもあるんです。
重要なのは、すべてをリーダーシップチームが決めるのではなく、現場に近い人が適切な判断をできる状態を作ること。そのために、CEOのGakuさんやCTOのEthanといった経営陣はピラーの中には基本的に入らず、方向性の合意だけ取ったうえで、日々の判断は各チームに委ねています。
PMは各ピラーの事実上のリーダーとして、開発マネジメントのみならず、会社にとって重要なビジネスゴールを各組織と連携して推進することになります。
ーどんなPMと一緒に働きたいと考えていますか?
徳生:建設的に手を動かせる人、そして何より前向きな人ですね。どんな会社でも課題や制約はあるし、ピラーのような仕組みを作っても、すぐに完璧に機能するわけではありません。そういう中で「じゃあ自分ならどうするか」「どうすれば皆にとって良くなるのか」を考えて、前向きに改善に取り組んでくれる人と一緒に働きたいと思っています。
あとは学ぶ力ですね。PMのやりがいって、やっぱり自分が作ったものが実際にユーザーに使われて、価値を生んでいると実感できるところにあると思うんです。
今、MODEの注力分野の一つは建設業界に特に力を入れているのですが、実は私たちの誰ひとりとして、もともと建設業界出身というわけではありません。だからこそ、今のPMのメンバーは実際に現場に足を運んで学んでいますし、私自身も日本にいるときは、できる限りお客様との打ち合わせや現場に顔を出すようにしています。
そういう意味でも、「前向きである」ということの中には「常に学ぶ姿勢があること」も含まれていて、それはとても大事な要素だと思います。
MODEが挑むAI時代のプロダクトリーダー像
ー 今後、プロダクト全体の展望についてどのように考えていますか?
徳生:お客様とお話ししている中で常に感じるのは、「DXを本当に実現する」って、どの業界でも非常に難しいことだという点です。技術的には可能なことが増えている一方で、自社の強みとどう結びつけるか、そして本当に役に立つものに落とし込むというのは、どの会社にとっても大きなチャレンジだと思います。
そういう中で、もしBizStackがその一助になれるのであれば、とても意義があると感じています。
BizStackの強みは、物理的なデータを蓄積し、可視化・活用できる点にあります。特に、設備監視のように「定常的に動いている現場」には非常に適したプロダクトです。例えば事例にあるニチレイ・ロジスティクスエンジニアリングでは、全国各地の冷凍倉庫で運用される冷凍機の稼働状況を監視しています。MODEの掲げるミッションは「あらゆる企業が、データとそこから得られる知見により、企業オペレーションを飛躍的に強化するノウハウとツールを提供」すること。これは、設備監視にとどまらず、もっと広い領域で活用できることを意味しています。
そこに今、AIやLLM(大規模言語モデル)などの技術が出てきたので、それらを活用して、従来の時系列データだけでは解決できない課題にも挑んでいきたいと考えています。
たとえば建設業界のように、定常状態が存在しない現場もあります。ビルの建設はゼロから始まって日々変化するもので、現場にデータの価値とAIの価値を導入するためには、全く違うものが必要になる可能性があると思うんですよね。
だからこそ、我々が提供しているAIアシスタント「BizStack Assistant」は、全く違う価値提供のあり方になる可能性がある。BizStackというプラットフォームの完成度が高いからこそ、それをいかに広げていくかは大きな挑戦です。
ただ、今のチームは前向きに新しいものを生み出そうとしている人たちが集まっているので、方向さえ間違えなければ、本当に価値のあるプロダクトを作れると思っています。だからこそ、これからがとても楽しみです。
— スタートアップとしてのMODEの魅力はどこにあると思いますか?
徳生:MODEの魅力のひとつは、まさに今「第2創業期」と言えるようなカオスなタイミングにあることだと思っています。
IoTからAIへ。これまでの強みを活かしながら新しい領域に踏み出そうとしていて、挑戦できる方向やチャンスもすごく多い。でも当然、リソースは限られているので、どこにフォーカスするかを常に考え、選び取っていく必要がある。そういう意味で、ただ言われたことをそのまま開発するのではなく、「これは本当にやるべきことなのか?」と、プロダクト側としても自分たちの視点を持って向き合う必要があります。
その混沌とした中で、自分で考え、自分で決めて動いていける人には、すごく面白い環境だと思いますね。
もうひとつの魅力は、創業者の存在です。GakuさんとEthanは、元Yahoo!やGoogleのエンジニアで、シリコンバレー的なスピード感と「とりあえずやってみよう」という試行錯誤の文化が根付いています。
Gakuさんは任せるスタイルで、細かく管理するタイプではない。一方、Ethanはモノづくりに対してとても真剣で、プロダクトの細部にまで気を配ってくれる。2人ともすごく話しかけやすいし、今はまだ60人規模の会社なので、誰でも創業者とフラットに話せる距離感があります。これは、他の会社ではなかなか得がたい良さだと思います。
人も前向きで、まっすぐな人が多いですね。いわゆる“変に尖った人”がいないというか、純粋にいいものをつくりたいと思っている人たちが集まっている。そういう文化や空気感も、MODEならではの魅力だと感じています。
— これから入社される応募者にメッセージをください
徳生:IoTからAIの時代へと進む中で、まったく新しい価値を生み出すチャンスがMODEにはあります。だからこそ、前向きにチャレンジできる人にぜひ来てほしいですね!
個人的にすごく大事だと思っているのは、「テクニカルなバックグラウンドがあること」と「カオスを楽しめること」。MODEはまだまだ整っていない部分も多くて、与えられた仕事をきっちりこなすだけでは物足りないと思います。状況が変化する中で、自分で考えて、判断して、手を動かしていける人の方が楽しめる環境です。
あと、これは魅力でもあり前提でもあるのですが、チームはかなりグローバルです。エンジニアの半分以上はアメリカ在住で、公用語は英語。たとえばEthanも日本語は話せませんし、日本採用のPMであっても英語は必須ですし、最低でも年に1回はアメリカに来て直接対面で戦略を議論する機会も作っていきたいです。
そういったインターナショナルでダイナミックな環境の中で、ご自身の技術力とカオスを楽しむ前向きさ耐性を武器に、新しい価値を作っていきたい方と一緒に働けたら嬉しいです。お会いできるのを楽しみにしています!