MODEは、現場のリアルタイムデータや既存システムのデータを一元的に統合し、業務効率化や安全性向上を実現する「BizStack」を開発・提供する、シリコンバレー発のスタートアップ企業です。日々新しい挑戦に満ちたフィールドで、私たちは「次世代の社会を支える力」になりたいと願っています。
現場の最前線で、設計・開発から運用まで一貫して関わるソリューションエンジニア。今回は、そんな立場から「BizStack」の進化を支える榮枝(さかえだ)さんに、仕事のリアルとその魅力を伺いました。
目次
技術の始まりから、現場のその先まで
ー現在担当されている業務について教えてください。
ー1日の流れについて教えてください
ー同じ「デリバリーチームのエンジニア」でも、ソフトウェアエンジニアとは違いがあるのでしょうか?
わからないから、やってみたくなる
ーこの仕事で特に印象に残っているプロジェクトやエピソードはありますか?
ーフルスタックで技術を担うなかで、わからないことや初めての領域にぶつかったとき、どうやって解決しているのでしょうか?
ーなぜこの職種、そしてMODEという会社を選ばれたのでしょうか?
会社をもっと良くするために、僕にできること
ーチーム内や他部門との連携において、意識していることはありますか?
ー社内では部活動にも積極的に参加されていますよね?
ー今後の目標について教えてください。
ー最後に、どんな人と一緒に働きたいですか?読者へのメッセージもお願いします。
技術の始まりから、現場のその先まで
ー現在担当されている業務について教えてください。
榮枝:主な業務は、設計・開発、デリバリー対応、トラブル対応です。
最初の要件整理はセールスやソリューションアーキテクトが主に行いますが、僕もそこに少し入って「技術的にどうやって実現するか」という部分の設計に関わることが多いです。お客様と話し合いながら「こんな形でいかがでしょうか?」と確認を取りつつ進めていきます。
例えば「こんなシステムが欲しい」とお客様から要望をいただいたときに、MODEのプロダクトである「BizStack」だけではカバーしきれない部分を補うような、追加の機能やシステムを設計・開発することが多いですね。
また、表から見えない部分、例えばダッシュボードの表示や通知の出し方なども調整しますし、お客様の既存のシステムと連携が必要な場合は、相手側の開発部門と細かい仕様のやりとりもします。
作ったあとのテストや、現場への導入対応、導入後のアフターサービスなどもあります。例えば「ダッシュボードのこの部分、ちょっとだけ変えたいんだけど…」「複数現場で同じウィジェット設定を使いたい」という要望にも応えています。
それ以外にはトラブル対応もあります。その場合は、原因調査から対応まで担当しますね。IoTなので、現場の物理的な状況も影響することがあります。ログが取れれば遠隔でも対応できるんですが、何も情報が取れない場合は、お客様に操作していただいたり、写真を送っていただいたりして確認します。それでも解決できない場合、機械を送ってもらうか、僕たちが現地に行くこともありますね。
要するに、設計から始まり、開発、導入、運用、トラブル対応まで一連のプロセスすべてに関わっています。さらに、お客様との定例ミーティングで「今後はこういう機能を追加しましょうか」といったアップデートの相談にも乗っています。
どちらかというと「何をやりたいか」をヒアリングして引き出すというよりは、「やりたいことがある程度決まっている状態」で、「それをどうやって技術的に実現するか?」というところを考えたり、実際に手を動かしたりする部分が多いですね。
ー1日の流れについて教えてください
榮枝:1日の流れは日によって全然違います。例えば開発に集中する日は、朝からずっと資料を作ったり、コーディングしたり。誰かと話すわけでもなく、ひたすら机に向かって進めていく、みたいな感じですね。
一方で、納品が絡む日はけっこうバタバタします。例えば、出張で現場まで機材を持っていって、実際に取り付け作業をして、「あれ、動かないぞ…?」ってなったらその場で調査して直す。そういう日は、予定どおりに帰ってこられないこともあります。
それに加えて、トラブル対応が入る日もあるんです。朝イチで「データが取れなくなったんですけど」といった連絡が来ると、一気に調査モードに入ります。ログを確認したり、お客様とやり取りしたりして、1日まるごとそれにかかりっきりになることもあります。
そうした業務の合間に、定例ミーティングやプロジェクトチームとのミーティングが散らばっています。
ー同じ「デリバリーチームのエンジニア」でも、ソフトウェアエンジニアとは違いがあるのでしょうか?
榮枝:僕は基本的に、プロダクトそのものの開発には関わらず、カスタム領域に特化しています。一方、デリバリーチームのソフトウェアエンジニアは、プロダクト側の開発まで手を出すことがあります。
プロダクトに対して「こういう機能があったらいいな」といった要望は出しますが、自分で実装まで手を動かすことはないです。お客さんとの対応もある中で、そこまで手を広げるのは現実的ではないと思ってます。
ただ、完全に線引きしてるわけでもなく、例えば今回のカスタムで「これ、他のお客さんでも使えるよね」というものがあった場合は、共通部品っぽく作って、再利用できるように意識することもあります。

わからないから、やってみたくなる
ーこの仕事で特に印象に残っているプロジェクトやエピソードはありますか?
榮枝:技術的に面白いプロジェクトはたくさんあります。入社してすぐのタイミングで、MODEの仕組みもまだよく分からない中で、要件だけ渡されて、どのように実現するかから全部自分で考えて、設計から実装まで丸ごと担当した案件は、大変ではありましたけど、良くも悪くもすごく印象に残っていますね。
IoTってセンサーをクラウドに繋ぐだけでしょって思われがちなところがあるんですが、実はその裏側には設計の工夫がたくさん必要なんです。例えば、データの送信先がクラウドではなく、別のシステムだったり、接続するデバイスの種類によって制約があったり、それと、クラウドに繋いだあとどのようにユーザーにその情報を届けるかも重要だったりします。IoTだからこそ、現場の物理的な制約やセキュリティも考慮しないといけないんですよね。そういった制約を総合的に踏まえた設計が求められるのが、Web系とはまた違った面白さだと思います。
それから、この仕事の魅力は技術面だけではありません。出張で全国の現場に行くことも多くて、観光ではなかなか行かないであろう場所に行けたりするのも、個人的にはすごく楽しいです。
現場に行くと、実際にお客様がどう機器を使っているかが分かるので。この仕事は、単に繋ぐだけではなく、どう使われるのかまで想像して設計する必要があるので、実際に現場を見させていただけるのは、とても貴重で良い機会だと思います。
ーフルスタックで技術を担うなかで、わからないことや初めての領域にぶつかったとき、どうやって解決しているのでしょうか?
榮枝:プロダクトの仕様や、既存の仕組みに関することであれば、社内で頼れる人に相談することも多いです。
ただ、それ以上に多いのが、誰もやったことがないことにぶつかるケースですね。例えば、新しいセンサーを接続する場合とか、現場で発生したトラブルや障害の原因がまったく見えていないとき。そうなると、どうやって原因を切り崩していくか、から自分で考える必要があります。そこが一番難しいところですね。
最近は、技術的な調査にもLLMを活用することも多いです。こちらが適切に質問を投げてあげればとても高いレベルで回答してくれるので助かっています。
また、現場でのトラブルを含め様々な不確実性のある仕事なので、例えばその不確実性を前もって予測してお客様とちゃんと共有するなど、不確実性と適切に向き合っていくことがすごく大事なんです。
実際にトラブルが発生した後の対応も同じです。「現時点で考えられる原因はこのあたり」「遠隔では調査できるのはここまで」など、状況を整理して共有します。それでも解決しなければ「この部品を交換しましょう」とか「一度メーカーに問い合わせてみましょう」など、次の手を提案していきます。
要するに、何が不確かで、どこにどうリスクがあるかをはっきりさせる。そのうえで、どこから着手するかをお客様の合意を得ながら進めてていく。そんなスタンスでやっています。
その意味で、求められるのは「総合力」ですね。IoTはもちろん、Web系開発で言うフロントエンドからサーバー接続、バックエンド、インフラにも全部関わる。過去の知識も総動員しつつ、ChatGPTにも助けてもらいながら、新しいこともどんどん学んでいます(笑)。
ーなぜこの職種、そしてMODEという会社を選ばれたのでしょうか?
榮枝:もともとエンジニアになった理由として、知らないものを知りたい、どうやって動いてるのかどうやって作っているのかを理解したい、という欲求がすごく強かったんですよね。
Web系の会社にもいたことがあるんですが、しばらくすると、過去得た知識や経験の中で得た技術の範囲内で対応できる仕事に感じるようになってしまって…。もっと未知のものに触れて、自分でも「これどうやって動いてるんだろう?どうやって作ろう?」って考えられる環境に行きたくなったんです。
その点、MODEはIoTという領域なので、Web開発だけでは味わえない面白さがあると思いました。
例えば、現場で使われるセンサー端末がどう動いていて、どうクラウドと繋がっているのか。そういうリアルとデジタルが交差する部分にすごく興味がありましたし、それを自分で触って確かめられるというのが、すごく魅力的でした。
しかも、MODEは工場だったり、建設現場だったり、トンネルの中だったり、普段の生活では絶対に触れないような場所で使われるんです。そういう現場の仕組みを見たり聞いたりできるのも、新鮮でした。
とはいえ、ロボティクスとか宇宙開発みたいなハードコアな領域は、自分のスキルセットからの乖離が大きくて、手が出せない。でもMODEのやっていることは、ちょっと自分の限界からはみ出すくらいの「面白そう」の範囲にちょうどあったんです。だから、ここなら、自分でもチャレンジしながら楽しめる!と思って入社を決めました。

会社をもっと良くするために、僕にできること
ーチーム内や他部門との連携において、意識していることはありますか?
榮枝:そうですね、出社することも意識している工夫のひとつです。
MODEはリモートファーストの会社ですが、リモートと出社は半々くらいです。週2〜3日は在宅で、コードを書いたり開発に集中したりしています。残りの日は会社に行ったり、お客様のところに行ったりですね。
特にセールスの方たちと連携するには、やっぱり顔を合わせて話すのが一番早い。
エンジニア同士ならソースコードや技術ドキュメントで話ができたりもしますけど、セールスの方と細かいニュアンスをすり合わせるには、対面の雑談レベルの会話が一番スムーズなんです。だから会社にはよく顔を出しています。
ー社内では部活動にも積極的に参加されていますよね?
榮枝:はい、ゴルフ部とコーヒー焙煎部に参加しています。
特にコーヒー焙煎部は、「なんだそれ?」と思って参加したんですが(笑)、出社することが多い分、社内でもトップクラスでコーヒーを飲んでるんじゃないかというくらいなので、そこに何かしら貢献できたら…という気持ちもありました。
それに、部活を通じたコミュニケーションって、思ってる以上に仕事に効いてくるんです。ちょっとした雑談の中で質問がしやすくなったり、それがきっかけでプロジェクトの進め方が変わったり、新しいアイデアが生まれたり。セールスチームと「この提案、どう持っていこうか」と戦略を練るときにも、顔を突き合わせて話すからこそ伝わるニュアンスがあったりします。
ー今後の目標について教えてください。
榮枝:20〜30代はずっと、自分自身のスキルアップを軸にキャリアを築いてきました。でも今は、自分だけじゃなく、会社や周囲の人をどう成長させていくかを考えるフェーズに入ってきたなと感じています。
最近では、日々の業務に加えて、チーム全体の役割や業務の棚卸しにも取り組んでいます。というのも、MODEはまだまだ成長フェーズで、組織や業務フローが整いきっていない部分もあって。
「この人は何をやっているのか」「この役割って具体的に何を指すのか」が、社内でも見えにくくなっているところがあるんです。なので今、デリバリーチームの中で、各メンバーが担っている業務をちゃんと文章に起こして整理するという動きを進めています。
さらに、「デリバリー改善プロジェクト」という形で、いくつか仕組み化の試みも始めました。
例えば、Slackなどで散らばっていた受発注のやりとりを、ちゃんとルール化して、「この作業はこう依頼すればいい」と明確に分かるようにしたい。業務とコミュニケーションの両方を見える化して、属人化しない仕組みにしたいんです。
MODEという会社をもっと良くして、大きくしていくには何ができるか。そう考えたときに、業務の整理や、AIをどう活用するかというところにも力を入れたいと思うようになりました。
AIを業務システムに組み込む取り組みは、すでに多くのSIerやITコンサルが進めています。でも、MODEの強みは点検や検査といった「ラストワンマイル」を担えること。そこにAIをどう融合させ、他社の構築するシステムとどう連携させていくか。現場に一番近い自分たちだからこそ生み出せる価値があると思っています。
例えば、さまざまな種類のセンサーからデータを集約し、それをAIが分析して判断・アクションを起こすような仕組み。人間が介在しなくても、現場で何か起こったときに即時対応できるようなシステムがあれば、IoTの可能性はさらに広がるはずです。
ー最後に、どんな人と一緒に働きたいですか?読者へのメッセージもお願いします。
榮枝:自分の知らないものにどんどんアタックしていける人は、きっとMODEに向いてると思います。新しい技術やツールを自分で試してみたり、分からないことを誰かに聞いたり、自分でちゃんと考えたり。そういったことを、楽しい!と感じられる人にぜひ来てほしいですね。
MODEでは、今までなかったものを実際に作っていく最先端というか、技術的に面白い瞬間に立ち会えます。しかもまだまだこれから大きくなっていくフェーズの会社で、自分がその成長を支える一員になれるというのは、すごくやりがいがありますよ。
僕自身も、これからもっと会社を大きくしていきたいと思ってますし、その中で、面白い技術を作る人になっていきたい。
だからこそ、一緒に楽しみながら走れる仲間が来てくれると嬉しいですね。


/assets/images/3130266/original/d1e42f7f-f993-4fae-998c-71f977b6f873?1538544503)


/assets/images/3130266/original/d1e42f7f-f993-4fae-998c-71f977b6f873?1538544503)

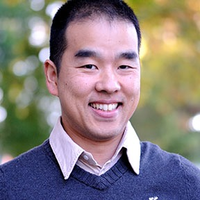


/assets/images/3130266/original/d1e42f7f-f993-4fae-998c-71f977b6f873?1538544503)

