彼の経歴は、東京大学工学部でのコンピュータービジョン研究、そしてITベンチャーでの高度な画像処理AI開発と、エンジニアとして最高の環境を経験してきました。しかし、彼が今いる場所は、日本の「ものづくり」の未来を、泥臭く、しかし情熱的に切り拓くスタートアップの最前線。それが、
株式会社WOGOのCTO、長谷川祐也氏の現在地です。
株式会社WOGO CTO
長谷川 祐也
東京大学 工学部電気電子工学科卒業
幼少期に培われた職人気質。ものづくりへの純粋な感動。そして、作り上げた技術を「ちゃんと世に届ける」という強い渇望。穏やかな表情の奥には、確固たる信念と、妥協なきプロ意識が垣間見えます。
彼は、なぜ安定した技術者の道ではなく、起業という挑戦の道を選んだのか。そして、どのような「職人」たちと共に、日本の未来に確かな足跡を残そうとしているのか。彼の言葉の奥から、その答えを探ります。
幼少期
── 「目に見えない細部」へのこだわり──
本質的な価値提供にこだわる「職人気質」
学生時代はまさか自分が起業するなんて、全く想像もしていませんでした。
ただ、僕のキャリアを形作る上で大きな影響を与えたのは、父親が内装屋だったことです。小さい頃はよく職場について行っていたんですが、そこで見たのは、お客さんの目には見えないけれど、細部にこだわるのが当たり前という職人の世界でした。
この原体験が、僕の中に「職人気質」みたいなものを醸成したんだと思います。「どうせやるならやれるところまでやる、きちんとやる」という徹底したマインドは、大学のバレーボール部で厳しい両立を経験した時代も含め、ずっと僕の基盤になっています。これは、技術者として本質的な価値を生み出す上で、今でも一番大切にしている部分ですね。
──ものづくりに魅せられた大学時代と、3Dへの情熱──
僕とプログラミングの出会いは大学一年でした。知人が教室を開きたいと言うので、友達と一緒にテスター生徒として受講したのが最初です。その時、ある本を使って初めてプログラムを体験したんですが、その内容が「単純な作業をコンピューターに自動でやらせる」というものだったんです。
今考えれば凄く簡単なシステムなんですけど、自分が手を動かして作ったものが、全自動で動いているのを初めて見た時は本当に感動しました。何か自分が生み出したものが、世の中で動き出す。あの感覚こそが、「ものづくり」にのめり込むきっかけだったと思います。
その後、情報系に進み、元々興味を持っていた3Dを研究できる研究室を選びました。特に、3Dの空間認識に強い関心があって。将来はロボットや自動運転などを扱う会社で活躍したいと思っていたので、研究テーマとしてもそういった題材を選びました。
── テクノロジーの社会実装へ──
LiDARが満たした「世に届ける」渇望
大学4年の頃、僕はAI開発の会社でPM/PLとして働いていました。予算のついた大きな案件を回す中で、達成感もあり、「もっと自分自身でやってみたい」という思いは強くなったんです。
ただ、担当していたのが医療系の案件で、僕自身が使ってくださる方々の前に出られなかったこともあり、実際のユーザーの声が聞ける環境になかった。「作っているけどちゃんと世に届けている感がない」。これが、僕の中で大きな課題感として残っていました。
そんな時、後にCOOとなる澤田と共にWOGOを立ち上げる秦と出会います。秦から、ちょうどiPhoneにLiDARがついたから「不動産系のアプリを作りたいので手伝って欲しい」と誘いを受けました。時間があったこと、インターンの経験からもっと自分でやってみたいと思っていたこと、そしてテーマがまさに僕が興味を持っていた3Dの空間認識(スキャン)だったこと。これは天啓だと思いました。
その後、ちょうどコロナだったこともあり、使われていなかった一軒家の一階をご厚意で借りて、創業メンバーが泊まり込みながら開発を進め、WIDARというアプリを世に出しました。それがエンドユーザーに使ってもらえて、直接ユーザーの声を聞けた時、あの渇望していた「世に届ける」という感覚が満たされたんです。
創業当時 右 CEO秦、左 COO澤田
── AI時代を生き抜く ──
WOGOが求める「全体の成果に200%貢献する職人」
僕たちがやろうとしているのは、簡単な挑戦ではありません。だからこそ、最高のプロフェッショナル集団で挑む必要があり、僕たちが求めるのは「全体の成果に圧倒的影響力を持つ職人」です。
まず、僕たちが強く求めるのは、個人の成果ではなく、プロダクト・プロジェクトの成功軸で思考できることです。
その上で、開発者として成長したいという強い気持ち、そして与えられずとも自走して成長できる能力を備えていることが大前提。挑戦を楽しむためには、体力や経験も重要だと考えています。
プロとして、期待されていることを達成するのは最低限と考え、常にその期待を超え、細やかな部分までこだわりとプライドを持ってそれ以上のものを生み出すことを目指しています。仕様書にない部分に関しても当たり前に高い水準に持っていくのがプロの証だと考えています。
また、密なコミュニケーションでクライアントとの認識を一致させ、過度な負担を招かないよう、事前に計画を調整できる能力が求められます。そして、僕たちはシステムのプロとして、クライアントの提示する要求の奥にある、本質的な課題を見抜く姿勢を大切にしています。成果を出すことはもちろん、要求の本質を見抜き、責任をもって、クライアントへ期待以上の価値を提供できるエンジニアが必要です。
── 「互いに成長できる」相互関係 ──
プロフェッショナル同士の最高のチーム
僕たちが目指すのは、「プロフェッショナル同士の最高のチーム」です。このチームこそが、AI時代を生き抜くもう一つの鍵だと確信しています。
- 経験や役割に依らない徹底した議論を是とします。開発者としての上下はなく、書いたコードに「誰が書いたか」は関係ありません。だからこそ、「教える → 教えられる」ではなく、「互いに成長できる」という相互の関係でなくてはいけない。
- 異なる意見やお互いを尊重した上で議論を深める。システム開発においては議論が発生しないほうが危険だと考えています。僕たちは常に本質的な最適解を求める。
- 適切な知見の共有システムがあり、各個人がチームへの還元を意識している。どんなに小さな気づきでも気軽に共有し、問題の発生を未然にチームで発見・解消できる文化こそが、僕たちの強さです。
── 未知の道を切り拓く──
新たな仲間たちへ
僕自身、学生の頃は「大企業に入らないといけない」という固定観念があったように思います。でも、実際に仲間と起業しスタートアップという道に飛び込んでみて、「意外といけるな」と実感しました。やりたいことをやるのに、会社の規模や名前、そこにいる人の数は関係なく、情熱さえあればなんとかなる。 これは与えられた仕事だけでなく、「自分でやりたい!」という気持ちを追求し、泥臭く挑戦してきた中で確信したことです。
僕たちが求めるのは、その挑戦を責任感を持ってやり遂げられる人です。
AIが進化する未来では、ただコードを書くだけのエンジニアは不要になると思います。僕たちエンジニアが価値を生み出し続けるために必要なのは、責任を持つこと、そして、求められた以上の成果を出すことです。クライアントの要求の裏にある、本当に必要な価値に気づけるか。なぜ今これをやっているのか、納得、理解して取り組めるか。
僕たちが挑む業界の変革は、決して平坦な道ではありません。しかし、そこには明確な課題があり、それを解決した先には大きなイノベーションが存在すると確信しています。
もし、新しい道を自らの手で切り拓くことにわくわくする方がいれば、ぜひ一度お話ししましょう。情熱と責任感を持って、この道を共に楽しんでくれる仲間を待っています。
長谷川の思いを聞いて感じたこと
彼が求める「職人」とは、単に技術力が高い人間ではありませんでした。
それは、自分の生み出すものに責任を持ち、チーム全体の成功のために、未来のために、期待を超え続けることを是とするプロフェッショナルの姿です。
彼のルーツである「父譲りの職人気質」は、最新の技術と結びつき、「妥協しないものづくり」というWOGOの文化の核となっています。「世に届ける」への渇望から生まれたWIDAR開発の情熱は、今、日本の製造業という巨大な課題に挑む原動力となっています。
WOGOが築こうとしているのは、AI時代にも価値を失わない、人と技術、そして情熱に裏打ちされた、本質的なものづくりの未来です。
この挑戦の道は、決して平坦ではないでしょう。しかし、彼の静かな目の奥には、その道を切り拓く技術と、共に歩む仲間への確かな信頼が灯っていました。この困難な道の先に、日本の「ものづくり」の未来を描く、確固たる決意と、挑戦にわくわくする「職人」の熱が、そこにはあります。



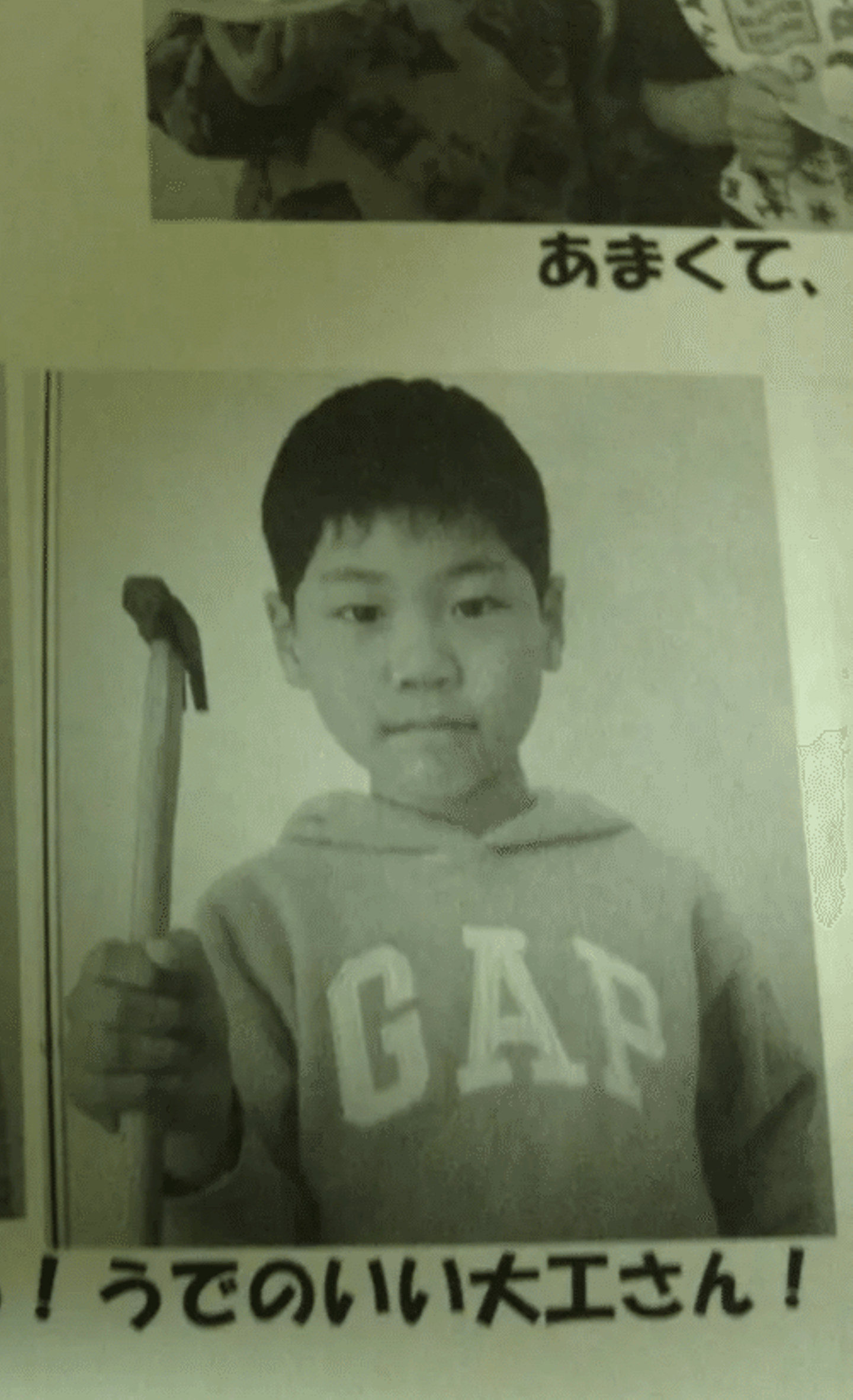

/assets/images/21191185/original/6f748797-e1cd-46c6-a714-96ffaf1a2d48?1748095493)

/assets/images/21191181/original/7a7f1b01-84b0-4cfa-a2ba-75565f4eeee5?1748095188)
/assets/images/21191181/original/7a7f1b01-84b0-4cfa-a2ba-75565f4eeee5?1748095188)

