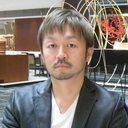今回は特に「私の意見」を展開したいと思います
ウェルビーイング。どことなく既に陳腐感のあるこの言葉、日本人的にはこの4、5年でようやく市民権を得たくらい新しめのWORDなのですが、そのルーツはなんと1946年に世界保健機関(WHO)が設立される際、同憲章で「健康の定義」として織り込まれた概念です
自分が良い状態であればより幸福感を感じられる。より幸福であれば業務生産性も上がる、という論理は誰しも否定しないでしょう。しかし、幸せの定義や感じ方は人それぞれ違います。一人が幸せという人が居れば一人だと孤独で生きていけないという人も居ますし、「お金や衣食住が充実してこその幸せ」を支持する人が多数派である一方で、貧乏や金欠でも光輝いている人を私は数多く知っています
全ての幸せの源泉は「自分の中にある」と私は考えています。環境や他人から提供されるのではなく自家発電するものという意味です。自分の価値観と意思が基礎にあり、ハード(物質)ではなくソフト(感じるもの)であり、相対的なものでなく「自分がどう感じるか」といった絶対的指標であるという意味です
Well-beingの対義語は一般的には「不健康」ですが、本質的なところを探れば「孤独」を指し、その正体はこの世界で「誰かの役に立っていると感じられないこと」というのが私の帰結です。誰かの役に立つためには、自分が自分がではなく、周りの人たちに目を配り、困っている人がいたらどうにかして手を差し伸べようとする、そんな「意思」があってのことだと考えるのです
そうすると必ずこう云う人が現れます。「自分が幸せでなくてなぜ他人を幸せに出来るのか」「自分が満たされてこそ他人に目を向けることが出来るのではないのか」と。こうした人のいう「幸せ」や「満たされている状態」の概念定義がそもそも私の主張とは異質なものだと感じています
あなたの周りに居る「Well-beingな人」とは、どんな方でしょうか?

スマホからInstagramストーリーズに投稿しよう
カメラを起動してQRコードをスキャンしてください。
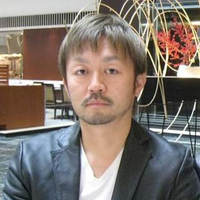

/assets/images/9196911/original/7eeb9127-b22a-4d20-8c5f-9fc08e0509b9?1649120504)
/assets/images/19997422/original/7eeb9127-b22a-4d20-8c5f-9fc08e0509b9?1734601014)