私はラクス社の楽楽精算一括設定代行業務を担当して今年で8年目になります。
設定代行業務の概要を理解して頂くために、業務経験から5点ほど私が面白いと感じているポイントをお伝えしたいと思います。
また、最後に実例3つ上げさせていただきました。
楽楽精算設定代行の「制約があるからこその面白さ」を共有できましたら幸いです。
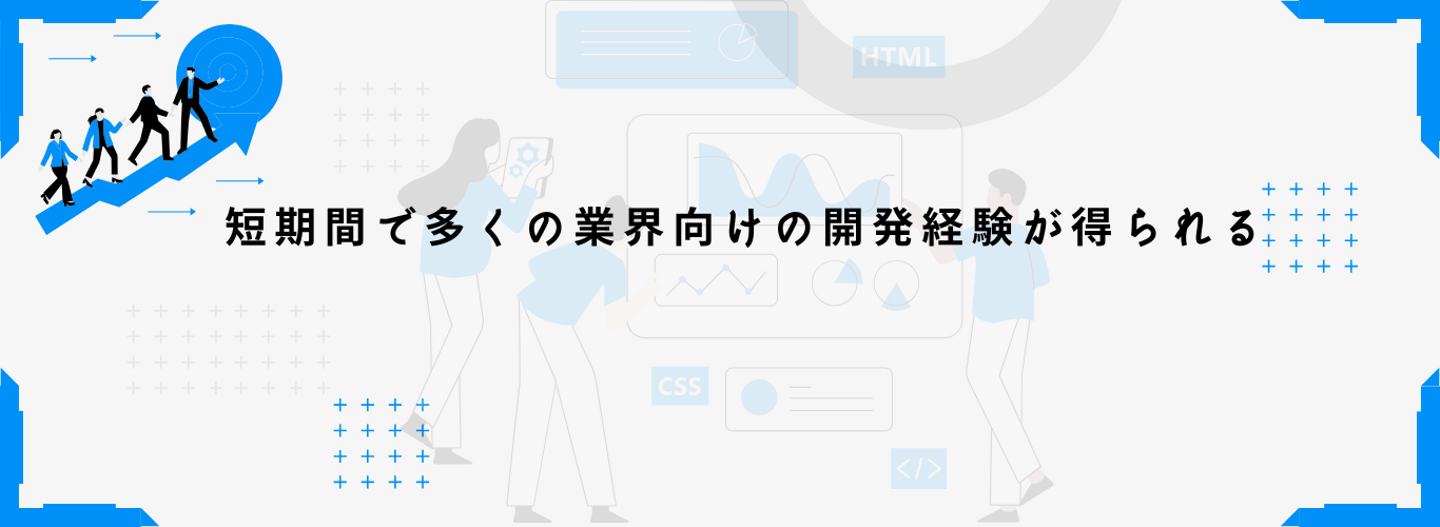
要件定義⇒開発⇒検収までの流れを3カ月(12週間)で対応します。検収後はサポート期間と言って設定代行担当者がそのまま運用に向けた技術支援や質問回答を中心としたサポート業務を行います。
対応期間の平均ではなく必ず3ヶ月で完了する必要があるため、一般的な開発に比べてかなり短くタイトなスケジュールになります。
設定内容はお客様によって幅の違いがありますが、旅費・経費精算を扱う点では共通していますので、 業務習熟は比較的早くできるのではないかと思います。
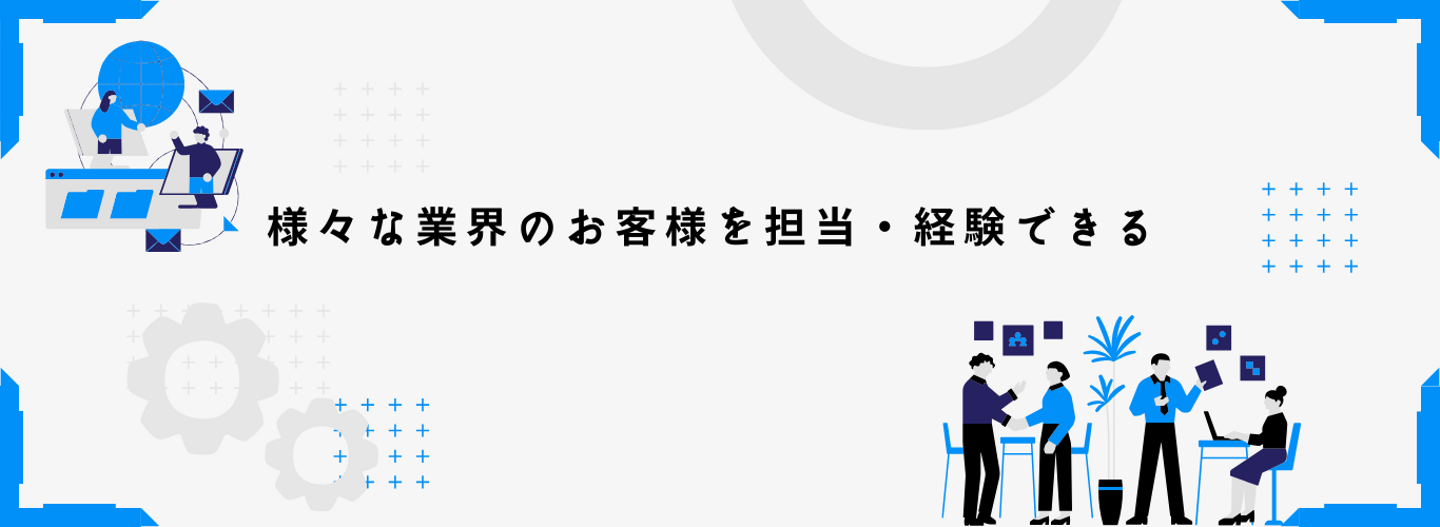
大手から中小まで大小さまざまな企業規模の事業者様が導入を検討されているため、多様な業界のお客様対応を経験できます。
旅費・経費精算という限られた切り口ではありますが、会社様ごとに精算に際しての捉え方や手当規定、出力する仕訳データの構成や要求仕様などが異なる点が面白いところです。
また、設定経験はそのままお客様への提案材料にもなるため、経験するほどに提案力が上がっていく仕事と考えます。
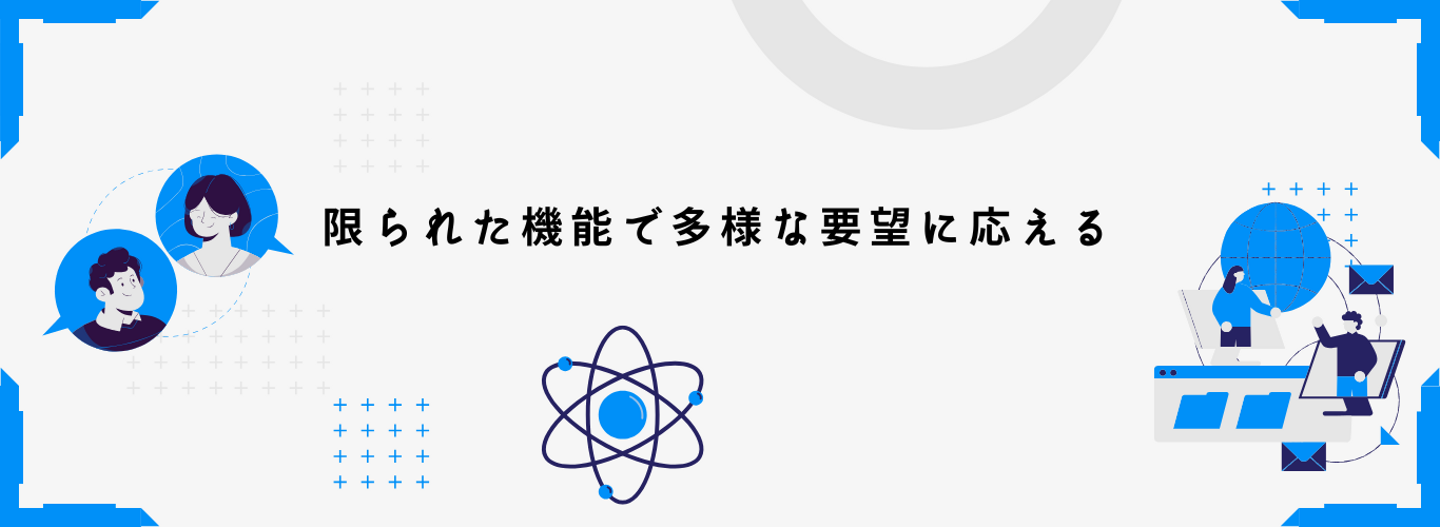
楽楽精算では詳細な設定のカスタマイズが可能ではありますが、足りない画面や設定を新規に作るような機能はありません。
限定された機能・マスタ・画面数を使ってお客様のご要望をどのように実現するかが腕の見せ所になります。一般的な開発業務と比較すると標準機能ではどうしても対応範囲に限りがあります。
システムやマスタの構成を熟知し、お客様の要望を実現できる瞬間は設定代行の醍醐味ともいえます。 また、運用で対応できない部分を運用方法で補っていただくことも多く、お客様にどのように説明してご納得いただくか、コミニュケーション能力が問われる部分も多くあります。

楽楽精算は精算システムなので課題の多くは精算処理のDX化なのですが、業界や会社に応じて精算の手続きにはさまざまなバリエーションがあります。
業界ごとの特色や類似事例などもあるため、同じ課題に対して様々なアプローチがあることが学べる機会になると考えます。
3か月で案件を完遂しなければならないため、目的意識と進捗管理が非常に重要です。作業の前後関係、資料のご提供依頼、スケジュールが遅れた場合のリカバリ方法など、お客様と社内の作業メンバーを引っ張っていくために積極的にコミニュケーションを取る姿勢が求められます。
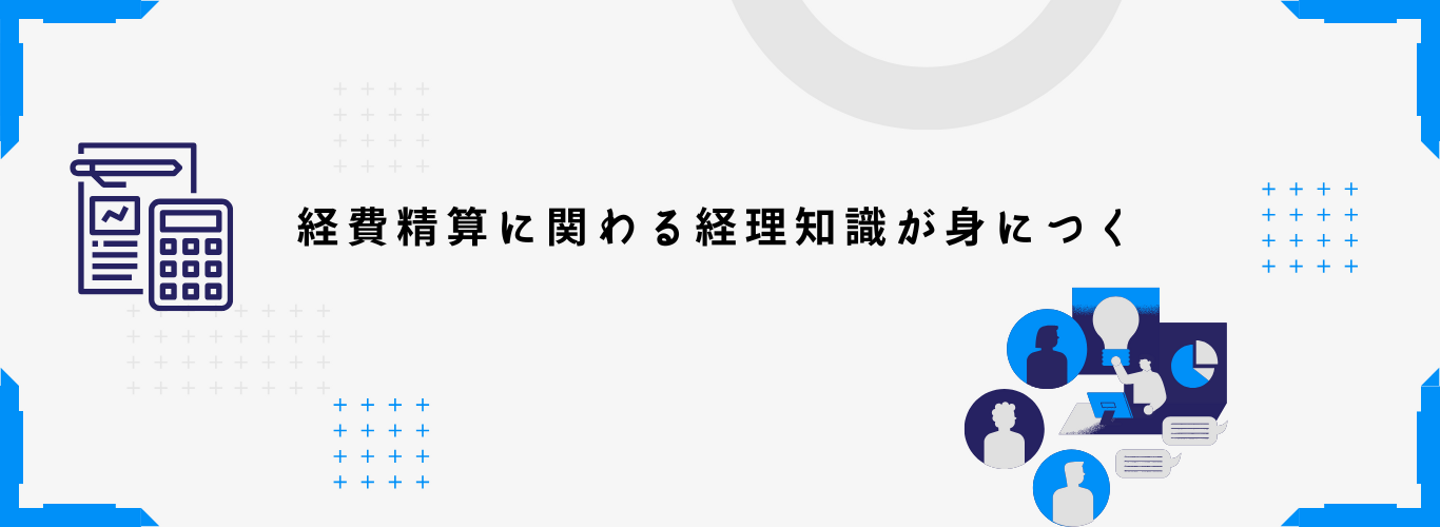
楽楽精算の設定の最終目的はCSV形式や固定長などの仕訳データを出力して会計システム(代表的なところでは勘定奉行、弥生会計など)に連携することです。
お客様によって経理処理(使用される勘定科目の組み合わせなど)の考え方が異なるため、
・楽楽精算が実現可能な仕訳内容
・お客様ご要望の仕訳内容と考え方
2点を照らし合わせてシステムで対応できる仕訳の形式を調整する必要があります。
基本的な簿記・経理知識が求められますが、出力のパターンには傾向があるため、業務を進める中で経費精算に関わる仕訳の仕組みや考え方を学ぶことができます。

工事の未成・完成の状態によって勘定科目や費用分析項目の付け替えが必要になり、経費申請時と精算処理時に完成状態の差異があると経費担当者様が勘定科目の修正に追われることになってしまいます。
そのため、システム導入を機に未成・完成の差異を吸収する仕組みが求められました。
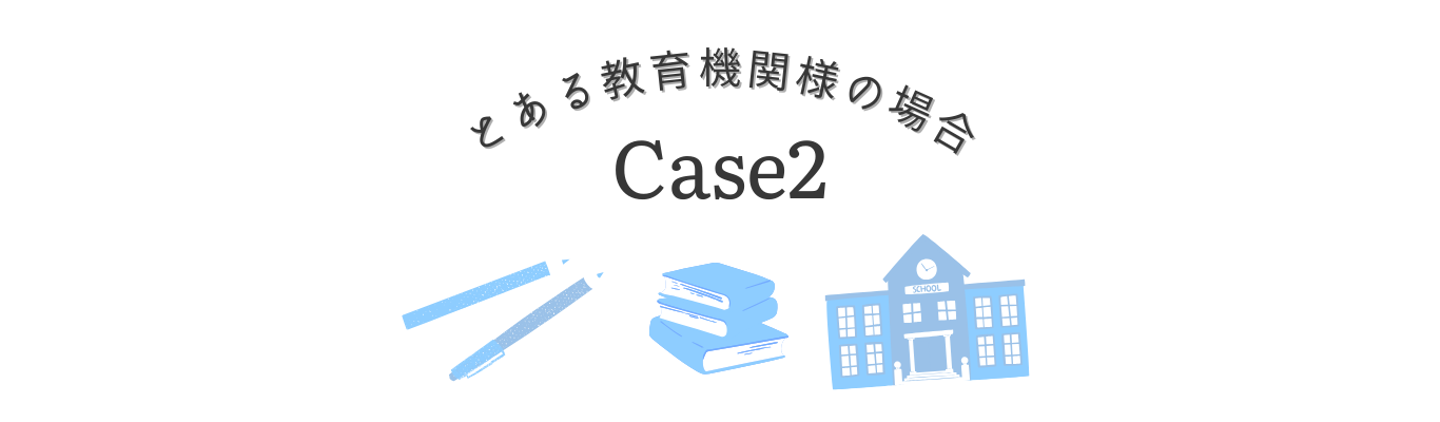
現行の経費精算システムからのリプレイス(運用システムの切替)として設定させていただくことになりました。
楽楽精算は本来、明細に配置した交通機関・内訳マスタの内容で費用科目や税区分を決定しますが、教育機関ということで費用は非課税、連携する税区分もありません。
楽楽精算では税区分コードの設定が必須となるため、会計連携では使用しない楽楽精算内のみで使用する仮の税区分コードを使用する方針としました。
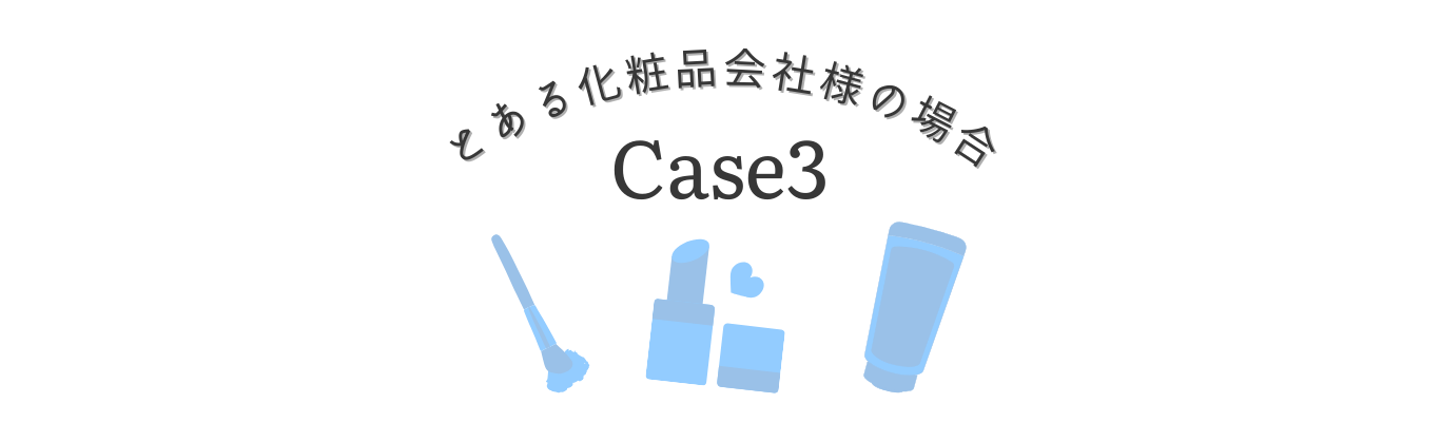
交通費・経費などを1画面ですべて入力したいというご要望が強く、日当など手当の支給もあるため、標準の「出張精算」をベースに画面構築を行うことになりました。
出張精算では精算項目の費用科目や税区分などをプルダウンリストで選択しますが、1画面のためプルダウンリストに数多くの項目を配置することになり、対策として項目名の頭に記号やアルファベットで精算種類を表す符号を付与することで選択のしやすさを確保しました。


/assets/images/18188517/original/67bc12fd-2c98-4f5d-972e-495ee653c9de?1718079493)


/assets/images/18188517/original/67bc12fd-2c98-4f5d-972e-495ee653c9de?1718079493)

